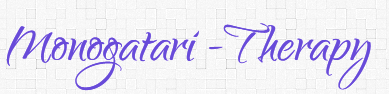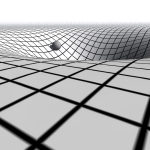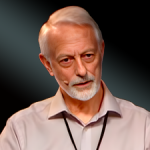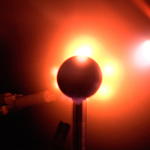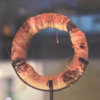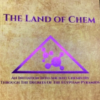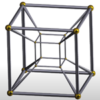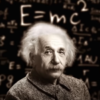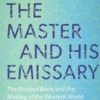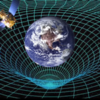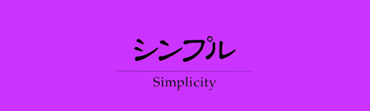重力の力が伝わる速度は、光速の少なくとも200億倍速くなければならない
アインシュタインの相対性理論を揺るがす論文
光と重力の伝播速度が異なるかもしれないって考えた事がありますか?
どういうことかというと、「重力は光よりも速く伝わるに違いないという主張は、次のようなものである。もしその速度制限が光の速度であるならば、……1200年で地球と太陽の距離が2倍になる……もちろん、これは起こっていない」ことだからです。
重力は光よりも速く伝わるに違いないというトム・ヴァン・フランダーン博士の論文を紹介した、この記事の著者トム・ベセル氏は「物理学の理解にとってこれほど根本的なことが、いまだに議論の対象となっているのは奇妙に思えるかもしれない」と言います。それは「多くの教師やほとんどの教科書がこの質問を避けているから」です。
トム・ヴァン・フランダーン博士の論文は、この次の記事で紹介する予定ですが、今回の記事でフランダーン博士の論文の意義について知っていただければ嬉しいです。なぜなら「本稿では、新たな人物と議論を紹介する。特殊相対性理論が取って代わられると、量子論を含む20世紀の物理学の多くが、その観点から再考されなければならないため、この問題は重要である」からです。控えめな表現をされていますが、今日標準の宇宙論がひっくり返ります。

Tom Van Flandern Articles
トム・ヴァン・フランダーン 記事
Meta Research
PO Box 115186
Chevy Chase, MD 20825-5186
Email: tomvf@metaresearch.org
最新情報および関連する興味深い記事については、The Meta Researchのウェブサイトをご覧ください。
タイトル:重力の速度 – 実験結果が示すもの
著者:VAN FLANDERN, TOM
所属:AA (Meta Research)
ジャーナル:アメリカ天文学会、DDA会議 #30、#10.04 発行
日:1998年9月 出典:AAS
抄録 著作権:�1998:
アメリカ天文学会 書誌コード:1998DDA….30.1004V
[要約]
もし太陽からの重力波が光速で外向きに伝播するならば、伝播遅延は太陽を周回する天体の角運動量を急速に増大させ、約1000回転で軌道半径が2倍になる。天体の方向と加速度の直接測定※により、あらゆる波長の光が有限速度の直接的な結果として収差を受ける一方で、重力にはそのような収差や検出可能なレベルでの伝播遅延がないことが示されている。
連星パルサーの動力学的研究により、重力源の位置と速度が光の時間遅延なしに予測されるだけでなく、重力源の加速度も予測されることが示されている。実際、一般相対性理論が低速・弱磁場限界で収束すると想定されているニュートンの万有引力の法則では、重力の伝播速度は無限大であることが必要とされる。これらのパラドックスは、一般相対性理論の重力の湾曲時空解釈によって説明されると考えられている。しかし、この解釈は、特に連星ブラックホールの場合に顕著な、同様に解決不可能な新たなパラドックスを引き起こす。
※"直接測定"とは、測定しようとするものを正確に測定することを指し、"間接測定"とは、何か他のものを測定することで何かを測定することを意味する。直接測定の例としては、重量や距離などがある。したがって、もし私が木片の長さを測定したい場合、それを測ればよい。しかし、例えば、風の吹く速さなど、測定が少し難しいものを調べたいとしよう。風の実際の速度を測定することはできないかもしれないが、風車があれば、風車がどれだけの力を生み出しているかを測定できる。そして、この情報を使用すれば、風の速度を逆算して求めることができる。これが、何かを"間接的に"測定しなければならない例である。
さらに、その解釈は中性子干渉計実験の結果と矛盾している。この矛盾の解決策のひとつは、実験を文字通りに解釈し、そこから重力の伝播速度は少なくとも2×1010cであると推論することである。これはアインシュタインの特殊相対性理論の解釈とは矛盾するが、ローレンツの同理論とは一致する。物理学の法則で許容されるものについての考え方を微妙に変えることで、いくつかの有益な結果がもたらされる。その例として、量子力学における局在性のジレンマや、自然界における特異点("ブラックホール")の存在の問題などがある。
最新発表論文:重力の速度 ─ 実験結果から、トム・ヴァン・フランダーン著、物理学レターA、250(1998)1-11。
関連論文:縦方向に振動する重力および電場における伝播速度※0、ウィリアム・D・ウォーカーおよび J・デュアル著(PDF)
相対性理論の再考
トム・ベセル
まだ誰も注目していないが、権威ある物理学専門誌が、その結論が、もし一般的に受け入れられるならば、現代物理学の基礎、特にアインシュタインの相対性理論を揺るがすことになる論文を掲載した。物理学レター誌A(1998年12月21日)に掲載された記事は、重力の力が伝わる速度は、光速の少なくとも200億倍速くなければならないと主張している。これは、1905年の特殊相対性理論に反する主張である。特殊相対性理論では、光よりも速いものは存在しないと主張している。光の速度の特別な地位に関するこの主張は、20世紀の教養ある素人の世界観の一部となっている。
一般相対性理論(1916年)とは対照的に、特殊相対性理論は"何度も何度も"確認されているため、専門家は批判の対象外であると考えている。しかし、少数派の物理学者たちは、相対性理論の難解な(幻覚作用のある)複雑さを回避し、事実をよりシンプルに捉える方法があると信じている。彼らの主張は素人にも理解できる。
私は5年以上前に、こうした反対派の一人であるペトル・ベックマンについて書いたことがある(TAS、1993年8月、およびTAS※、1993年10月の通信)。
※TAS=The American Spectator(アメリカンスペクテイターは、ニュースと政治を扱う保守的なアメリカの雑誌)
本稿では、新たな人物と議論を紹介する。特殊相対性理論が取って代わられると、量子論を含む20世紀の物理学の多くが、その観点から再考されなければならないため、この問題は重要である。
物理学誌『Physics Letters A』に掲載された記事は、メリーランド大学の物理学部の研究員であるトム・ヴァン・フランダーンによって書かれた。同氏は「天文学における有望だが不人気の代替案」を支持する『Meta Research Bulletin』も発行している。1990年代には、地上の観測者が自分の位置を約30センチ以内の精度で特定することを可能にする原子時計を搭載した衛星群である全地球測位システム(GPS)の特別コンサルタントとして働いていた。ヴァン・フランダーンは、GPSがまだ稼働する前から興味をそそる論争が巻き起こっていたと報告している。特殊相対性理論を信奉する人々は、それが本当に機能するのかどうか疑う理由があった。実際には、GPSは問題なく機能している。(ただし、これについては後ほど詳しく説明する。)
彼の論文が発表されたことは、ある意味でブレイクスルーである。長年にわたり、主流の物理学専門誌の編集者の大半は、特殊相対性理論に異議を唱える論文を自動的に却下してきた。この方針は、ハーバート・ディングルの論争を受けて非公式に採用された。
ロンドン大学の科学教授であるディングルは、特殊相対性理論を一般に広める本を書いたが、1960年代にはそれが真実ではないと確信するようになった。そこで彼は、最初の著書を否定する内容を書いた『岐路に立つ科学
Science at the Crossroads※1』(1972年)という本を書いた。科学雑誌、特に『ネイチャー』には、彼(および他の人々)の手紙が殺到した。
物理学レター誌の編集者は、ヴァン・フランダーンに、彼の論文が従来の定説と矛盾しているという理由だけで査読者が拒絶することはできないと約束した。ヴァン・フランダーンは、イェール大学で天体力学の大学院生として学んだ “最も驚くべきこと"から話を始めた。それは、すべての重力相互作用は瞬間的に起こると考えなければならないということだ。同時に、学生たちはアインシュタインの特殊相対性理論が、真空状態では光よりも速く伝播するものは何もないと証明していることも学んだ。
ヴァン・フランダーンは私に、この相違は「刺激物(イライラさせるもの)のようにそこに存在していた」と語った。彼はいつかその解決策を見つけ出すと決意した。今日、彼は相対性理論の新たな解釈が必要かもしれないと考えている。
重力は光よりも速く伝わるに違いないという主張は、次のようなものである。
もしその速度制限が光の速度であるならば、その作用にはかなりの遅延が生じなければならない。太陽の"引力"が地球に到達するまでに、地球はさらに8.3分間(光の速度)"移動"することになる。しかし、その時点では、太陽の地球に対する引力は、地球の太陽に対する引力と同じ直線上にはない。これらの位置がずれる力の影響により「1200年で地球と太陽の距離が2倍になる」ことになる。
もちろん、これは起こっていない。惑星の軌道の安定性から、重力は光よりもはるかに速く伝わるに違いない。この推論を受け入れ、アイザック・ニュートンは重力の力が瞬間的でなければならないと仮定した。
天文学的データもこの結論を裏付けている。例えば、地球は太陽の見かけ上の位置から20秒角(天文学における角度の何度、何分、何秒の"秒")前方に向かって加速していることが分かっている。つまり、太陽の真の瞬間的な方向に向かって加速している。その光は一定の方向から私たちに届いているが、その"引力"はわずかに異なる方向から作用している。これは、光と重力の伝播速度が異なることを意味している。
物理学の理解にとってこれほど根本的なことが、いまだに議論の対象となっているのは奇妙に思えるかもしれない。しかし、それ自体が、物理的世界について私たちが本当にどれほど理解しているのか、という疑問を抱かせるべきである。ヴァン・フランダーンは、「あるインターネット上のディスカッション・グループでは、"重力の速度とは何か"という質問や議論が最も多くなされている」と書いている。教室ではあまり聞かれないが、それは「多くの教師やほとんどの教科書がこの質問を避けているから」に過ぎない。彼らは、重力は非常に速いはずだという議論を理解しているが、同時にアインシュタインの定めた速度制限を越えるようなことはしないよう訓練されている。
つまり、特殊相対性理論にはやはり何か問題があるのかもしれない。
バートランド・ラッセルは著書『相対性理論のABC』(1925年)の中で、かつてコペルニクス的宇宙観が不可能に思えたが、今では当然のことのように思えるように、いつかアインシュタインの相対性理論も「容易に思えるようになるだろう」と述べている。しかし、相対性理論は依然として"難しい"ままであり、その理由は数学が簡単または難しいからではなく(特殊相対性理論は高校レベルの数学で理解できるが、一般相対性理論は本当に難しい)、基本的な論理を放棄しなければならないからである。"やさしいアインシュタイン
Easy Einstein “の本は、ほとんどの人にとって依然として不可解である。
一方、太陽を中心とした太陽系は、ずっと以前から理解しやすいものだった。それでもなお、特殊相対性理論(直線上の運動を扱う)は非の打ちどころがないと考えられている。一般相対性理論(重力や加速運動一般を扱う)は、それほど畏敬の念を持っては見られていない。スタンフォード大学のフランシス・ エヴェリットは、来年宇宙に打ち上げられる予定の一般相対性理論の実験テストの責任者であり、この二つの理論の現状について次のようにまとめている。
「アインシュタインの一般相対性理論が破綻しても、私はまったく驚かない」と彼は書いた。「アインシュタイン自身も、その理論には重大な欠点があることを認識していた。また、現代物理学の他の部分と調和させるのは非常に難しいということも、一般的な根拠からわかっている。一方、特殊相対性理論に関しては、私はもっと驚くだろう。実験的な根拠は、より説得力があるように思える」
これが大多数の見解である。
特殊相対性理論に対する異議は、少数かつ散発的である。しかし、それは存在しており、拡大しつつある。ヴァン・フランダーンの記事は、その最新の表明に過ぎない。1987年には、コロラド大学で教鞭をとっていたペトル・ベックマンが『アインシュタイン・プラス・トゥー Einstein Plus Two ※2』を出版し、相対性理論につながる観察結果は、ユニバーサルタイム(万国標準時、グリニッジ標準時に代わる、原子時計で計測される世界標準時で、グリニッジ標準時とはわずかなずれがある)を維持する形でより簡単に再解釈できると指摘した。彼が創刊した学術誌『ガリレオ電気力学 Galilean Electrodynamics』は、コネチカット大学のハワード・ヘイデン Howard Hayden※3(物理学)が引き継ぎ、現在はタフツ大学のエレクトロオプティクス技術センターのシンシア・コルブ・ホイットニーが編集している。ヘイデンはニューイングランドの複数の大学でベックマンのアイデアに関する研究会を開催したが、反論を試みる物理学者は一人も見つからなかった。
アインシュタインが物理学にもたらした最も有名な貢献について簡単に触れておこう。誰もが知っているあの公式だ。異端が広まっていると聞くと、相対性理論を擁護するために「原子爆弾は機能するよね?」と尋ねる人もいる。彼らは次のように論理を展開する。E=mc2という方程式は、アインシュタインの(特殊)相対性理論の副産物として発見された。(その通りだ)。相対性理論は、世界の仕組みを理解する上で不可欠であると彼らは結論づけている。しかし、それは正しくない。有名な方程式の別の導出(論理的に結論をひきだすこと)は、相対性理論なしで済ませる。そのひとつは、1946年にアインシュタイン自身がもたらしたものである。そして、それは相対性理論の複雑な説明よりも単純である。しかし、アインシュタインに関する書籍や伝記のほとんどは、この別の導出について言及していない。彼らは複雑さを賞賛し、それに固執している。
ワシントン大学のクリフォード・M・ウィルは、今日における相対性理論の有力な提唱者の一人である。「特殊相対性理論なしの生活は想像しがたい」と、彼は著書『アインシュタインは正しかったのか?』で述べている。
「特殊相対性理論が役割を果たしてくれている、私たちの世界のあらゆる現象や特徴について考えてみてほしい。原子力エネルギー、爆発的なものも制御されたものも。有名な方程式E=mc2は、質量が膨大なエネルギーに変換される仕組みを教えてくれる」と述べている。
「役割を果たす」という誤解を招きやすい述語に注目してほしい。「不可欠である」というより強い主張は、不正確であるとして非難されるだろうということを彼は知っている。
相対性理論なしでは孤立してしまうだろう事実を、別の見方で捉える方法はあるのだろうか? もっと単純な方法はあるのだろうか?
単純さの基準は、理論のどちらかに決める際にしばしば控訴裁判所のような役割を果たしてきた。十分に複雑にすれば、プトレマイオス天動説でも惑星の位置を正確に予測できる。しかし、太陽中心の天動説の方がはるかに単純であり、最終的にはその理由からこちらの方が好ましい。
トム・ヴァン・フランダーンは、問題は"ミンコフスキー図と物理的に存在する相対論的思考"に慣れ親しんだアインシュタインの専門家たちが、ユニバーサルタイムと"ガリレイ空間※4“の代替案を、自身の数学的創造性(創意工夫の能力、創造力)よりも実際にはるかに不可解だと感じていることにあると述べている。相対論の専門家が徹底的に訓練を受けた後でも、素人が時間遅延や空間収縮を理解するのと同じくらい、古典的な観点からこのテーマを再考するのは難しいと彼は言う。しかし、素人や相対性理論を専門としていない物理学者(つまり物理学者の大半)にとっては、ガリレイ流の方がアインシュタイン流よりもはるかに単純であることは疑いのない事実である。
特殊相対性理論は、マイケルソン・モーリーの実験(1887年)の結果、物理学に生じた大きな難点を回避する方法として初めて提案された。ジェームズ・クラーク・マクスウェルは、光と電波は波長が異なるだけで、同じ電磁スペクトルを共有していることを示していた。海の波には水が必要であり、音波には空気が必要である。したがって、電磁波には伝播するための独自の媒体がなければならないという主張がなされた。それは"エーテル"と呼ばれた。
「惑星間および恒星間の空間が空虚ではないことは疑いようがない」とマクスウェルは書いた。「そこは物質で満たされており、それはおそらく我々の知る限り最も大きく、均一な物質である」
今日の反体制派の見解では、マクスウェルの均質性の仮定こそが誤解のもとだった。
マイケルソンとモーリーのこの実験は、このエーテルを検出しようとしたものである。地球が軌道運動でこのエーテルの中を通過するはずなので、"エーテル風"は検出できるはずである。ちょうど、移動中の車の窓の外でそよ風を感じることができるように。しかし、繰り返し試みたにもかかわらず、エーテルのそよ風は感じることができなかった。マイケルソンの装置を回転させると、干渉縞のパターンが移動するはずだった。しかし、フリンジシフト(干渉パターン内の干渉縞の移動または変位)は見られなかった。
アインシュタインは、この結果を大胆な方法 radical fashion で説明した。エーテルは必要ない、と彼は言った。そして、フリンジシフトは起こらない。なぜなら、接近する光波の速度は観察者の運動の影響を受けないからだ。しかし、光の速度が常に一定であるならば、時間そのものが遅くなる必要があり、空間は、空間を時間で割った値が常に同じ値、すなわち不変の光速度となるように、必要な分だけ収縮しなければならない。この結果を導いた公式は極めて単純であり、数学的にはすべてうまくいき、観測結果とも一致した。
一方、懐疑的な人々は、次のような説明で懐柔させられた。
「物が動くと時間が遅くなり、空間が収縮するのは奇妙に思えるかもしれないが、心配はいらない。測定可能な影響が出るのは、日常生活で経験するものよりもはるかに高い高速の場合だけだ。だから、実用上はこれまでと同じように考えていいのだ」(一方、空間と時間は速度に従属させられた。それに慣れることだ)
ここで、いくつかの現代の実験的発見について触れよう。
今日、私たちは1日につき10億分の1秒まで正確な時計を持っている。アインシュタインが予測したごくわずかな差異は、現在では測定可能である。そして興味深いことに、実験により、原子時計は動くと実際に遅くなり、原子粒子は実際に長生きすることが示されている。これは、時間そのものが遅くなることを意味するのだろうか? それとも、もっと単純な説明があるのだろうか?
私が言及した反対派の物理学者たちは、さまざまな点で意見が分かれているが、この命題に関しては一致し始めている。電磁波が伝わるエーテルは実際に存在するが、それはマクスウェルが提唱したようなすべてを包み込む均一なエーテルではない。むしろ、それはすべての天体が周囲に引き連れている重力場に相当する。(太陽、惑星、恒星の)表面付近では、その場、つまりエーテルは比較的密度が高い。空間へと離れていくと、それはより希薄になる。ベックマンの『アインシュタイン+2』がこの仮説を初めて紹介したと思うが、彼によると、1950年代にプラハの無線工学電子工学研究所の大学院生、ジリ・ポコルニー Jiri Pokorny から最初に示唆されたという。ポコルニーは後にプラハのカレル大学の物理学科に移り、現在は退職している。
特殊相対性理論や一般相対性理論を必要とすると思われるすべての事実は、局所重力場に対応するエーテルを仮定することで、より簡単に説明できると私は考えている。マイケルソンは “エーテル風"、すなわちエッジシフトを観測できなかったが、それはもちろん地球の重力場が地球とともに移動するからである。アインシュタインを一躍有名にした一般相対性理論の証明である太陽付近での星明かりの屈折については、光が不均一な媒体を通過するという前提があれば簡単に説明できる。
波面がより密度の高い媒体に入ると方向が変わることは物理学のよく知られた法則である。ハワード・ヘイデンによると、屈折した星明かりは"高校代数学の数行"で導き出せるという。そして、正確に導き出せる。一般相対性理論のテンソル解析とリーマン幾何学は近似値しか与えない。同様に、レーダービームが太陽の近くを通過し、水星から跳ね返ってくる際に観測される"シャピロ遅延効果※5“もある。アインシュタインの定式化(素人には理解不可能だと思うが)を使って、これらすべてを"時空の曲率※6“という観点から理解しようとする人もいるかもしれない。しかし、はるかに単純な代替案が存在することを知っておくべきである。
水星の軌道における近日点の移動は、一般相対性理論の別の有名な証明であり、より詳細な調査に値する(近日点は、軌道上で太陽に最も近い地点である)。科学史上のこの特異なエピソードについては、いつの日か学術論文が書かれるかもしれない。
アブラハム・パイスの著書『神は微妙であるSubtle Is the Lord(アインシュタインの伝記)』によると、アインシュタインは自身の計算が水星の軌道と一致したのを見て、「自分の中で何かがパチンと音を立てて折れたような感覚を覚えた……」という。「この経験は、アインシュタインの科学者人生において、おそらく生涯を通じて最も強烈な感情的な体験であったと思う。自然が彼に語りかけたのだ」。
事実:水星の軌道を説明する方程式は、相対性理論が発表される17年前にすでに発表されていた。著者のパウル・ゲルベル Paul Gerber は、重力は瞬間的なものではなく、光速で伝播するという仮定を使用していた。アインシュタインが一般相対性理論の導出(論理的に結論をひきだすこと)を発表し、同じ方程式に到達した後、ゲルベルの論文は『物理年報 Annalen der Physik(物理学に関する最も古い科学雑誌のひとつであり、1799年から発行されている。この雑誌は、実験物理学、理論物理学、応用物理学、数理物理学および関連分野に関するオリジナルの査読済み論文を掲載している)』(アインシュタインの相対性理論論文が掲載された学術誌)に再掲載された。編集者たちは、アインシュタインはゲルベルの先行を認めるべきだと感じた。アインシュタインは自分が何も知らなかったと主張したが、ゲルベルの公式はアインシュタインが研究していたことで知られるマッハの『力学の科学
Science of Mechanics 』に掲載されていたことが指摘された。では、両者はどのようにして同じ公式にたどり着いたのだろうか?
トム・ヴァン・フランダーンは、ゲルベルの仮定(重力は光速で伝播する)が誤りであると確信していた。そこで彼はこの問題を研究した。彼は、問題の公式は天体力学では周知のものであると指摘している。よって、この公式に到達することを目的とした計算の"目標"として使用することが可能である。彼は、ゲルベルの方法は「天体力学の原理から見て、まったく意味をなさない」と気づいた。アインシュタインは(1920年の新聞記事で)ゲルベルの導出法は「徹頭徹尾、間違っている」とも述べていた。
では、アインシュタインはどのようにして同じ公式を導き出したのだろうか?
ヴァン・フランダーンは計算を検討し、驚くべきことに「近日点への三つの別々の寄与、そのうちの二つは足し算、もう一つは他の二つの一部を打ち消す。そして、ちょうどよい倍数になる」ことを発見した。そこで彼は、プリンストン高等研究所で若い頃にアインシュタインと時期が重なっていたメリーランド大学の同僚に、アインシュタインがどのようにして正しい乗数を導き出したと思うか尋ねた。その同僚は、「答えを知っていた」アインシュタインが「正しい値が出るまで論拠をいじくり回した」というのが自分の印象だと述べた。
一般相対性理論の方法が正しいのであれば、それは太陽系だけでなく、どこでも適用されるはずである。しかし、ヴァン・フランダーンは、その例外として、質量の著しく異なる二つの恒星を指摘する。その軌道は、アインシュタインの公式では予測できない動きをする。
「物理学者はそのことを知っており、肩をすくめるだけだ」とヴァン・フランダーンは言う。彼らは「これらの星には何か特殊な性質があるはずだ。例えば、扁平率や潮汐効果など」と言う。もう一つの可能性は、アインシュタインは水星の軌道を"説明"するために必要な結果を得るようにしたものの、それは他の場所には適用されないというものである。
ヴァン・フランダーンは、こうしたことを「気が狂うことなく」理解する最も簡単な方法は、アインシュタインの相対性理論を捨て、「光を伝達する媒体がある」と仮定することだと言う。時計がこの媒体の中を動くと、「原子時計の電子が軌道を一周するのにかかる時間が長くなる」。したがって、静止した時計よりも、与えられた時間内に刻む"カチカチという音"が少なくなる。つまり、動く時計は「この媒体の中を突き進み、よりゆっくりと動く」ため、遅くなる。遅くなるのは時間ではない。遅くなるのは時計なのだ。特殊相対性理論を"証明"したとされる実験はすべて、地球の表面にある研究室で行われたものであるため、移動する粒子や原子時計はすべて、実際には地球の重力場を"かき分けて進む"ことになり、その結果、遅くなるのである。
アインシュタインと局所場の理論の両方とも、同じ結果をもたらすだろう。限定された範囲で。
ここで、GPS(全地球測位システム)に話を戻そう。GPSの時計が地球を周回する高高度では、重力場が地球から20,000キロ上空では希薄なため、地上よりも1日あたり約46,000ナノ秒(10億分の1秒)速く進むことが知られている。また、軌道を回る時計は、秒速3キロという軌道速度でその重力場を通過する。そのため、静止している時計よりも1日あたり7,000ナノ秒遅れて時を刻むことになる。
この二つの影響を相殺するために、GPSエンジニアはクロック速度をリセットし、打ち上げ前に1日あたり39,000ナノ秒遅くした。その後、軌道上で地上のクロックと同じ速度でカウントを進め、システムが"動作"する。地上の観測者は、実際、非常に高い精度で位置を特定できる。しかし、アインシュタインの理論では、軌道を周回する時計はすべて高速で移動し、地球表面上のどこに位置する地上観測者に対しても異なる速度で移動するため、アインシュタインの理論では、関連する速度は常に観測者に対する速度であるため、時計の速度には相対性理論に基づく補正を絶えず加えなければならないと予想されていた。そうなると、GPSに扱いにくい複雑さが持ち込まれることになる。しかし、こうした補正は行われなかった。それでも、「打ち上げ後、相対論的補正は一切使用していないが、システムはなんとか機能している」とヴァン・フランダーン氏は言う。「彼らは基本的にアインシュタインの理論を無視(吹き飛ばす)している」
最新の調査結果は、相対論的な予測と一致していない。この発見を調整するために、アインシュタイン信奉者たちは、物事を異なる"参照フレーム"から見れば、すべてうまくいくと主張することに長けている。しかし、それはあたかも逆立ちをしているようなもので、説得力に欠ける。すべての事実を説明できるよりシンプルな理論が、いずれ、ますますルーブ・ゴールドバーグ※7のようなものに取って代わるだろう。今まさに、その変化が起こり始めていると私は思う。
※Rube goldberg-like:ルーブ・ゴールドバーグ・マシンは、アメリカの漫画家ルーブ・ゴールドバーグにちなんで名付けられたもので、連鎖反応型の機械または仕掛けであり、単純な作業を間接的かつ(非現実的なほど)複雑な方法で実行するように意図的に設計されている。
ディングルの問い:
ロンドン大学のハーバート・ディングル教授は、特殊相対性理論がいつ初めて学んだとしても常に論理と矛盾する理由を示した。その理論によると、二人の観察者がそれぞれ時計を持っている場合、一方が他方に対して動くと、動いている方の時計は止まっている方の時計よりも遅く進む。しかし、相対性理論そのもの(理論の不可欠な一部)は、あるものが別のものに対して直線的に動いている場合、どちらも動いていると見なすことができると主張している。つまり、AとBの二つの時計があり、そのうちのひとつが動かされた場合、時計AはBよりも遅く動き、時計BはAよりも遅く動く。これは不合理である。
ディングルの質問はこうだった。どちらの時計が遅く動くのか?
物理学者たちは答えに同意することができなかった。議論が続くなか、1973年7月にカナダの物理学者が『Nature』に次のような手紙を書いた。
「おそらく、答えを出したい人たちが一堂に会して公式な答えを出す時が来たのかもしれない。さもなければ、この問題を聞いた一般人は、専門家が意見を異にしている場合、彼らの意見が正しいとは限らないが、間違っている可能性はあると主張する権利を行使するかもしれない」。
問題は解決していない。MITのアラン・ライトマンは、著書『物理学の偉大なアイデア』(1992年)の中で、満足のいく解決策とは言えない解決策を提示している。
「各観察者が、自分の時計よりも相手の時計の方が遅く進んでいると見るという事実は、矛盾を導くものではない。矛盾が生じるのは、二つの時計が再び並んで置かれるのが二つの異なる時刻である場合のみである」。しかし、常に相対運動を続けている時計が一直線上に並ぶことは「一度だけ、すれ違う瞬間にしか起こりえない」。したがって、この理論は、それを検証することが不可能であるという理由で、その内部論理から守られている。このような理論が科学的であると言えるだろうか? ── TB(Tom Bethell)
トム・ヴァン・フランダーン著『メタリサーチ・ブルテン』(15ドル)および『ダークマター、ミッシング・プラネッツ』(24.50ドル)は、P.O. Box 15186, Chevy Chase, MD 20825から入手可能。ペトル・ベックマン著『アインシュタイン・プラス・トゥー』(40ドル)は、Golem Press, P.O. Box 1342, Boulder, CO 80306から入手可能。ベックマンの著書はかなり専門的である。一方、ヴァン・フランダーンの著書は、素人にも理解しやすい内容である。
トム・ベセルはTAS(The American Spectator)のワシントン特派員である。彼の最新著書『最も高貴な勝利』は、最近、セント・マーティンズ・プレス社から出版された。(1999年4月28日投稿)(ザ・アメリカン・スペクテイター、1999年4月号)
──おわり
トム・ベセル
著者のトム・ベセル氏を(wiki)から引用します。当然にも、人為的な地球温暖化の存在を否定、エイズを否定、進化論を否定していますね。
トム・ベセル(1936年 – 2021年)は、主に経済と科学の問題について執筆したアメリカのジャーナリスト。
論争
1976年、ベセルは『ハーパーズ・マガジン』誌に「ダーウィンの誤り」と題する論争を呼ぶ記事を書いた。ベセルによれば、適合性の独立した基準は存在せず、自然淘汰は同義語であるという。ベセルはまた、ダーウィンの理論は「崩壊寸前」であり、自然淘汰は支持者の間で「ひっそりと放棄」されていると述べた。これらの主張は生物学者たちによって否定された。古生物学者のスティーブン・ジェイ・グールドは、ベセルの主張に対する反論を書いた。
ベセルはHIV-AIDS仮説の科学的再評価グループのメンバーだったが、このグループはHIVがAIDSの原因であることを否定している。著書『ポリティカリー・インコレクト・ガイド・トゥ・サイエンス』(2005年)では、人為的な地球温暖化の存在否定、エイズ否定論、進化論の否定(ベセルはこれを"真の科学"ではないと否定している)を推進した。ベセルは、インテリジェント・デザインを扱ったドキュメンタリー映画『追放: インテリジェンス・アローワッド』を推奨した。
メタリサーチについて
科学的見地から主流のパラダイムに挑む
メタリサーチのウェブサイトへようこそ。
天文学の分野では何かが間違っている。広く信じられている多くの考えは、観測結果と反している。理論は、矛盾を解消するために無理な解釈を強いられ、もはや単純な言葉では説明できないほどになっている。代替案は、現状に異議を唱えるという理由だけで、即座に却下されることが多い。その結果、今日の理論の多くは不必要に複雑になっている。
メタ・リサーチは、この分野に常識を取り戻すことに専念している。ここでは、これまで常に予測を外してきた考え方に異議を唱え、新しいパラダイムを検証し、さらに検討と検証に値する最も価値ある考え方を提唱している。
直感的に、ほとんどの人は、ある考え方が人気があるからといって、それが妥当であるという適切な尺度にはならないことを理解している。しかし、広く受け入れられている理論に疑問を呈する人々は無知とレッテルを貼られ、それでも主張を続けると変わり者、ペテン師、あるいはもっと悪いレッテルを貼られる。メタ・リサーチは、すべての答えを持っていると主張するつもりはない。しかし、少なくともここでは、無礼な質問をしても安全であり、代替仮説を主張してもよい。
トーマス・C・ヴァン・フランダーン博士の訃報
Obituary for Dr. Thomas C Van Flandern
Non est ad astra mollis e terris via
トーマス・C・ヴァン・フランダーン博士の訃報
地球から星まで行く簡単な道はない
メディアリリース
2009年1月13日(火) – 即時公開
ワシントン州スクイム ── 有名な天文学者トーマス・C・ヴァン・フランダーン博士は、2009年1月9日に大腸癌のため亡くなった。彼は1962年にザビエル大学を卒業し、1963年にジョージタウン大学に短期間在籍した後、1969年に天体力学を専門分野としてイェール大学で天文学の博士号を取得した。ヴァン・フランダーン博士の初期の業績は、その分野では高く評価されているが、より広く(そして物議を醸し)知られているのは、その後の科学的貢献である。
幼い頃から天文学に魅了されていたヴァン・フランダーン博士は、19歳で初めてその分野に貢献した。1959年、トムと友人デニス・スミス(当時17歳)は、シンシナティのムーンウォッチ・プロジェクトの一環として、1か月間に追跡した人工衛星の数で世界記録を樹立した。トムは新聞配達で稼いだお金で買った個人用の望遠鏡で観測を行った。
ヴァン・フランダーン博士は米国海軍天文台で21年間勤務し、航海暦局の天体力学部門の主任となった。彼のチームは、航海暦の定期的な発行に貢献した。公務員を退職後、ヴァン・フランダーンはメリーランド大学物理学科の研究員となり、陸軍研究所の全地球測位システム(GPS)のコンサルタントも務めた。
ヴァン・フランダーン博士は著書『ダークマター、ミッシングプラネッツ、アンド ニューコメッツDark Matter, Missing Planets and New Comets』の中で、いくつかの物議を醸している理論を提示している。最も注目すべきは、重力の速度は光速よりもはるかに速く伝播しなければならないというもの、彗星と小惑星は惑星の爆発による残骸であるというもの、宇宙背景放射は宇宙の膨張によるものではないためビッグバンは無効であるというもの、火星は小惑星帯にあった惑星が爆発して逃れた月であるというもの、そして、火星にある建造物のいくつかは人工物である。
ヴァン・フランダーン博士は、衛星を持つ小惑星の発見を予言し、重力の速度に関する査読付き論文をJ.P.ヴィジェと共同発表し、流星群予測モデルの改善においてエスコ・リッティネンと協力した。残念ながら、彼の火星の人工物に関する主張を悪用して、彼と彼の研究を貶める者が後を絶たない。
ヴァン・フランダーン博士は、天文学における有望だが人気のない代替案の研究支援を得るという広範な問題に対応するため、1991年にメタ・リサーチ社を設立した。メタ・リサーチ社は季刊誌を発行し、インターネット上でも metaresearch.org で情報を提供している。
オハイオ州クリーブランド生まれのヴァン・フランダーン博士は、ワシントンDCで妻バーバラと四人の子供たちとともに暮らし、働き、退職した。晩年はワシントン州オリンピック半島の町、スクイムで過ごした。
トム・ヴァン・フランダーンの闘病年表:https://www.metaresearch.org/media-and-links2/press-releases/chronology-of-tom-van-flanderns-illness
お悔やみのメッセージ:https://www.metaresearch.org/media-and-links2/press-releases/condolence-messages
詳細については、マイク・ヴァン・フランダーン(360-504-1169、ワシントン州シークイム)までお問い合わせください。mikevf@hotmail.com
注
※1. 縦振動する重力および電場の伝播速度

著者らは数年にわたり、重力相互作用の速度を測定できる実験室での実験の開発可能性を調査してきた。1950年代から1960年代にかけて、複数の研究者が、ある質量の近くにある別の質量を縦方向に振動させ、その結果生じる重力による縦振動を検出できる可能性を提案した。そうすれば、振動周波数、質量間の距離、二つの質量の振動の位相差の測定値から位相速度を決定できる。これらの初期の研究者たちは、重力の位相速度は光速に等しいと仮定していた。典型的な実験セットアップで予想される位相シフトは、1マイクロ度程度だった。当時の技術では限界があったため、重力実験は実施されなかった。1963年、R. P. ファインマンは、振動電荷の電界を分析した一般物理学書を出版した。ファインマンの結論は、振動する電場は振動軸に沿ってほぼ瞬間的に伝播し、光速よりもはるかに速いというものだった。類似した振動質量問題の類似性から、物理学界ではそれ以来、縦方向に振動する重力場と縦方向に振動する電場の位相速度は、近距離場実験では測定できないほど速いという結論に達している。
※1. 岐路に立つ科学

『岐路に立つ科学』は、アインシュタインの特殊相対性理論における時計のパラドックスをめぐる英国の科学界との苛烈な論争の末に、1972年にハーバート・ディングルによって出版された。これは今でも重要なテキストであり、アインシュタインの特殊相対性理論を学んだり、その教えを受けたりしているにもかかわらず、全体と部分の論理的関連性を理解しようとする試みが成功していないために、その理論に納得できないという広く行きわたった状況に置かれている読者にとって、そのパラドックスの問題をデカルト的な明快さで理解し、評価することを可能にする。この心理状態を経験したことのある人は多く、それを認めることもできる。このように、『岐路に立つ科学』はアインシュタインの特殊相対性理論とその歴史的背景について知る上で重要な知識源となっている。
『岐路に立つ科学』には、哲学や認識論に関する多くのアイデアが盛り込まれている。この論文は、明晰で明瞭な区別が豊富に盛り込まれた古典的な印象があり、非常に洗練されたスタイルである。1920年以降の反古典物理学の数学的観念論に関する無数の研究可能性について、私たちはここで出会う(ディンゲルが示唆するように、現代科学の実証的方法の支持者として、形而上学ではなく物理学と呼ぶのが依然として正しいと仮定する)。
ディングルが書いたすべてのページは、ディングルがマクスウェル自身における数学的観念論の起源と、与えられた数学的関数の連続性を確保するために仮定された変位電流について観察したことから始まり、1970年代に顕著になったこの種の思考の極端な傾向、例えば最終章で言及されているホイル教授のケースのように、「自然が何をするかを見るのではなく、自然に何をすべきかを伝える」というプロセスを明確に支持している。自然が何をするかを見るのではなく、自然に何をさせるかを指示するプロセスを支持している」と述べている。当然のことながら、ディングルの研究を現在まで継続することは、私たちの任務である。現在の電子版には、編集者による序文が掲載されており、この序文では、『岐路に立つ科学』を十分に理解するために読者が備えておくべき基本的な知識について説明している。(brave)
※2.「アインシュタイン+2」Beckmann’s Einstein Plus Two
「アインシュタイン+2」は、ペトル・ベックマンが1987年にゴーレム・プレス社から出版した著書である。この本は、アルバート・アインシュタインの相対性理論に異議を唱え、空間と時間を歪めることなく相対性原理を満たす代替理論を提案している。ベックマンの理論は、アインシュタインの理論から派生する実験的に検証済みの現象すべてに加え、電子軌道の量子化とティウシウス系列という二つの現象を導き出している。本書は三つのセクションに分かれている。アインシュタイン プラス ゼロ、ワン、ツーである。最初のセクションでは、ベックマンが過去の実験を再検証し、局所場に対する運動を理解することでそれらの実験を説明できることを示している。また、本書には水星の軌道の詳細な分析も含まれており、ベックマンは、アインシュタインより17年も前に古典物理学を用いて水星の公式を導き出したパウル・ゲルベルに謝意を表している。
本書は好意的な評価を受けており、8件のカスタマーレビューに基づく平均評価は星5段階中4.7となっている。Kindleや印刷物など、さまざまなフォーマットで入手可能であり、Amazonやその他の書店で購入できる。(brave)
※3. ハワード・ヘイデンHoward Hayden
気候変動に対する姿勢
ヘイデンによると、「人々が予想していた恐ろしい温暖化に関する過去の予測は実現しなかった。だから、それはまったくのデタラメだ。そのどれも信じる理由はない」。
ヘイデンが編集する『The Energy Advocate』は次のように述べている。「おそらく地球温暖化は存在し、おそらく人間の影響もあるだろう。そして、それは悪いことかもしれない。しかし、私たちは地球温暖化の流行には乗らない。前世紀の気温上昇が異常なものであったという信頼に足る証拠は何もなく、ましてや地球温暖化によって今よりも居住に適さなくなるという証拠はまったくない。また、海面上昇を理由に読者を脅かすようなことはしない。なぜなら、海面上昇は年間わずか5セント硬貨の厚さ分にしかならないからだ。何千年もの間、海面は上昇し続けている」
※4. ガリレイ空間 Galilean space
ガリレイ空間とは、古典力学における概念で、ガリレイ=ニュートン原理に基づく時空構造を説明するものである。それは、事象間の距離を測定する特定の方法によって特徴づけられる。二つの事象が異なる時刻に発生した場合、それらの間の距離は、それらの間の時間間隔として測定される。それらが同時に発生した場合、距離は空間におけるユークリッド距離として測定される。
n)次元ガリレイ空間において、二つの点(x)と(y)間の距離(d(x, y))は次式で定義される。 [ d(x, y) = ∑ (x^{i} – y^{i})^{2}} & テキスト形式の数式: x^{1} = y^{1} である場合
この空間は、虚数1の半擬ユークリッド空間と見なすことができ、等方円錐が退化する擬ユークリッド空間の極限的なケースであると考えられている。
ガリレイ空間は、等角曲線(等角曲線は、光の方向に対して一定の角度を持つ曲線)の研究など、さまざまな幾何学的研究にも使用されている。これらの研究では、回転面や作図面が頻繁に登場し、ガリレイ幾何学の観点からこれらの曲線の特性が探求される。
さらに、ガリレイ空間は曲線の運動の研究にも関連しており、制約のない曲線の進化を記述するために使用され、無粘性および粘性バーガーズ方程式のような方程式の導出につながる
※5. シャピロ遅延効果 Shapiro Time-Delay
シャピロ遅延効果(Shapiro Time-Delay)は、一般相対性理論のひとつの重要な検証方法である。この効果は、1964年にアーウィン・シャピロによって提案された。
シャピロ遅延効果は、レーダー信号が大質量物体(例えば太陽)の近くを通過する際に、その物体が存在しなかった場合よりもわずかに長い時間をかけて伝播する現象である。これは、重力ポテンシャルが光の速度に影響を与えるために生じる時間遅延によるものである。
具体的には、地球から金星へのレーダー信号が太陽の近くを通過すると、太陽の重力によって信号の伝播時間がわずかに増加する。この時間遅延は、1960年代の技術でも観測可能な程度であり、初の実験は1966年から1967年にかけて行われた。
この効果は、一般相対性理論が正しいことを示す重要な証拠のひとつとされている。(copilot)
※6. 時空の曲率 curvature of space-time
時空の曲率は、アインシュタインの一般相対性理論における基本概念であり、質量とエネルギーの存在によって時空が歪むことで重力が生じることを説明するものである。この理論によると、質量の大きい物体は時空を曲げることになり、この曲率がその中にある他の物体の運動に影響を与える。
古典物理学では、時空は三つの空間次元と一つの時間次元を合わせた、平らな四次元連続体とみなされている。しかし、一般相対性理論では、時空は平らではなく、質量体の存在によって湾曲している。この湾曲は物体の運動に影響を与え、物体の軌道は直線ではなく湾曲して見える。
時空の曲率は、その時空に存在する物質や放射のエネルギーと運動量に直接関係している。この関係は、時空の曲率を物質や放射のエネルギーと運動量に関連付ける偏微分方程式の集合であるアインシュタイン場方程式によって記述される。
この曲率効果は、着色された球体で表された質量体の存在によって歪められる単純化された二次元の表面として視覚化することができる。質量体が時空の中で移動すると、曲率が変化し、時空の幾何学は常に進化する。
時空の曲率を理解することは、惑星の軌道、質量体の周囲で曲がる光、ブラックホールの挙動などの現象を説明するために不可欠である。また、加速する質量体が引き起こす時空の曲率の波である重力波の予測にも役立つ。(brave)
※7. ルーブ・ゴールドバーグのような Rube goldberg-like
“ルーブ・ゴールドバーグのような"とは、アメリカの漫画家ルーブ・ゴールドバーグの作品にインスパイアされた、単純な作業を行うことを目的とした複雑で過剰に複雑な機械のスタイルを指す。これらの機械は、一連の単純な無関係な装置によって特徴づけられ、各装置の動作が次の装置の起動を引き起こし、最終的に目的の達成につながる。以下に、ルーブ・ゴールドバーグ・マシン的な装置とコンテストの例をいくつか紹介する。
⚫︎ルーブ・ゴールドバーグ・マシン・コンテスト:学生たちがルーブ・ゴールドバーグ・マシンを設計・製作し、複雑な方法で特定のタスクを実行する、という毎年恒例のコンテスト。このコンテストは、参加者の創造性と問題解決能力を奨励する。
⚫︎ミッション・ポッシブル:学生たちがルーブ・ゴールドバーグ・マシンに似た装置を製作し、一連のタスクを実行する、科学オリンピックのイベント。このイベントは、学生たちの複雑な機械の設計・製作能力を試す。
⚫︎Perchang:ルーブ・ゴールドバーグ・マシンのような機械を操作してボールを漏斗に落とし入れるビデオゲーム。ルーブ・ゴールドバーグ・マシンの複雑さとゲーム性を組み合わせたもの。
⚫︎驚くべき機械:ルーブ・ゴールドバーグ・マシンのような装置を製作してさまざまなパズルを解き、課題を達成するビデオゲームシリーズ。
これらの例は、教育コンテストからビデオゲームまで、さまざまな場面におけるルーブ・ゴールドバーグ・マシンの根強い人気と教育的価値を示している。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。