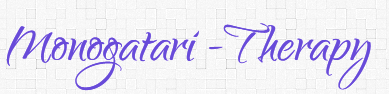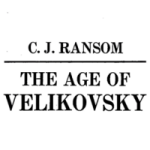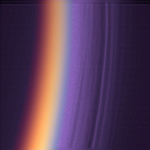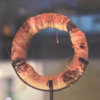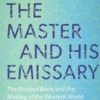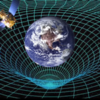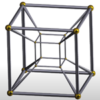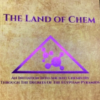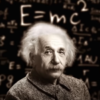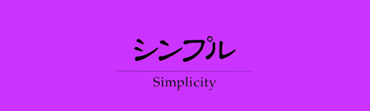ヴェリコフスキーの時代 ② ── C.J.ランサム(彗星、金星、火星、月など、提起された疑問点)
C. J. ランサム著『ヴェリコフスキーの時代①』の続きです。
今日ほど、いわゆる権威とされるものがいかにイカサマだったのかが暴かれていく時代はありません。自民党から始まって、財務省、都知事、ワクチンを推進した厚労省などの官庁、学者、専門家の嘘と腐敗、移民歓迎という名の外国人犯罪者の跋扈、それを許している司法と警察、行政。わたしたちは多民族共生という名の “他民族強制" を押し付けられ、日本の文化の破壊が進み、報道という名のメディアの洗脳が危険な状況を隠し正当化しています。しかし、気が付かない人は何が起きているのか全くわからない。
しかし、このようなこと、つまり、権威は正しいはずだ、テレビが報道することは間違っているわけがない、という思い込みは深層意識にまで刷り込まれています。刷り込まれているがゆえに疑うなんてことはその人の中ではご法度なのかもしれません。それは今も、テレビの中でうんざりするほど繰り返されています。そういえば、厚労省はワクチンの効果について「知らない」と言ってましたね。
今から50数年前、私が中学生の頃、NHKのテレビなどで、カール・セーガンという御用学者が科学番組によく出ていました。当時、人気の科学者でした。へぇー、そうなんだ、と素直に信じ込んでいました。当時は疑ってみるという発想すら浮かびませんでした。
「1973年のNASA記者会見で、セーガンはヴェリコフスキーが “はっきりと" 木星の大気中にカエルが存在すると予言した……」。
これは当時の科学を代表する"権威"の発言です。そのまま信じた人も多かったのでしょう。
真実は、セーガンはヴェリコフスキーが木星の大気中にカエルが存在すると予言したと偽りの話を流布しました。こんな感じで、学者と言われる方々の不誠実、恥知らずとも言えますが、そんな実例がこの本の中で数多く紹介されています。と言っても、嘘や不正に対する単純な非難ではなく、抑制の効いた皮肉といえばよいのか、そこにもランサム氏の深い知性を感じます。
ヴェリコフスキーは『衝突する宇宙』を発表した1950年代から亡くなるまで、学会から猛烈な非難を浴びました。それは今日で言えば、コロナが流行った頃、ワクチン接種に反対した人々が叩かれた状況と似ています。ところが、ワクチンは効果はなく、逆に被害が明らかになるにつれ事態は反転し始めています。騙されていたということです。
ランサム氏は、この本の中で「ヴェリコフスキーが提唱した主要な考えのほぼすべてが、著名な科学者によって再提唱されている」と指摘しています。ヴェリコフスキーという人は定説とか常識とされているものをそのまま信じるのではなく、どういう経緯で定説とされたのかというところまで考えを巡らせ、定説とされているもののあやふやさにも気がついたのだと思います。そこから導かれる予測が、一般に受け入れられている学説に反し、どんなに常識からかけ離れていようと、さらに周りから叩かれようと、自らの確信を貫いた人でした。
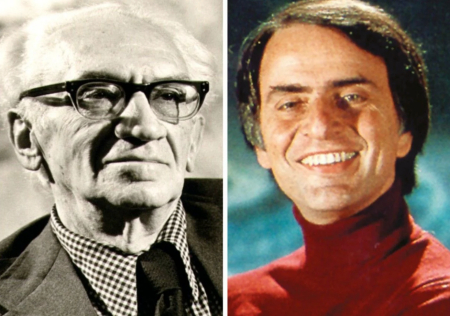
- 1. 第四章
- 2. 第五章
- 2.1. 惑星と月 THE PLANETS AND MOON
- 2.1.1. 異なる時期における形成 FORMATION AT DIFFERENT TIMES
- 2.1.2. 後に形成された惑星の起源 ORIGIN OF LATER PLANETS
- 2.1.3. 形成エネルギー ENERGY FOR FORMATION
- 2.1.4. 後に形成された惑星の密度 DENSITIES OF LATER PLANETS
- 2.1.5. 惑星の特徴 CHARACTERISTICS OF THE PLANETS
- 2.1.6. 木星 JUPITER
- 2.1.7. 金星 VENUS
- 2.1.8. 火星 MARS
- 2.1.9. 水星 MERCURY
- 2.1.10. 月 THE MOON
- 2.1.11. 資料
- 2.2. 共有:
- 2.1. 惑星と月 THE PLANETS AND MOON
第四章
よくある疑問 THE COMMON QUESTIONS
これまでの章では、ヴェリコフスキーが提唱した太陽系の近現代史の再構築について基本的な概観を提供してきた。ここでは、このモデルに対して提起されてきた疑問点を見ていく。最初に、そして最も頻繁に問われる疑問の一つは、「彗星」という語と金星の関連性に関するものである。
彗星とその影響 COMETS AND EFFECTS
『衝突する宇宙』で、ヴェリコフスキーは繰り返し「彗星金星」に言及している。よく問われる疑問はこうだ。「定義上、金星が彗星であるはずがないのに、なぜヴェリコフスキーは金星を彗星と呼んだのか?」。これには二つの答えがある ― 簡潔なものと詳細なものだ。長文の説明には彗星の物理的詳細が含まれるが、どちらの答えも質問文自体に部分的に示されている。つまり、あらゆる現象に対する人間の「定義」はその理解とともに変化する。
簡潔な説明 SHORT FORM
古代人は現代人と同じ彗星の物理的パラメータを持っていなかった。「彗星」という言葉はギリシャ語の「コマ(髪)」に由来する。古代人が空を見上げ、拡散した「毛髪状」の大気を持つ見慣れない天体を見たとき、彼らはそれを英語で「彗星」と訳される名称で呼んだ。しかしそれは、その言葉自体が「科学的」定義を暗示していたからではない。
古代の用語は文字通り解釈すると、しばしば「髪」や「煙」「火」を連想させるものだった。これらは後に金星と呼ばれる天体に古代から適用されていたが、現在では当てはまらない。
ペルーにおける金星の名称は今も「チャスカ(波打つ髪)」である。メキシコの初期伝承では金星を「煙る星」と表現しており、これは彗星を指す彼らの用語でもある。彼らは金星を「たてがみ」とも呼んだ。
古代文化が金星の本質を理解できなかったのは、かつて彗星であったとみなしていたためと考えられている。誤解していたのは彼らではないかもしれない。しかし古代人が実際に金星を大気を持つ天体として見ていたか、あるいは幻覚を見ていたかに関わらず、彼らはそれを「彗星」と表現した。ヴェリコフスキーは古代人の議論を記述しているため、その用語使用は正当化される。彼の論理は『衝突する宇宙』に明記されており、真に関心を持つ者はこれを理解できる。「彗星」という語の使用を非難するのは、フォルクスワーゲンを「虫」と呼ぶ者を非難するのと変わらない。
長文の説明 LONG FORM
『衝突する宇宙』の文脈においてヴェリコフスキーが彗星という語を適切に使用しているにもかかわらず、一部の人々は依然として非合理的に、ヴェリコフスキーが「彗星崇拝」を主導しており、現代の厳密な定義では金星を彗星と見なすことは絶対に不可能だから彼は間違っていると主張する。実際、彗星に「厳密な」定義は存在せず、今日でさえ金星を排除する判断は恣意的かもしれない。
多くの人々は、彗星は高度に偏心した軌道、長いガス状の尾、そして小さな質量によって定義されると考えている。したがって彼らは、金星はほぼ円形(低偏心率)の軌道を持ち、尾(拡散した大気)を持たず、大きな質量を持つため、彗星のようなものとは到底考えられないと主張する。
どの程度、円軌道であれば彗星と分類されなくなるのか? オテルマ彗星やシュワスマン・ワハマン彗星は惑星のような(ほぼ円形の)軌道を持つ。これらは「例外的な彗星」とされるが、ストレームグレンは、現行の観測機器では検出範囲を超えた太陽軌道を回る、このタイプの彗星が多数存在すると示唆した(1)。
天文学者は、軌道のみに基づいて彗星と判定できない天体が存在することを認めている。アラン・リゴー彗星が彗星と指定されたのは、軌道が小惑星に類似しているにもかかわらず、時に拡散性を示したためである(2)。W. バーデがイダルゴを発見した際、彗星と呼ぶか小惑星と呼ぶか迷っていた。彼は小惑星(asteroid)と呼ぶことに決めた。その科学的根拠は、当時天文学者の間で小惑星の方が彗星より人気があったため、小惑星として発表した方がより注目されると考えたからだ(3)。
1961年の第10回月惑星探査学会で、当時グリフィス天文台の名誉所長だった D. アルターは、彗星と小惑星の軌道を比較すると、この二種類の天体には関連性があることがわかる、と述べた。また、彗星や小惑星が発見されたとき、それがどちらであるかを判断するのは難しい場合が多い、とも主張した(4)。
古代人は拡散天体(明確ではっきりと区切られた境界を持たず、空間に広がって見えたり散らばって見える天体の一種)を彗星と呼んだが、現代においても拡散性(あるいは「毛髪状の」外観)が天体を彗星と呼ぶ基本基準として残っていることがわかる。
彗星の定義における質量は、さらに厳密に定義されていない。彗星の質量は測定が難しいが、一般的には1017から1020グラム(5) と考えられている。一方、金星の質量は1027グラム程度である。彗星の定義によっては、質量が 1021グラムまでのものも含まれる(6)。しかしボブロヴニコフは、ある彗星が月の質量(1024グラム)と同程度だった可能性を計算している(7)。したがって彗星の最大質量は完全に恣意的であり、現代の経験に基づいて設定されているようだ。
ヴェリコフスキーの表現に対する反響を考えると奇妙に思えるかもしれないが、金星の特定の特徴は近年、現代の科学者によって「彗星的」と称されている。ストックホルム王立研究所プラズマ物理学部門のマックス・ウォリスは1970年、「金星と太陽風の彗星的相互作用」と題する報告書を作成した(8)。その後、マリナー10号の観測結果により、この同じ用語が用いられるようになった。複数の著名研究機関の専門家が共同執筆した論文では、金星の太陽風下流(流れの方向)に「彗星のような尾の存在」を示す兆候が広範囲に認められると述べられている(9)。
金星を彗星と呼び始めようと言っているわけではないが、科学の名のもとに繰り広げられてきた多くの名称論争は、科学ではなく語義論(意味論、セマンティクス、表面的な言い回しばかりにこだわった中身のない理論)に過ぎなかったことは明らかだ。いわゆる反語義論者である必要はなくとも、「金星は彗星ではない」という主張を(今もなお)展開する人々が、この問題を客観的に捉えていないことは明らかである。
様々な天文学者による金星への「彗星」呼称への苦情の後、その一人であるW. C. ストラカが『ペンセ』読者に「彗星的な金星」と題する論文を紹介した。彼は「1948年発表でヴェリコフスキーより数年早い」と述べ、参照する価値があると指摘した(10)。ストラカは「いかなる場合にも」ヴェリコフスキーの仮説が「彼独自のものでも、彼が最初に提唱したものでもない」という根拠のない主張を支持しようとしていたため、1948年の論文への言及は本質的に、金星がかつて彗星であったというヴェリコフスキーの主張に正当性はないが、万が一に備えて、彼が最初にそれを提唱したわけではないと言いたいだけである。
ストラカは、この記事を「ご覧になると興味を持たれるかもしれない」と言うことで、参考文献をチェックしてもらえると嬉しいという印象を残そうとしている。しかし、もし彼が本当にそう感じていたなら、その記事について言及することはなかっただろう。なぜなら、彼が議論していると主張する主題とはほとんど関係がないからだ。報告されているのは、17世紀末にウェストミンスターの市民ガドベリーが、金星が「地球大気の状態による異常な光学現象のため彗星のように見えた」と二度にわたり記録した事実である。
古代人が金星を彗星と呼んでいたとヴェリコフスキーが指摘したことに非科学的な点は全くない。しかし科学者たちの反応は根拠のないものだった。後述するように、ヴェリコフスキーの研究に関してこのような反応が起こったのはこのケースだけではない。
彗星の起源(素性) ORIGIN OF COMETS
S. K. ヴセフスヴィャツキー博士 Dr. S. K. Vsekhsvyatskii
は、キエフ天文台の所長を務める著名なロシア人天文学者である。彼は長年にわたり彗星の性質と軌道を研究してきた。彼は「彗星は巨大惑星、特に木星の内部またはその近傍に起源を持つ」と結論づけている。彼の研究は、米国で受け入れられている見解と一致しないため、一般的に無視されている(ヴェリコフスキーは金星が木星から放出されたメカニズムについて、ヴセフスヴィャツキーが彗星の放出に提案したものと同一の理論を提唱していないが、彼の研究の他の部分はヴェリコフスキーが論じた概念とよく合致する)。
ヴェリコフスキーのアイデアに興味を持つ人たちだけが、ある定説が強調される一方で、合理的な代替案が軽視されることがあることに気づいているわけではない。最近、ノーベル賞受賞者が彗星の性質と起源に関する論文を共著した。この論文では、教科書や書評が主流理論のみを強調し代替理論に言及せず、「主流見解に反する観測事実さえも隠蔽する」傾向があると指摘されている(11)。ヴセフスヴィャツキーの研究は主流見解に反するだけでなく、少なくとも二つの点でヴェリコフスキーの提案と関連している。第一に、ヴセフスヴィャツキー及び彼の理論を検証した研究者らによる軌道計算は、金星に提案された軌道獲得・変化のタイプを支持する傾向がある。第二に、ヴセフスヴィャツキーの研究は長年、巨大惑星領域における活動が「冷たく死んだ惑星」という概念から予想されるよりもはるかに活発であることを示唆してきた(最近の宇宙探査機データもこれを支持する傾向にある)。
約160年前、ラプラスとラグランジュは彗星の起源について相反する仮説を提唱した。当時、彗星に関するデータは軌道運動に関する観測結果などごくわずかしかなく、両者の仮説は主に推測に基づいたものだった。ラプラスは、当時新たに発見された彷徨う星雲に興味を持ち、彗星の起源は太陽系外にあると主張した。彼は、観測される彗星は太陽系外から捕獲された天体だと考えた。小惑星も当時新しく発見された天体だったが、ラグランジュは、かつて存在した惑星の爆発によって小惑星が生成されたという仮説と整合するような彗星の起源に関する仮説を提唱した。
選択は単に「漂流星雲」対「爆発した惑星」ではなかった。それは「太陽系外かつ遠い過去における彗星の起源」か、「太陽系内かつ比較的最近の起源の可能性」かの対立だった。当時の風潮に沿い、最も広く受け入れられたのは「遠い昔・遠い場所」における彗星起源説だった。これは現代アメリカで広く支持される彗星起源理論にも当てはまる。ヴセフスヴィャツキーら多数の研究者によれば、この黙認は主に信仰に基づくものである。
彗星起源に関する最も一般的な見解は、カイパー、ウィップル、オールトの理論であり、中でも最も著名なのはオールトの彗星-雲理論である(12)。オールトは、彗星が他の天体とほぼ同時期に形成され、太陽系の外縁部に巨大な雲状に蓄積されたと仮定する。銀河内の他の天体による摂動が、時折個々の彗星を惑星系へと送り込む。擾乱を受けない彗星は低温保存状態にあるため崩壊しない。太陽系内側に入り太陽の熱を受ける彗星のみが劣化し始める。
この種の推測についてヴセフスヴィャツキーは次のように述べている:「これらの仮説は何も説明しておらず、彗星問題を不確かな過去と太陽系のかなり遠隔領域へと先送りしているに過ぎないことを考慮すべきである」。 本質的な論理も必要な効率性も欠くこうした仮説が、なぜ一部の研究者を満足させ得るのか不思議でならない。一方で、小天体(彗星を含む)の形成過程や発展過程が全く異なる方法で起こったことを示す数多くの論拠が存在する」(13)。
ヴセフスヴィャツキーは、彗星が惑星系に起源を持つという考えを支持するいくつかの根拠を提示している。しかし彼の最大の根拠は、既知の彗星軌道の定量分析に由来する(14)。1972年7月『ソビエト科学レビュー』掲載の総括論文で、ヴセフスヴィャツキーは「彗星パラメータの分析は、彗星とその崩壊生成物が太陽系内で形成されたこと(そして平均的には惑星よりはるかに後世に)を疑いようもなく裏付けている」と述べている。
彗星と石油 COMETS AND PETROLEUM
科学者たちは近年、彗星と地球の相互作用によって石油が生成される可能性を提唱し、実験的に裏付けようとしている。『衝突する宇宙』においてヴェリコフスキーは、地球の大気と金星の彗星状大気が初めて遭遇した際、古代人がこの過程を目撃したと示唆している。1950年当時、科学者たちはこのような事象が起きたことは決してないと断言していた。
当時、石油はすべて数千万年前に形成されたと想定されていた。二つのプロセスが検討された。非生物起源説(高温高圧下で水素と炭素から石油が形成されるという説)と、有機起源説(動植物の残骸から石油が形成されるという説)である。
イェール大学の地質学者 C. R. ロングウェルは、当時編集長を務めていた『アメリカン・ジャーナル・オブ・サイエンス』1950年8月号において、石油が宇宙起源である可能性を嘲笑し、石油が数百万年前のものだという仮定こそが、ヴェリコフスキーの「一部の油田は最近形成された」という主張を否定すると主張した(彼は全ての油田が宇宙起源であるとか、宇宙起源の可能性のある油田が全て金星と地球の接近に起因すると主張したわけではない)。インディアナ大学の地質学者 J. B. パットンもまた、液状炭化水素が近年の堆積物からは決して発見されていない事実がヴェリコフスキーの説を誤りと証明すると論じた。
ヴェリコフスキーが炭素年代測定法の創始者 W. F. リビーに石油層の炭素年代測定可能性を問い合わせた際、リビー博士は P. V. スミスの論文を紹介した(15)。スミスはメキシコ湾地域の最近の堆積物から採取した石油の炭素年代測定を行っていた。
この年代測定法の仮定は、石油が形成された可能性のある条件下ではおそらく有効ではない。したがって、絶対年代は9000年程度であったとはいえ重要ではない。重要な点は、この手法で使用される化学同位体である炭素14が、約5万年で検出不可能な量まで崩壊することだ。数百万年にわたり大気から炭素14を吸収していない石油は、炭素年代測定値を示すはずがない。
1961年までにオロは、隕石と地球の相互作用による重要な結果として「地球上に比較的大量の炭素化合物が蓄積されること」を提唱していた。これらは「自発的にアミノ酸、プリン塩基、その他の生化学的化合物へ変換されることが知られている」と述べた(16)。その後、オロとハンは「芳香族炭化水素やその他の有機化合物は、還元性大気を持つ惑星への大型隕石衝突の結果として形成された可能性がある」と述べた(17)。
オロとハンはさらに「これらの化合物の形成が現在も木星の局所領域で進行中である可能性」を指摘。ノーベル賞受賞者リビーが1966年ヒューストン航空宇宙工学特別セミナーで「木星に"石油"が降っている」と示唆した事実も引用している。これが真実ならば、地球が金星接近時に獲得した炭化水素の起源を解明するにあたり、木星起源説を無視すべきでないというヴェリコフスキーの提唱を支持するものである。
この種の動きは、現代の石油流出事故や古代汚染問題を想起させる。1969年、カリフォルニア州サンタバーバラ沖でユニオン石油会社の油井が破裂した。修復されるまでの11日間、原油が海峡へ噴出した。その後、南カリフォルニア大学のアラン・ハンコック財団が調査を実施した。このプロジェクトは納税者と西部石油ガス協会が共同出資したが、研究内容や発表内容に制限は設けられなかった。主要な調査結果は予想外に楽観的であった。全体的な被害は予想より「はるかに少ない」とされ、地域は回復しつつあった。原油の大部分は水路に流れ込んだシルトに付着し、盆地の底に沈殿していた(18)。 (ウッズホール海洋研究所による類似研究とは一部矛盾するが、後者は原油ではなく精製油の流出を扱ったものである)。
これは、石油流出を擁護する意図で述べられているわけではない。人々が環境保護に努めているにもかかわらず、環境はすでに深刻な損傷を受けており、規制なしで済ませるのは常軌を逸していると言えるだろう。とはいえ、上記の知見は、数千年前に海に流出した石油が、今日も海面に浮いているとは考えにくいことを示唆している。
もちろん、石油が現在の場所に存在するようになった経緯という問題がある。これは地質学者やオロ、ハンにとっても、ヴェリコフスキーにとっても同様に難題である。ただし、「仲間うち」には、悪意ではなく好奇心から質問が投げかけられるものだ。最近の地球資源衛星の写真は、この問いに対する手がかりを提供するかもしれない。石油が豊富な地域のいくつかには、過去の地殻の亀裂の痕跡が見られる。
サンダースらは、既知の鉱物・炭化水素埋蔵地の兆候を探るため、テキサス州とニューメキシコ州地域の ERTS-1画像を評価した。その結果に彼らは驚いた。画像に確認できる構造線状構造と地形学的証拠は、テキサス州西部の石油生産地であるセントラル・ベイスン・プラットフォームを疑いもなく明瞭に示している(19)。またリッチはカリフォルニア州北部海岸山脈とサクラメント渓谷のデータを分析し、「サクラメント渓谷内の石油・ガス田群と関連しているように見える」潜在的に重要な断層系を報告した。彼はさらに、その後の ERTS(地球資源探査技術衛星)画像が現地検証評価の対象地域を特定できる可能性を示唆した(20)。
ヴェリコフスキーはまた、適切なガス混合物中で作用する放電によって炭化水素が形成される可能性にも言及した(21)。後年、ユーリーはおそらく独立して、本質的に同じ提案を行った。これが真実であることは幾度も実証されており、この方向性での最近の研究はザイトマン、チャン、ローレスによって行われている(22)。
※ミラー・ユーリー実験:メタンなどのガスの混合物の中で電気放電を行いアミノ酸を形成させた。生命の起源に関する論争を呼んだ実験。1953年
石油が食料を生む PETROLEUM MAKES FOOD
石油の話題に触れたところで、この物質がプラスチックや燃料の製造以外に何に活用できるかを知れば驚くかもしれない。科学者たちは石油が食用炭水化物に変換可能であることを実証している。ヴェリコフスキーは、古代人が最初の地球-金星接近後にこのプロセスを利用したようだと指摘した。1950年当時、多くの科学者は石油から食料を製造できないと考えていた。
ヴェリコフスキーは、古代史に記された食用物質の生成可能性の一つとして、前述した石油への微生物作用を提示した。第一章で紹介した天文学者セシリア・ペイン=ガポシュキンは、石油から食料が生産できるという考えは馬鹿げていると主張した。さもなければ、世界の飢えた人々すべてを養えるはずだと彼女は述べた。
アメリカ化学会の元会長アラン・C・ニクソンは最近、天文学者ペイン=ガポシュキンが不可能と断じたことをまさに実行しようと提案した。彼は石油から直接タンパク質と脂肪を生成する技術が存在する点を指摘した。また、現在の食料生産は石油エネルギーを消費する量が生産される食料のエネルギー量にほぼ匹敵するため、この方法は聞こえほど非効率ではないとも述べた(23)。
1971年、ブリティッシュ・ペトロリアム社は年間4000トンの食料を石油から生産可能なプラントの操業を開始した(24)。同年後半にはフランス・マルセイユ近郊に第二プラントが稼働し、年間1万6000トンの生産能力を計画した。1976年までに、石油からのタンパク質生産技術は11年以上にわたる厳格な試験を経てきた。
この製品の商標はトロペリナ Troperina である。他の成分と混合することで、一般的な動物飼料よりも栄養価が高く、同等のコストで提供できる高タンパク飼料となる。石油由来タンパク質を人間用として製造する計画も進行中である。
さらに、ウォン・キー・クオンは、地球上層大気における反応を通じて炭化水素から炭水化物を生産する少なくとも六つの可能性を示している(25)。例えば、炭化水素が水素層や酸素層と混合する可能性がある。燃焼と宇宙線照射により、二酸化炭素と水素、一酸化炭素、水蒸気の混合物が生成される。この混合物にさらに照射を加えるとホルムアルデヒドが生成され、重合やアルドール縮合によって様々な糖類や澱粉類が作られる。
古代の文献によれば、この順序は正しいとさえ言える。混合物は日中に放射線を浴び、特に塵粒子上で、より涼しい夜間に重合が起こる。最終生成物は早朝に地面に落下する。
ストーンヘンジ STONEHENGE
ストーンヘンジは重要な天体を追跡するための精巧なコンピュータとして建造されたと信じ込まされている人々がいる。これはおそらく最後の大変動以前に成されたとされる。そこで重要な疑問が生じる。もし大変動が起きたのなら、ストーンヘンジはなぜ今も機能しているのか? 機能しているのなら、という前提で。
ストーンヘンジは、イギリスのオックスフォードからほど近いソールズベリー平原にある石組みである。重さ何トンもある巨大な一枚岩が、本来の目的は定かでないデザインで配置され、積み重ねられている。この地域はおそらく、ドルイド教の宗教儀式から降霊会、ハロウィーン・パーティーまで、あらゆるものに利用されてきたが、これらの活動は、ストーンヘンジがすでに存在していることを発見した人々によるものだった。建設者たちがストーンヘンジを何に使ったのかは、まだ議論の余地がある。
主要な石の円環の直径は約120フィート(約37メートル)である。石群、内側の二つの円環状穴(Z穴とY穴)、外側の円環状穴(オーブリー穴)、周囲の溝と土塁からなる円形システム全体の直径は約340フィート(約104メートル)である。円環から北東方向へ延びる幅約80フィート(約24メートル)の通路は「アベニュー」と呼ばれる。
ヒール・ストーンと呼ばれる石は現在、アベニュー中心部から外側へ約75フィート離れた位置にあり、円形構造の外側溝の脇に立っている。この石がアベニュー内の別の場所に存在していたか、あるいは他の石がアベニュー内に配置されていた可能性を示す痕跡が確認されている。
他の石柱の一部も元の位置にない。過去100年の間に数基は推定される正しい位置に再配置されたが、他の石柱は建造当時の位置とは異なっている。
ジェラルド・S・ホーキンス著『ストーンヘンジ解読』の出版により、ストーンヘンジは広く知られるようになった。この本を基にしたテレビドキュメンタリー番組が米国で繰り返し放映された。『ストーンヘンジ解読』の基本的な結論は、建造者たちが卓越した天文学者であり、長年にわたり星々を観察した後、複雑な天文データを巧みに石の配置に暗号化したというものだった。ホーキンスはコンピューターを用いてストーンヘンジを解読したと主張し、あたかも石の配置者が再び星々を観察したあのスリリングな昔日に我々を連れ戻すかのように語った。
ストーンヘンジの創始者たちは紀元前687年(火星と地球が最後に接近した時期)以前に放棄したと一般に考えられており、おそらく紀元前1500年頃かそれ以前に建造したとされる。そこで明らかな疑問が生じる。もしストーンヘンジが本当に解読され、斉一説の前提に基づいて今日でも機能しているなら、どうして大きな変化が生じ得たのか?
ヴェリコフスキーはストーンヘンジ問題への回答を1967年4月号の『イェール・サイエンティフィック・マガジン』に掲載した(26)。その論考の一部を以下に概説する。
解読の反論 DECODING REFUTED
ホーキンス理論の初期前提の一つは、夏至にストーンヘンジ中心位置から見た太陽がヒールストーン(土塁群入口外側のアベニュー内に立つ、単一の巨大なサルセン石の巨石)真上に昇るというものだ。またこの時ヒールストーンの影が祭壇石に落ちるという説もある。ストーンヘンジ研究の権威である考古学教授 R. J. C. アトキンソンは「これらの広く信じられている説はいずれも正しくない」と述べた。同教授はさらに、現在の夏至では太陽はヒールストーンの左側から昇り、斉一論者の計算ではストーンヘンジ建造当時さらに左側に昇っていたと指摘。加えて「ヒールストーンの真上からの日の出は今後1000年以上起こらない」と補足している(仮に現在ヒールストーン上で日の出が観測されても、3000年前には存在しなかった現象である)。
ホーキンスはまた、古代人が日の出の瞬間をどう定義したかの記録が存在しないとも主張する。これにより彼は、ある計算では最初の太陽光線を用いながら、別の計算では太陽の全直径が地平線上に現れるまで待つという、追加の誤差要因を導入できる。ヴェリコフスキーは、多くの古代文化の記録が日の出の瞬間を「最初の光線が見える時点」と明確に規定していると指摘する。
アトキンソンはホーキンスの理論を批判する複数の論文を発表したが、ホーキンスは後にそれらの論点の一部に応答している(27)。しかしながら、ホーキンスの誤差幅は、精密な天文計算において通常有用とされる範囲を依然として上回っていた。
大きな誤差の範囲を許容しても(そしてその範囲を超えても)、165の位置に関連する 27,060の可能な配置があっても、惑星や恒星との検出可能な相関関係はまったく見られない。唯一の有意な相関は、ホーキンスが 56年の月食周期と呼んだものだった。しかし、1967年にコルトンとマーティンは、56年の月食周期は存在せず、実際には 65年の周期であると指摘した。
一周期の月食のほとんどはストーンヘンジからは見えないが、ホーキンスは、月食が不意打ちのように起こるよりは、起こらない月食のために軍隊を召集したほうがよいと主張している。見えなかったものは、魔術師の偉大な力によって回避されたと言える。
ホーキンスは言う、こうした事象を予測できることが重要だったと。なぜならそれらは「最も恐ろしいもの」だったからだ。しかしもし正確に予測できなければ、誰もがそうした最も「恐ろしい」出来事の真っ最中に眠り続けることになりかねなかった。
1973年7月、メキシコシティで開催された会議で論文を発表した際、ホーキンスは、自分の研究はおそらくストーンヘンジの解読には至らなかったと述べた(28)。
ストーンヘンジは解読されていないが、ホーキンスの研究を分析することは依然として重要である。あらゆる可能性とあらゆるコンピューター分析にもかかわらず、天体の動きを追跡するために建設されたと考えられているこの記念碑について、重要な天文学的関連性はまだ発見されていない。しかし、この否定的な結果という結果自体が重要な意味を持っている。
ストーンヘンジの意味ありげ STONEHENGE SIGNIFICANT
ストーンヘンジは一般的に天文観測所と考えられているが、何も機能しない。これはストーンヘンジが観測対象とした天体の軌道に変化が生じた結果かもしれない。ストーンヘンジが繰り返し再配置・再建された事実は重要であり、それゆえストーンヘンジⅠ、Ⅱ、IIIA、IIIB などの様々な呼称が存在する。ヒールストーンさえ移動された可能性がある。「アベニュー」には巨大な石を収容できる大きさの穴が残っているが、その石は失われている。もしストーンヘンジが実際に星や惑星の観測に使用され、変更が必要だったとしたら、それは観測対象の見かけの動きが変わったためではなかっただろうか? ホーキンスは、ある配置が突然放棄されたように見えると指摘し、建設者たちが装置が期待通りに機能しないことに気づいたためだと示唆している。おそらく彼らは、突然、以前と同じように機能しなくなったことに気づいたのだろう。
その他の構造物 OTHER STRUCTURES
ストーンヘンジに似た巨石記念碑を説明しようとする試みは他にも数多く行われてきた。最も注目すべきは、おそらくアレクサンダー・トムの研究だろう。トムや他の研究者たちの研究は、これらの考えに対する反論を論じた議論と同様、文献で入手することができる。この主題については、本一冊分の本が書けるほど多くの研究があり、これらの理論を一つひとつ分析することは、この本の意図する範囲を超えている。しかし、アンドルー・フレミングの記事からの引用は、これらの理論を紀元前7世紀以前の一様性の「証拠」とみなすならば、それは純粋に信仰に基づく行動であるということを示している。フレミングの記事は「巨石天文学:先史学者の見解」と題されていた(29)。彼のコメントの一部を以下に示す。
トムの研究は、巨石遺跡の正確な測定に関する最近の研究の中で、おそらく最もよく知られているものである。彼の研究は、かつてはさまざまな集団間の文化的交流がほとんどなかったと考えられていた広大な地域において、標準的な測定単位が知られていたことを示唆しているようだ。トムの示唆を整合させるには、場合によっては先史時代の概念を大幅に見直す必要がある。フレミングはこう述べる。「しかし、トムの考えを取り入れるために変更を加えたヨーロッパ先史時代のプロセスモデルは、それ自体が信憑性を損なう可能性が高い」。これはあくまで意見であり、必ずしも正しいとは限らない。幸い、トムの結論の多くは、仮に正しかったとしても、ヴェリコフスキーの結論に影響を与えないだろう。
一様性に影響を与える可能性のある提案は、天文学に関するものである。これについてフレミングは、単なる意見ではない以下の見解を述べている。「残念ながら、先史学者たちは現在、起伏のある地平線、横になった立石、発掘された深い穴、石列、石塚や古墳、説明のつかない隆起や凹凸、さらにはある事例ではおそらく近代的な直線道路に至るまで、あらゆる種類の天文学的指示とされるものに向き合わざるを得ない。立石は一般的な指針として解釈されることもあれば、精密な指標として解釈されることもある。様々な時期において、その頂部、下部、あるいは平らな側面が重要だ Significant(意味がある)と考えられる」。
フレミングは、建造者たちが太陽の動きをある程度理解していたことを示唆する粗い相関があると述べている。だが彼は続けて、鳥もまた、太陽の動きを心得ているかのような向きで巣を作ることがあると指摘する。太陽や惑星の見かけの動きに大きな変化があったとしても、そうした巣の向きには大した影響はないかもしれない。記念碑についても、同じことが言えるだろう。結局のところ、意味のある配置 Significant alignments(重要な整列)とは、それを見つけたい者の願望が生み出したものなのかもしれない。
トムのデータ THOM’S DATA
この願望はトムのいくつかの研究に見られる(30)。彼は特定の巨石構造物を用いて、建造当時の地球軸と黄道面の角度を測定できると仮定している。彼の結果は斉一説の理論曲線に合致する。しかし、この角度を測定したことが独立に確認されているデータは、理論とよく一致しない(31)。
太陽を通過し地球の軌道を含む平面は黄道面と呼ばれる。地球の自転軸はこの平面に対して垂直ではなく、垂直から約23.5度傾いている。ただし正確な角度は時間とともにわずかに変化する。斉一説の仮定に基づき、デ・シッターとニューカムはこの角度を時間の関数として計算する公式を導出した。各計算結果は紀元前1000年以前を除き同一であるが、この時期にはごくわずかな差異が生じる。
トムが古代人が測定しようとしたと推測する対象から得られたデータは、理論に完全に合致する。一方、古代人が測定したと主張する対象から得られた他のデータは理論から乖離しており、測定値と理論の差は時代を遡るほど拡大する。したがって、古代人が実際に何を測定したかを知らなければ、斉一説理論に解決策を適合させる方が容易であるように思われる。
ティティウス・ボーデの法則:記憶を助ける「法則」TITIUS-BODE: THE MNEMONIC “LAW"
ボーデの法則は、惑星と太陽のおおよその相対距離を簡単に記憶するための経験則である。一般にボーデの法則と呼ばれるが、実際には法則ではなく、ボーデによって発見されたものでもない。元々はティティウスによって発見され、より正確にはティティウス・ボーデの法則と呼ぶべきである。
この式は一般にr= 0.4 + 0.3╳2m と表される。文字 r は太陽から惑星の軌道までの距離を表し、m は惑星の順序番号を表す。m は水星の場合、予想されるように 0 や 1 から始まらず、負の無限大から始まる。水星、金星、地球、火星……に対応する順序はそれぞれ −♾️, 1, 2, 3, …… となる。距離は天文単位(AU)で表され、1AUは太陽から地球までの距離である。表Ⅰにはティティウス・ボーデの法則による予測値と実際の距離が示されている(32)。天王星の軌道を越えると、予測値と実測値が急速に乖離することがわかる。
ヴェリコフスキーに対する意義 SIGNIFICANCE TO VELIKOVSKY
シャッツマンは、多くの宇宙論的理論がボーデの式が惑星形成時(約50億年前)の太陽系の状態を反映していると仮定していると述べた(33)。この仮定は、太陽系における近年の変化説に対する反論として用いられてきた。例えば1975年、スクローワーは太陽系と惑星運動に関する数学的関係性を記述し、ヴェリコフスキーの一般理論自体は否定しないものの、太陽系の秩序が乱れたかどうかには疑問を呈した。その根拠の一つがボーデの法則が成立することである(34)。
ヴェリコフスキーの説に対する反論としてティティウス・ボーデの法則が用いられ始めたのは、早くも1951年にさかのぼる。プリンストン大学の天文学者ジョン・Q・スチュワートは、金星が太陽系形成後に現在の軌道に入ったとは考えられないと主張した。なぜならそれはボーデの法則に矛盾するからである(35)。より近年(1974年)には、バスがコロンビア大学天文学部長ロイド・モッツとの会話を記述している。「モッツ博士は、ヴェリコフスキーの仮説を受け入れられない理由の一つとして、その法則がボーデの法則と明らかに矛盾することを挙げた。ボーデの法則は1781年以降、少なくとも三つの主要な予測(天王星、ケレス、土星の第7衛星ハイペリオンの軌道)を正確に予言してきた実績があるが、金星が太陽系から除去されればこの法則は破綻するだろう」(36)。
変更を加えた法則 MODIFIED RULE
この考えから、私は内側の惑星が一つ除去されても他の変化がなければ、ティティウス・ボーデの法則の形式はどうなるのか考え始めた(最も外側の惑星が除去されたり、最後に新しい惑星が追加されたりしても、形式に変化が生じないことは明らかである)。簡単な数学的解析により、公式の一般的な形における0.3を0.6に変更すると、金星の軌道が消失する以外は全ての惑星軌道が同一に保たれることが判明した(表Ⅰ参照)。したがって、ティティウス・ボーデの法則は「原始太陽系に変化は一切生じなかった」という見解を正当に支持するものではないようだ。
これは、ティティウス・ボーデの法則がヴェリコフスキーが記述した事象の発生可能性を排除しないことを効果的に示している。しかし、この公式の背後にある物理的メカニズムの可能性を探ると、彼の理論に関連する追加情報が明らかになる。
表Ⅰ TABLE 1 (p.92)
| 惑星 | 実際の距離 | ティティウス・ボーデの法則 | 修正式 |
| 水星 | 0.39 | 0.4 | 0.4 |
| 金星 | 0.72 | 0.7 | |
| 地球 | 1.00 | 1.0 | 1.0 |
| 火星 | 1.52 | 1.6 | 1.6 |
| 小惑星 | 2.80 | 2.8 | 2.8 |
| 木星 | 5.20 | 5.2 | 5.2 |
| 土星 | 9.55 | 10.0 | 10.0 |
| 天王星 | 19.20 | 19.6 | 19.6 |
| 海王星 | 30.10 | 38.8 | 38.8 |
| 冥王星 | 39.50 | 77.2 | 77.2 |
値は天文単位(AU)で表示。第1列は太陽からの実測軌道距離。第2列は通常使用されるボーデの公式から計算した値。第3列は修正式で計算した値。
物理的メカニズム THE PHYSICAL MECHANISM
前述の通り、単純な形のティティウス・ボーデの法則は天王星以遠ではうまく適合しない。多くの研究者が様々な数学的手法を用いて式を修正し、予測値と実測値の相関を改善しようと試みてきた。ニエトはこれらの研究を詳細に論じている(37)。
これらの試みのいくつかは成功を収めている。ある方程式は、惑星の軌道だけでなく木星・土星・天王星の衛星の軌道までも正確に記述するように設計されている。しかし、その方程式がまさにその目的で開発されたのだから当然である。データに式を当てはめるための数学的解析を行えば、それが機能しても驚くべきではない。しかし、これらの曲線は現象の背後にある物理的理解を提供せず、原始太陽系の配置について何ら示唆するものではない。これが1951年にヴェリコフスキーがスチュワートへの反論の根拠とした点である(38)。
バス、オーヴェンデン、ヒルズはそれぞれ独立して調査を行い、惑星がボーデ型公式で容易に表現される分布を獲得した根本的な物理的理由を理解する手がかりを提供した。彼らの研究はまた、ティティウス・ボーデの法則がヴェリコフスキーが記述した事象の可能性を排除しないことも示唆している。
1960年ストックホルムで開催された第11回国際宇宙航行会議において、ロバート・W・バス博士はN体問題(重力相互作用する一群の天体の個々の運動を予測する問題)を解くための新たな変分原理(変分法によって物理的な問題を解けるようにする数学的手続き)に関する論文を発表した(39)。本論文の第Ⅲ部において、バスは「最小平均ポテンシャルエネルギーの原理」と呼ぶ概念を導入している(40)。太陽の重力場における惑星のように、中心力場中の天体は、相互作用が最小となる位置を獲得する傾向にあるというバスによる数学的に合理的な提案である。これらの軌道はボーデ式によって記述可能となる。
後にオーヴェンデンは、バスの研究を知らずに、直感的に次のように指摘した。すなわち、中心力(古典力学において、原点と物体を結ぶ線に沿っている方向に働く力)周りを公転する天体の系は、惑星同士が離れている時にはその配置をゆっくりと変化させ、近づいている時には速く変化するだろうと。これはヒルズとオーヴェンデンによるコンピュータ・シミュレーションで確認された。オーヴェンデンはこの結論を「最小作用の原理」と呼んで一般化した(41)。オーヴェンデンはバスが数学的に証明した内容を経験的に実証したのである。
彼らの結論は基本的に、惑星が中心力周囲の軌道に投げ込まれ、相互作用を続けながら相互作用が最小となる点に達すると、その軌道はボーデの関係式で記述できるというものだ。これはヒルズが到達した結論でもあり、彼はこの過程を「力学的緩和」と呼んでいる(42)。
この過程にどのような名称が与えられようとも、数学的・経験的証拠は、精度のために洗練されたボーデ方程式でさえ、全ての惑星が現在の軌道で形成されたことを証明しないことを示している。オーヴェンデンは特に、自身の結果が「……惑星の現在の分布は太陽系の起源に関する情報を与えない」ことを示唆すると述べている。これら三人の研究者は、ティティウス・ボーデ則の根底にある物理的過程が、惑星の形成後に惑星間相互作用が起こり得たこと、そして現在の配置がこれらの遭遇の結果である可能性を示していることを実証した。
ティティウス・ボーデ法則は無視される TITIUS-BODE IGNORED
天文学者たちは時に、ティティウス・ボーデの法則が太陽系誕生以来「何も変わっていない」ことを示していると主張し、この系が数十億年にわたり安定していたことが証明されたと主張する。しかし彼らは、ヴェリコフスキーが示唆したような軌道変化を仮定することを、この事実によって妨げられることはない。
一例が月に関する近年の見解に関連している。潮汐摩擦に関する論文でマクドナルドは、特定の情報が「地球-月システムが地質学的時間を通じて存在してきたという仮説と整合しない」と論じている(43)。シンガー※は後に「月はどこで形成されたのか?」と題する論文を発表した(44)。彼は月岩石について発見された性質の一部と、それらの性質が生じた可能性に関する先行研究の意見を言及している。その後、地球軌道内の物質の降着過程と、他の場所で降着した後に地球によって一つの天体として捕獲された物質の降着過程に関する計算を行っている。彼は「月は地球軌道内でなく、別の惑星として形成され、後に地球に捕獲されたと結論づけられる」と述べている。
キャメロンはこの概念をさらに発展させた(45)。彼は、記述された特性を持つ月が形成される自然な場所は水星の軌道内側であり、月と水星の軌道半径の相対的な差は他の隣接惑星間よりも小さいと論じる。「したがって、二天体の軌道に対する重力摂動はおそらく蓄積され、接近が起きた時点で月軌道の要素に非常に大きな変化が生じる可能性が生じる。もし修正後の月軌道が地球接近を許容するほど十分に大きければ、たとえ可能性は低くとも、地球による月の重力捕獲が実現可能となる」。キャメロンはローズとヴォーンが金星・火星・地球の軌道変化を考察したのと同じ手法による「説明的」エネルギー解析を継続している(46)。
ローズとヴォーンは、ヴェリコフスキーが記述した事象に特に関連する可能性のある軌道変化を検討した。彼らは古代の記述と従来の天体力学に合理的に適合するシナリオを計算した。彼らが仮定した軌道が過去の軌道であると主張するわけではないが、合理的な適合を得ることが可能であることを示している。
彼らの軌道体系では、火星は元々地球と太陽の間の軌道上にあった。ローズは独自にこの仮説を提唱した(47)。この独創的な提案は、惑星が存在するべき場所に関する先入観を排除し、物理的状況が最も有利な位置を決定する余地を与えた結果だった。ローズが指摘したように、この位置から金星が失った軌道角運動量の大部分を火星が獲得できたのである。
近年、多くの天文学者も太陽系の起源に関する古い仮定から思考を解放しつつある。これらの仮定は時にヴェリコフスキー説の誤りを「証明」するものとして用いられるが、最新情報によって支持されていないことがますます明らかになりつつある。
天文学者が太陽系の変化という考えに動揺しなくなっていることを示す追加的証拠は、ハリントンとヴァン・フランダーンによる1974年の論文に見られる。彼らはこう記している。「したがって予想に反し、水星がかつて金星の衛星であった可能性を示す仮説に反証は存在しない」(48)。反発は遅れているかもしれないが、少なくとも現時点では、これがボーデの法則に合致しないことに対する激しい抗議は起きていない。
かつて不可能と考えられていた軌道変化が実際に起こり得ることを示す物理的実例さえ存在する。フォキンによれば、1938年以前には木星と土星の軌道間に完全に位置していたオテルマⅢ彗星は、木星に接近した際に軌道を変化させ、火星と木星の軌道間に完全に位置するようになったという(49)。
1965年以降、その軌道は再び木星と土星の間に戻った(50)。「その運動の特異性において、オテルマⅢ彗星は今世紀発見された彗星の中でも最も注目すべき存在である」。
バスは、太陽・木星・金星程度の質量またはそれ以下の第三天体を含む三体問題において、三天体の運動は第三天体の質量に本質的に依存しないと指摘する。これは広く知られ受け入れられている。誤差を無視できる範囲では、金星より小さな質量で代用できるため、彗星のようなより小さな天体の軌道変化効果と比較することで、金星の軌道変化の可能性を導き出せるのである(51)。
ティティウス・ボーデの法則が変化を支持するために利用される TITIUS-BODE USED TO SUPPORT CHANGES
一部の天文学者がティティウス・ボーデの法則が惑星が現在の軌道で形成されたことを証明すると主張した後、他の天文学者が変化を仮定する際にこれを無視した。その後、さらに別の天文学者たちが、この法則の物理的根拠を太陽系で変化が起こったことの支持として用いた。例えば、オーヴェンデンは小惑星帯付近にかつて惑星が存在したと結論づけた(52)。この惑星は地球の約90倍の質量を持ち、約1600万年前まで存在していたと計算された。
オーヴェンデンの仮説は、米国海軍天文台のトーマス・C・ヴァン・フランダーンによってさらに裏付けられた。1976年4月にワシントンD.C.で開催されたアメリカ地球物理学連合の会議で、彼は多数の彗星の軌道に関する計算の予備結果を報告した。計算は、多くの軌道が約600万年前に小惑星帯内の一点で交差する傾向があることを示していた(ヴセフスヴィャツキーの研究とヴァン・フランダーンの研究は、彗星起源に関するオールト理論に異議を唱えている)。
オーヴェンデンは自身の理論について考慮すべきいくつかの問題を指摘した。そのうち二点は関連しており、主要な問題がヴェリコフスキーの研究に関する疑問の一つと形式的に同一である点で興味深い(第五章参照)。オーヴェンデンが指摘した問題は、惑星を解体するエネルギーの源はどこか、そして地球の質量の約90倍に相当する物質の行方はどうか、というものである。この疑問が彼の論文発表前に解決されなかったため、オーヴェンデンは排斥されず、彼の仮説は現在も公に研究されている。金星を木星から放出するのに必要なエネルギーの問題は、おそらく解決が容易だろう。
太陽系の安定性は証明されていない STABILITY OF THE SOLAR SYSTEM UNPROVEN
別の疑問は太陽系の安定性に関わる。一部の科学者は、天体力学における特定の研究が太陽系が数十億年にわたり安定しており、ヴェリコフスキーが記述したような軌道変化は不可能であることを証明していると主張する。ロバート・W・バス博士はこの問題について鋭い分析を行い、そのような見解が根拠のないものであることを実証した(53)。彼の論文には複雑な数学的記述が多数含まれるため、ここでは結論のみを概説する。詳細は原著を参照されたい。
バスはブリガム・ヤング大学の物理学・天文学教授である。彼はローズ奨学生であり、1955年に当時世界最高の天体力学の権威であった故オーレル・ウィントナーの下で博士号を取得した。その後プリンストン大学でソロモン・レフシェッツの下、非線形力学に関する3年間の博士研究員研究を行った。これは彼の分析が完璧であることを保証するものではないが、「天体力学の背景を持つ者なら誰もヴェリコフスキーの研究を検討しない」という主張を反証するものである。
バスは、多くの天文学者が「太陽系が数百万年にわたり安定していたことが厳密に証明されている」という誤解を抱く理由を検証する論文を一編執筆した。問題の一端は、彼らが実際にヴェリコフスキーを非難した行為を自ら行っていた点にある。彼らは時代遅れの資料を用い、実際に参照した資料も十分に読み込んでいなかった。
1773年、ラプラスは太陽系の安定性を示し、惑星が接近衝突したり軌道を交換したりしないことを証明したとされる定理を発表した。ポアソンはこの定理を改良し、後にラプラスはラグランジュが開発した手法を用いて安定性をさらに裏付ける別の定理を発表した。しかし、1899年のポアンカレの研究により、権威ある研究者たちはその結果がせいぜい限られた期間のみ有効であることを認識していた。そこで調査すべき問題は、安定性がどれほど長く持続し得るかとなった。ラプラスは以前、証明なしに1000万年と推測していた。
現在受け入れられ広く称賛されている一部の専門家の見解では、有効な時間間隔は数億年である。彼らの主張する根拠は、実際に計算を行った他の専門家たちによるものだ。最も頻繁に引用される専門家の一人が E. W. ブラウンである。特にブラウンとシュックの著書『惑星理論』の152ページと249ページは、太陽系の安定性を示す権威ある証拠として頻繁に引用される。コパルが近著『太陽系』で言及するブラウンは、コパル自身が「この主題について最高の権威をもって語れる」と認める人物であり、安定期間が数億年に及ぶと主張している。バスは実際のところ、彼らの著書において ブラウンとシュックは確かに「初読では誤解されかねない表現」を用いたが、精査すれば「断定的な主張とは程遠い」と指摘している。さらに読み進めると、両者は時間に関する問題を曖昧に扱い、長期安定を示唆する自らの結果を無効化する条件を認識していたことが明らかになる。
ブラウン自身、太陽系の安定期間に関する自身の推定値を大幅に下方修正した。1895年、ニューカムは1000億年と推定した。後の推定ではこれが1億年に短縮され、ブラウンはさらに100万年へと修正した。この10万倍もの変化を伴う時間枠は厳密な計算に基づくものではなく、様々な研究者が “感じ" “推定し" “考え" “想定した" 妥当な期間を反映したに過ぎない。ブラウンは共鳴現象の問題を、時間枠を短縮すべき主な理由として挙げている。
1953年、グラスゴー大学王立天文学教授 W・M・スマート博士は『天体力学』を出版。その中で彼は、ラプラス・ラグランジュ・ポアソン型の「安定性」計算はせいぜい300年の時間枠でしか信頼できないと示唆している。
萩原雄祐は、計画中の全5巻からなる天体力学論の4巻を出版している。バスは「……今後数十年にわたり、これが天体力学に関する最も網羅的で決定的な研究となることは明らかである」と記している。萩原は最高権威の一人であり、天文学者が100億年を超える時間スケールでの安定性を主張する際に最も広く引用する文献の一つが、彼による『太陽系』(カイパー編)への寄稿である。しかしバスは、これらの推定に用いられた方程式が、スマートが「1~2世紀」と期間を限定するに至った方程式と連動している点を指摘する。バスは次のように述べている。「したがって、六つの連立方程式体系は数世紀以上には有効ではない(第二近似は300年後に破綻するため、第三近似は長期間にわたって適用できないと事前に判断される)」。
バスが提示した他の考察や引用から、萩原が安定期間の推定における厳密性の欠如を認識していることは明らかである。時間間隔の問題について萩原は「現在の数学では、実際の太陽系について、この問題を満足に解答することはほとんど不可能である」と述べている。また、不変平均距離に関する自身の議論から軌道変化についての結論を導き出せないことも明らかに認めている。太陽系の安定性に関する多くの誤解は、萩原の留保的発言がしばしば見過ごされるために生じている。
バスは、数学的解析が安定性の証明に至らない理由を簡潔に検証し、「現代最高の天体力学者三人」が、現在受け入れられている天体力学ではヴェリコフスキーの仮説が不可能であると決定的に証明できないことを示唆していることを想起させる。バスはさらに、自身の検証結果が「ヴェリコフスキーの中心仮説がニュートン力学と相容れないと主張してきた天文学者たちが、客観的事実を根本的に誤解したまま研究を続けてきた証拠」を提供すると主張する。彼は結論として「誠実で献身的な学者の生涯をかけた業績は、誰もが批判的に検証できるよう全ての出典を公開している。それなのに、真の専門家がとっくに幻想として退けた時代遅れの考え方の妥当性について、単なる集団的合意に基づいて軽率に退けるべきではない」と述べている。
次に権威が「太陽系は過去も現在も永遠に安定していることが完全に証明された」と断言するのを耳にした時、その言葉にほんの少しの信仰心がにじんでいることに気づくかもしれない。そのような厳密な証明は存在せず、多くの権威がこれを認めている。
重力対電磁場 GRAVITY VERSUS ELECTROMAGNETIC FIELDS
ヴェリコフスキーは、古代人が天体接近時に地球と外部天体間で放電現象を観察していたと指摘する。両天体が同一電位ではないと結論づけるのは自然なことだった。また地球軸の傾きは、地球と他天体間の電磁的相互作用によって最も容易に説明できるとも述べた。接近遭遇に伴う他の多くの現象も電磁相互作用で説明可能である。しかし一部の天文学者は、重力では現象を説明できず電磁場は弱すぎると主張する。彼らは現在の位置にある帯電惑星について計算を行うが、これは議論の対象となる条件ではないため問題の解明にはつながらない。
ボーデの法則、軌道変化、安定性に関する議論は全て標準的な重力力学に関連していた。これは、現在の距離では重力理論が実用的なモデルであり、可能な限り多くの事象に対する第一義的な説明として用いられるべきだからである。ヴェリコフスキーが1950年に「必要とあれば、私の理論はニュートンの天体力学と整合させることができる」と記した際、この点を認識していたことは明らかである(54)。しかし同時に、彼は電磁場が太陽系の出来事において当時認められていた以上に重要な役割を果たすと理解していたことも明らかである(付録 IB参照)。例えば彼は、地球の磁場が月を超えて広がっていると示唆した。当時の天文学者はこれを不可能と見なし、メンゼルはこれをヴェリコフスキーの誤りを支持する根拠としてさえ用いた。しかしこの示唆はその後実証されている。
過去の事象における電磁場の影響は、重力に帰せられる要素と照らし合わせる必要がある。これを明確化するには、実用モデルと真のモデルを区別しなければならない。実用モデルは適用条件下では極めて正確な結果を提供するかもしれないが、実際に起きている現象を正確に記述しているとは限らず、その条件外では機能しない可能性がある。技術者や物理学者は時に「ブラックボックス」アプローチを用いる。特定の入力に対するブラックボックスの測定出力を計算する式が考案される。ボックス内の正確な回路は不明だが、特定の入力で適切な出力を得る回路は複数考案可能だ。これらの回路はいずれも実用モデルとなり得るが、いずれも箱の内容物の真のモデルであるとは限らない。
重力は、太陽系の惑星や他の天体が現在観測されている距離において、実用的なモデルである。ある質量が別の質量に及ぼす引力は、定数に両質量の積を質量間の距離の二乗で割った値に等しい(最近の研究では、これが厳密には正しくない可能性が示唆されている。長年にわたり小質量・小距離条件下で実験が実施された。その結果、100cm未満の極小距離では重力定数が距離と共に変化することが判明した。継続的な実験により、この定数が距離だけでなく質量と距離の両方に関係している可能性が示されるかもしれない。惑星質量が比較的近距離にある状態での最近の観測は行われていない。質量が小さく距離も短い条件下で予想外の結果が得られたことから、惑星半径の数倍程度の距離にある惑星質量が重力的にどのような挙動を示すか、我々は正確には把握していないと考えるのが妥当である。電磁場が加われば、古代人が観測したような近接相互作用において何が起こるか、我々が正確に理解していないことは確実である)。
多くの天体の運動は標準重力モデルによって予測可能である。これは真のモデルであることを意味せず、ましてや重力の正体を真に理解していることを示すものではない。重力は太陽系の全運動を説明できず、これは科学文献で認められている事実だ。しかし天文学者が「現距離では実用的な作業モデルであり、可能な限り使用すべき」と主張するのは正当である。
残念ながら、重力を用いた軌道計算で厳密に知られていることと、これらの計算に関する仮定が、しばしば「既知の事実」という一つのカテゴリーにまとめられてしまう。このため、重力と電磁場の重要性に関する誤解の一端は、天文学者自身にも責任がある。彼らは電磁場に要求される負荷を過大に設定し、その誤りに基づいてヴェリコフスキーが自身の理論を正当化できないと非難したのである。
1950年代の天文学者たちは、ヴェリコフスキーが記述した軌道変化の大半が既知の重力法則に完全に反すると誤って想定した。惑星間の放電現象や古代観測の特徴から、電磁場が重要であることはヴェリコフスキーにとって明らかだった。彼は当然、重力に起因しないものは他の力に起因すると結論づけた。この結論は今も正しい。ただし、1950年に天文学者が自らを説得した「重力が10%未満で電磁効果が90%超」という比率は正しくないかもしれない。おそらく主たる要因は重力であり、電磁的摂動が加わる形だろう(とはいえ、重力が経験的モデル以外の何物でもないという事実は変わらない)。
第五章
惑星と月 THE PLANETS AND MOON
ヴェリコフスキーの仮説における欠陥を指摘する際、多くの科学者は、議論されている点についてヴェリコフスキーが誤っているだけでなく、そのような事象の可能性を「真の」科学者が検討することなどありえないと示唆する。しかし1950年以降、ヴェリコフスキーが提唱した主要な考えのほぼすべてが、著名な科学者によって再提唱されている。その例の一部は既に論じたが、惑星に関連する注目すべき事例がいくつか存在する。
本論考では、理論的推測や解釈と実際の発見とを区別するよう努める。また、様々な論点に関連して提示される理論に必ずしも同意するわけではない。それらを挙げる主な目的は、専門家による議論の前後を通じてヴェリコフスキーが嘲笑された特定の仮説について、現在では権威ある研究者たちが公開された科学文献で議論している事実を示すためである。提示される説明が誤っている可能性はあるものの、こうした現象の説明として理論が提唱され続けている事実は、現在の「権威」がそれらを研究に値する対象と見なしていることを確かに示している。
異なる時期における形成 FORMATION AT DIFFERENT TIMES
1950年当時、ほとんどの科学者は全ての惑星が現在の軌道で形成されたと固く信じており、その説に異を唱えたヴェリコフスキーを嘲笑する者も多かった。しかし1960年までに、当時王立天文学会会長だった W. H. マクレアは、太陽系星雲から木星軌道より太陽に近い位置で惑星が形成された可能性はないとする理論的論証を発表した(1)。その後 J. G. ヒルズは、土星軌道外側で惑星が初期に形成された可能性はないことを示そうとした(2)。これらの論文発表の間に、後にノーベル物理学賞を受賞するハンス・アルヴェーンは、巨大惑星が「地球型(小型)惑星」より先に形成された可能性を提唱した(3)。同氏は逆の順序説も論じた。いずれにせよ、わずか数年で少なくとも三人の著名な科学者が「全ての惑星が同時に、かつ現在の軌道で形成された必要はない」と主張したのである。
もし当初、木星軌道内や土星軌道外に惑星が形成されていなかったなら、ほとんどの惑星が形成された後に大きな軌道変化が起こったに違いない。ヒルズは、現在土星軌道外にある惑星が他の惑星との遭遇によって現在の軌道にぶつかる可能性をはっきりと示唆している。この種の事象は近年理論的に説明可能となった。早くも1953年、著名な英国宇宙物理学者 R. A. リトルトンは、同僚らが少なくとも3年間「不可能」と主張してきたタイプの軌道変化を解明している(4)。
後に形成された惑星の起源 ORIGIN OF LATER PLANETS
惑星形成の時期差に加え、科学者たちは各惑星の形成過程についても様々な議論を重ねてきた。おそらく最も広く受け入れられている見解は、いずれの惑星も「降着」によって形成されたというものである。降着とは、微細な破片が小さな天体に集積し、他の天体との衝突を繰り返しながら巨大球体へと成長する過程を指す。球体が大きくなるほど重力吸引は強まり、より多くの破片を引き寄せる能力が増す。最終的に惑星規模に達する。
他の方法も議論されてきた。N. D. スヴォーロフの理論研究は1971年、惑星が太陽から個別に放出される可能性を結論づけた(5)。 前年、サルヴァジナは太陽から放出された帯電体が太陽の周回軌道を得る可能性を論じた。その後、I. P. ウィリアムズがこの提案を再検討し、サルヴァジナの電荷値の推定は過大だが、このメカニズムには依然として可能性があると結論づけた(6)。
歴史的証拠は、少なくとも一つの惑星がこの方法で形成されなかった可能性を示唆している。ヴェリコフスキーは、古代人が金星が人類の記憶の範囲内で木星から噴出したと教えたと指摘している。1950年、『衝突する宇宙』の多くの批判者は、特に歴史時代においてそのような事象が起こり得るとの考えを嘲笑した。しかし一部の資格を持つ科学者たちは、ヴェリコフスキーを支持するためではなく、単に過去に何が起こり得たかを調査する過程において、そのような可能性を検討している。
1961年、リトルトンは自身の結論として「地球型惑星は巨大惑星から噴出したに違いない」(7)
と発表した。彼は、特定の条件下では木星の現在の軌道付近で形成された巨大惑星が、蓄積した物質の角運動量を保存する結果として非常に高速で回転すると述べた。質量が増すにつれ回転は加速し、最終的に不安定化して「二つの非常に不均等な破片」へと分裂せざるを得なくなるという。
多くの宇宙論者は、太陽系の主要な出来事が数億年あるいは数十億年前に起こったと仮定したがる。しかしリトルトンの理論によれば、巨大惑星の起源から経過した時間が長いほど、分裂する可能性は高まる。
形成エネルギー ENERGY FOR FORMATION
非常に高い回転速度は、木星から大きな天体を放出するのに必要なエネルギーの大部分、あるいは全てを供給しうる。木星の質量は地球の約318倍、半径は地球の11倍強である。したがって、木星が「数時間で」回転するというのは印象的だ。あれほどの質量があれほどの面積に広がり、あれほどの速さで回転するというのは不可能に思える。しかし実際には、木星は「10時間弱」で回転している。これが測定値でなければ、10時間という周期も同様に不可能に聞こえただろう。
多くの天文学者や物理学者が、金星を木星から放り出すのに必要なエネルギーを計算してきた。その過程で、彼らの大半は初級物理学の授業では落第点となるような誤りを犯している(8)。しかし、そうした重大な誤りは答えにわずかな差しか生じない。必要な修正と精緻化を加えても、エネルギー量は依然として約1040エルグに達する。これは膨大なエネルギーだ(スヴォーロフの理論も同様に膨大なエネルギーを必要とする)。
ヴェリコフスキーは、古代人の記録によれば、土星と木星はかつて接近衝突を起こしたと記している。この事象は木星による巨大天体の放出とも関連していたようだ。ヴェリコフスキーは、もしこれらの古代の観測が正しいならば、金星を木星から放り出すのに必要なエネルギーは、接近遭遇時の土星の影響力によって相殺されるはずだと指摘している。
人々は、この放出エネルギーを太陽から1年間に受け取るエネルギーや、同じエネルギーで自転車で赤道を何周できるかという数値と比較したがる。あたかも「そんな膨大なエネルギーはありえない」と言わんばかりに。実際、こうした指摘はエネルギーが得られないことを示すものではなく、単に「確かに膨大な量である」と強調しているに過ぎない。
もし今日午後5時に太陽系でこれほどのエネルギーを伴う突発的事象が発生すれば、6時のニュースには即席の説明が用意され、3週間後には学術誌に理論論文が大量に発表されるだろう。
宇宙には短時間で1040エルグを超えるエネルギーを必要とする事象に関する理論が数多く存在する。その一部は、対象現象が観測される以前から存在していた。しかし大半は地球から遠く離れた場所で発生する。こうした事象はすべて「はるか昔、はるか遠くで起きた」と位置付けさえすれば、いかなる規模の事象についても立派に理論化できるという原則に沿っている。
おそらくリトルトンの推測は、木星に関する他の近年の見解とも矛盾しない。木星が質量を蓄積し角運動量を保存するため回転速度を上げた際、重力増加により半径が縮小した可能性がある。この半径縮小は、スケーターが腕を体に寄せると回転速度が上がるのと同じ原理で、自転速度をさらに加速させるだろう。
重力収縮による木星半径の継続的・現在進行的な減少は、複数の研究者によって検討されてきた。パイオニア10号の観測結果に関する論文でマクドノーは、同探査機が木星が太陽から受けるエネルギーよりも多くのエネルギーを放出していることを確認したと述べている。彼はさらに「この放射の源は主要な理論的問題である」と付記している(9)。スモルホフスキーは以前、一部の理論家がこの放射を木星の重力収縮(年間約1ミリメートル)で説明できると考えることを指摘した(10)。リトルトンの理論と同様に、この現象は時間の経過とともに木星の自転速度を増加させるだろう。
後に形成された惑星の密度 DENSITIES OF LATER PLANETS
平均密度が極めて低い木星が、なぜ全て平均密度が高い地球型惑星を生み出したのか? 木星の平均密度は1.334グラム/立方センチメートルであるのに対し、内惑星全体の平均密度は5グラム/立方センチメートルに近い。
この疑問への答えは、ほぼ「平均密度」という用語の定義に関わる問題である。これは、地球の平均密度が5.52g/cm³であるのに対し、水の平均密度がわずか1.0g/cm³であるにもかかわらず、なぜ地球上に大量の水が存在すると予想されるのかを問うことに類似している。しかし実際には、状況はこれよりもやや複雑である。木星の理論モデルの中には、木星中心部付近の高圧なしでは高密度を維持できない物質の核の存在を否定するものもある。しかし岩石質核を必要とするモデルも存在する。
木星の正確なモデルを決定することが、異なる平均密度に関する疑問の解明に役立つはずである。1965年以前は、ヘスとミードによれば、木星と土星のほとんどのモデルは「それらが完全に冷たい惑星であるという仮定に基づいていた」(11)。この仮定により、ヴェリコフスキーへの反論は容易になった。1974年、アンダーソンは、木星と土星の正確なモデルを構築する上での主な問題は、それらが太陽から受け取るエネルギーよりも多くのエネルギーを放出しているという事実だと指摘した(12)。
1974年以前にもこの複雑な問題は存在していたが、それまでは木星の「固体水素コア」モデルが主流だった。この非岩石コアモデルでは、木星が内部の一部を放出することで平均密度の高い惑星を形成したことを想像することは困難だった。しかし、1972年に A. H. クックは「全ての惑星が地球と類似の組成を持つ核を持ち、その周囲を異なる種類のマントル(地球型惑星はケイ酸塩、木星・土星・天王星・海王星は主に水素)が取り囲むことが可能である」との結論を発表した(13)。この構造が正しければ、リトルトンの内惑星形成理論とヴェリコフスキーの金星起源説の両方がより説得力を持つことになる。
かつて NASAの研究センターで、木星の固体水素核モデルを支持する研究に従事する数名の研究者にクックの論文について触れたことがある。彼らは自分たちが正しいモデルに取り組んでいると主張した。クックの論文を読んだかと尋ねると、彼らはそれまでその存在すら知らなかったと答えた。しかし彼らは、自らの説が正しいという前提のもと、クックが間違いだと確信していた。ヴェリコフスキーの研究が主要な話題でなかったなら、彼らのアプローチはもう少し科学的だったに違いない(※ヴェリコフスキーの研究が議論の中心だったために、彼らのアプローチが科学的でなくなってしまったことを暗に批判している)。どちらの理論が正しい方向にあるかは、しばらくの間はわからないかもしれない。いずれかのモデルが実際に確認されるまでは、平均密度に基づく反論は、ヴェリコフスキーの研究に対してほとんど説得力を持たないだろう(密度問題が存在しないという考えをさらに裏付けるものとして、ラルフ・ジョーガンズによる『クロノスⅡ』第1号(1976年)掲載の論文を参照のこと)。
惑星の特徴 CHARACTERISTICS OF THE PLANETS
1950年当時、様々な惑星には特定の「既知」の特徴があると考えられていた。ヴェリコフスキーは、これらの特徴の多くが『衝突する宇宙』で記述された出来事が実際に起こった場合に予想されるものと一致しないことに気づいた。そこで彼は、それらの出来事と整合する惑星の特徴をいくつか仮定し、これらの提案は「事前の主張 advance claims」として知られるようになった。
ヴェリコフスキーによるこれらの「事前の主張」は、数学的解析や物理理論の結果ではない。また、時折示唆されるような超能力やその他の手品的技法によって導かれた予測でもない(「予測」という言葉は科学的議論で頻繁に使用されるが、一部の科学者はヴェリコフスキーに関連して使用する際、超自然的なニュアンスを与えようとしてきた。おそらくこれが、彼が「事前の主張」という表現を好む理由である)。
ヴェリコフスキーの事前の(前もってなされた)主張は、古代人が記述した出来事が実際に起きた場合、今日の太陽系で何が発見されるべきかを考察した結果である。数学的能力や機転は全く関係がない。結論は演繹的推論によって導かれた。したがって、ヴェリコフスキーが数学物理学の学位を持たないという理由でこれらの主張を無視するのは愚かなことだ。
木星 JUPITER
1950年当時、木星は冷たく死んだ惑星と考えられていた。1961年になってもなお、木星の温度が理論値より高い可能性を示唆する観測結果を多くの研究者が軽視し、「測定の不備」や「特定量の誤った推定」によるものだと主張していた(14)。1964年になっても、アシモフはノンフィクションを意図した著作の中で、木星は表面を温めるのに十分な熱を発生せず、そこにある暖かさはすべて太陽放射によるものだと記していた(15)。
※ちなみに、アイザック・アシモフは「ヴェリコフスキーの説が正しいと証明されたら、私は喜んで自分が間違っていたと認めるだろう。そして地獄でスケートもするつもりだ。その頃には地獄も凍りついているだろうからな」(ロバート・W・バスへの私信、1974年8月23日)と記していました。
電波ノイズ RADIO NOISE
しかしヴェリコフスキーは、木星は既存理論が示すよりも活発であるはずであり、実際にこの巨大惑星は電波ノイズを放出していることが判明するだろうと主張した。木星のこれらの特徴は、いずれも確認されている。
木星からの電波ノイズは、アインシュタインとヴェリコフスキーが何度も議論したテーマである。アインシュタインは、宇宙には磁場やプラズマは存在せず、したがって木星が電波を放出する理由はないと確信していた。ほとんどの天文学者もこの見解を共有しており、木星からの電波ノイズの可能性を検証する試みは行われなかった。
しかし、1955年、バークとフランクリンが木星からの電波ノイズを発見した。F. グラハム・スミスが電波天文学に関する著書で述べているように、「幸運な偶然がなければ、木星の電波フラッシュについては何も知られていなかったかもしれない」のである(16)。アインシュタインはこの発見に非常に感銘を受け、ヴェリコフスキーが他の調査を行うのを支援することを申し出た。しかし、それは遅すぎた。アインシュタインは翌週、亡くなってしまった。彼の机の上には『衝突する宇宙』が置かれていた(17)。
ダブルデイ社の編集者が電波ノイズの発見者に手紙を書き、ヴェリコフスキーがそのような結果を予測していたことを伝えた。そのうちの一人は、ヴェリコフスキーでさえ、たまには「ニアミス」を許されるだろうと返事を書いた(18)。
現在、木星からの電波放射に関する著名な権威であるジェームズ・ワーウィック博士(※ボイジャー 1 号および 2 号惑星電波天文学装置の主任研究者)は、より寛大である。彼はヴェリコフスキーの予測を正当なものと認めつつも、同時にこの予測に対する彼の功績を認めさせる試みは一切しないと述べている。この行動(あるいは不作為)は、過去および現在の出来事を踏まえると理解できるものである。
ワーウィックはまた、注目すべき提案に対して十分な評価を得られていないのはヴェリコフスキーだけではないと指摘している。これは科学界を擁護するものではなく、単なる事実の表明である(19)。
赤斑 RED SPOT
もし木星が巨大な天体を放出したならば、惑星に構造的欠陥が残されたと合理的に推測される。ヴェリコフスキーは、木星の最も顕著な特徴の一つである赤斑が、金星が放出された傷跡に関連する大気現象であると示唆している。
ハイドは、赤斑が木星構造の異常の結果であり、この擾乱が大気上層の厚い雲層に現れていると示唆している(20)。彼はその後「テイラー柱(※コリオリの力の結果として生じる流体力学の現象)」の観点からこの説明を拡張し、この考えをさらに支持する実験を行った(21)。しかし最近の探査機データは、表面異常を必要としない解釈がなされている。
生命 LIFE
1973年のNASA記者会見で、セーガンはヴェリコフスキーが「はっきりと」木星の大気中にカエルが存在すると予言したと偽りの話を流布した。セーガンがヴェリコフスキーの著作を倫理的に検証した上で、どうしてこの結論に至ったのか理解に苦しむ。
ヴェリコフスキーが実際にカエルについて記したのは、金星接近時に「地球内部で発生した熱と彗星の灼熱ガス自体が、地球の害虫を猛烈な速度で繁殖させるのに十分だった。カエルの災い(「地はカエルを産み出した」)やイナゴの災いといった一部の災いは、そうした原因に帰せざるを得ない(22)。(強調は筆者)
ただし彼は、古代の伝承ゆえに疑問が生じるとも記している。すなわち金星が害虫を地球に蔓延させたのか否か ─ それは金星の尾状大気中に運ばれた可能性もある。彼はこれを事実ではなく考察すべき問題として提示している。他の惑星の環境が地球と大きく異なる以上、「地球と同じ生命形態が存在するとは信じがたい。一方で、生命が全く存在しないと結論づけるのは誤りである」と強調する(23)。
「地球への幼虫汚染というこの仮説に真実があるかどうかは誰にもわからない。多くの小型昆虫とその幼虫が極寒や酷暑に耐え、酸素のない大気中で生き延びる能力は、金星(そして金星が起源である木星も)が害虫に侵されているかもしれないという仮説を、全くあり得ないこととは言い切れないものとしている」(24)。
ヴェリコフスキーは、他の惑星に生命が存在するという仮説を最初に提唱した者ではないと述べているが、明らかに最後でもなかった。近年の惑星探査機には生命探知を目的とした実験装置が搭載されており、地球上でも他の惑星における生命の可能性を評価するための実験が行われている。特にコッホは、一部の地球生物が木星の大気圏で生存可能だと結論づける実験を実施している(25)。
金星 VENUS
1946年という早い時期に、ヴェリコフスキーは金星に関する三つの予測を検証のために提示した。いずれも『衝突する宇宙』で記述された出来事が実際に起こった場合、驚くべきことではない特性に関するものだったが、太陽系の起源と進化に関する斉一説的概念に基づけば、いずれも予想されるものではなかった(26)。これらの予測は、金星の自転、温度、雲の組成に関連していた。
自転 ROTATION
太陽系の平面より北側から見た場合、反時計回りに自転する惑星は順行回転(prograde rotation, or direct rotation)と呼ばれる。太陽系星雲からほぼ同時期に同様の過程で全ての惑星が形成されたという概念は、全ての惑星が同じ方向に自転し、自転軸の傾きもほぼ同じであるべきだと示唆する。これはあまりにも論理的に思えるため、そのような条件が存在しないことを述べるのはほとんど申し訳なく感じられるほどである。
地球と火星の軸傾斜は約23度であり、他のいくつかの惑星の軸傾斜も大きく異なるわけではないため、これは長い間標準と考えられてきた。木星の3度の傾斜は斉一説の要件を満たすのに十分近いと考えられていた。しかし天王星は90度を超える傾斜により逆行回転を示すため、悪い基準点と見なされた。それでも、ほとんどの科学者はこれを無視できると考えていた。なぜなら、セーガンが主張したように、これは逆行回転の「例外的な事例」と見なせるからである(27)。
したがって1950年当時、惑星は一様性の概念に適合し、金星も例外ではないと考えられていた。金星は順行回転を持つとされ、初期の研究者たちはその傾斜角を23度近くと推定していた。ただしカイパーによる研究では最大32度の傾斜角が示されていた(28)。しかしヴェリコフスキーは、金星が他の惑星との最近の激しい相互作用により異常な回転を示す可能性を指摘した。
宇宙探査機のデータと地上レーダー観測により、金星の自転特性が斉一説と明らかに矛盾することが確認された。傾斜角はほぼ0度であり、自転は順方向ではなく逆方向、つまり金星は「逆回転」している。
この後者の発見後、いくつかの破局的な性質を持つ説明を含む多くの試みが発表された。セーガンは潮汐摩擦を原因としたが、裏付けとなる証拠は提示しなかった(29)。シンガーは、逆行軌道を持つ衛星が金星とほぼ衝突し、金星の自転を(斉一説理論によれば)本来持っていたはずの順方向から逆方向に反転させたと提案した(30)。太陽系には逆行衛星軌道が存在するが、それらは既存理論では説明が困難である。シンガーは逆行衛星の起源については、逆行衛星問題に関心を持つ研究者に委ね、金星の逆行自転のみを説明しようとしている。
いくつかの証拠は金星の自転がさらに特異な異常性を示す可能性を示唆しているが、これは依然として議論の的である。金星は地球と太陽の間を通過するたびに、常に同じ面を地球に向けているように見える。この現象がどの程度正確に当てはまるかは、どの測定結果を採用するかによって異なる。当時マサチューセッツ工科大学地球惑星科学科に所属していたルイスは1971年に「金星に対する太陽の潮汐力が地球の約104倍大きいにもかかわらず、金星の自転が地球に同期しているメカニズムは全く不明である」と述べた(31)。コパルは地球と金星の同期メカニズムを「不明瞭」と呼んだ(32)。ゴールドスタインは次のように述べている。「こうして我々は金星の自転に関する二つの異常、すなわち逆行方向と地球との少なくとも近似的な同期性を考察せざるを得ない」(33)。慎重な「近似的」という表現を用いた理由は、地球との同期周期が 243.16日であるのに対し、彼の観測誤差範囲では金星の自転周期が 242.6±0.6日と推定されたためである。
バスは「非線形共鳴振動子は、軌道的に安定した形で共鳴に固定され、その後の摂動によってわずかに乱されるだけである」と指摘している(34)。この現象が、地球が金星とより強い重力相互作用を持っていた時代に遡る場合、その後の火星による両天体への接近は、この結合を破るのに十分な影響力を持たなかった可能性がある。
一方ローズは、火星-金星相互作用が、火星-金星および火星-地球相互作用以前に遡る地球-金星結合を消去した可能性が高いと考える(35)。もしそうなら、この現象が実際に存在するとしても、ヴェリコフスキーが記述した事象とは無関係かもしれない。
太陽系内の複数の天体が示す準共鳴状態は、太陽系が数十億年にわたり安定化してきたという仮定を支持する斉一説の根拠として用いられてきた。ローズは、ほとんどの天体について様々な共鳴状態を区別するには測定精度が不十分であると指摘した。彼は次のように述べている。「事実として、ほぼあらゆる想定可能な出来事が、何らかの共鳴状態に比較的近い」(36)。また彼は「多数の準共鳴状態の存在は、太陽系が歴史的時代において劇的な再編成を経験していない証拠とはなりえない」とも説得力を持って論じた。
この問題の結論がどうであれ、金星の自転を斉一説に無理に当てはめることが困難であることは明らかである。
温度 TEMPERATURE
1952年、ハロルド・ユーリーは地球と金星の歴史は「非常に類似しているはずだ」と記した(37)。この見解に基づき、当時広く受け入れられていた金星の性質に関する多くの見解は不合理ではなかった。金星の平均地表温度は地球よりわずかに高い程度で、大気は主に窒素で構成されていると考えられていた。雲は水蒸気で構成されていると考えられ、メンゼルとウィップルはこの考えをさらに発展させ、金星の表面は水で覆われているはずだとさえ示唆した(38)(分光研究では水の証拠が全く得られていなかったにもかかわらず、データは誤解を招く可能性があると再び主張された)。
1940年、ワイルドは金星表面温度が摂氏135度に達する可能性を予測した(39)。カイパーは1952年時点で入手可能なデータを用いてこの推定値を再評価し、熱帯地域の日中表面温度を摂氏77度と算出した。これは金星全体の平均表面温度が約摂氏マイナス23度であることを示唆していた(40)。
ヴェリコフスキーは、既知の値よりはるかに高い温度が観測されると予想していた。彼の研究によれば、「金星は誕生と激しい環境下での放出を短期間で経験し」、その後、地球と火星の両方との接近遭遇を経験したという。「これら全てが紀元前3000年紀から1000年紀の間に起こったため……」、金星には冷却される十分な時間がなかった。ヴェリコフスキーはまた、金星は大気中の石油を蒸発させるほど高温のままである可能性があると述べた。彼の著書からは、金星が地球よりわずかに暖かいだけだと予想していたわけではないことが明らかである。その後、金星は地球よりかなり高温であることが判明している。
実際、1950年時点で入手可能なデータはこの結論を支持していた。しかし、情報を既存理論に適合させようとする試みの中で、混乱を招く解釈がなされた。
データの解釈は科学において普遍的な作業であり、有用かつ必要である。しかし事実の取得と正しい説明の間には大きな隔たりがある。メンゼルとウィップルが誤っていた事実自体が、彼らの研究を非科学的とするわけではない。あらゆる科学者はいずれかの時点でデータを誤解釈する。これらのデータに関連する不幸な出来事は、ヴェリコフスキーが示唆したため合理的な解釈が無視された点にある。彼がこの代替説を提示した際、非科学的であるとか「事実」を認めないなどと非難された。実際には、彼は単に事実の「公式解釈」に異議を唱えていただけである。
1950年まで、金星の熱に関する二つの基本観測は、実際の雲頂温度測定と自転速度に関する間接的証拠に基づいていた。惑星の暗部からかなりの熱が放射されていることが判明した。金星の明るい部分は暗い側よりそれほど高温には見えなかった。もし惑星の自転が遅いなら、太陽光の当たる側は暗い側より高温であるべきだ。したがって、金星は暗部が再び太陽で加熱される前に冷却される時間がないほど高速で回転しているに違いないと、一部の人々は示唆した。
しかしこの情報は、金星の回転速度が遅いことを示すデータと矛盾しているように見えた。
金星の切れ目のない雲の層は途切れることがなく、地表を観察することは不可能である。地球から見た金星円盤の反対側にあるポイントの半径方向速度を分光法で測定したところ、この方法では測定できないほど回転速度が遅いことが示された。これはおそらく20日以上の公転周期を意味していた。もし金星の自転周期が地球の1日に匹敵するなら、金星は極部が平坦化しているはずである。しかし金星の精密な測定結果からは扁平性は認められず、この点からも金星の自転は非常に遅いと考えられた。この見解はその後確認されている。
矛盾が生じた。金星の夜側が冷却されないことから、回転速度は速いはずだと主張する者もいれば、遅いはずだと主張する者もいた(1959年になっても、米空軍のための研究において、ショーとボブロヴニコフは、暗部と明部の双方がほぼ同量の熱放射を発するため、金星の自転周期は数週間以内であるに違いないという主張を繰り返した)。各説に支持者が存在し、1950年当時この議論が続いていた中でヴェリコフスキーは「矛盾は存在しない。金星は確かにゆっくり回転しているが、それは極めて高温であるためだ」と主張した(41)。
ヴェリコフスキーの提案は、熱の発生原因がどう説明されようと論理的だった。論理的であるだけでなく、後に正しいと判明した。この事実が明らかになると、反対派は「ヴェリコフスキーが正確な温度を特定しなかった」と反論した。彼らは「高温」は相対的な表現であり、彼ら自身も金星が地球より高温であると予想していたため「高温」と表現していたと主張した。しかし、これまで議論してきたことから明らかなように、論争の双方は当初から自らの立場を明確にしており、金星が極端に高温であると予想した天文学者は一人もいなかった。もしそのような天文学者がいたならば、彼は回転と温度に関するデータ間の明らかな矛盾を、ヴェリコフスキーが提示した合理的(そして後に正しいと証明された)解決策を容易に受け入れたはずである。
マイクロ波観測が最初に示唆したのは、金星の表面温度が高いという事実であり、これは現在では宇宙探査機によって確認されている。現在の推定では約750ケルビンである(42)。斉一説の概念に適合する説明が必要とされたため、1960年にセーガンはワイルドの温室効果説を再提唱した(43)。セーガンは温室効果を成立させるために金星に必要な水蒸気量を推定した。1963年、モロズは2~2.5マイクロメートル帯域における金星の反射スペクトルを分析し、この分析結果が「水蒸気に起因する温室効果の概念と矛盾する」と結論付けた(44)。
他の多くの科学者も温室効果説に異議を唱え、金星の環境条件が効果的な温室メカニズムに必要な条件を満たしておらず、予測される温度が金星で実際に観測される温度ほど高くないことを実証した。検討すべき他の理論はヴェリコフスキーの説のみだったため、「暴走型」あるいは「増強型」温室効果理論が提唱された(45)。その正確な物理的要因は説明不可能だったが、科学者たちはそれでも金星の高い表面温度を説明する唯一の理論であると確信した。
雲 CLOUDS
ヴェリコフスキーは、金星と地球の接近が地球に炭化水素を残したならば、その炭化水素の源はおそらく金星であると推論した。金星はまだ誕生時の熱をすべて失っていないため、その炭化水素は依然として気体状態にあり得る。したがって、金星の雲の一部は少なくとも部分的に炭化水素で構成されている可能性がある。金星に関する彼の諸説の中で、ヴェリコフスキーはこの説を最も示唆に富む可能性があると見なしていた。しかし、金星に関する彼の諸説の中で最も議論されてきたにもかかわらず、これまで最も示唆に富む結果は人間の本性に関するものだった。
この問題は重要ではあるが、一部の科学者が人々に信じ込ませているように、ヴェリコフスキーは自身の理論全体をこの結果に依存させてはいない。これは、彼が記述した出来事が実際に起こった場合、金星で合理的に発見される可能性のあるものについての、また別の示唆に過ぎなかった。それは仮定として表現された:「この研究に基づき、金星には石油ガスが豊富に存在すると推測する」(46)。また彼は(1950年に)こう述べている。特定分光技術が開発されれば「金星の分光図は、大気上層部(太陽光が到達する領域)に炭化水素ガスが存在することを明らかにするかもしれない」(もし第四章で述べたオロとハンの研究が正しい方向性を示しているなら、炭化水素は金星固有のものではなく、大気相互作用によって生じた可能性もある。この場合、金星上の炭化水素の豊富さはヴェリコフスキーが当初予想したほどではないかもしれない)。
何事にも文句を言う者は必ずいる。ゆえに、ヴェリコフスキーがこの考えを仮説として述べたことを非難する者もいる。しかし、仮説を事実と称するよりも、仮説を「仮説」と呼ぶ方が論理的であるように思われる。
1955年、ホイルは金星に炭化水素が豊富に存在する可能性を推測した。多くの科学者はこれを非現実的と反論したが、彼の論理展開を追う試みは行った(48)。おそらくこれはあらゆる可能性を網羅する試みだった。金星で炭化水素が発見されればホイルが正しかったことになり、発見されなければヴェリコフスキーが誤っていたことになる。いずれにせよ「科学」は一様性を維持したのである。
金星の大気は主に二酸化炭素で構成されている。しかしこれは雲についてほとんど何も教えてくれない。金星の大気中に二酸化炭素を検出したからといって雲に炭化水素が含まれないと言うのは、地球の大気が主に窒素で構成されているからといって地球の雲が水蒸気ではないと言うようなものだ。
金星の雲はかつて、水氷または水蒸気で構成されていると固く信じられていた。これは金星と地球の類似性が想定されていたことも一因である。いくつかの相違点が明らかになった後も、氷理論は生き残り、最終的に「証明された」と見なされるようになった。セーガンはかつて「……金星の雲が実際に水でできていることは最近になって確立された」と記している(49)。
「確立する」とは安定させる、確固たるものとする、確認する、証明する、検証する、立証することを意味するが、「権威によって制定または布告する」という意味もある。明らかにヴェリコフスキー研究者たちだけが、セーガンが後者の定義に過度に依存することがあると信じているわけではない。彼の決定の後、金星の雲に関する他のいくつかのモデルが生まれたからだ。そのうちの二つが塩酸モデルと亜酸化炭素モデルだった。その後、ハンセンとアーキングは証拠を再検証し、これらのモデルが完全に排除されたわけではないものの、いずれの妥当性もさほど高くないと判断した。彼らは雲の組成に関する新たな調査が必要であると示唆した(50)。また屈折率から純水が排除される点についても言及しており、これはヴェリコフスキーが以前に指摘していたことである(51)。
新たな研究としてハプケが「汚れた塩酸モデル」を提唱した(52)。リアは上層雲が塩酸溶液である可能性を再確認した(53)。また、こうした雲が胃への刺激を引き起こす可能性があるため、炭酸水素塩を含んでいるのではないかという説も提案された(54)。
※ブルース・ハプケが1972年に提唱した「汚れた塩酸モデル」によれば、金星の雲の粒子は、主に溶解性および不溶性の鉄化合物を含む塩酸 (HCl) で構成されたマイクロメートル サイズのエアロゾルであり、その発生源は火山または地殻の塵である可能性が高いとされている。
1969年、当時マサチューセッツ大学物理学・天文学科のウィリアム・プラマー博士(現ポラロイド社上級科学者)は『サイエンス』誌に報告書を発表し、上層雲が氷粒子で構成されているという説を支持する証拠が依然として存在すると結論づけた。同記事でプラマーは、ヴェリコフスキーが先行して示した主張の一部は正しかったと寛大に認めつつも、炭化水素に関する彼の説は誤りと証明されたと述べた。
ヴェリコフスキーはプラマーへの反論を提出したが、『サイエンス』誌は掲載を拒否した。理由は複数の査読者が金星大気の酸化特性に関するヴェリコフスキーの記述に異議を唱えたためとされた。しかし、その記述はプラマー論文掲載の翌週に『サイエンス』誌に掲載されていた(酸化させる下層大気という概念は、最近プリンストン大学のロッソウによって再提唱されている(56))。ヴェリコフスキーの反論は後に『ペンセ』誌にプラマーの論文と共に掲載された(57)。
ヴェリコフスキーは、プラマーの論証が結論に至っていないことをいくつかの理由から示した。第一に、炭化水素に関する調査は、ヴェリコフスキーの主張について三つの誤った前提に基づいていた。すなわち、彼が凝縮した炭化水素を想定していたこと、それらを雲の唯一の構成要素と見なしていたこと、そして炭化水素が上層雲を形成していたことである。しかし、『衝突する宇宙』におけるヴェリコフスキーの当初の記述は、彼が必ずしも唯一の構成要素ではなく、上層に存在しない可能性もある気化した炭化水素を提案していたことを明確にしている。
第二に、プラマーによる近赤外域(波長2.4マイクロメートル)の議論は関連データを網羅しておらず、ヴェリコフスキーが引用したデータの一部はプラマーの結論を修正するものだった。ヴェリコフスキーはまた、前年にポラックとセーガンでさえ金星スペクトルの1~3マイクロメートル域は明確な組成で解釈できないと記していた点を指摘している。
第三に、雲が氷の結晶であるとするプラマーの結論は、雲の屈折率が氷よりも高いという証拠と矛盾する。しかし、いくつかの炭化水素は観測された屈折率を示している。水の氷では黄色がかった色を説明できないが、この色は炭化水素で計算可能である。最後に、雲の上層大気における水蒸気の低含有量は、氷理論と相容れないように思われる。
プラマー論文の再版とヴェリコフスキーの反論を掲載した『ペンセ』誌には、アルバート・バーグシュターラー博士による金星雲に関する全証拠の検証論文(1973年8月号)も収録されていた。彼は、測定された雲の屈折率が 0.55マイクロメートルで約1.45であることを指摘した。これは水(1.33)や氷(1.31)には高すぎる値である。この値は塩酸溶液モデルとも矛盾し、さらに金星大気スペクトルの 9.5~11.2マイクロメートル領域に見られる吸収帯の説明にも失敗している。バーグシュターラーは、他のいくつかの提案された雲の構成要素もこれらの条件を満たしていないことを指摘した。
バーグシュターラーは、当時主流だった「上層雲層が約75%の硫酸で構成される」という見解が最も正しい可能性が高いと結論付けた。この理論は G. T. シルによって提唱され、1973年に A. T. ヤングによって発展させたものである。屈折率は一致し、7~11.5マイクロン領域のスペクトル特性もかなり良く一致していた。
バーグシュターラーの論文に続き、ヴェリコフスキーが論争を検証した論文を発表した。ヴェリコフスキーはバーグシュターラー論文からの引用で構成された表を掲載。バーグシュターラーが扱った様々な主題の下に、炭化水素と硫酸に関する言及を表形式でまとめた。各列は炭化水素に帰属し得る証拠を引用していた。一方、硫酸ではスペクトルの紫外線領域における特定の特徴や、近赤外領域の特徴のいずれも説明できなかった。当時の通説を代表するレビュー記事であるバーグシュターラーの論文は、金星に炭化水素が存在しないことを「証明」しているとされる。しかしそれは証明に失敗しているばかりか、むしろ上層雲が硫酸で構成されていないことをより説得力を持って証明している。
翌年2月の AAAS会議で、セーガンはヴェリコフスキーのバーグシュターラーへの反論を読んだが感銘を受けなかったと述べた。セーガンは依然として雲が硫酸で構成されているという見解を支持していた(どうやら雲が水であるという見解はもはや「確立された」とは考えていなかったようだ)。しかし翌年、バーグシュターラーが硫酸モデルの開発者の一人として言及した A. T. ヤングが再び金星雲の物理化学的性質を検討し、こう記した:「金星の雲現象に関する現在主流の解釈はいずれも、全データと整合しない」。観測証拠のかなりの部分が誤っているか、誤解釈されているか、あるいは金星の雲は現在の単純化されたモデルよりもはるかに複雑であるかのいずれかである」。また、「雲の確かな理解は、まだ数年先のことのようだ」(58)。
この見解を持つ科学者はヤングだけではないようだ。1975年4月11日、王立天文学会は王立気象学会および地質学会と合同会議を開催し、金星と水星に関するマリナー10号の観測結果を議論した。参加者の一人(ハント)が雲頂層における硫酸の可能性について言及したものの、地表に近い層の物質が何かは明らかに未知であることが示された(59)。
炭化水素の存在については依然として議論が続いている。しかし、副次的な論点の一つは、金星の下層大気における石油火災の可能性について言及したヴェリコフスキーが指摘したように、そのような火災は副産物として水を発生させ、その後、水は上層大気中で分解され、水素の一部が逃げていくというものである。したがって、ヴェリコフスキーは、金星の上層大気中に遊離酸素が存在するはずだと主張した。
これに対しセーガンは「地上分光観測で明らかに示されている通り、存在しない」と反論した(60)。翌月、『サイエンス』誌はマリナー10号の探査結果を掲載。ある報告には「データは金星上層大気中に水素、ヘリウム、炭素、酸素原子が著しく濃縮されていることを示した」と記されていた(61)。酸素の起源については議論の余地があり、これはヴェリコフスキー説を支持する根拠として言及されているわけではない。これは単に、セーガンが誤っていたもうひとつの例に過ぎない。
セーガンが誤った仮定を繰り返し支持し、それを事実として主張する姿勢は、科学を進歩させようとする誤った試みと解釈することも可能だろう。しかし、彼が反対理論について虚偽を捏造し、それを永続させていることを考えると、彼が念頭に置いている進歩は科学的というより個人的なものだと信じる方が容易である。
外観 APPEARANCE
ロシアの探査機は最近、金星への軟着陸に成功し、地表の写真撮影を行った。これらの画像には、鋭利な縁を持つ岩石が確認されており、それらは「若々しい外観を呈するもの」として分類された。ヴェネラ9号および10号によって撮影された地表は、若々しい様相を示しており、これにより金星が「濃密な大気による温室効果の進行によって窒息しつつある最終段階ではなく、進化の初期冷却段階にある」とする仮説が提起された(強調引用)。この見解に基づき、進化的尺度において金星は「若く、なお生命的活動を有する惑星群」に分類されるべきであると示唆された(62)。
(ネイチャー誌の記事で、セーガンは「侵食がほとんど起きていないはずだから、岩石は若く見えるべきだ」と述べた(63)。また、古く見える可能性のある岩石の侵食に関する説明案を示し、若く見え実際に若い岩石の起源についても記述している。彼が扱わなかった唯一のケースは、古い岩石が侵食されて若く見える場合である。可能な限り多くのケースを考慮することは賢明だが、多様な可能性の中から一つを選ぶことは、若く見える岩石が若くないという証拠にはならない)。
1968年、ジャストロウとラスールは金星が理論上は地球と多くの類似点を持つが、実際には著しく異なる惑星であると指摘した(64)。同年、ノーベル賞受賞者リビーは「地球と金星は、大きさと平均密度が非常に似ているため、組成も似ており、したがって火山活動の歴史も似ているかもしれないという考えを、私たちは非常に渋々ながら放棄すべきである」と主張した(65)。しかし、両者の歴史が同時に始まらなかった可能性を過度に渋るべきではない。書籍には地球初期の歴史における条件や出来事についての推測が満ちている一方で、私たちはたった一軌道先にある、地球初期の条件の実験室例を無視してきたのかもしれない。
火星 MARS
火星は少なくとも金星と一回、さらに地球-月系とは数回の大規模な遭遇を経験している。火星は金星や地球よりかなり小さいため、 火星にはこれらの接近に起因する特殊な地表特徴が存在すべきである。ヴェリコフスキーは特定の可能性の高い特徴を具体的に論じたが、彼のモデルでは合理的でありながらはっきりと言及されなかった火星の特性も存在する。これらの特性の一部は斉一説的概念では容易に説明できない。
角運動量とリニアメント ANGULAR MOMENTUM AND LINEAMENTS
角運動量とは、物体の質量とその質量分布と、その物体の自転速度との関係である。1974年のAAAS会議において、太陽系の長く安定した歴史を裏付ける追加的証拠として、J. D. マルホランドは「質量の関数としての角運動量の滑らかな連続性がほぼ全ての惑星に満たされている……(そして)これは全システムの形成にのみ関連付けられる……」と述べた(66)。これは事実として提示された意見である。現在の文献を検証すると、この滑らかな関数は、滑らかに見せるために特定の情報が意図的に排除されている場合にのみ成立することが明らかである。マルホランドでさえ、水星・金星・月・火星が理論に順応するほど「思いやり」がなかったことを認めている。コロンボは、水星や月、木星のいくつかの衛星が奇妙な角運動量を持つ一方で、金星と火星の挙動ははるかに説明が困難だと指摘している(67)。
長距離にわたって直線的な傾向を示す地表の亀裂はリニアメント(線構造、断層などの、表面に現れた直線的な構造)と呼ばれる。マリーナー4号が撮影した火星写真の分析により、明瞭なリニアメント・システムが明らかになった。初期の火星探査機が送り返したわずか8枚のフレームに、約160本のリニアメントが確認できる。バインダーはこう述べている。「これらのリニアメントの存在は、火星がその歴史の中でかなりの角運動量を失ったことを示唆しているかもしれない」(68)。後にフィッシュはこう指摘した。「火星が減速した可能性のある手段は問題となる」(69)。
マリナー6号と7号はリニアメントの追加的証拠を提供した。マリナー4号のデータとは対照的に、これらの後続写真には容易に識別可能なリニアメントが多数含まれていた。バインダーとマッカーシーは、これらのデータが「リニアメントが体系的・優先的な傾向を持つ地表構造の実在要素の表現であることを実証している」と述べている。これらの構造は月や地球でも見られ、三天体すべてにおいて自転軸に対して同様の向きを示している。バインダーは、これらすべてが回転角運動量の損失に起因する可能性を示唆している。さらに彼は、火星における損失は火星とその衛星フォボス・ダイモス、あるいは太陽との潮汐相互作用では説明できず、他のメカニズムを探る必要があると指摘している。
運河 CANALS
これらのリニアメントは地上望遠鏡では小さすぎて観測できず、いわゆる火星の「運河」と混同すべきではない。スキアパレッリは1877年と1879年、火星の各地を横切る多数の細く暗い直線状の構造を発見したと発表した。彼はこれらを「カナーリ canali(水路)」と呼び、1881年にはその多くが鉄道の複線のように二重化する場合があると報告した。1892年と1894年にはピッカリングとダグラスも火星の運河canals を報告している。その後、運河の存在に疑問が生じ始めた。極端な例がローウェルで、彼は火星の赤みがかった領域と暗い領域の両方に、幾何学的な正確さで広がる400本以上の複雑な運河の拡張を目撃したと主張した。反対の極端な立場にはバーナードがいた。彼は当時最高峰の望遠鏡を用いて長年にわたり観測を続けたが、幾何学的な細い線からなるそのようなシステムの痕跡は一切確認できなかった。ただし時折、短く拡散したかすかな線や、長くぼんやりとした平行な流れをいくつか観察したことはあった。両者の間には、いくつかの運河とかすかな線を目撃した観測者たちも存在した。これらの報告は全て、良好な観測条件下で火星を長期間にわたり注意深く研究した、訓練を受けた経験豊富な観測者たちの熟考を経た判断である。しかし、彼らの相反する解釈が全て正しいはずはない。科学界は「運河」論争の時期を「アメリカ科学にとって恥ずべき時代……」と呼んでいる(71)。
多くの人々は「運河」を火星における絶滅した、あるいは現存する高等生命体の証拠と見なしたがっていた。この見解は一般向け記事で頻繁に言及されたものの、1950年までに大半の真剣な研究者はもはやこれを最も合理的な解釈とは考えていなかった。ヴェリコフスキーもこの見解に同調した。彼は、火星が金星の2割未満の大きさであるため、金星と火星の接近は火星により大きな破壊をもたらしたはずだと論じた。『衝突する宇宙』の中で、火星に「運河」が存在するとすれば、それは知性ある存在によって造られたものではなく、「衝突時に作用する外力に対して地質学的力が亀裂や裂け目として応答した結果」であると記している(72)。16年後、オピックはこう述べた。「運河は衝突物質の衝撃点から放射状に広がる地殻の亀裂である可能性がある」(73)。
表面の傷 SURFACE BLEMISHES
他の惑星の接近も火星表面に大きな擾乱をもたらすと予想される。ヴェリコフスキーは火星に巨大な山脈が存在するとはっきりとは示唆しなかったが、興味深いことに彼の研究に反対する者たちはまさにその反対を明確に主張していた。ローウェルは火星に750メートルを超える山は存在しないと推定していた(74)。後にローウェル天文台の天文学者スリファーは、特定の観測が「……火星に高い山が存在せず、地表が驚くほど平坦であることを決定的に証明している」(75) と述べた(「高い」という言葉の使用に注意。「熱い」よりも確かな表現なのか? ヴェリコフスキーの「熱い」と同様、他の入手可能な情報を考慮すれば、下限を示す何らかの手がかりが読み取れた)。
ゴールドスタインによる後のレーダー調査では、火星の峰と谷の間に13,000メートルの高低差が存在することが示された(76)。またマリナー9号の火星写真は、高さ約24,000メートルの「超巨大火山」を捉えている。その基底部の幅は約500キロメートル(310マイル)、頂部の幅は65キロメートル(24マイル)に及ぶ。しかしスリファーが火星表面の形態を不正確に判断した点では、彼も決して孤立した存在ではなかった。『スカイ・アンド・テレスコープ』誌によれば、セーガンとポラックが推測した火星表面の起伏は「実際の火星地形とは全く相関していない」という(77)。
再びヴェリコフスキーは火星の火山発見をはっきりとは予測していなかったが、彼が火星の近現代史について記述した状況を考えると、その存在は驚くべきことではない。また、今日に至るまで火星で活動が続いていることも不思議ではなく、マリナー9号のデータは「風化と火山活動が火星でかなりの程度進行している」ことを示している(78)。これは斉一説では予期されていなかった。
『現代天文学』編集者デール・R・ハンキンは記す。「1950年代から1960年代初頭に至るまで、火星に火山活動が存在する可能性を提唱した者たちは、天文学界の “変わり者" 扱いされた」。彼はさらに、過去100年間の火星観測記録には、火星の火山活動を示唆する証拠が容易に解釈できる形で含まれていると述べている。こうした研究の多くはアマチュアによって行われたため、専門家はそれを無視することを好んだ。それは斉一説と容易に一致しなかったからである。しかし、専門家が真剣に火星を研究した際には、アマチュアと同じ観測結果を得たのである(79)。
熱 HEAT
一部の科学者は、ヴェリコフスキーが火星が太陽から受ける熱よりも多くの熱を放出することが発見されると予測したと主張している。彼らはさらに、火星が平衡温度にあることが「知られている」以上、彼の理論は間違っているに違いないと主張する。
第一に、ヴェリコフスキーはそんな予測をしていない。第二に、彼の理論全体がこの一点に依存しているわけではない。第三に、火星が実際に平衡状態にあるかどうかは疑問である。
『衝突する宇宙』においてヴェリコフスキーは、火星が太陽から受ける熱量よりも多くの熱を放出していることを示す特定の天文観測結果に言及した。もし火星が実際に現在の軌道で数十億年にわたり平穏な状態にあったならば、このような現象は予想されない。しかし彼は、もし観測結果が正しいならば、火星は最近の接近遭遇時に膨大な熱を獲得したため、今も過剰な熱を放射し続けているに違いないと推論した。これは予測ではなく、報告された観測結果に対する単なる説明の提案だった。
より新しいデータは、火星が太陽から受ける熱量よりも多くの熱を放出している可能性を示唆する一方、他の測定値は逆の結果を示している。残念ながら、火星は平衡点に十分近く、この問題を解決するには測定精度が不十分であるようだ。この問題を説明するために、火星の平衡温度が正確に-46℃であると仮定しよう(80)。実際の温度が-45℃または-44℃であれば、火星は太陽から受ける熱量よりも多くの熱を放出していることになる。しかし、測定値は数度程度の誤差を超えることは稀で、時には±30度もの誤差が生じることもある(81)。したがって、火星が熱平衡状態にあることを示すとされる測定結果は、実際には平衡状態に近いことを示すに過ぎない。もし数十億年にわたり火星に何の変化も起きていなければ、その平衡温度に達していると考えるのは合理的だが、大まかな測定値で火星が数十億年間変化していないことを証明することはできない。
火星で深度プローブによる調査が可能になれば、火星から熱が流出していることが判明しても驚くべきことではない。
赤い RED
火星の赤みを帯びた大気は、褐鉄鉱と呼ばれる酸化鉄が原因かもしれない。バインダーは、この鉱物は現在の火星環境下では形成不可能であり、過去に異なる条件が存在したはずだと述べる。おそらく赤い惑星はこの特徴を、紅海の名前の由来となったのと同じ過程で獲得したのだろう(『衝突する宇宙』参照)。
ドルフスは赤色物質が褐鉄鉱であると提唱した。シャロノフも火星の大部分が褐鉄鉱の微粒子からなるシルト(沈泥)で覆われていることに同意した。彼はさらに「火星表面に広範囲に存在する褐鉄鉱シルトの大量堆積自体が、説明を必要とする状況である」と指摘している(84)。モロズは火星スペクトルの0.4~4ミクロン領域を分析し、データが褐鉄鉱の反射スペクトルと一致すると結論付けた(85)。バインダーとクルックシャンクも赤外線分析を実施し、この示唆を支持した(86)。フィッシュは、特定の偏光研究が火星表面物質の相当部分が褐鉄鉱であることを示唆していると述べている(87)。後年、バインダーは塵が褐鉄鉱である可能性を認めた(これはバイキング着陸船によって裏付けられている)が、現在の火星大気では形成不可能だと繰り返し主張した。彼は大気が過去に異なっていたに違いないと結論づけた(88)。
火星の大気は過去に異なっていた可能性が高いが、褐鉄鉱は元々火星で形成されたものではないかもしれない。
アルゴン ARGON
1946年、ヴェリコフスキーは火星の大気に大量のアルゴンとネオンが含まれている可能性を示唆した。この基本的な提言は『衝突する宇宙』でも繰り返された。1974年まで、これは「ヴェリコフスキーが間違っている証拠」として広く利用された。その後、ソ連の火星探査機が火星大気に「数十パーセント」のアルゴンが存在し得ると示唆した。後にカプランは、二酸化炭素線の圧力拡がりからアルゴンの存在が推測できると述べた(89)。また、レバインとリーグラーは、放射性崩壊によるアルゴン生成に関するハリソン・ブラウンの仮説を再考し、この方法によって火星大気中に最大28パーセントのアルゴンが生成され得ると主張した。さらに注目すべきは、ロシア人天文学者モロズが赤外線・紫外線分光観測と火星大気その他の測定値を統合分析し、「これら全てのデータは火星大気中のアルゴン含有率が 25~35%であることを示唆する」と結論付けた点である。これらは全て、火星大気にアルゴンが存在すると予想する根拠はないと 20年以上主張されてきた後に生じた現象であった。
一部の科学者がこの説に根拠がないと主張する一方で、他の科学者たちは同じ説を提唱していた。ハリソン・ブラウンは、カリウムの放射性崩壊によるアルゴン生成と関連付け、大気中のアルゴン含有量について論じた。彼は「火星の場合、アルゴンが大気主成分である可能性は十分にある」(91) と述べている。
火星の大気中にアルゴンが大量に存在するという考えを繰り返し主張する者もいたが、この説は広く受け入れられなかった。1952年、ユーリーは「火星にはアルゴンと窒素からなる相当量の大気がある」と述べた(92)。出典が明記されていないため、これが彼の推測なのか、あるいはヴェリコフスキーやブラウンの後期の研究を読んだ結果なのか判断が難しい(ユーリーが「相当量」をどう定義したかは不明である。また、その「相当量の大気」においてアルゴンが主要成分なのか、あるいは窒素が主要成分でアルゴンが微量成分なのかも判然としない。こうした主張をする人物が、ヴェリコフスキーの正確な計算や数値推定の欠如を批判しているのは皮肉である)
ソ連の測定結果によれば、火星の極域には高濃度のアルゴンが存在し、他の地域では希薄化が起きている可能性がある。バイキング1号の測定値では、その地点のアルゴン濃度は1~2%を示した。これが火星大気の平均濃度なのか、それともソ連の測定が正確で、この地点が希薄化領域の一つなのかは現時点で不明である。
ヴェリコフスキーは火星のアルゴン起源について論じていない。彼は単に、火星に元々存在したアルゴンの一部が地球と月によって除去された可能性を示唆したに過ぎない。近年、一部の科学者は理論上、火星の大気には1~2%以上のアルゴンが存在すべきだと提唱している。現在存在しないとしても、数千年前までは存在していた可能性がある(火星の大気に関する詳細は『クロノスⅡ』第1号、1976年、p.105を参照のこと)。
※ 火星大気の具体的な組成は、二酸化炭素が約95%、窒素が約3%、アルゴンが約1.6%を占め、その他に酸素、一酸化炭素、水、メタンなどが微量に含まれている
生命 LIFE
火星の生命に関する推測は長年流行してきた。ヴェリコフスキーはこの領域に踏み込むことはなかったが、仮に生命が存在する場合、それが必ずしも火星固有のものではないことは明らかである。
実験は火星生命の可能性を支持している。1963年、この問題を調査した実験者らは、火星に複雑な生物が存在し得ると結論付けた。彼らは「高等植物の成長を抑制するには非常に高いレベルの紫外線放射が必要である」と指摘した事例もある」(93)。 (実験ではアルゴンを非常に高濃度に含む気体混合物を使用した)。1965年、アベルソンは火星における生物起源の合成は極めて起こり得ないと結論付けた(94)。火星起源でない生命が存在しないことは、火星に生命が存在しないことを意味しない。
フォボスとダイモス PHOBOS AND DEIMOS
火星にはフォボスとダイモスの二つの衛星がある。ヴェリコフスキーは、これらの衛星の公転周期が、望遠鏡で観測される以前に書かれた架空の物語に記載された周期と極めて近いことに注目した。彼は、その作者ジョナサン・スウィフトが古代文献の情報を含む書物にアクセスしていた可能性があり、一部の古代人が実際の観測から周期を決定したかもしれないと示唆した。このデータは、火星が金星とその長い尾によって損傷を受けた後、火星が地球に接近した際に得られたものと考えられる。
マリナーとバイキングの撮影データは、これらの衛星が不規則な形状でクレーターだらけの天体であることを明らかにした。特異な物質で構成されているようには見えないが、1966年にセーガンは人工衛星である可能性は「真剣な検討に値する」と述べた(95)。疑いなく、ヴェリコフスキーによる太陽系の近現代史に関する綿密な研究は、宇宙人に関する空想的な推測よりも常に真剣な検討に値するものだった。
フォボスを撮影したバイキング軌道船の写真には、画像に映る衛星の領域の半分以上にわたって顕著な縞模様が確認される。縞模様の原因は不明だが、ジェット推進研究所の研究員が様々な可能性を推測している。提案された原因の二つは、フォボスが破片の雲を通過したことと、何らかの古代の大災害でフォボスの大部分が分離したことである(96)。
水星 MERCURY
未発表の著作において、ヴェリコフスキーは紀元前1500年以前の出来事を記述している。当時の物語は後世のものより断片的で曖昧であるため、実際に何が起きたかについてはより多くの理論が展開されている。このためヴェリコフスキーは、『衝突する宇宙』で示された考え方がより十分に検証された後に、この著作を出版することを決めた。しかし彼の結論は、研究者ごとに全く異なる見解が生まれるほど曖昧な資料に基づくものではない。他の研究者たちも独立して同様の結論に到達している(97)。
水星は紀元前1500年以前のこれらの出来事のいくつかに関与していた。この分野が議論の余地を広げつつあるため、水星の特性について触れておく。
人類がこうした性質の一つを理解するに至った歴史は、科学者たちが特定の結論について互いに合意しても、その結論が依然として誤り得ることを示している。
軌道 ORBIT
ヴェリコフスキーは水星が地球の近年の大災害的出来事に関与していたと考えるため、当然ながら水星が現在の軌道に就いたのはごく最近のことだと結論づけている。この説の真偽は永遠に証明されないかもしれないが、近年(1975年)に天文学者たちも水星が本来の軌道にない可能性を示唆した事実を改めて強調する価値がある(第四章)。これらの研究者たちはおそらく水星が現在の軌道を最近獲得したとは考えていないが、バスが示したように、軌道変化に通常必要とされる長い時間軸は疑問の余地がある。
回転 SPIN
水星は88日で太陽を公転する。1965年以前、水星の自転周期も88日と考えられていた。これは水星に共鳴軌道を与え、惑星の片側が常に太陽に向く状態となる。月も同様の状況にあり、常に同じ面を地球に向けている。水星についても前世紀から同様の説が提唱されていた。スキアパレッリ(スキャパレリ)が88日の周期を結論づけたのがその起源である。
惑星表面は写真に写り、地形の識別点も存在する。この88日の自転周期は斉一説の概念に合致し、公式に認められたため、後の写真研究もこの結果を裏付けるように見えた。しかし最近のレーダー調査により、水星の自転周期は実際には約58.65日であることが判明した。その後、写真証拠が再解釈され、驚くべきことに分析結果は58.65日周期を裏付けるものとなった(98)。
また、88日という値は分析に使用された方程式の解の一つに過ぎないことが突然判明した。これまで無視されていた別の解が58.65日の周期に適合する。
非対称クレーター形成 ASYMMETRIC CRATERING
水星に関するもう一つの驚くべき観察結果(ただしヴェリコフスキーの説と全く矛盾しない)は、この惑星の表面特徴が半球ごとに不均一に分布していることである。この証拠から、月・火星・水星はいずれもクレーターと溶岩流で覆われた半球を併せ持つことが明らかになった。これは惑星間の接近遭遇説とよく符合する。ただし、月の非対称性は地球との軌道共鳴に起因するとされるため、この事実は月に関する理論の再評価を必要とするとの指摘もある(99)。
熱 HEAT
ヴェリコフスキーは、水星が過去に他の惑星と接近遭遇したため、その際に何らかの加熱を受けた可能性を指摘した。もし周囲環境との熱平衡に達する時間が十分でなかった場合、夜側は予想外に高温であるかもしれない。これまでの観測結果は決定的ではない。仮に水星が最近、他の惑星と接近遭遇したとしても、加熱がごくわずかだったため、余剰熱を急速に放射した可能性がある。仮に接近遭遇による残留熱が存在するとしても、現在の測定精度ではそれを明らかにするには不十分かもしれない。
大気 ATMOSPHERE
ヴェリコフスキーの水星に関する提唱で、確認されたと思われるのは水星に大気があるという説である。斉一説の観点からは予想外だった。火星よりもさらに小さい水星には、大気を保持するのに十分な質量がないからだ。しかしマリナー10号のデータは、水星に大気が存在することを示している。極めて希薄ではあるが、予想以上に厚い。興味深いことに、水星に大気を予測したのはヴェリコフスキーだけではなかった。マリナー10号の結果以前に、多くのアマチュア天文学者が水星の大気を報告していた。しかし彼らはアマチュアに過ぎず物理学を理解できないとみなされたため、「理論上」大気は存在し得ないと説明されたのである。非専門家の観測者が大気と考えたものは、理論を理解する者たちによって「錯覚」と呼ばれた。
この大気の存在については、その後数多くの場当たり的な説明が現れた。水星に大気があるという最初のマリナー報告は1974年初頭に出され、間もなく『ネイチャー』誌が大気の存在に関する理論的説明を発表した(100)。著者は水星に希薄な大気が存在し、主に水素で構成されていると結論づけた。さらに「放射能によって放出されたヘリウムやアルゴンは、この大気に閉じ込められ、検出されるはずだ」とも述べた。
こうしてわずか数週間のうちに、水星は「大気を保持し得ない」(101)
という証明された結論から、大気の観測と、その存在を説明する立派な理論的根拠へと移行した。
太陽の電荷による影響 EFFECT FROM CHARGE ON THE SUN
1952年、メンゼルはヴェリコフスキーの提唱の一部が成立するには、太陽表面に1019ボルトの電位差を生じさせるほどの過剰電荷が必要だと計算した。本論考において、メンゼルの主張が正しかったかは重要ではない(102)。重要なのは、メンゼルが「太陽にこれほどの電荷が存在することは不可能」と断言し、まともな物理学者がそのような主張をすることはないと示唆した点である。他の研究者も、太陽にこれほどの電荷があれば水星の軌道が劇的に影響を受けると述べている。
1960年、オーストラリアの物理学者ベイリーは、恒星が正味の負電荷を持つと仮定することでいくつかの天文学的現象が説明可能だと主張した。さらに彼は、太陽表面電位が約1019ボルトに達するほどの電荷が存在し得ると計算した。ベイリーはメンゼルの研究やヴェリコフスキー論争を知らなかった。両者が同一の数値を得たのは偶然である。しかしメンゼルは、自身の研究や他の米国人科学者によるヴェリコフスキー批判の妨げとなるとして、ベイリーに理論の撤回を要求した(103)。
ベイリーは、反ヴェリコフスキー勢力に迎合するためだけに自身の理論を放棄するよう求められることを快く思わなかった。ベイリーは、自身の理論を検証する実験を行うために予定していた米国訪問の前に死去した。後に、ベイリーの研究に精通していたバーマンは、この規模の太陽電荷が水星の近日点運動にどのような影響を与えるかを考察した。彼は、この量の電荷では有意な影響はないと結論づけた(104)。
月 THE MOON
月は地球に近接しているため、ヴェリコフスキーが『衝突する宇宙』で記述した過去の破局的出来事にも関与していた。古代人の観測は、月が金星と火星の両方の通過の影響を受けた可能性を示唆している。ヴェリコフスキーは、古代人が実際に観察した事象を正確に再構築したと確信し、月面に見られるこれらの遭遇の証拠に関する多くの提案を行った。
これらの提言はすべて、人類初の月面着陸以前に、そして多くは月への有人飛行が真剣に検討される以前になされたものである(105)。ヴェリコフスキーは、月岩石に残留磁気が検出され、内部から地表への測定可能な熱流出があり、月物質に過剰なアルゴンが存在するはずだと主張した。追加の観察事項には、特定の年代測定法による年代測定結果、地表に形成された気泡、月震、炭化物の痕跡、局所的な放射能領域が含まれていた。これらの各アイデアは、地球の天然衛星に関する当時の通説に反するものだった。
残留磁気 REMANENT MAGNETISM
残留磁場とは、外部磁場によって岩石材料に誘導され、外部磁場が弱まったり除去された後も残留する磁場である。溶融岩石の温度がキュリー温度を下回り、かつ岩石が外部磁場中に存在する時、磁場によって整列した特定の分子が固定される(強磁性体がキュリー温度と呼ばれる臨界温度以上に加熱されると、磁気配列が乱れ常磁性状態となる。常磁性率により粒子は外部磁場が存在する場合にはそれに沿って配列され、キュリー温度以下に冷却されると、この乱れた磁場の影響として新たな強磁性秩序が固定される。鉄のキュリー温度は1043 Kである)。冷却がキュリー温度に達した後、外部磁場を完全に除去しても、凍結された磁性はほぼ永久に保持される。したがって、適切な測定により、冷却時の外部磁場の方向と強度を示す手がかりが得られる。
初の有人月面着陸の数ヶ月前、ネイチャー誌は「月岩石に残留磁気が存在しない」とする記事を発表した(106)。ヴェリコフスキーは反対の見解を持っていた。彼は、月が歴史時代およびそれ以前に大災害に巻き込まれた場合、溶融した岩石の一部が磁場に浸されたままキュリー温度以下まで冷却されたはずだと考えた。したがって、彼は岩石試料の月面の方位基準に対する向きを記すよう提案した。しかし、これは実施されなかった。なぜなら、当時の定説では残留磁性は予想されていなかったからである。
月面から地球に初めて持ち帰られた岩石に残留磁気が発見された時、研究者たちは非常に驚いた。この現象の起源については様々な理論が提唱された。それらは、月の内部磁場、過去における月と地球の接近、輸送宇宙船内の磁場、実験室内の磁場といった仮説に基づいていた(107)。最終的に、この磁性は月固有のものであり、月面から採取後の環境や岩石の取り扱いによる人工的なものではないと結論づけられた。
ノーベル賞受賞者で地球化学者のハロルド・ユーリー宛ての手紙で、ヴェリコフスキーの友人たちは、彼がこのような発見を予期していたと述べた。ユーリーは返答で、従来の科学者たちはヴェリコフスキーが示唆したすべてのことを予期していたと述べた(108)。
ユーリーの発言は他の科学者たちの見解と矛盾し、彼自身の後の発言とも食い違う。1973年5月、ユーリーは E. K. ランコーンとの共著論文で「アポロ計画における最も予想外の発見の一つは、回収された結晶質岩と角礫岩の双方が安定した残留磁場を保持していることである」と記している(109)。
月の磁気に関する見解の変化を扱った無署名のネイチャー誌記事(1974年)では、フラーによるこの主題のレビューが言及されている。同記事では、フラーが指摘するように「有人月面着陸以前、月は一般的に『磁気的に興味の湧かない』存在と見なされていた」と述べるのは「歴史的に見て極めて正しい」と記されている。さらに、着陸前の10年間に行われたほとんどの測定は月が磁気的に不活性であることを示しており、これは「惑星体の磁気的性質全般、特に月の性質に関する先入観と完全に一致する結果」だったと回想されている(110)。
1973年に第4回月科学会議が開催された時点でも、この問題は依然として存在していた。ある報告書は次のように述べている。「しかし、月岩石がどのようにして磁化されるに至ったかは、容易に説明できるものではない」。そして後段で「この磁場(この場合、残留磁気を生み出すために必要とされる磁場を指す)の存在を合理的に説明することは非常に困難である」と記している(111)。
月の磁場起源の説明には、しばしばダイナモ理論が引用される。これは地球の現在の磁場を説明するのと同じ理論である。専門家でさえ、ダイナモ過程が適切に説明されているとは一致していないことを念頭に置くべきである。したがって、「月が地球と同様の方法で内部磁場を生成していたなら」といったダイナモ理論に関する記述を読む際には、地球の磁場生成メカニズムすら我々が真に理解していない事実を念頭に置くべきである。しかしこの理論を援用した結果でさえ、「月の残留磁化を説明する上で月ダイナモ説は成立し得ない」との指摘がなされている(112)。
1976年にはゴールドとソーターが、月岩石の磁性は月への衝突によって生じたとさえ提案した(113)。水星と火星の磁場も同様の衝突に起因するとされた。
最終的な説明が何であれ、ヴェリコフスキーの理論以外では一般的に予想されなかった事象の説明に、膨大な量の紙が費やされてきた。
温度勾配 THERMAL GRADIENT
歴史時代に月が受けた宇宙的暴力のため、ヴェリコフスキーは内部から地表へ強い熱流が今も続いていると示唆した。これは一般的見解ではなかったが、宇宙からのロシアの測定結果がこの可能性を示唆していた(114)。ユーリーは、これも誰もが予想していることだと主張したが、よく言えば大げさになる傾向があった(115)。月研究によって現在では無効と判明しているユーリー自身の月の起源説は、現在では月の研究によって無効であることが示されているが、これも必ずしもこのことを示しているわけではない。一部の理論家は、内部放射能によるわずかな熱流を予想していたが、測定された熱流は、このプロセスからさえ予想されるよりもはるかに大きい。
アルゴン ARGON
ヴェリコフスキーの研究は、アルゴンが火星の大気の重要な構成要素である可能性を示唆した(火星大気中のアルゴンについては、KRONOS誌第1巻第3号、1975年秋号、88-90頁を参照のこと)。この結論が正しいと仮定すれば、彼は月の火星との相互作用が月に過剰な量のアルゴンを残した可能性があり、これがカリウム-アルゴン法で年代測定された試料に異常に高い年代をもたらすと推論した。
実際、この問題は月面試料に関してまさに生じた。その後ほぼ忘れ去られたが、研究者らは当初「予想外の」過剰なアルゴンに衝撃を受けた。
初の有人月面着陸は1969年7月だった。同年9月までに、アルゴンが月面における最終主要活動の年代測定に問題を引き起こしていることを示す報告が既に公表されていた。角礫岩と微粒子が極めて大量の希ガスを含んでいることが判明した。「カリウム-アルゴン(K-Ar)年代測定法で決定された年代は、本質的にも実験的にも不確実である」と認められた(116)。
その後、タイプC角礫岩と指定された試料に関連して、「この物質は36Arと40Arの両方を非常に大量に含有しており、結果として試料の現実的な年代を算出することが不可能だった……」と指摘された(117)。「あきれるほどに高い」(70億年超)K-Ar年代に関する所見が公表された(118)。
やがて月に関する新たな謎、アルゴン40の起源が認識されるに至った。一部の証拠は、希ガスが「土壌フラグメントにおいて表面と相関しているように見える」ことを示唆していた ─ すなわち、特定の試料において表面積と体積の比率が大きいほど、その総質量に対するアルゴンの「過剰量」も大きくなるという現象である。
これらの吸収、閉じ込められたガスの起源として最も可能性が高いのは太陽風または太陽宇宙線と提案された。しかし同時に「試料中の元素比が太陽値から著しく異なる場合がある」ことも指摘された。ファンクハウザーらは次のように述べている。「土壌と角礫岩中に検出された大量の希ガスは、これほどの量のガスを供給する他の源が知られていないことから、太陽大気が月土壌に閉じ込められていることを示唆している」(119)。したがって、その組成は誤っていたものの、他に思いつかないので太陽風だということになった。
しかし太陽風理論は短命に終わった。1970年7月までに、太陽風は月面における希ガスの過剰量を説明する上で、単なる補助的な説明材料に過ぎなくなっていた。科学者たちは、アルゴン40が月内部でのカリウム崩壊の結果であるという説に傾きつつあった。アルゴン40は拡散して外へ漏れ出し、希薄な月大気中へ逃げた後、太陽風粒子との衝突力によって土壌へ押し戻されたと考えられていた。
測定結果によれば、希薄な月大気中のアルゴン40濃度は変動する。捕獲されたアルゴン40の一部が月 “大気" 由来のガスであることは認められている。しかし月面上のアルゴン40の大部分の起源については、依然として議論の余地がある。注目すべきは「(⁴⁰Ar/³⁶Ar)比が、古代の月大気では現在よりもアルゴン40が豊富だったことを示唆するような変動を示す」点である(120)。
過去にアルゴン40がより豊富だったというこの示唆は、ヴェリコフスキーによる太陽系の近現代史の再構築と一致する。
月の年齢 AGE OF THE MOON
ヴェリコフスキーはそれぞれを正確に予測していたにもかかわらず、先に述べた月の特徴が個々に無視されているように見えるかもしれない。しかし、月齢に関連する他の月データの解釈のせいで、それらはまとめて無視されているのである。
従来の考え方によれば、数十億年にわたり月では重要な変化は起きていない。したがって、ヴェリコフスキーが予測した個々の月の発見がどれほど多くあろうと、それらがたとえ驚くべき特徴であっても、最近になって得られたものではないと結論づける者もいる。
この結論には疑問を呈する二つの点がある。第一に、月の年齢と、そこで最後に何かが起こった時期がしばしば混同されている。第二に、年代測定法とその結果の解釈が揺るぎない正確さを有すると仮定されている。後述するように、放射性年代測定の基本前提を再評価すべき十分な根拠が存在する。
ヴェリコフスキーは月の実際の年齢について推測を試みたことはない。二つの公認年代測定法(ウラン-鉛法とルビジウム-ストロンチウム法)が月の年齢(正確か否かは別として)を示している。さらに第三の方法(カリウム-アルゴン法)も、ほぼ同じ「年代」を示している。この方法は、月で最後に大災害が起きた時期を特定できるとされる。したがって、これらの年代測定法の結果は、少なくとも35億年もの間、月に何の変化も起きていないという三つの独立した証拠として誤って解釈されているのである。
(19世紀、偉大なケルビン卿は「地球の年齢について三つの論拠を持っていた。第一の論拠は太陽の推定年齢に基づくもの、第二は地球が溶融状態から現在の温度まで冷却するのに要した時間に基づくもの、第三は月の長期的な加速とそれに伴う潮汐摩擦による地球自転の減速に基づくものだった。これら三つの方法はいずれも証明されていない仮定と非常に不安定な推定値を用いていた。それにもかかわらず、それらは都合よく合意された地球の年齢について一致していた」(強調は筆者)。多くの著名な科学者たちが、自らの数値をケルビンが提示した「公認」値と一致させるべく懸命に努力した。そして「たとえ “ごまかし" のケースでなかったとしても、異なる疑わしい手法を用いる様々な科学者たちが、同じ誤った結果を導き出すには、なお多くの活発な想像力を要したのである」)(121)。
月面年代測定に最も一般的に用いられる手法は、ウラン-鉛、ルビジウム-ストロンチウム、カリウム-アルゴン比の測定である。しかし、最後の手法のみが、試料が最後に加熱または衝撃を受けた時点からの時間の推定値を提供する。加熱や衝撃が発生した場合、崩壊生成物であるアルゴンがすべて逃げてしまい、放射性年代測定器がリセットされ、ゼロに戻される可能性がある。
逆に、後からアルゴンが追加されると、試料はより古いように見える。この問題は地球でも遭遇している。わずか数百年の既知年代を持つ物質に対し、数百万年という仮説上の年代が「発見」されてきた(122)。ヨークは、月の過剰なアルゴンがカリウム-アルゴン法を「複雑化」させたことを認めつつも、「補正」係数が正しいと仮定すれば、三つの手法はいずれもほぼ同等の年代を示すと主張している(123)。
前述の理由により、月における最後の災害以降の経過時間を測定する方法は一つしか存在せず、この方法が信頼されるのは、月の年齢を測定するとされる他の二つの方法と類似の結果を示すからに過ぎない。残念ながら、放射性年代測定に共通する問題に加え、他の二つの方法もカリウム-アルゴン法で言及された問題と同様の固有の問題を抱えている。
対象元素の存在比が変化すると、異なる年代が示される。この変化は、一方の元素の他方に対する存在量を減少または増加させることで引き起こされる。例えば試料を加熱すると、一方の元素の一部が気化して環境中に逃げる可能性がある。
ウランと鉛を含む試料を鉛が蒸発する温度まで加熱すると、鉛の一部が試料から離脱し、別の場所で再凝縮する。再凝縮地点には、明らかなウランの前駆物質を伴わない鉛の堆積物が形成される。このような堆積物から採取した試料は、実際の年代よりはるかに古い年代を示すことになる。関連するウラン(またはトリウム)を伴わない鉛は、親元素のない鉛
parentless lead と呼ばれる。
親元素のない鉛は月面でも発見されている(124)。これは約8億5000万年前の月における「重要な熱的現象」に起因するとされる。これは近世からは程遠いものの、その年代は保証されておらず、月が最後に著しく活動した時期として一般的に引用される35億年からも大きく隔たっている。どうやら、30億年以上もの間、月で何か重要なことが起きている証拠は何もないという趣旨の発言は、そのような発見に対する無知と、実験室の結果の選択的な容認に基づいているようだ。
ライトはルビジウム-ストロンチウム年代測定法における気化問題について論じている(125)。 彼はルビジウムとストロンチウムの蒸気圧が大きく異なる点を指摘した。月の長い日中に到達する高温は、ルビジウムが気化して涼しい場所に移動する温度を容易に上回る。したがって、月が通常の状態であるとしても、この方法による月の形成年代測定には大きな疑問がある。
実際、あらゆる月面年代測定技術は疑わしいため、ヴェリコフスキーの月に関する正確な予測を総括的に否定することは全く成り立たない。最後の主要な月面イベントを年代測定する一つの疑わしい手法だけでは、斉一説が全く予想していなかったいくつかの重要な発見を成功裏に予見した理論を反駁するには不十分である。
まだ言及されていない一つの年代測定法は「サーモ ルミネッセンス」に基づくものである。注意深く適用され、かつ試料の質が適切であれば、この技術は試料が最後に加熱または衝撃を受けた時から経過した時間の推定値を与えることができる。月面における通常の温度変動でさえ、約6インチ(約15センチ)の深さまで物質に影響を与える。したがって、月の土のより深い層から採取したコアサンプルを採取する必要がある。コア抽出方法は試験結果に影響を与え、決定的な結論を妨げる可能性がある。しかし、一部の試験結果は、約1万年前に月面で何らかの擾乱が発生した可能性を示唆している(126)。この事象の正確な性質、原因、規模は不明である。
バブルズ BUBBLES
ヴェリコフスキーは月について他にもいくつかの仮説を提唱したが、これらは彼の宇宙論と特に関連付けられるものではない。月のドーム構造はその典型例である。
これらのドームの一部は、月面が加熱された際に発生したガス放出と気泡形成の結果である可能性が示唆されている。月の表面には多くのドームが観測されているが、その起源は依然として不明である。NASAのアルフォンソス・アンド・フラ・マウロ地域の写真には二つの小さなドームが写っている(127)。別のアポロ計画の写真には、ベハイム・クレーター中央に「滑らかなドーム」が確認できる(128)。
複数の科学者が、バブリング効果による月のクレーター形成について議論している。スハノフは、多くのクレーターが明らかにこの種の起源を持つと述べた(129)。ロンカは、クレーターが衝突クレーターから、火山活動によって変化した衝突クレーターを経て、完全に火山性のクレーターに至るまで多様であると提案した(130)。ミルズは、気体または液体の上昇流によってクレーターが形成される「流動化」と呼ばれるプロセスについて論じた(131)。このプロセスは、火山モデルよりも少ない加熱で済む。
ヴェリコフスキーは、現存するドームがバブリングによって形成されたと主張していた。ドームの存在自体は知られていたものの、彼はドーム(未破裂のバブル)と特定のクレーター(破裂したバブル)に対する自身の説明を提示するにあたり、有力な研究者たちと肩を並べていた。
ジョーガンズはクレーターの一部について別の起源説を論じたが、一部のクレーターが破裂したバブルであるという概念は、『衝突する宇宙』で提示された考えにとって全く周辺的な重要性しか持たないと指摘した(132)。
クレーターの起源が何であれ、月がかつて「熱問題」を抱えていたことは疑いの余地がないようだ。「明らかに、我々がアクセス可能な月の部分は、いずれかの時点で完全に溶融したことがある」(133)。月の最外層(深さ数百キロメートル)の加熱について論じる際、月面サンプル分析計画チームは「そのような現象の熱源はほとんど理解されていない」と指摘した。この加熱は「主に、後期の広範な地表付近の溶融を説明することが困難であるため、その天体の形成中または直後に発生したと考えられている」(強調は筆者)(134)。
同チームはまた、月岩石の化学組成と、各種成分の分布および割合に関する可能性のある説明についても議論している。しかしながら、彼らの「化学的問題の解決は、熱発生の領域において困難を生じさせる」ことが適切に指摘された。斉一説モデルに基づく計算は特定の冷却分布を示し、「外部エネルギー源が関与しない限り、地殻下層または地殻下帯域で温度が再び上昇することはない」とされた。
月震 MOONQUAKES
ヴェリコフスキーはまた、太陽系における最近の激しい変動から月が立ち直り続ける間、月震が依然として頻繁に発生すると示唆した。ただし彼は、地震が数多く発生するとは述べたものの、それが大規模なものになるとは示唆しなかった。実際、月震は極めて小さく、そのほとんどは地球上で検出できない。その規模は中村雄三(「深部月震源の空間的広がり – 再検討の予備報告」)らによって予測された範囲内に容易に収まる(135)。ただし一部は歪みの解放に起因するとされ、その歪みの起源は『衝突する宇宙』で記述された遭遇に由来する。
(既知の周期的な流星群が検出されないことから、ネイチャー誌の執筆者は最近、地震計が実際に測定すべき対象を計測しているのか疑問を呈した)(136)。
炭化物(カーバイド)CARBIDES
地球に加え、原始惑星金星との接近遭遇時に炭化水素が月にも降り注いだ場合、ヴェリコフスキーはこれらの物質の残骸が後に加熱され、おそらく炭化物を形成したと推論した。実際、月面では炭化水素と炭化物の両方が発見されている(137)。検出量は比較的少なかったものの、この物質の実際の起源については依然として議論の余地がある。
放射能 RADIOACTIVITY
ヴェリコフスキーは、惑星と月の間の放電現象が十分に強力であり、局所的な放射能ホットスポットを生成したと示唆した。特に、アリストルコス付近に一つのホットスポットが存在すると予測した。地球大気中の稲妻放電が放射性炭素を生成することは実証されているため、より強力な放電が他の放射性物質を生成し得ると考えるのは合理的である。
月面では局所的な放射能ホットスポットが確認されており、その一つがまさにアリストルコス地域である。アポロ15号および16号のガンマ線分光計による測定では、アリストルコス地域が放射能増強を示す3地点の一つと判明した。さらにアポロ15号のアルファ粒子分光計は、この地域で高いカウント率を検出した。アルファ線分光計はラドン崩壊を検出するとともに「異常な放射能活動」を示す領域を特定するよう設計されていた(138)。様々な可能性を検討した結果、研究者らはこのアルファ線活動をラドン222の放出増加に起因すると結論付けた。
ラドン222の半減期は3.8日であり、半減期1620年のラジウム226の崩壊生成物である。ジョーガンズは「仮に約2700年前にアリストルコス衝突跡で放電によりラジウムが生成された場合、その25%以上が依然として残存し、ラドン222を放出しているはずだ」と指摘している(139)。
──つづく
資料
地球温暖化説に異議を唱えたフレッド・シンガー
フレッド・シンガーは、大気物理学および宇宙物理学の研究で知られる物理学者であり、気候変動に関する議論において顕著な存在だった。地球温暖化やその他の環境問題に関する科学的コンセンサスにしばしば異議を唱えた。1971年から1994年までバージニア大学環境科学科教授を務め、米国運輸省主任科学官や環境保護庁政策担当副次官補など、様々な政府職を歴任した。シンガーはまた、科学と環境政策プロジェクト(SEPP)および非政府国際気候変動パネル(NIPCC)の創設者でもあった。これらの組織は、彼らが科学的根拠が乏しいと考える政府の環境政策に異議を唱えることを目的としていた。
シンガーの初期の科学者としての経歴には、地球観測衛星と大気研究の発展への重要な貢献が含まれる。宇宙放射線や高層大気オゾンの測定を行う初期のロケット実験に関与し、初期の気象衛星におけるオゾン監視に使用された後方散乱光度計を発明した。国立気象衛星センターの初代所長を務め、マイアミ大学環境惑星科学部の創設学部長も務めた。1970年代の彼の研究には、大気中メタンへの人為的寄与量の算出や成層圏オゾンへの影響予測が含まれ、これらは後に実証された。
初期の科学的功績にもかかわらず、シンガーは気候変動に関する逆説的な見解で広く知られるようになり、その脅威は誇張されており、地球温暖化の影響は概ね有益であると主張した。確立された気候科学に疑問を投げかける彼の取り組みから、"疑念の商人"と評され、特定の科学者が環境科学の信用を傷つけるためにどのように利用されたかを検証した著書『Merchants of Doubt(疑念の商人たち)』の中心人物となった。彼の見解は科学界からしばしば批判され、アンドルー・デスラーなどの専門家は、彼の科学的主張は時の試練に耐えるものではないと指摘した。シンガーは 12冊以上の著書と数多くの論説を執筆または共著しており、最新のものは 2018年、94歳のときに発表された。
※主流の科学界に異議を唱えると、このような扱いを受ける一例です。いずれ温暖化は嘘だったということが常識となるでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。