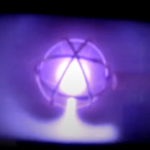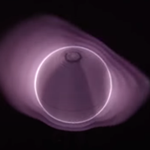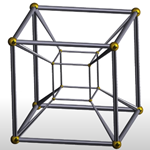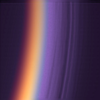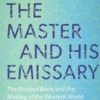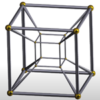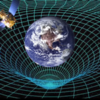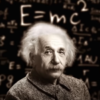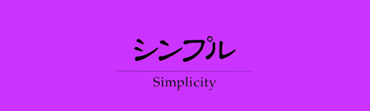電気で動く太陽という大胆な仮説 ── 天体力学とヴェリコフスキーの天変地異説の調和
万物は電気で動いている

私が子供の頃、今回紹介する論文が書かれるよりも前の話ですが、宇宙は真空で何もない空間だと教えられてきました。その後、何もないところからビッグバンというイベントで宇宙は始まり拡大し続けているというふうに。そしてその何もない空間を引力というものが伝わり…… ということでした。何もないところから何かが生まれるというのも不思議な話ですが、それが仏教などの教えになっている"無"とか"空"というものとオーバーラップしてイメージしていたものです。
しかし、宇宙の99.999%はプラズマで出来ていることが証明されています。プラズマというものがなにかということは、こちらの記事を読んでいただけたらと思います。
もちろん、科学の世界でもプラズマは研究されています。しかし、プラズマを"イオン化ガス"として扱います。宇宙関連の記事などを読むと"ガス状の"とか"星間ガス"という表現を目にすると思います。そこで電気は何の役割も果たしていないというのが大前提とされています。ヴェリコフスキーは科学はいまだに電気が利用される時代の前のガス灯の時代に留まっていると嘆いていましたが、その通りなのです。
1972年に書かれたラルフ・ジョーガンズ(ユルゲンス)Ralph E. Juergens は今回紹介する「天体力学とヴェリコフスキーの天変地異説の調和」の中で、電気の役割を無視する宇宙論に異議を唱え、電気で動く太陽という大胆な仮説を提出しました。そしてそのアイデアを太陽系全体に広げたとき、ヴェリコフスキーの唱えた、そう遠くない過去、惑星はその軌道を変えたという主張の根拠として電気の可能性を考察しました。
ニコラ・テスラについても触れています。
「地球上には膨大な数の自由電子が存在することを証明していた」
「彼は、必要な電気がすでに大量に存在していることを発見した」
私たちが教えられた、そしてメディアを通じて見聞きする現代科学、特に宇宙論に何が欠けているのか「『電気的宇宙論Ⅱ』第1章」から引用してまとめてみると、
「現代の宇宙論には基本的な要素が欠けている。その要素とは、電気である。すべての物質が電気を帯びた粒子で構成されていることを考えると、この欠落は不思議なことだ」
「1世紀以上も前から、数人の一流の研究者が、地球上だけでなく宇宙でも電気現象が起きていることを発見していた。しかし、最も影響力のある宇宙物理学者たちが、過去150年間の偉大な電気理論家たちにほとんど注意を払わなかったために、現代の宇宙論から電気が消えてしまった。現在の天文学者や宇宙学者の多くは、宇宙で物質を組織できる力は重力だけであると考えている」
「宇宙は真空であり、完全な絶縁体であると考えられていたため、この"空虚"に電流を流すことは不可能だった」
「しかし、新たに発見された"プラズマ宇宙"を前にして、宇宙物理学者たちはそれまでの議論を覆し、プラズマは電荷のない"超伝導体"であり、電気力の異常な強さは、電子があらゆる電気的差異を短絡させるために電光石火の速さで移動することを保証するとした。この主張により、宇宙物理学者は、宇宙プラズマにおける電流の主要な役割を無視して、プラズマを磁化可能な気体として機械的に扱い続けることができた」
「電波望遠鏡が映し出す宇宙には、磁場や電磁波が存在していることは、天文学者にとって避けて通れない事実だ。磁場は電流によって作られる。電波を発生させるには電力が必要だ。宇宙空間の磁場は、宇宙全体の膨大な電流の流れを示す宇宙のサインなのだ」
ソーンヒルは「ジョン・チャペル記念講演──エレクトリック・ユニバースの恒星」でラルフ・ジョーガンズについて、
「彼は70年代、1972年に、太陽のガス放電モデルを発表しました。彼は『太陽のエネルギーを太陽内部の深いところでの熱核反応によるものとする現代の天体物理学的概念は、太陽のほぼすべての観測可能な側面と矛盾する』と書いています。私は彼の論文を読んで感銘を受けました。彼は、すべての星に適用できる詳細なガス放電モデルを提供してくれました。すべての星に適用できる単一のモデルです。これは、星ごとに個別の理論を持つ現代宇宙論とは全く異なるものです」
ラルフ・ジョーガンズという人
“エレクトリック・ユニバース"を初めて知った方にとって、ラルフ・ジョーガンズ(ユルゲンス)Ralph E. Juergens
という方の名前は初めて耳にする名前かもしれません。この論文を訳していて、私が言うのもおこがましいですが、ラルフ・ジョーガンズという人は、かなり頭の切れる人だなという感想を持ちました。論理が一貫しているし、そこから導き出す結論がとても"率直、素直"です。50代で早くに亡くなられてしまったことが惜しまれます。ラルフ・ジョーガンズという方の略歴を紹介しようとした時、資料がとても少ないことに気がつきました。写真もあまり残っていません。やむなく、個人的には好きなサイトではありませんが、そこから引用したいと思います。
「ヴェリコフスキー百科事典」からラルフ・ジョーガンズの略歴を紹介します。この「ヴェリコフスキー百科事典」はその名の通りヴェリコフスキーについての情報が整理されています。ですが、ウィキのようなもので、コンセンサス・サイエンスの立場で書かれた"百科事典"であることに留意してください。
(以下、引用)
ラルフ・ジョーガンズ(1924年5月6日-1979年11月2日)は、共著者のアルフレッド・デ・グラツィアとリビオ・ステッキーニとともに、いわゆる「ヴェリコフスキー事件」を記録したことで知られている。その後、太陽は核融合で動いているという標準的な考え方に反して、太陽や星は電気で動いているという仮説を提唱した。"電気の太陽"仮説は不評だったが、非主流のエレクトリック・ユニバース仮説の中核をなすものとなっている。
ケース・ウェスタン・リザーブ大学で学士号を取得し、アリゾナ州に居住した。また,マグロウヒル社の出版部門で編集者を務め,『Pensée』誌のアソシエイト・エディター、『Kronos』誌のシニア・エディターを歴任している。
ヴェリコフスキー事件
1960年に退職したジョーガンズは、イマニュエル・ヴェリコフスキーの研究を追求し、それに関与するために、中西部からプリンストン近郊のハイツタウンに移った。その直後、ヴェリコフスキーは、作家のアルフレッド・デ・グラツィアに、ジョーガンズをヴェリコフスキーの話をまとめた本の科学編集者に、リビオ・ステッキーニを歴史的部分の執筆者に推薦した。
1963年、デ・グラツィア、ジョーガンズ、ステッキーニの記事が『American Behavioral Scientist』誌の1963年9月特別号に掲載され、1966年には本「ヴェリコフスキー事件:科学に対する科学主義」が出版された。
1968年6月2日、デ・グラツィア、リチャード・P・クレイマー、ステッキーニ、ジョーガンズの四人に、ホレス・カレン、ハリー・H・ヘス、A・ブルース・メインウェアリング、ジョン・ホルブルック・ジュニア、ロバート・C・ステファノス、ワーナー・サイズモアが評議員として加わり「The Foundation for Studies of Modern Science(現代科学研究財団)」が発足した。
1972年、ジョーガンズは雑誌『Pensée』に初めて「天体力学とヴェリコフスキーの破局論の調和」という論文を発表し、次のような考えを強調した。
「惑星間物質は、太陽と惑星が電気を帯びていることを示唆しているだけでなく、太陽自体が宇宙の放電の焦点であり、そのすべての放射エネルギーの可能性のある源である」
しかし、ヴェリコフスキーは熱核説が正しいと思っていたので、ジョーガンズの説を受け入れなかった。
電気的太陽仮説
アール・R・ミルトンは、ジョーガンズの"電気的な"太陽の概念を次のように回想している。
「1972年8月、ラルフ・ジョーガンズは電気で動く太陽の概念を紹介した(1a) 。彼は、電磁力が太陽系の天体の表面を削り、軌道を形成する上で重要な役割を果たしているというイマニュエル・ヴェリコフスキーの主張、(1b) 電磁場と重力場を統一しようとしたメルビン・クックの試み、(1c) チャールズ・ブルースの膨大な文献に触発され、恒星の大気で観測される現象が放電モデルで適切に記述できることを示唆した(1d)」
「しかし、ジョーガンズは、宇宙の天体とその相互作用の両方に電気を通すことで、他の指導者たちよりもはるかに進んでいた。彼は天体を、電気を帯びた布のように表現できる、宇宙に浸された、本質的に帯電した物体として認識したのである(1e)。宇宙の物体に局所的に現れる電荷は、銀河規模での正イオンと電子の分離から生じていると彼は考えていた(1f)。その後、太陽内部が本当に星のエネルギー源である場合の問題点(1g)や、太陽の光球として観測される現象の性質についても論じている(1h)。
(1g)と(1h)に引用されている二つの論文が、1979年11月に早世する前に彼が電気的な太陽について発表した最後のものとなった」(参考文献は原文のまま)
ミルトンの回想
「ジョーガンズは最初の論文で、宇宙線(太陽系にあらゆる方向から相対速度で衝突する陽子)の入射束を調整する太陽の能力を、太陽の駆動電位である陰極降下に関連づけている(1i)。彼は100億ボルト以上あれば十分だと見積もった。また、地球軌道上で観測された太陽風プロトンの束から、太陽放電のために10¹⁵アンペアの太陽風電流が流れていると計算した(1j)。太陽の明るさが3.9×10²⁶ワットということは、一見するとジョーガンズの見積もりの40倍を超える放電電流が必要になるが、彼が選んだ陰極降下量と放電電流の値はいずれも最小値であるため、電力不足が深刻になることはなく、どちらか一方、あるいは両方の値を調整して不足分を解消しても、彼の主張の信憑性に影響はない」
「その後、ジョーガンズは太陽の光球は放電管の"房状の陽極の輝き tufted anode glow “に例えられると指摘した(1k)。房状になるのは、太陽本体が惑星間プラズマ(その内側の境界はコロナと呼ばれる微弱な太陽の外側の領域)に浸されていて、周囲の電気を帯びた銀河空間に放電を維持できないからである。ジョーガンズは、この問題が以下のような条件で発生する可能性があると指摘している。
(1) 放電に必要な電流を流すには、太陽体の表面が小さすぎること
(2) 周囲のプラズマが冷たすぎる(1l)
(3) 陰極の落差が大きすぎる
太陽体 solar body の"表面"から切り離された"陽極の房 anode tuft “は、太陽が電子を集めることのできる有効な表面積を増やしている。"タフト"の中では、太陽から蒸発した揮発性物質がガス密度を高め、ガス原子間の頻繁な衝突の多くがイオン化するため、大量の余分な電子を提供する」
1972年、ジョーガンズ記
「惑星間物質の既知の特性は、太陽と惑星が電気を帯びていることを示唆しているだけでなく、太陽自体が宇宙の放電の焦点であり、そのすべての放射エネルギーのおそらく源であることを示唆している」
ジョーガンズ、謝意
「クック博士は言及していないが、太陽が電気を帯びている可能性を示唆している点では、彼の方が何年も前から私よりも先行しているように思える。1958年に出版されたクック博士の著書『強力爆発の科学 The Science of High Explosives』の付録には、単位時間当たりの太陽の電荷の"蓄積の運動エネルギー"は、太陽の放射エネルギーの割合と同じオーダーであると指摘している」そして、こう付け加えた。
「どうやら、このようにして、太陽定数のエネルギー放出率について、太陽のコアで行われているとされる生成を含む必要がないか、少なくとも相対的な重要性がほぼ同じであるという、ありそうな説明ができたようだ」
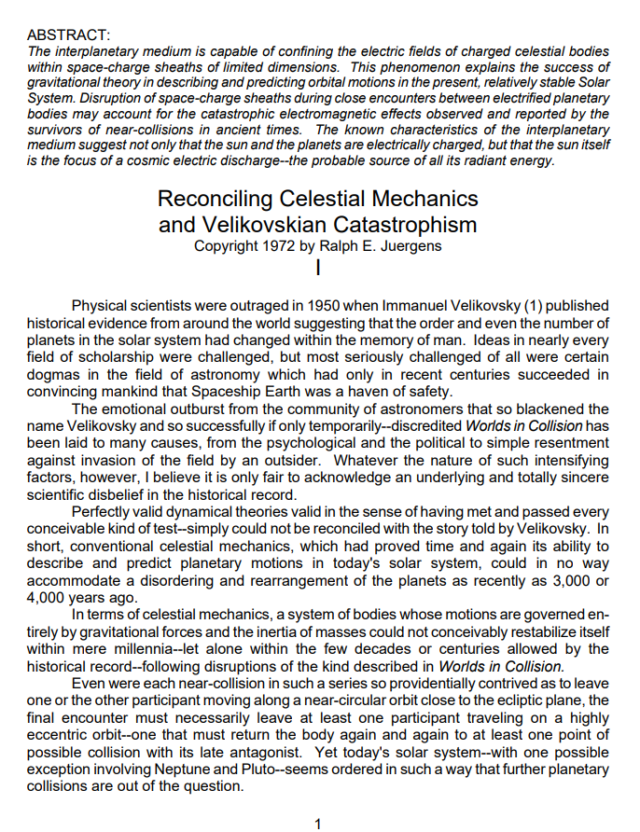
天体力学とヴェリコフスキーの天変地異説の調和
Reconciling Celestial Mechanics and Velikovskian Catastrophism
[要約]
惑星間物質は、電荷を帯びた天体の電場を、限られた体積(容量)の空間電荷シース内に閉じ込めることができる。この現象は、重力理論が、現在の比較的安定した太陽系における軌道運動の記述と予測に成功していることの説明になる。電気を帯びた惑星体が接近する際に空間電荷シースが破壊されることで、古代に異常接近の生存者が観測・報告した壊滅的な電磁効果を説明できるかもしれない。惑星間物質の既知の特性は、太陽と惑星が電気を帯びていることを示唆しているだけでなく、太陽自体が宇宙放電の焦点であり、太陽のすべての放射エネルギーの源である可能性が高い。
天体力学とヴェリコフスキーの天変地異説の調和(和解)
Copyright 1972 by Ralph E. Juergens.
I(宇宙の雷は、電気のポテンシャルを均等にしようと、天体の間で閃く)
1950年、イマニュエル・ヴェリコフスキー(1)が、太陽系内の惑星の順番や数が人間の記憶の中で変化したことを示唆する歴史的証拠を世界中から集めて発表したとき、物理学者たちは憤慨した。ほぼすべての学問分野の考え方が問われたが、中でも最も深刻な問題となったのは、天文学の分野におけるある種のドグマだった。ドグマは、ここ数世紀の間、人類に"宇宙船地球号"は安全な場所であると信じ込ませることに成功していた。
天文学者のコミュニティが感情的になってヴェリコフスキーの名を汚し、一時的にせよ『衝突する宇宙』の信用を落とすことに成功したのは、心理的なもの、政治的なもの、部外者による分野の侵犯に対する単純な憤りなど、さまざまな原因がある。しかし、そのような激化する要因がどのようなものであったとしても、歴史的記録に対する科学的な不信感が根底にあることを認めるのが妥当だと思える。考えられるすべてのテストに合格したという意味で、完全に有効な力学的理論は、ヴェリコフスキーが語った話とは単純には両立しなかった。
つまり、現在の太陽系における惑星の運動を記述し、予測する能力があることを何度も証明してきた従来の天文学的力学は、3,000年または4,000年前に惑星が無秩序に再編成されたことには到底対応できなかった。天体力学の観点から言えば、重力と質量の慣性によって運動が支配されている天体のシステムは『衝突する宇宙』に書かれているような混乱が起きた場合、わずか数千年、ましてや歴史的記録で認められている数十年から数百年の間に再び安定することは考えられない。
このような一連の衝突のたびに、参加者の一方または他方が黄道面に近い円形の軌道に沿って移動するように神の計らいがあったとしても、最終的な遭遇では、必然的に少なくとも一方の参加者が非常に偏心した軌道を旅することになり、そのような軌道では、遅れてきた敵対者と衝突する可能性のある少なくともひとつの地点に天体を何度も戻さなければならない。しかし、現在の太陽系は、海王星と冥王星の例外を除いては、惑星同士の衝突が起こらないように秩序が保たれているように見える。
ヴェリコフスキーは、自分の研究結果と現在の天文学の常識との間に不一致があることをよく理解していた。しかし彼は、その原因が歴史上の証拠ではなく、力学的理論にあるはずだと主張した。彼は、太陽や惑星は電気を帯びているはずであり、電磁力や静電力は衝突を和らげたり、回転運動を変えたり、軸を傾けたり、比較的短い時間で軌道の偏心を和らげたりすることが簡単にできるはずだが、天界では認識されていない役割を果たしているのではないかと考えたのである。
これから説明するように、太陽系の主要な天体である太陽、地球、月が電気を帯びていることを示す有力な証拠がある。しかし、重力理論が惑星の運動を正確に説明していることは、この証拠と矛盾するように思える。例えば、反発的な電気力による擾乱は、今日ではどこにも見当たらない。 ──彗星の尾の奇妙な振る舞いもそうだが、これについては後ほど詳しく説明する。
天体力学と宇宙の電気的相互作用の概念の間にあるこの行き詰まりは、ずっと前から認識されていた。地球上に電荷があることを示す最も明白な証拠を説明するために、半ダースの歴代の物理学者たちは、あらゆる種類のエキゾチックな理論を考案しなければならなかったほど、和解はあり得ないことだった。
そのような場当たり的な理論の虚しさを示す重要な手がかりが、1962年にマリナー2号から地球に向けて発信された。人類初の金星探査機であるマリナー2号は、惑星間の媒質が、多くの天文学者が考えていたような真空に近い状態ではなく、正イオンと電子が解離したガスであるプラズマであることをはっきりと示した。この発見(情報開示)により、惑星が電気を帯びていれば、疑問の余地がないほど明らかに互いに干渉するという議論は無効となった。
電気の物理学では、誘電体である真空中の孤立した電荷を帯びた物体は、その周囲に距離の2乗に比例して強さが減少する無限大の電界を帯びるとされている。したがって、真空の惑星間媒体、あるいは中性の原子や分子のガスの媒体の中でも、惑星の電荷は電界を生じ、それが惑星の運動に影響を与えることで検出できるはずである。
しかし、イオン化したガスで構成された惑星間空間では、状況は大きく異なる。
プラズマの主要な特徴のひとつは、これまで天文学者からはほとんど注目されていなかった。それは、プラズマと接触したり、プラズマの中に入ったりして、プラズマの電位とは異なる電位に帯電した物体の電界を遮ることができることだ。この現象を最初に研究した人たちは、この遮蔽のメカニズムを"空間電荷シース space-charge sheath “と名付けた。
空間電荷シースでは、正負の電荷が集まり、異質な電位を持つ物体の電界がその周囲の限られた領域に収まるように配列されている。これは、孤立した物体の全電荷を、シース(鞘)内の等しく反対の電荷で補わなければならないという意味ではない。むしろ、周囲のプラズマの電位と一致するように、シースの外側の境界の電位を増減させるのに十分な電荷がシースに集まっていなければならないということだ。
空間電荷シースは実験室の現象として、半世紀前に説明され、研究され、定量的な理論的説明がなされた。最も分かりやすいのは、完全に電離した気体を指す"プラズマ"という言葉を作った物理学者、アービング・ラングミュア(2)の論文だろう。
ここまで、私は空間電荷シースとプラズマに関する最も重要な二つの事実について言及してこなかった。
⑴ 電流によって異質な電位を継続的に更新していない孤立した物体は、すぐに周囲のプラズマの電位を獲得し、そのシースは消滅してしまう。そして、
⑵ プラズマは必ずしも固有の電位を持っているわけではない。
しかし、放電中にプラズマが形成された場合──ラングミュアが研究したのはこの点である──プラズマはゼロでない電位を持つようになる。
これらは明らかに非常に重要な問題だ。この問題については後ほど触れたい。
とりあえず言えることは、プラズマに覆われた太陽系において、局所的なプラズマとは異なる電位を持つ荷電惑星は、その電場が限られた体積の空間電荷シースに束縛されているということだ。軌道上での衝突がない場合には、通常の天体力学で説明される力の方向に沿って、システムは穏やかに動作する。
しかし、このシステムの中で、電気を帯びた二つの主要天体の軌道が交差した場合、どのようなことが起こるかを想像してみよう。当然、二つの天体が別々の時間軸で別々の道を進むうちに、やがて、いずれかの軌道上の接触点でランデブーするような状況になるだろう。天体の空間電荷シースは天体そのものよりも大きな体積を占めるので、シース同士の衝突の方が、天体同士の直接衝突よりも起こりやすく、いずれにしても最初に起こることになる。
必然的に遭遇する瞬間が来ると、シースは接触する。放出された電界は衝突する。ほとんど瞬間的に、重力よりも計り知れないほど大きな力が、帯電した天体に加わることになる。宇宙の雷は、電気のポテンシャルを均等にしようと、天体の間で閃く。
(以下、原文ではイタリック体になっています)
アリゾナ州フラッグスタッフ在住の土木技師ラルフ・ジョーガンズ Ralph Juergens は、マグロウヒル社の技術出版物の副編集長を務めていた。ここで述べられている仮説は彼自身のものであり、必ずしもヴェリコフスキー博士のものではない。
考えられないような悲惨な結果になることは、枚挙にいとまがない。しかし『衝突する宇宙』には、宇宙空間での電荷シースの破壊に関連する現象が、古代の人々が実際に経験し、生き延びたことを示す歴史的な証拠が記されていると、少なくとも私は考えている。
II(地球の大気電場)
ここで、惑星間プラズマにどっぷり漬かっている太陽や惑星が、そのプラズマの電位(ゼロと推測される)を獲得しているように見えるという問題を考えてみよう。
ある人は、この問題自体が偽りであると主張するかもしれない。この問題を排除することは『衝突する宇宙』をゴミ箱に捨てるのと同じくらい簡単なことだと主張する人もいるだろう。それにもかかわらず、私はこの問題は現実であると主張する。そして、この問題を解決するためには、太陽系の様々な場所で得られた観測的証拠を集める必要がある。
この問題は実際にある。なぜなら、太陽、地球、月が電気を帯びた物体であるという十分な証拠があるからだ。三つの天体のうち、月だけが周囲の環境と同じ電位を持っているように見える。このことから、環境自体が月と同じくらいの電位を持っているとしか考えられない。ここで、この問題の現実性を確認するために、いくつかの証拠を簡単に紹介する。
太陽は非常に複雑な磁場を持っていることが知られている。皆既日食の際に太陽の極に発生するコロナストリーマーを観察すると、磁場の少なくとも一部が地球の磁場と同じような双極子の形 dipole configuration(双極子配置)をしていることがわかる。また、太陽の下層大気では、磁場が絶えず苦しめられていることが示唆されている。しかしながら、電界の存在、さらには下層大気中の複雑な電界の存在は、電流に起因するとしか考えられない。理論家たちがどんなに小さくしたり、否定したりしても、電流だけが磁場を発生させるという事実は変わらない。
単に"動く電荷 moving charges “が磁場を発生させるというだけでは、誤解を招く。例えば、イオン化したガス体は、荷電粒子が実際に動いているので、動く電荷の集まりと言えるかもしれない。さらに言えば、そのようなガスの中を移動する荷電粒子のひとつひとつが、素粒子の電流を構成していると言える。しかし、正負の電荷の差動がない限り、正味の電流はゼロとなる。気体がどんなに激しく動かされても、磁場は発生しない。
(ただし、一方の符号の電荷が他方の符号の電荷よりも優勢であり、ガス体が実際に正味の電荷を持っている場合には、バルクガスの運動の影響は全く異なるものとなる)
太陽のイオン化ガスの運動に磁場や効果が作用するという事実は──太陽黒点の回転運動に関連して明らかになる強い電界がその典型例である──、太陽ガスが──太陽ガスはある種の粒子を過剰に含んでいる──正または負の電荷を帯びているが、ほぼ確実に負の電荷を帯びているという結論によって、最も簡単かつ納得のいく説明ができる。
太陽磁場の双極子成分は、20年以上前にヴェリコフスキー博士が指摘したように、帯電した太陽全体の回転に起因するとしか考えられない(3)。地球の磁場は、約100年前にとりあえず地球上の電荷に起因するものと見なされた。1878年、ローランド H.A.Rowland は、観測された磁場を生み出すために地球が維持しなければならない電位を計算しようとした。その結果は、4×10¹⁶ボルト以上の負の値だったが、彼はあまりにも馬鹿げていると思い、すぐに却下した。地球にそのような電位を与えるのに必要な大きさの電荷は「間違いなく地球を引き裂き、その破片を宇宙の最果てにまでばらまいてしまうだろう(4)」とローランドは書いている。
このような議論は、ローランドの時代以来、地球物理学者たちに、地球上の電荷が地球の磁気の原因となることはないと確信させてきた。
最近では、地球の磁場を説明するのに、いわゆるダイナモ理論 dynamo theory で満足することが流行している。地球の磁場は、溶融したコアの運動によって発生するとされている。しかし、そのような運動によってどのようにして電流が発生するのかは、まだ誰も示していない。
コロラド大学のジェームズ・ワーウィック James Warwick 教授は最近「ダイナモ理論は、宇宙の磁場を予測することには成功していない。今日、ダイナモ理論が使用されているのは、観測結果とより密接に対応する代替理論がないという前提(思い込み)に立っている(5)」[ワーウィックのイタリック体(青い字)]と指摘した。
NASAエイムズ研究センターのパーマー・ダイアルとカーティス・W・パーキンのこの発言には、ダイナモ理論に対するさらに強い反論が込められている。
「地球の永久磁場を満足のいく説明ができる厳密な理論は存在しない(6)」
「満足のいく」とは、もちろん、地球の電荷を認めないという意味である。
その前に、巨大な電荷が地球を吹き飛ばすに違いないというローランドの見解を考えてみよう。これは、1952年にドナルド・メンツェル Donald Menzel が、太陽が電気を帯びているという「ヴェリコフスキーの荒唐無稽な仮説に対する量的反証」(7)にメリハリをつけるために唱えたものと同じ考えだ。
そもそも、フェルナンド・サンフォード教授が40年前に指摘したように、
「このような結論はすべて、電荷が[重力]によって導体に保持されているという仮定に基づいている……もしこの仮定が正しければ、地球の重力場の中では、どんな小さな導体にも負の電荷を与えることはできないだろう(8)」
また、サンフォードは「同じ直径のシャボン玉とプラチナの球体を接続線でつなぎ、同じ電源から充電した場合、均等に充電される。このことは、電子を帯電した導体につなぎとめる力が何であれ、電子と導体の原子の間に働く力ではないことを決定的に示している。このケースでは、導体上の電荷の外向きの圧力は、導体を引き離す動き(性質)はない」と指摘している。
地球の大気電場は、約200年前に発見されて以来、論争の的となってきた。問題となっているのは、その原因となる電荷がどこにあるかということだ。──地球上の負の電荷か、大気中の正の電荷か?
1803年、ベルリンのエルマン Erman 教授は、簡単な実験で地球が負電荷を帯びていることを証明した。彼は、先の尖った短い集電棒を取り付けた金箔検電器を、まず接地してから数フィート空中に上げると、正の電気を帯びることを発見した。それを上の位置で保持したまま地面に放電し、その後下に降ろすと、負の帯電を示した。集電棒の上にボールを置いても、装置全体を密閉したガラス管の中に入れても、同じ結果が得られたことから、マイナスに帯電した地球からの電気誘導によるものだと正しく結論づけた(9)。
エルマンの発見は嘲笑され、すぐに忘れ去られてしまった。
しかし、そのわずか一年後には、二人の気球乗りが、彼らの集電装置と検電器が、期待していた正電荷ではなく、高空から負電荷だけを集めたことで、不思議に思ったのだった(10)。
1836年、ペルティエ Peltier は、エルマンの実験と似ているが、よりエレガントな実験に基づいて、同じ結論に達した。地球はマイナスに帯電しており、この帯電が大気電場を発生させている(11)。
以来、エルマンとペルティエの説より説得力のある大気電気の理論は、誰も思いつかなかった。何度も何度も 、科学者たちは、大気中の過剰な正電荷を何らかの方法で検出しようとしたが、いつも無駄に終わっていた。
(1972年3月のサイエンティフィック・アメリカン誌では、A.D.ムーア教授が「静電気」というテーマで次のように書いている。
「地球の大気中にはどういうわけか正電荷が供給されており、晴れた日には1メートルあたり100〜500ボルトの下向きの電界が発生している」
(「どういうわけか」という説明には疑問を感じるが、誰もその存在を証明できていない現象には十分な説明だ)
19世紀末、電気の天才ニコラ・テスラは、コロラド州の山中に電気天文台を建設・運営していた。彼は早くから、地球上には膨大な数の自由電子が存在することを証明していた。当時、彼が夢中になっていたのは、地中に電波を送ることだった。彼は、もし地球がマイナスに帯電していなければ、電気的に振動する状態にするために莫大な量の電気を注入しなければならない広大なシンク(受信側、受信装置)として機能するだろうと推論した。彼は、必要な電気がすでに大量に存在していることを発見した(12)。
テスラの発見は、最近になって、しかも気付かずに(うかつに)、月に対しても繰り返された。1971年11月12日付の『ネイチャー』誌で、スミソニアン天体物理観測所のウィンフィールド・ソールズベリーとダレル・ファナードが、アポロ15号の司令船が月の裏側にいた時に信号を受信したと報告した。この信号は、X線[放射線]不透過性と思われる月の曲面を、月の表層部の電波によって運ばれていた(13)。
では、太陽も月も地球も電気を帯びた天体であるとすれば、太陽系内にプラズマが遍在していることとどう折り合いをつけたらよいのだろうか。
リンデマン F.A.Lindemann が1919年に次のように書いた太陽の自由電荷[過剰電荷]については、あながち間違いではなかったのではないかという疑念が頭をよぎる。
「太陽には相当な静電気力が存在しないことは簡単にわかることだ。外層は…… 確かに高度にイオン化されているに違いない…… だから、太陽全体の電荷はイオンの放出によって速やかに中和されるだろう(14)」
言い換えれば、過剰な同種の電荷が互いに電気的に反発し合うことで、太陽から遠ざかるように駆動されるに違いない。
リンデマンはさらに、電気的な力と重力が釣り合っていなければならないと仮定した。──これは後にサンフォードによって無効であることが示された概念である。しかし、重力を無視すると、リンデマンが計算した数千ボルトではなく、太陽の電位はゼロにしかならないという結論になってしまうようだ。
さらに、リンデマンのケースは、惑星間の媒体に関する現在の知識からも得られるようだ。確かに、宇宙空間を覆う導電性のプラズマは、太陽による過剰電荷の散逸を促進するに違いない。
しかし、リンデマンの主張が妥当なのは、二つの暗黙の前提が有効な場合に限られる。
⑴ 惑星間の媒体には電気的な歪みがなく、プラズマはそれ自体に電位を持たないので、太陽の過剰な電荷のシンクとして機能する。そして、
⑵ 太陽の電荷は電流によって継続的に更新されない。
私はこの二つの仮定に挑戦したいと思う。
しかしながら、読者の皆様はすでにお察しのことと思うが、これは、太陽や惑星の静電容量を否定する以上に、気取った天体物理学的ドグマに挑戦するという代償を払わなければできない。
ここから先は、太陽系は電気を帯びていないというあらゆる論拠にもかかわらず、なぜ、どのように電気を帯びているのか、その理由についての私の考えを、ごく簡単にまとめたものだ。
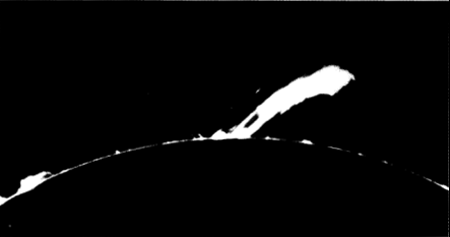
「熱核理論に基づいて太陽を半世紀にわたって研究してきた中で、観測と理論の間の矛盾や、太陽大気の個々の特徴を実質的に説明するために、その場しのぎの余分な理論を考案しなければならなかったことに、わずかな違和感を示したプロの宇宙物理学者はほとんどいなかったというのは驚くべきことだ」
III(現代の天体物理学的概念は、太陽の観測可能なほぼすべての側面と矛盾している)
このことをそつなく述べる方法が見つからないので、率直に言わせていただく。太陽のエネルギーを太陽内部の深いところでの熱核反応によるものとする現代の天体物理学的概念は、太陽の観測可能なほぼすべての側面と矛盾している。
半世紀にわたって熱核理論に基づいて太陽を研究してきたが、観測と理論の間の矛盾や、太陽大気のほぼすべての特徴を説明するために、その場しのぎの余分な理論を考案しなければならなかったことに、わずかな違和感を示したプロの宇宙物理学者はほとんどいなかったというのは驚くべきことだ。
数年前、フレッド・ホイルは、しっかりした手つきでこう書いている。
「単純な計算に基づいて、太陽は単純かつ平凡な方法で自らを"終わらせる"と予想すべきである。光球の上の高さが増すにつれて、太陽物質の密度は非常に急速に減少し、2〜3km上ではほとんど無視できるほどになるだろう…… それどころか(太陽の)大気は巨大な膨らんだエンベロープ(外皮、膜)のようになっている(15)」
そして今日、私たちはこの"膨張したエンベロープ"が惑星の間にも広がっていることを知っている。
理論的には太陽が"終わり"を迎えるはずの光球でさえ、期待通りにはいかない。もしそれが本当にエネルギーの源であるならば、その不透明さは、太陽がその内部エネルギーを放射するのを妨げることになる。光球の粒状構造は"非定常対流"によるものとされているが、ミンナルト Marcel Minnaert は数十年前に、光球ガスのレイノルズ数が臨界値の10の8乗、つまり1億倍を超えていることを指摘しており、したがって光球の対流は完全に乱流であるはずだとしている(16)。
(対流自体は、光球の不透明性にもかかわらず、内部の放射エネルギーがすべて地表にもたらされることを説明するために仮定されている)
中高度の太陽大気中では、天文学者が驚くほど多様な現象を観測しているが、熱核理論のように、太陽がその内部深くから解放されたエネルギーを放出することを最大の目的としているのであれば、そのような現象は何の関係もないことがわかる。
太陽内部には光球に向かって下がる急な温度勾配があり、それに沿って内部のエネルギーが外に向かって流れているというのが、この説の本質だ。
一般的な理論にとって、太陽内部には光球に向かって下降する急な温度勾配があり、それに沿って内部エネルギーが外に向かって流れているという信念が絶対必要だ。この内部の温度勾配と、観測された太陽大気の温度勾配(光球に向かって内側に急降下)を重ねると、物理的に不条理な図を描いていることに気がつく。この二つの勾配が光球の谷を作り出している。これは熱エネルギーが光球に集まり、温度を上げて谷をなくすまでそこに留まることを意味している。これが起こらないことは誰も気にしていないようだ。
しかし、仮説(仮定)の内部の温度勾配を取り除いたとする。するとどうだろう。なんと、太陽の膨らんだ大気と、その大気の"間違った"温度勾配は、太陽エネルギーの外部供給源を強く示唆していることがわかる。
メルビン・クック教授は1950年代にあえてこの問題に注意を促した(17)。しかし、彼はプロの宇宙物理学者ではなかったので、彼のコメントは注目されていなかったし、求められてもいなかった。
光球の現象、彩層の現象、コロナの現象、そして既知の惑星間物質の特性は、太陽に外部から供給されるエネルギーに基づく統一的な仮説にうまく当てはまるので、ここで言及しないわけにはいかない。私は、太陽は周囲から電流を集める陽極 anode の役割を果たしていると考えており、太陽が放射するエネルギーは、すべてこの想定される放電によってもたらされていると考えている。
ブルース C.E.R. Bruce は、1944年の時点で、数多くの太陽大気現象を放電効果として特定していた(18)。その後、宇宙物理学の分野でも、宇宙放電の包括的な理論で見事な予測実績を残している(19)。しかし、どうやら──彼の銀河系の性質に関するいくつかの結論からすると、不可解なことだが──彼は、太陽や星が熱核エンジンであり、周囲の環境を全く気にせずに生きたり死んだりしているという考えに疑問を抱いていない。
ここでは触れないが、私はブルースに、星のエネルギーは電気的なものであるという考えを取り入れた壮大な計画を修正することを勧める。そうすれば、私の考えでは「電界の崩壊こそが…… 最初から宇宙を形作り、照らしてきた(20)」という彼のビジョンが最終的に正当化されることになる。
私が考える太陽放射の原因となる放電は、必然的に星間空間の電位で駆動されなければならない。──これは、壮大なスケールの電荷の分離によって電気を帯びた銀河で予想される条件である。ブルースは、銀河系の螺旋状の腕を、銀河空間全体に広がる放射状の電界が破壊されて発生した放電であると説明しているが、まさにそのような状況を想定している。そして、このような状況では、放電仮説が必要とする非常に高い空間電位(マイナス)が得られる。私の考えでは、次のようになる。太陽はすでに非常に高い電位でマイナスに帯電しているが、星間環境がマイナスの意味でさらに高い電位を持っているため、陽極として振る舞い、より多くのマイナス電荷を集めることになる。それは相対的な電位の問題だ。
実験室で研究された放電との類似性から、もし太陽が本当に電気的に燃料となっているならば、惑星間空間ではどのような状態になるかを予測することができる。とりあえず、これだけは言っておきたい。地球近傍の惑星間物質は、陽子と電子の数がほぼ同じであることから、真のプラズマであると考えられる。もっと遠く、例えば木星の軌道付近では、陽子はかなりの速度で太陽から遠ざかり、電子は陽子よりも少ない数しか存在しないはずだ。
「光球……彩層……コロナの現象、そして惑星間物質の既知の特性はすべて、外部から太陽に供給されるエネルギーに基づく統一的な仮説にうまく適合する。私は、太陽はその環境から電流を集める陽極として振る舞い、太陽が放射するエネルギーはすべて、この仮定された放電によって供給されると考えている」
願わくば、1970年代後半にNASAが計画している外惑星探査機"グランド・ツアー"には、惑星間の媒体を採取するための装置が搭載され、放電仮説を支持あるいは反論する証拠を提供してくれることを期待したい。木星のような太陽コロナからの熱電子の存在は、この仮説を非常に不安定なものにしていると思われる。しかし、その距離で陽子だけがまだ太陽から離れて加速されているのであれば、惑星間空間に電流が流れているという結論以外にはあり得ないだろう。
ところで、地球周辺でも、太陽風理論家は、粒子の密度や温度の観測結果と、ユージン・パーカーの「太陽風は、太陽の高温コロナによって不可避的に沸騰した物質である」という仮説(21)との整合性をとるのに非常に苦労している(その数百万度の温度は、放電仮説に基づいて予測できるが、従来の恒星エネルギー理論では説明できない)。太陽風に含まれる正イオンは、パーカーの予測に近い速度と数で地球の軌道を横切る。一方、太陽風の電子は、ゲームのルールを知らないようだ。数的には陽子とほぼ同じだが、移動速度が遅すぎて、磁力線に沿って脇道にそれてしまう傾向がある(22)。
興味深いことに、予測と観測の一致に平均以上の成功を収めている太陽風モデルは、ベルギーの二人の科学者、ルメール J.Lemaire とシェラー M.Scherer のモデルである(23)。このモデルの目立った特徴は、太陽コロナ中の高い位置にある電場が、電子を減速させ、陽子を観測された速度まで加速させるとしていることだ。
さらに興味深いのは、最近9年間の太陽風速の観測結果をまとめたものである。1971年にゴスリング J.T.Gosling らによって発表されたこの研究(24)では「1962年から1970年の間の太陽風バルクスピードの年ごとの分布は……年ごとに驚くほど一定であることがわかった。太陽活動の増加に伴って、太陽風速度が増加する傾向はない」
このことから、太陽風は黒点周期よりも、同じく驚くほど一定である太陽のエネルギー供給に近い関係にあると考えられる。もし太陽エネルギーが実際に太陽内部のプロセスに由来するものであれば、黒点サイクルの最も活発な時期に特徴的なタイプの擾乱がエネルギーの外向きの流れに影響を与えることが予想される。しかし、もし太陽エネルギーが太陽の外からやってくるものであれば、太陽表面の事象がエネルギーを可視光線や不可視光線の形で宇宙に散逸させることに影響を与える可能性ははるかに低いだろう。
木星が太陽から受けたエネルギーの数倍のエネルギーを放射していることは、放電の通電路として考えられている惑星間物質によって説明がつく(25)。木星とその空間電荷シース(磁気圏)が、太陽に向かう高エネルギーの一次電子を遮断しているとすれば、巨大惑星の過剰エネルギーの源はもはや謎ではない。
宇宙線には、未だに解明されていない謎がある。素粒子はどこで、どのようにして加速され、地球に到達したときに膨大な運動エネルギーを発揮するのか。しかし、宇宙線が地球に到達するという事実から、地球がマイナスに帯電しているという重要な証拠がもうひとつ見つかった。そして、放電仮説は、宇宙線エネルギーの謎に対する答えの可能性を示唆している。
エドワード・ハルバート Edward O. Hulburt は『サイエンティフィック・マンスリー』誌(1954年2月号)で、一次宇宙線が地球に非常に大きな正電荷を与えることを指摘している。
彼の計算によると、7×10⁶クーロンの正電荷がわずか16年半で蓄積されることになる。これは、エネルギーが10¹⁰電子ボルト以下の宇宙線陽子がこれ以上地球に到達するのを防ぐのに十分な量である。
つまり、年間で4×10⁵クーロン以上の正電荷が地球に蓄積されていることになる。
ハルバートは、宇宙線の中に負の電荷である電子が発見される前に、これらの事実を明らかにしていた。現在、電子は、1950年代初頭にはなかった高感度・高性能の装置で検出されるようになった。しかし、電子は宇宙線全体の中で陽子の約1%しか存在しないことが分かっている。つまり、実用上はハルバートの計算が有効である。
宇宙線は、毎年4×10⁵クーロンの正電荷を地球に届けているにもかかわらず、年々減少することなく届き続けている。
おそらく"ずっと"そうしてきたのだろう。もし"ずっと"が数十億年単位であると仮定すると、地球は最初から10¹⁶クーロンを超える負電荷を持っていて、その間、宇宙線の陽子がその負電荷を打ち消すことができなかったのか、あるいは地球は他の方法で毎年少なくとも同量の負電荷を拾っているのか、という結論になる。いずれにしても、地球は電気的に中性でも正電荷でもなく、負電荷を帯びていることだけが、宇宙線の証拠に合致する。
一見すると、宇宙線の陽子が太陽系の内部に到達しているという事実に太陽放電説は戸惑っているように思える。どっちみちこの仮説では、太陽からの陽子が加速されて太陽系外に出ることが前提となっているからだ。そして実際に、局所的な擾乱が星間空間に及ぶ限り、これらの陽子が実質的にすべての放電電流を運ぶことになる。宇宙線も──その99%が正電荷の粒子──同じように加速されて系外に追い出されるのではないだろうか?
しかし、太陽の駆動電位(太陽と放電の境界線の間の電位差)が100億ボルトのオーダーだとしてみる。そうすると、境界に到達した太陽の陽子は、100億電子ボルトのエネルギーを持って星間空間に飛び出す。それ自体が宇宙線になるのだ。
天体物理学者によると、太陽はエネルギーを放射するという点では、かなり平凡な星だそうだ。もし太陽が電気的に動いているとすれば、その平凡さの原因のひとつは、比較的パッとしない駆動電位にあると、少なくとも暫定的には結論づけることができそうだ。つまり、より高温で高光度の星は、太陽よりも大きな駆動力を持っているはずであり、その結果、太陽宇宙線よりも大きなエネルギーの宇宙線を放出するはずだ。
駆動電位──カソードドロップ(陰極降下)という言葉の方がしっくりとくる──が200億ボルトしかない星は、太陽に届くほどのエネルギーを持つ陽子を排出し、100億電子ボルトのエネルギーの余裕を持って到達する。このようなものは、私たちが地球上で知っている平均的な宇宙線に過ぎない。実際には、銀河宇宙から1,000億電子ボルトのエネルギーを持つ粒子が地球に到達しており、そのような宇宙線に対しては、太陽が想定している100億ボルトのカソード・ドロップの逆電界は無視できないものになる。
これらのことから、私は、地球に到達する宇宙線の陽子やその他の原子核は、太陽以外の星の使用済みの電流キャリアに他ならないと考えている。これに関連して、興味深いのは、我々の銀河系における宇宙線のエネルギー密度の計算値が、星の光を含む電磁放射の総エネルギー密度に匹敵するということだ。これは、電気を帯びた星が原因であるとすれば、当然のことである。
IV(彗星の尾に関する大雑把な説明)
このように、一見『衝突する宇宙』の主題からは大きく外れてしまったようだ。とはいえ、太陽系内の問題に何らかの意味を持たせるためには、遠くの星や銀河系外縁部といった宇宙空間の天体物理学的な問題に、このように踏み込んでいく必要があると私は確信している。ブルースの言うように銀河系が電気を帯びているとすれば、その事実は太陽系に大きな影響を与えざるを得ない。銀河系が電気を帯びていないとすれば、太陽系内の電力の供給(帯電)の証拠と、それを否定するような天体の動きとを調和させる見通しは、今後も立たないように思われる。
(以下、原文では赤い字で強調されています)
本稿の冒頭で、空間電荷シースと彗星の尾の話に戻ることを約束した。実は、太陽を中心とした放電を想定した場合、これらは二つのテーマではなく、一つのテーマのふたつの側面に過ぎないように思われる。
極端に偏心した軌道を持つ彗星は、太陽系の最果てで過ごす時間が圧倒的に多い。これは、ケプラーの法則により、遠日点付近の軌道速度が近日点付近の軌道速度よりも非常に小さいためである。放電仮説が要求するように、このような地域の空間ポテンシャルが太陽の近くよりも負の意味で非常に大きいとすれば、長周期彗星は太陽から遠く離れたところにいる間に、局所的な空間ポテンシャルを容易に獲得することが期待される。また、かなりの確率で彗星の表面に蓄積された電荷に反応して、彗星本体の物質が電気的に分極される可能性もあるだろう。
次に、この電荷を帯びた電気的に分極化した物体が、軌道上で太陽に向かって速度を増しながら戻ってくるとどうなるかを考えてみよう。木星の軌道に到達する頃には、太陽風の陽子が表面の負電荷を剥ぎ取ってしまう。表面電位はもはや周囲の電位と一致していないが、内部(半径方向)の分極により外部電界が発生している。ちょうどワックスでできたエレクトレットの分極が地球上で外部電界を示すように。彗星の異質な電界から惑星間のプラズマを守るために、空間電荷のシースが形成され始める。
彗星が太陽に向かって走ると、シースは長い尾の形になって太陽から伸びていく。これは、電気を帯びた太陽が尾部の物質をはじくからではなく、彗星と惑星間プラズマの電圧差が方向によって大きく変化し、シースの厚さが電圧差だけでなくガス圧によっても決まるからである。彗星の頭部と太陽方向のプラズマとの電位差は相当なものになるかもしれない。しかし、いずれにしても、太陽から遠く離れたプラズマと彗星の間の電位差は、さらに大きくなる。また、プラズマの密度は、太陽に近い方が遠い方よりも大きい。したがって、シースは太陽に向かう側では彗星の近くに留まり、反太陽側ではおそらく数百万マイル先の宇宙にまで達している。
このような彗星の尾に関するかなり大雑把な定性的説明は、ここでは彗星の尾の謎に対する最終的な答えのようなものとしては説明しない。少なくとも放電仮説に照らして議論できる説明の一例として掲載しているに過ぎない。願わくば、惑星間プラズマが彗星の尾のガスが太陽の電荷に反発するという考えを打ち砕くという事実に騙されたと感じている人にも、この説明が慰めになることを願っている。
同じように分析すると、地球は宇宙環境にそぐわない電位を持っていて、そのために空間電荷のシースに包まれているという結論になる。彗星のシースが太陽から離れて細長くなっているのと同じ理由で、地球のシースにも尾があると考えられる。つまり、地球のシースは地球のいわゆる磁気圏と同じだと考えている。
地球の"磁気の尾(磁気圏尾部)“は火星まで達していないので、このふたつの惑星はもはや電気的にはお互いに干渉しないということがかなり確立されているようだ。
(しかし、月は毎月地球のシースに入ったり出たりしているので、重力以外の力で動かされているように見える。──ヴェリコフスキー博士が何度も強調していたことである)
しかし、火星を地球から安全な距離の軌道に乗せるためには、地球の空間電荷のシースが長く伸びていることが重要な役割を果たしたと考えられる。
今から100年前、ジェームズ・クラーク・マクスウェルは、その記念碑的な著書『電気と磁気に関する論文』の中で、次のような予言的な言葉を残している。
「放電現象は非常に重要であり、その理解が深まれば、電気の性質だけでなく、気体や宇宙を覆う媒体の性質にも大きな光を当てることになるだろう」
その後50年間、放電の研究は精力的に行われ、世界はエレクトロニクスの時代へと導かれていった。しかし、その後、1970年にノーベル物理学賞を受賞したハンス・アルヴェーン教授は思い出させた(念を押した)(26)。
「ほとんどの理論物理学者は、複雑で厄介で、数学的にエレガントな理論にはまったく向かないこの分野を見下していた」
理論家たちは、"数学的にエレガントな"理論につながる気体の運動論を用いてプラズマ物理学にアプローチすることを好んだと、アルヴェーンは言う。
アルヴェーンの評価は
「今日の宇宙プラズマ物理学は…… ある程度、実験室でプラズマを見たことのない理論家の遊び場である。彼らの多くは、実験室での実験で間違っていることがわかっている公式をいまだに信じている…… 宇宙プラズマの理論の基礎となっているいくつかの基本概念は、宇宙で起こっている状況には適用できない。それらは、ほとんどの理論家によって"一般的に受け入れられている"ものであり、最も洗練された数学的手法を用いて開発されたものである。しかし、その理論がいかに美しいものであるかを"理解"できず、それらに従うことを絶対的に拒否しているのは、プラズマそのものだけである……」
アルヴェーンの発言の意味するところは明白である。天体物理学者は、これまで軽視されてきた放電現象の分野に熱心に取り組まなければならない。少なくとも私は次のように考えている。そうすれば(天体物理学者が放電現象の分野に熱心に取り組めば)新しい研究の流れは、星が熱核で動くという考えを、すぐに否定することになるだろう。
参考文献
- I. Velikovsky, Worlds in Collision (Doubleday, New York, 1950).
- I. Langmuir, Collected Works (Pergammon Press, 1961), Vols. 3 & 4.
- Velikovsky, Cosmos Without Gravitation (Scripta Academica Hierosolymitana, 1946), p 18.
- H. A. Rowland, American Journal of Science, (3)15 (1878), 30-38; cited by F. Sanford, Terrestrial Electricity (Stanford University Press, 193 1), P. 79.
- J. W. Warwick, Phys. Earth Planet. Interiors, 4 (North-Holland, 1911), p 229.
- P. Dyal and C. W. Pirkin, Scientific American (August, 1971),66.
- D. Menzel, Proceedings of the American Philosophical Society, 96 (1952) 525.
- F. Sanford, Terrestrial Electricity (Stanford University Press, 1931), p. 80.
- Gilbert’s Annalen, 15 (1803), 386; cited by Sanford, ibid., p. 106.
- F. Sanford, op. cit., p. 107.
- Ibid., p. 107.
- J. O’Neil, Prodigal Genius – The Life of Nikola Tesla (Ives Washburn, 1944), 178.
- Science News (November 20, 1971).
- F. A. Lindemann, Philosophical Magazine, Series 6, Vol. 38, No. 228 (December, 1919), 674.
- F. Hoyle, Frontiers of Astronomy (Mentor Books, 1957), p. 103.
- M. Minnaert , Chapter 3 in The Sun, G. P. Kuiper, ed. (University of Chicago Press, 1953), pp. 171-172.
- M. A. Cook Bulletin of the University of Utah, Vol. 46, No. 16 (November 30, 1955).
- C. E. R. Bruce, A New Approach in Astrophysics and Cosmogony (London, 1944).
- C. E. R. Bruce, Problems of Atmospheric and Space Electricity, S. C. Coroniti, ed., (Elsevier, 1965), pp. 577-96.
- Private communication, September 21, 1965.
- E. Parker, Astrophysical Journal, 128 (1958), 664-67.
- See, for example, M. D. Montgomery et al, EOS Transactions of the American Geophysical Union. Vol. 52, No. 4 (April, 1971), 336; and K. W. Ogilvie et al, Journal of Geophysical Research, Vol. 76, No. 34 (December 1, 1971) 8165ff. See also J. V. Hollweg, Journal of Geophysical Research, Vol. 76, No. 31 (November 1, 1971),749lff.
- J. Lemaire and M. Scherer, Journal of Geophysical Research, Vol. 76, No. 31 (November 1, 1971), 7479ff.
- J. T. Gosling, R. T. Hansen, and S. J. Bame, Journal of Geophysical Research, Vol.
76, No. 7 (March 1, 1971), 1811ff. - Science News (June 13, 1970).
- Lecture published in Science, 172 (June 4, 1971), 991-94.
PENSEE Journal II
最後までお読みいただき、ありがとうございました。