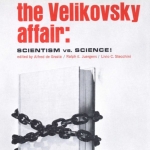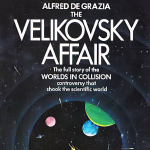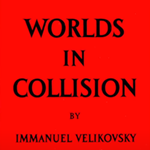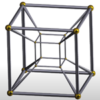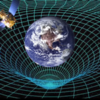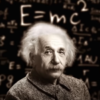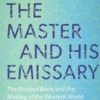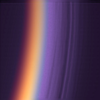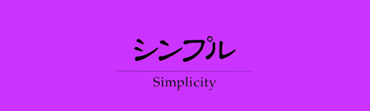ヴェリコフスキー事件 ─ 科学主義 対 科学②リヴィオ・ステッキーニ教授
金星が最近形成された惑星であるという仮説をめぐって
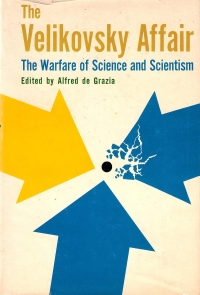
科学主義対科学』初版
「ヴェリコフスキー事件、科学主義 対 科学」の2回目はリヴィオ・カトゥッロ・ステッキーニ教授の寄稿を三つ紹介します。ステッキーニ教授の論文も日本で紹介されるのは、おそらくこれが初めてだと思います。
天体の動きをどう解釈するのか、プラトン、アリストテレスから始まり、ガリレオ、ニュートン、ラプラスなどの思想の変遷。また、古代バビロニアの楔形文字を解読し、碑文を初めて正確に解読した人物として知られるクーグラーとファエトンの神話の関係など、かなり突っ込んだ哲学的視点からの分析です。この二番目の論文は楔形文字解読の歴史としても面白いです。例えば、
「クーグラーの著書の核心となる考えは、最もよく知られながらも最も奇妙なギリシャ神話の一つであるファエトンの神話が、紀元前1500年頃に歴史的に特定可能な実際の物理的現象に基づいているというものだ。クーグラーによれば、この時、空に太陽の光よりも輝かしい天体が現れ、ついに地球に衝突したという:"かつて確かに、火と洪水の同時の大惨事が実際に起こったのだ"……」
「……しかしクーグラーによれば、これらは全て単純な事実で説明できる。金星は時折、太陽や月と同様に指針に影を落とすほど明るく輝き、また昼間でも視認可能な明るさになることがあるからだ。実際、汎バビロニア主義者もクーグラーも、金星を “太陽のように輝くダイヤモンド" や “空の真ん中に現れる威厳ある奇跡的な姿" といった表現で記した楔形文字の文書については説明できなかった」
背景にあるのは、ヴェリコフスキーが、合理主義者であり、宗教的信仰の敵だと非難され、一方で、宗教的迷信や聖書原理主義のために科学を転覆させようとしていると非難されていたこと。つまり、合理主義すぎると批判され、同時に宗教的すぎるとも非難され、両極から同時に攻撃されていたことです。
著者の略歴を「ヴェリコフスキー百科事典」から引用します。
リヴィオ・カトゥッロ・ステッキーニ(1913年10月6日 – 1979年9月)は科学史家であり、ニュージャージー州パターソン州立大学の古代史教授だった。彼は1963年9月発行の『アメリカ行動科学者』誌のイマニュエル・ヴェリコフスキー特集号に寄稿し、その後改訂・増補されて書籍『ヴェリコフスキー事件』(1966年)として出版された。
アルフレッド・デ・グラツィアは次のように記している:
「フライブルク、ローマ、ジェノヴァ、ハーバードで哲学、法学、古代史の学位を取得したステッキーニ博士は、ヴェリコフスキー研究において特別な位置を占めている:1978年版『ヴェリコフスキー事件』の序文で、デ・グラツィア博士が指摘したように、彼が初めてヴェリコフスキーの思想に触れたのはリヴィオ・ステッキーニによる紹介によるものだった。この紹介が『アメリカ行動科学者』の特集号につながり、問題を広く一般に知らしめ、最終的に『イェール・サイエンティフィック・マガジン』や『パンセ』をはじめとする後続の学術誌における調査研究の契機となった。彼の特別な関心は古代の測定単位にあり、ピーター・トンプキンスの著書『大ピラミッドの秘密』にこの主題に関する貴重かつ広範な付録を寄稿した。
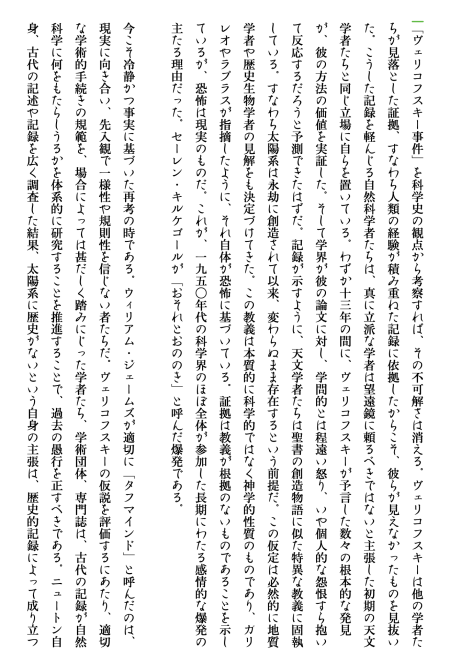
記事の内容を書籍の体裁で組んでみました。使ったフォントは私が10数年前に作成したものです。
3. 移ろいゆく天界
リヴィオ・C・ステッキーニ著
現代天文学体系は今や全ての探究者に広く受け入れられ、初等教育の不可欠な要素となったため、我々は通常その根拠を厳密に検証しない。この主題の初期著述家たちを研究することは、今や単なる好奇心の対象となっている。
── デイヴィッド・ヒューム『自然宗教をめぐる対話』(1779年)、第二部
ほんの数年前まで、天体の運動が電磁界の影響を受けるというヴェリコフスキーの主張を、天文学者たちは一様に荒唐無稽として退けていた。今日では創造的な天文学者たちが電磁気学の研究に没頭している。歴史家は、この変化がいかに急進的であるかを説明するのに苦労する。それは300年にわたる宇宙論的思考に挑戦し、我々をウィリアム・ギルバート(1544-1603)やヨハン・ケプラー(1571-1630)の議論へと逆戻りさせたのである[1]。この革命の新しさは、アインシュタインとヴェリコフスキーの書簡交換に明らかだ。アインシュタインは地球規模のカタストロフィー仮説をすぐに妥当と認め、当初は完全に反対していた、金星が最近形成された惑星であるという仮説にも、最終的には理解を示すようになった。しかし彼は生涯を通じて、電気と磁気が天体の運動に影響を与えるという主張を頑なに否定し続けた。
宇宙探査機から得られた新たな宇宙像の示唆に天文学者たちが困惑する一方で、ヴェリコフスキーは最初から明確だった。10年前に彼と交わした最初の会話の一つで、彼はこの考えをこう要約した。彼の研究が示す意味の一つは、宇宙の構造理解においてデカルトをニュートンの正当な対抗者として再評価することだと。ヴェリコフスキーは、天体力学における二つの見解の有名な対決の結果について、ハーバート・バターフィールドによる以下の総括を引用した。「物質で満たされ渦巻く現象に満ちたデカルト的宇宙観に対し、科学的な観測によってその存在が裏付けられなかったのに対し、清浄で比較的空虚なニュートン的宇宙観が最終的に勝利を収めた」[2]。
ヴェリコフスキーはこの証拠が発見されると確信しており、実際に見つかった。電荷と磁場を考慮した新たな研究が、まず彗星の挙動、特に太陽近傍での行動を説明することに成功するだろうという合理的な根拠がある。現在の説明、すなわち太陽光の圧力が彗星の頭部が近日点に近づいた際に尾を剛体棒のように巨大な速度で駆動するという説は、ニュートンが提唱した説 ─ 彗星の尾が太陽から離れるのは、火の煙が大気中で垂直に、あるいは移動物体の場合には斜めに上昇するのと同じ理由による ─ より満足のいくものではない[3]。その後、地球や木星のような惑星の場合、それらは磁気圏に囲まれ、太陽系に浸透する磁場とそこを吹き抜けるプラズマ風の中を移動する。この点についても、定量的な分析が行われることになるだろう。
太陽系のメカニズムへの新たな参加者が現れることで、その安定性の問題は新たな光を当てられることになる。
心理的前提(根拠)
精神分析の訓練と経験により、ヴェリコフスキーは人類が宇宙的大変動の蓄積された記憶や記録を寓話として片付けがちだと気づいた。聖書原理主義者でさえ、文字通り解釈すると主張する書物に平易な言葉で記された内容を、そのまま受け入れることはない。
ヴェリコフスキーの説で定められた最後の大変動から数百年後、アリストテレスはヘラクレイトスの宇宙論を論破しようと苦闘した。そしてキケロは、ルクレティウスやオウィディウスといった同時代の他の作家たちが詳細に起こったことを記述していたにもかかわら「世界はこれほど安定しており、永続のためにこれほどよくまとまっているので、この目的により適したものは想像すらできない」と宣言した[4]。惑星は神々であり、その神聖な性質ゆえに完全かつ不変の秩序を保っている。別の箇所でキケロは同じ見解を、中世のスコラ派自然哲学者たち、そして後述するようにニュートンの追随者たちにとっての信条となった言葉で展開している:
したがって天界には、偶然も、無目的な漂流も、信頼に足らぬものも存在しない。むしろ万物は完璧な秩序と信頼性と目的性と不変性を示している…… したがって、万物の支えと安全が完全に依存するこれらの天体の驚くべき秩序と信じがたい運動の精密さが、理性によって導かれていないと主張する者は、自ら理性の能力を全く欠いていると見なされねばならない[5]。
しかしこれは、神々の間の争い、すなわち惑星の神々の争いという古い信仰の逆転だった。プラトンの母の従兄弟であるクリティアスは、その劇『シーシュポス』において、デモクリトスとその追随者たちが擁護した反対の見解を強調した。すなわち、惑星の神々への信仰は、あらゆる人間の恐怖の中でも最悪のものと結びついているという見解である。以下の引用は、私が後述する問題、すなわち天体の構成が倫理の基礎と見なされるようになったという問題を明らかにしている:
彼[シーシュポス]は言った ─ 神々が住まうのは、
人々が最も恐れるその場所、
彼がよく知っていたように、
そこから人間は恐怖に襲われ、
あるいは苦しみを癒す救いを授かる。
それは高く、空の大きな円環の中、
稲妻が閃き、
雷鳴の不吉な轟きが響き渡り、
星々の顔が見える場所 ─
(時の巧みな細工が生んだ美しき造形)、
星の溶けた石が炎をまとって降り、
雨が地上への旅を始める場所。
彼は人々にそんな恐怖を送り、
その手段によって神々を
しかるべき住処に据えたのだった。
(言葉ひとつで成し遂げた見事な策略)
こうして彼は、無秩序を法によって鎮めた[6]。(copilot訳)
現代の作家たちも同様の疑念を抱いている。ジョン・デューイは『確実性の探求』(1929年)の冒頭に「危険の回避」と題した章を設けている。彼は、恐怖こそが不変の完全なる存在を求める原動力であり、多様性や変化を犠牲にして規則性と不変性を称賛する源泉だと指摘する。天体を神々として信仰する考えを合理化し、それらを理性的で規則正しく不変である高次の領域の表現(一層高い物理的・道徳的)と位置づけることで、アリストテレスは古典科学の基礎を築いた。
同様にフロイト[7]は問う。「人間は、外界と人間環境の双方の危険から身を守るために、いかなる基盤の上に安全感を築き上げるのか」と。その答えとして彼は宣言する。「カントの有名な格言を思い出せ。彼は星々の天と我々の心の中の道徳律を、一息に言及した。この組み合わせは奇妙に聞こえる。天体が、人間が他人を愛するか殺すかという問題と何の関係があるというのか。しかしそれは深い心理的真実を突いている」
フロイトが言及するカント(1724-1804)の一節は、『実践理性批判』の結論部分である:
二つのものが、思考する精神がそれらに向き合うほど、絶え間なく増大する驚嘆と畏敬の念で心を満たす。それは、我々の頭上に広がる星々の天と、我々の内に宿る道徳律である。
しかし星々の天は、古代人に遍在する恐怖を抱かせた一方で、我々に正当な安定感を与えるのだろうか?
ルネサンス宇宙論
ニコラウス・クザーヌス(1401-64)は『学識ある無知について』において、天と地の質的差異を否定した。彼はアリストテレス形而上学の関連命題の残りを退け、地動説を復活させ、地球は完全な球体ではなく、惑星の軌道は完全な円ではないと述べた[8]。彼は天体の運動に本質的な安定性はないと主張し、古代の著述家たちの記述の一部は、彼らが当時とは異なる空を見ていたことで説明できるという仮説を立てた。物理的宇宙について正確で永遠かつ絶対的な記述を定式化することは不可能であるため、彼は科学を「学識ある無知」と定義した。
コペルニクス(1475-1543)の立場は比較的保守的だった。なぜなら彼は、地動説を伝統的な円運動(太陽を回る)の概念や、恒星の球体に囲まれた有限宇宙の概念と結びつけたからである。コペルニクスへの反対は、彼が地動説に数学的構造を与えたことで、ニコラウス・クザーヌスが結びつけていた形而上学の転覆を支持することになったという認識によって決定づけられた。
創世記の本文への疑問はコペルニクス説の成り行きとして始まった。もし地球が太陽を回る惑星に過ぎないなら、その創造が天の神の摂理によるものだったとは疑わしい。コペルニクスの編集者オシアンダーの娘婿が、聖書物語の神聖な権威に対する最初の率直な異議を唱えた:「聖書の物語(ユダヤ人の神話)を持ち出して反論しないでくれ」[9]。学者たちは宇宙が一度限りで永遠に創造されたという概念に疑念を抱き始めた。彼らは古代年代学の研究に着手し、地質学と古生物学の基礎を築いた。
宗教改革の時代には、一部の宗教的弁証家たちが、宇宙全体の創造と地球の創造とは区別されねばならないと主張した。聖書の記述は後者の創造を指していた。
ジョルダーノ・ブルーノ(1548-1600)は、投獄直後に出版された最後の最高傑作『計り知れないものと数えきれないものについて』において、自然の無差別性の原理の主張の意味を明らかにした。彼は、自然界に摂理的な秩序が存在しないこと、したがって円運動説と結びついた太陽系の安定性も存在しないことを否定した。また、天体が円運動し、長期的には元の位置に戻るという考えは、当時の学者たちが不完全な天文観測しか行えなかったために生まれたと宣言した。(円運動およびあの世界年[※プラトン的宇宙周期、約26,000年の歳差運動など]の虚しさについて ─ プラトンや他の者たちの幻想に基づくもの)[10]。そして、天体の運動は必然的に無限に複雑である(差異と、それぞれの差異における不規則性。※自然界や宇宙の秩序は、単純な分類では捉えきれない)[11]と指摘した。
惑星の単純かつ規則的な運動への信仰は、幾何学的自然観への信仰と希望の下での占星術的思考の幻想的な産物だと彼は続けた。数学的天文学をプラトン的・ピタゴラス的な形而上学的付加物から解放することが必要だ。運動の相対性から時間の相対性が導かれる。完全に規則的な運動は発見できず、また、すべての天体が地球に対して以前と全く同じ位置を占め、その運動が厳密に規則的であったことを証明できる記録を我々は持っていないため、時間の絶対的な尺度を見出すことは不可能である[12]。
この新たな自然観は、ジョン・ダンの詩『世界の解剖』(1611年)に端的に表れている:
そして新しい哲学が、すべてを疑いの中に投げ込む……
人々は率直に認める、この世界はもう使い果たされたと。
彼らが惑星や天の大空に、
いくつもの新しいものを探し求めるとき、
この世界は再び砕かれ、微粒子へと崩れていく。
すべてがバラバラになり、つながりは失われた……
星々もまた、円を描いて走ると誇っていたが、
そのどれもが、始まりの場所に戻ることはない。
すべての均衡は崩れ、沈み、そして膨らむ。
※新しい自然哲学(科学)の登場によって、世界観が崩れ去る様子を、詩的かつ痛切に描いている。この詩は、コペルニクスやガリレオの時代に起きた宇宙観の転換を、まるで世界の崩壊のように描いている。[copilot]
ヴェリコフスキーは、天文学の研究を地質学、古代の伝承、古代年代学、古代科学と融合させたことで嘲笑されてきた。しかしそうすることで、彼はルネサンス期の学者たちの道を歩んだ。太陽系の不変性という教条的信念が疑問視されれば、そのような道筋は必然だからである。新しい天文学は古代の伝承や年代学に関する一連の研究を生み出し、エジプトやメソポタミアの科学への関心の誕生をもたらした。例えば、アタナシウス・キルヒャー神父(1601-80)は『地下世界』で地質学研究の礎を築き、『エジプトのオイディプス』でエジプト科学研究の先駆けとなった。ジョン・ノーデンは『物事の変遷』(1600年)においてこれらの思索に言及し、それらはヴェリコフスキーによって蘇った:
古代の詩人たちは、その詩の中で
とりとめのない寓話の奥に、神秘を語った。
パエトンの物語では、天の力が
炎の猛威によって反乱を起こしたことを。
ピュラとデウカリオンの歴史には、
水の激しさが描かれている
それは部分的に神意とも重なり合う ─
星々を見つめるエジプトの祭司たちは、
かつて火と水の争いによって
世界が悲惨な崩壊を経験したと語る。
そして、移ろいやすく貞節を欠いたこの世界は、
火と水に攻め立てられ、同じようには保てない。
地震と戦争、飢饉、憎しみ、疫病が、
地上に危機をもたらし、人間に不安を与える。[copilot]
サー・ウォルター・ローリーは『世界の歴史』(1616年)の中で、ガリレオが発見したばかりの金星の位相が、どうして古代の著述家たちに知られていたように見えるのかと疑問を呈した。彼は、オギュゲスの大洪水の際には「金星の星にこれほどの奇跡が起こった。前代未聞であり、後世にも見られないほどであった。その色、大きさ、形、そして軌道が変化した」と述べる権威者たちを列挙した。オギュゲスの名と結びついたカタストロフィー(大惨事)は、古代ギリシャ人にとっての時代区分であり、金星の完全な変貌と同時期に起こった。この記述は「ローマ人の中で最も博識な」ヴァロが、より古い科学者たちの権威に基づいて記したものである。太陽系の働きが最も精密な科学の域に達したニュートンの時代には、この記述が関心を喚起すべきだった。
しかし、古代著述家からの情報収集が新時代の天文学における複数の発見に寄与した一方で(地動説そのものもギリシャ・ローマの著述家の権威に基づいて提唱されていた)、ニュートンは古代資料を天文学研究の着想源とする慣行に終止符を打った。太陽系に歴史があるかもしれないという考えは(科学という新たな宗教の名のもとに)冒涜的なものとなった。中世の学者たちにとってそうであったように(聖アウグスティヌス、西暦354-430年、は古典作家の権威について異なる立場を取っていた)。
ニュートン宇宙論確立の前夜、宇宙的大変動に関する思索はごくありふれたものとなり、1672年にはモリエールが、新たな科学への情熱に駆られて天文学を学ぶ女性たちを風刺した戯曲『女学者たち(学者きどりの女たち)』(第四幕第二場)で、これを笑いものにすることができた。
素晴らしいニュースをお伝えします
奥様、私たちは寝耳に水でした
ある世界が私たちの横を通り過ぎました
私たちの渦中を通り抜けたのです
もし途中で私たちの地球に出会っていたら
ガラスのように粉々になっていたでしょう(フランス語)
(大変重要な知らせをお伝えに参りました。奥様、私どもは眠っている間に、危うく難を逃れました。一つの世界が私どものそばを通り過ぎ、私どもの渦に落ち込みました。もしその途中で地球と出会っていたならば、ガラスのように粉々に砕けていたでしょう)
ニュートン
“有為転変 mutability “という言葉で要約できるルネサンス的な人生観と世界観は、英雄的な気概を持つ人物たちによって創り出され、その維持にもそうした人物たちの指導力を必要とした。なぜなら、唯一の神が運命であり、測定と確率を超えて確かなものは何もない世界では、生きることが容易ではないからだ。フロイトが主張するように、神経症は、劣った生物学的素質と未熟な精神的成長が組み合わさった結果、何の恩恵も与えてくれない世界において、人間の条件の重荷に向き合うことに失敗することから生じるのだ。
ルネサンスの相対主義と分散化は天文学だけでなく政治理論にも表れ、マキャヴェッリのような思想家の影響は地理的発見によって増幅され、倫理的相対主義の教義を生み出した。イングランドでは、ルネサンス思想への反動の先駆けとなったのは神学者リチャード・フッカーだった。彼は、絶対的な理性と結びついた自然の法則、そして人間が絶対的な倫理に従うことへの訴えによって、新たな保守的立場を正当化できると考えた。『教会政体理法論』(1593-97年)において、彼は当時主流であった見解を検証した:
もし自然がその運行を中断し、たとえ一時的にせよ自らの法則の遵守を完全に放棄するならば。もしこの下界の万物を構成する世界の主要かつ根源的な元素が、現在有する性質を失うならば。もし我々の頭上に築かれた天の穹窿(アーチ)の構造が緩み、自ら解体するならば。もし天球が慣れ親しんだ運動を忘れ、不規則な回転で思いのままに動き回るならば。もし今や巨人として疲れ知らずの軌跡を走る天の光の君主が、衰弱したかのように立ち止まり休息し始めるならば。月が定められた軌道から外れ、年の時節が乱れ混ざり合い、風が息絶え、雲が雨を降らせず、大地が天の恵みを失い、地の果実が枯れた母の乳房で救いを求められぬ子のように萎れていくならば ― 今これら全てに支えられている人間自身はどうなるというのか? 万物が自然の法則に従うことが、この世界の支えであることは明らかではないか。
彼はニュートンや後続の科学者たちが受け入れた慰めの解決策を提案した:
しかし自然の軌道に時折生じるこうした逸脱があろうとも、自然の法則は自然の作用によって常に遵守されている。自然が営む事象が、常に、あるいは大部分において、同一の方法で営まれていることを否定する者はいない。
エレーヌ・メッツガー※は、ニュートンがこの反動的精神の影響下で理論を発展させたことを示している。彼女は、ニュートンの業績が「礼儀正しく、善良な考えを持つ体制的知識人層の同盟者となる運命にあった」[13]と判断した点では、確かに正しい。 しかし、ニュートンがなぜそのような保守的結論に至ったのか、またそれが科学にとって技術的にどのような意味を持つのかについては、詳しく分析していない。彼女の先駆的な研究は、アウシュヴィッツのガス室によって断たれた。
※ エレーヌ・メッツガーの科学史へのアプローチは、時代錯誤を避けようとした点で独創的だった。彼女は過去の科学者たちの思考を彼ら自身の言葉で捉え、その思想の起源を辿ろうとした。同時に、当時のフランス思想の潮流に沿い、科学史研究を “人間の精神"という普遍理論の枠組みに統合しようとした。彼女は、この精神理論があらゆる時代・文化に共通すると考えていた。今日では多くの科学史家が採用する反実証主義的な歴史手法こそが、メッツガーの研究が今も評価され活用される理由である(故トーマス・S・クーンが著名な『科学革命の構造』(1962年)でメッツガーを高く評価したことが、この点で決定的な役割を果たした)。同僚たちとの方法論的対立から、1930年代に彼女は自らの歴史記述法を解説する一連の論文を執筆した(『科学史における哲学的方法』に収録)。
以下の文は、1944年にアウシュヴィッツでナチスに命を絶たれる前、1936年に記されたもの
「進歩は本質的に儚いものであり、実際に消滅し得ます。文明社会が原始時代の野蛮さの攻撃的な復活から身を守るには、警戒心と一種の徳性によってのみ保証されます。そしてこの新たな野蛮さは、科学が生み出したあらゆる産業的成果を破壊するだろうから、特に危険です」
ヴェリコフスキーが自身の著作で言及する、地球の破滅的な過去という大筋の主張における先駆者の一人がウィリアム・ウィストン(ホイストン)(1667-1752)である。1717年、『プリンキピア』初版から7年後、当時ケンブリッジ大学のフェローであったウィストンはニュートンの熱心な弟子となり、2年後には『地球の新理論』と題する書物の原稿を師に提出した。この書物は当時流行していたトマス・バーネットの『地球論』(1681年)に取って代わることを意図したもので、ニュートンが20年以上も関心を寄せてきた主題を扱っていた。この書物は、旧約聖書に「大洪水」として記された大変動が紀元前3000年紀末の彗星衝突によって引き起こされたと主張している。また大洪水までは太陽年が360日しかなかったが、365日の新暦はナボナッサル(紀元前747年)によって導入されるまで待たねばならなかったと述べている。これらの主張は主に歴史的証拠に基づいていた。一方、彗星が惑星となり得るという仮説の根拠は、主に天文学的考察に基づいていた。
彗星はあらゆる惑星と方向の領域を通過するゆえに…… 惑星に巨大な変異をもたらすのに適合しているように見える。特に惑星が大気圏を通過する際に洪水や大火災を引き起こす…… 確かに現時点では混沌とした世界、あるいは混乱した世界のように見えるが、軌道がより円形に近づき、秩序ある状態へと落ち着き、惑星のように居住に適した状態へと変化する可能性はあり得る。しかしこれらの推測は、神の摂理が我々にさらなる光を授ける時、さらなる探究に委ねられるものである[14]。
ニュートンはウィストンの著作に深く感銘を受け、その時から彼と緊密な科学的関係を築いた。この本はジョン・ロックら他の同時代人からも高く評価された。2年後、オックスフォードのサヴィリアン天文学教授ジョン・キール(ケイル、1671-1721)は、バーネットの仮説と比較したウィストンの仮説を評価する本を献呈し、その中で次のような見解を示した:
……しかし、新地球理論の独創的な著者であるウィストンが、過去の理論家たちよりも優れた哲学的原理に基づいて偉大な発見を成し遂げたことは認めざるを得ない。彼の理論には、大洪水時に彗星が地球を通過したという可能性を確かに示唆する一致点がある[15]。
キールはまた、この大変動以前には太陽年が360日であり、12の太陰月(各30日)に分けられていたという主張も支持した。
1701年、ウィストンはケンブリッジ大学でニュートンの臨時代理に任命された。そして1703年、ニュートンがルーカス数学教授職を永久に辞任した際、彼はウィストンを唯一の後継者として推薦した。1713年、『プリンキピア』第二版が刊行される頃には、ニュートンのウィストンに対する感情は根本的に変わっていた。1720年、天文学者エドモンド・ハレー(1656-1742)らがウィストンを王立協会の会員候補として推挙した際、ニュートンは「会員がウィストンの入会を承認すれば、自分は協会会長職を辞任する」と脅した。ニュートンに深く忠誠を誓っていたウィストンは、自身の立候補を強行しないよう提案した。老齢のニュートンがこの問題に激しく動揺し、命を落とすかもしれないと考えたからだ[16]。ウィストンの『地球新理論』出版の1年半前、ハレーは王立協会で論文を発表し、大洪水を彗星衝突で説明していたが「不用意な表現で聖なる秩序の非難を買う恐れがある」として印刷を控えていた。彼はニュートンの行動に対し、30年の遅れを経て協会の議事録に回想録を掲載することで応じた[17]。科学史家はこの事件を軽視するが、ニュートンの思想変遷を理解する上で極めて重要である。1710年以降、異端の疑いで教職を解かれたウィストンは、英国国教会の主教会議で正式に裁判にかけられた後、より過激な立場を取るようになり、次第に保守的になっていったニュートンと対立するようになった。
ウィストンの主張は、創世記に記された創造物語を文字通り解釈すべきではなく、幾つかの宇宙的段階を経て進行する創造過程を指すものと解すべきだというものだった。当初、ウィストンの宗教的・科学的見解に共感していたニュートンは、その急進性に衝撃を受け、原理主義的な立場へと転向した。『光学』の結語は、ニュートンが当時の他の者たちと同様に、宇宙秩序に関する伝統的見解が放棄されれば、道徳の基盤が損なわれると考えたことを示している[18]。さらにニュートンは、ウィストンの仮説が、神の存在を証明する主要な論拠である「設計の論証」― すなわち、現在の自然の枠組みが生き物、特に人間の必要に賢明に適応しているという主張 ― を最終的に否定することになると感じた。『光学』において、ニュートンはウィストンを次のように反駁した:
天体を創造した者が秩序を定めたのは当然である。もしそうであるならば、世界の起源を他の何かに求めたり、単なる自然法則によって混沌から生じ得ると主張したりするのは非哲学的である。もっとも、いったん形成された世界は、それらの法則によって長きにわたり存続しうる。彗星が極めて偏心した軌道であらゆる位置を移動する一方で、盲目の運命が全ての惑星を同じ軌道で移動させることは決してありえない。わずかな不規則性を除けば、それらは惑星と彗星の相互作用から生じたものであり、この体系が再構成を必要とするまで増大する傾向にある。惑星系のこのような驚くべき均一性は、二者択一の結果であると認めざるを得ない[19]。
『プリンキピア』初版(1687年)は本質的に合理主義的精神に則り実証主義的手法を踏襲しているが、第二版(1713年)では神学的な関心事が支配的である。ニュートンは、世界の仕組みがあまりにも完璧に設計された体系であるため「機械的な原因」の結果ではなく、知性ある一貫した計画の結果でなければならないことを証明しようと固執した。さらに、世界が単一の行為によって創造されたという創世記の物語を支持するため、世界は安定しており、創造以来変わっていないとも主張した。しかしこの点は証明できなかった。なぜなら彼自身の理論によれば、太陽系の各天体間の引力は軌道を変化させる傾向があることを認めていたからだ。したがって彼は問題を回避し、神の摂理が時折介入して天の時計仕掛けを元の状態にリセットしなければならないと主張した。このニュートンの信条の核心はよく知られている。数学分野におけるニュートンの大いなるライバル、ライプニッツ(1646-1716)が皮肉を込めて論じた対象だからだ。その書簡で所見を述べたように、ニュートンは神を単なる時計職人(しかも下手な)としてだけでなく、時計修理人としても描いた[20]。
ラプラスが選んだ弟子ジャン=バティスト・ビオ(1774-1862)は、師と同様に『プリンキピア』第二版を非常に好ましくないものと見なしていた。彼はニュートンが1695年以降、創造的思考者でなくなったと主張し、その原因を18ヶ月に及ぶ精神疾患に帰した[21]。しかし実際には、ニュートンを妨げたのは精神の衰えではなく、宗教への執着だった。ビオが精神崩壊の証拠として提示する唯一の外部的事実は、1714年にウィストンとのやり取りで見せたニュートンの"幼稚な"振る舞いである。私の見解では、ニュートンが宗教的問題に固執するようになったものの、知的な柔軟性を全く失っていなかった証拠は、『プリンキピア』第三版(1726年)に現れた、わずかな追加部分にある。そこでは、神は物事の外見ではなく、人類の営みの中に自らを現すと彼が信じるようになったことが明らかになっている[22]。
学者たちは、ウィストンの学説の反駁がニュートンにとって重大な関心事だったことに気づいていない。『プリンキピア』において彼は、彗星は破壊的な要素どころか、元の秩序を摂理的(神意による、天の配剤)に維持するのに寄与すると主張した。地球の水の一定量は化学結合によって絶えず消費されるため、彗星の蒸発によって新たな水が供給されなければ、海は元の状態を保てないというのだ。彗星の摂理的目的という概念は、ニュートンの時代にもさらに発展した。彗星はまた、さもなければ次第に自らを消耗してしまう太陽に新たな燃料を供給する目的でも存在する。ニュートンの思想を広く普及させた重要人物の一人は、彗星がこうした摂理的機能を果たし得る一方で、同時に摂理によって地球への衝突を阻まれていると強調している:
次に、彗星の運動面が黄道面や惑星軌道と一致しない理由は極めて明白だ。もし一致していたなら、地球が彗星の尾の軌道から逃れることは不可能だっただろう。いや、彗星の天体が地球と直接衝突する可能性は頻繁に起こりうる。しかも彗星の速度がどれほど速いかを考えれば、二つの天体が衝突すれば互いに破壊し合うのは必然だ。さらに、惑星の住民は彗星の尾に頻繁に浸される状況に置かれれば、長く生き延びられないだろう。ましてや、惑星と彗星の軌道が全て同一平面上に配置されていた場合、それらの運動に生じざるを得ない不規則性と混乱については言うまでもない[23]。
著者はここでニュートンの論理に従っている。ニュートンは宇宙の摂理的な秩序が彗星に有益な特性を持つことを要求すると主張した。実際には、一部の彗星の軌道面は黄道面に対してわずかな角度をなしており、衝突の可能性は存在する。
ニュートンの伝記は、彼が晩年を捧げた著書『改訂 古代王国年代記』(1728年)を数行で片付けることが多い。彼らはこれを無関係な副次的な活動の産物と見なす。しかしその目的は明らかにウィストンの仮説を反駁することにある。ニュートンは、365日暦の証拠が紀元前887年まで遡ると主張し、この年がそれ以前には「ほとんど一般に普及していなかった」とはいえ、エジプト人の最初の天文観測と同じくらい古いと論じる。しかし、それらは紀元前1034年というかなり遅い時期に始まったに過ぎない。本書の主目的は、紀元前776年の第一回オリンピック競技大会以前には、信頼できる歴史はほとんど存在しなかったと主張することにある。最初のページで、古代の伝説や伝承(ウィストンが彗星による大災害を主張する根拠)は信頼できる情報源ではないと指摘されている。
ニュートンは、自身の宇宙論(『プリンキピア』第二版の有名な「一般注記」にまとめられた)が、ウィストンを反駁しない限り受け入れられないと信じていた。このため、第二版の刊行から約3か月後、ニュートンは大英博物館に未公開のまま残されている論文を執筆した。そこではウィストンと親交のあったウィリアム・ロイド(1627-1717)による批判 ─ 古代最古の暦は360日の太陽年に基づいているという主張 ─ に反論している。この文書から分かることは、ニュートンの反論が不十分なものだったということだ[24]。彼は、閏日制度なしで360日の暦が使われていたなら、季節の公式な始まりは70年周期で1年分ずれるはずだと主張した。しかしこの70年周期の痕跡は存在しないため、そのような暦は存在し得ないというのだ。しかしウィストンとロイドの主張は、太陽年が約360日であるため閏日が必要ないというものであった。ニュートンは太陽年が常に365日で構成されていると仮定することで、問題を先送りしていた。
ニュートンの著作において、太陽系の永遠の安定性という教義は、科学的データではなく摂理的秩序への信仰に基づく仮定として明確に提示されている。しかしニュートン主義を18世紀の基本教義とした大衆化の洪水は、ニュートンが信仰によって受け入れた驚異的な秩序について科学的数学的証明を提供したと主張した。この展開を『18世紀哲学者の楽園』(1932年)で検証したカール・L・ベッカーは、啓蒙思想家たちが自らを反キリスト教的あるいは無宗教的と信じつつも、ニュートンの力学(彼の宗教観ではなく)の名のもとに、ニュートンと共に中世神学の教義へ回帰していたと結論づけている。13世紀以来、信仰と理性のこれほどの結びつきはなかった。再び、不変の天体の動き ─ 神の完全性と永遠の法則の証 ─ に目を向けることが可能となった。ベッカーが指摘するように、ニュートン主義が教養ある大衆に即座に受け入れられたのは「普遍的な調和と共鳴したいという欲求が、人間の胸中に永遠に湧き上がる」からである[25]。
優れた歴史教科書は皆、ニュートンの天文学が宗教革命を引き起こしたと指摘している。ニュートンは自らが「啓示された宗教と一致する自然宗教」と呼ばれる宗教観を説いたことを完全に自覚していた。この新宗教は有神論と呼ばれ、そのニカイア信条(キリスト教の信仰を要約している公式の信条)は『プリンキピア』の「一般的注解」だった:
六つの主要な惑星は、太陽を中心に円を描くように公転している。その軌道は太陽と重なり合い、同じ方向へ向かい、ほぼ同じ位置にある。十の衛星が、地球、木星、土星の周りを、それらの天体と重なる円軌道で回っている。運動方向は同じで、それらの惑星の軌道面にもほぼ沿っている。しかし、彗星が非常に離心率の高い軌道で天球のあらゆる領域を移動することを考えると、単なる機械的な原因だけでこれほど多くの規則的な運動が生まれるとは考えられない。そのような運動によって彗星は惑星の軌道域を容易に通過し、極めて高速で移動する。また最遠点では、最も遅く動き、最も長く滞留するため、互いに最大距離まで離れており、相互引力による干渉を最小限に抑えられる。この太陽・惑星・彗星からなる最も美しい体系は、知性と力を備えた存在の摂理と支配によってのみ成り立つ。
ニュートンの思想が一般化される過程で、有神論は理神論(自然神論)へと変容し、その思想はラ・メトリー(1709-51)やドルバック(1723-89)の機械論的無神論へと発展した。これらの宗教観に共通していたのは、機械式時計の比喩で表現される宇宙の完璧な規則性への信仰である。「時計仕掛けの宇宙という理想は、17世紀が18世紀の理性時代に与えた偉大な貢献だった」[26]
現代の自然科学者の中には、これらは現代天文学のような観察科学とは無関係な形而上学的な関心事だと反論する者も少なくないだろう。しかし、自分たちには形而上学など存在しないと信じる者ほど頑固な形而上学者もいない。これは時宜にかなった例によって証明できる。
金星は地球に最も近い惑星であり、その大きさは地球と非常に似ている。つまり金星は地球の双子の姉妹のような存在だ。したがって、ニュートンと同様に自然の規則性を信じる者たちは、金星も約24時間で自転し、我々の月と似た衛星に囲まれているに違いないと推測した。18世紀には多くの天文学者がこの衛星を観測し追跡したと主張した。1769年の金星の太陽面通過後、ランバート(星雲説を提唱した一人)はこの衛星の軌道と大きさ(我々の月の28/27)を計算した。その後、望遠鏡の性能が向上したため、後世の天文学者たちは存在しないものを観測できなくなった。ニュートンによれば、金星の自転周期は地球と同様の23時間だった[27]。ジャック・カッシーニはこの数値を23時間20分に修正し、18世紀末には23時間21分20秒が定説となった。さらに1世紀の観測を経て23時間21分の数値が受け入れられるようになったが、1877年にジョヴァンニ・ヴィルジニオ・スキアパレッリは金星の自転が極めて遅く、おそらく1金星年 Cytherean year に1回転すると結論づけた。それでもなお、多くの天文学者が数十年にわたる観測報告を発表し、金星の自転周期が約24時間であるというニュートン派の見解の正しさを証明した。ドップラー効果の欠如や極部の扁平化がさらにこの見解を裏付けたにもかかわらず、金星が自転するとしても非常に遅いというスキアパレッリの見解は、1963年まで多くの天文学者に受け入れられなかった。
天文学者たちが、望遠鏡を通して見ていたものが、実は “心の目" で見ていたものだったと気づくまでには、2世紀半もの歳月がかかった。一方、哲学者デイヴィッド・ヒューム(1711–76)は、金星の研究における認識論的な問題をいち早く見抜いていた。彼はニュートン主義者の言葉を引用する ─「金星もまた地球ではないか? 我々が同じ現象を観察する場所なのだから」。 これに対してヒュームは、仮想の対話の中でガリレオの権威を引き合いに出し、こう反論する:「自然がこの小さな地球上で、かくも多様な働き方をしているというのに、その自然が、広大無辺な宇宙の中で、ひたすら自らを模倣し続けているなどと、我々は本当に想像できるだろうか?」[28]
※ヒュームが問いかけたのは「金星も地球と同じだ」と言うニュートン主義者の言葉には、秩序ある宇宙への信仰が透けて見える。でもヒュームは「この小さな地球ですら自然は多様なのに、宇宙全体が同じだなんて、そんな単純な話があるか?」と、認識の傲慢さを静かに突いている。(copilot)
金星の自転の事例は、科学者がニュートンの天文学的教義を全て受け入れる際に、神秘的なものと現代的意味での科学的なものを識別せずにいると生じる知的混乱の小さな例である。
王立協会ニュートン生誕300周年記念(ケンブリッジ、1947年)のために書かれた『ニュートンという男』という鋭く洞察に満ちた論文の中で、ケインズ卿はこう宣言した:
18世紀もそれ以降も、ニュートンは近代科学の最初の偉大な科学者、合理主義者として見なされるようになった。冷徹で教育を受けていない理性の枠組みで考えることを教えた人物としてだ。私は彼をそのような視点では見ていない。
この論文の主たる主張は、ニュートンが「片足を中世に置き、もう片方の足で現代科学への道を歩んでいた」というものだ。この主張は以前から他の学者によって提唱されていたが、今回は傑出した科学史家たちの賛同を得た。なぜならケインズはニュートンの未発表原稿にアクセスできたからである。
ニュートンの場合、3世紀にわたり、彼の崇拝者たちが学術的著作の約9割の公表を阻止するため、戦い続けてきたという特異な事例に遭遇する。ウィストンはニュートンの原稿公表を最初に叫んだ一人であり、彼自身の歴史理論を反駁する機会を得たかったからだ。公表への努力が実を結び始めたのはごく最近のことである。
もし全原稿が出版されれば、一部の学者が主張し、ニュートン自身が書簡で認めた事実が明らかになるだろう。すなわち、科学は彼の主たる関心事ではなく、神学の補助手段 ancilla theologiae(神学の侍女※)として捉えられていたということだ。彼が科学分野で並外れた成功を収めた事実は、天文学と宗教の調和を図ることが彼の主目的だったという主張を否定しない。ニュートンは、コペルニクスやガリレオの名と結びついた天文学革命が宗教的信念の基盤を破壊したと考え、中世的世界観への回帰が必要だと信じていた。彼は聖書原理主義者であり、とりわけ聖書に未来の歴史に関する予言が含まれていることを証明しようとした。彼の科学への関心は、科学さえも聖書的宗教と矛盾しないことを証明しようとする努力の副産物だった。彼が構想した聖書的宗教とは、聖書的宗教とプラトン・アリストテレス的宇宙論を中世的に統合したものと見なされていた。
※神学の侍女:哲学は神学の婢(はしため)、哲学は神学の侍女。哲学が神学に従属している状態を指す語。しかしこの言葉が,スコラ学における両者の関係を示すものとして,非難あるいは軽べつの意をこめて用いられるようになったのは近代以後であり,この表現を最初に用いたとされるペトルス・ダミアニにおいては,哲学的学問の越権を戒めるために用いられている。トマス・アクイナスも,神学は哲学的学問をいわば下位のもの,侍女として用いる,と語っているが,哲学がその固有領域に関して自律的であることを否定してはいない。
ニュートンの膨大な未発表著作は錬金術から政治まで多岐にわたるが、その大半は神学が占め、次いで古代史が続く。これらの未発表著作は単なる気まぐれな試みとして片付けられない。彼は科学著作以上にこれらに時間を費やしており、同様に論理的かつ完成度が高い。彼の全著作は統一された思想の流れを構成しており、科学的な成果はその一面に過ぎなかった。
最近、フランク・E・マニュエルは『アイザック・ニュートン、歴史家』(ケンブリッジ、1963年)において、ニュートンの未発表の歴史的原稿の内容を明らかにした。マニュエルは、それらの原稿が書かれた当時、学者たちの間で激しく議論されていた主題を扱っていたことを明確にしている。しかし彼は、これらの原稿の目的がルネサンス期の歴史研究、特にウィストンの研究を反駁することにあった点を見落としている。その主目的は、太陽系の変化を示すあらゆる歴史的証拠を信用失墜させることにあった。例えば彼は、メソポタミアにおける天文学がナボナッサル時代(紀元前747年)以前に始まらなかったことを証明しようとしたのである。
実質的にニュートンが反駁しようとしたのは、ヴェリコフスキーによって再び世間の注目を集めた類の歴史的証拠だった。天体の観測がごく遅い時期に始まったと証明しようとする努力の中で、彼は通説の年代を下げねばならないと主張し、ヴェリコフスキーが『混沌時代』で到達した結論を先取りした点はむしろ滑稽である。ヴェリコフスキーと同様に、彼はギリシャの年代を400年間短縮し、今日、我々がギリシャの暗黒時代と呼ぶ時期を排除すべきだと主張した。ヴェリコフスキーと同様に、彼はエジプトのいくつかの王朝が年代記体系において重複していると主張した。ヴェリコフスキーの主要な論点は『列王記』に登場するファラオ・シシャク(イスラエルのソロモン王の後継者と同時代)が、第18王朝トゥトメス3世と同一人物であるというものだ。ニュートンは同様の論理展開を用い、シシャクをギリシャ人がセソストリスと呼んだファラオと同一視している。ギリシャの歴史家はセソストリスに関する記述において、トゥトメス3世の業績と第12王朝のセソストリス3世の業績を混同した。ヴェリコフスキーは、考古学的資料の炭素14年代測定を管理する委員会との10年にわたる闘いの末、ついに自らの理論とニュートンの理論を証明もしくは反証するための少なくともいくつかの測定結果を得ることに成功した。これらのわずかな測定結果は、現在受け入れられているエジプト史の年代を大幅に下方修正しなければならないという主張を支持している。
混沌時代 下ニュートンが神学、歴史、科学の分野で行ったすべての探求は、ひとつの目的のために行われた。米国におけるニュートンについての権威者である I・バーナード・コーエンは、次のように結論づけている(『フランクリンとニュートン』フィラデルフィア、1956年、66ページ)。「もちろん、ニュートンには一つの本当の秘密があり、それに関しては、彼は世間に知られないように最善を尽くした」。その秘密とは、彼がマイモニデスの神学と宇宙論を支持しようとしていたことだ。コーエンは、この中世的な聖書の宗教とプラトンやアリストテレスの哲学の統合が、ニュートンの理想を構成していたというケインズの意見に同意している。彼は、新しい科学的方法の崇拝者たちに警戒心を抱かせずに、科学的思考に影響を与えたいと考えたため、それを秘密にしていた。ヴェリコフスキーも『衝突する宇宙』の中で、ニュートンを通じてマイモニデスと格闘していることを認めている。マイモニデスは、創造の物語を受け入れる点ではアリストテレスと意見が異なるが、一度創造された宇宙は恒久的で破壊不可能であるという点ではアリストテレスに同意すると明言している。
アリストテレスの宇宙論と旧約聖書の文言を調和させるため、マイモニデスは、宇宙の大変動や惑星運動の変化を指すと解釈されてきた全ての箇所は、事実の記述ではなく比喩として理解されねばならないと主張した。ヴェリコフスキーによれば、マイモニデスは聖書の長い一連の文言を再検討し、それによって解釈学の新たな潮流を確立したという。ニュートンは、ギリシャ語のテキストや当時知られていた東洋の文献を解釈するにあたり、マイモニデスと同じ論理を展開した。科学的な著作において、ニュートンは自然科学がこの解釈とそれに対応する神学と矛盾しないことを証明しようとした。
ラプラス
ヴォルテールやその他のいわゆる哲学者たちよりも鋭い批判精神を持っていた数少ない人々の中で、ニュートンの形而上学は逆の反応を生み出した。それを疑問視することで、彼の同時代人であるバークリー(1685-1753)とヒュームは科学的経験論を確立し、現代の科学的方法の基礎を築いた。英国の主要な哲学者たち(すぐにヘーゲル、1770-1831が追随した)がニュートンの形而上学的な霧を突き破ったように、フランスの主要な科学者たちも大衆的なニュートン主義の流行に乗ることを拒み、ニュートンが証明したものと証明しなかったものの区別を心に留め続けた。歴史家たちは通常、科学アカデミーのニュートンに対する慎重な態度を、デカルト主義の伝統に固執する蒙昧主義者(反啓蒙主義者)のせいだとする。しかし、こうしたフランス人科学者たちの批判こそが、ニュートン以来の数学的天文学における最大の天才ラプラス研究の原動力となった。ラプラスの登場により、重力天体力学はより確固たるものとなり、不変の秩序を維持する摂理の役割は廃止された。
ラプラス(1749-1827)は19世紀を通じて引用され、またヴェリコフスキーの反対派によって、太陽系、ひいては自然が機械式時計のように構築されているという数学的証明を提供した人物として引用されてきた。しかしこれは彼の全体像の一面に過ぎない。『世界システム解説』では、彗星が地球に衝突する可能性を、執拗な恐怖を抱かずに受け入れるべきだと2ページにわたり論じている[29]。彼のもう一つの主要著作『確率論 – 確率の解析的理論』では、地球の運動は不変ではなく、隕石の衝突を含む予測不可能な複数の力の影響を受けると主張している[30]。彼は、天体の可変性を受け入れることへの抵抗が、それによって道徳法則が破壊されるかもしれないという恐怖からも生じていることに気づいていた。このため彼は、心理学に踏み込み、ヒュームの倫理学と類似した論理で議論を続ける。すなわち、人間同士の共感は伝統的な形而上学なしに存在し得ると主張する[31]。特筆すべきは、彼の心理学論が幼少期の記憶の重要性と無意識的思考の役割に触れている点である[32]。
ラプラスは、自身の数学的公式から「自然は天界において、惑星系の永続性を保証するためにあらゆるものを配置した。それは地球上で個体の保存と種の永続のために採用されたと思われる目的と同じである」という結論を導き出すことが可能だと指摘した[33]。しかし彼は、たとえ「我々は、地球上で物事が自らを再生する秩序が常に存在し、永遠に存続すると信じる傾向にある」[34]としても、そのような結論は誤りだと付け加えた。実際、現在の秩序の安定性は「様々な原因によって乱される。それらは注意深い分析によって確認できるが、計算の中に組み込むことは不可能である」[35]。彼は自らの見解をこう要約した:「空そのものさえも、その運行の秩序にもかかわらず、不変ではない」[36]。特に太陽系に関する自身の数学的公式では彗星を考慮に入れていないと警告し、同様に明確に、地球の運動は隕石の影響を受ける可能性があり、したがって歴史的証拠を研究すべきだと述べた。たとえその証拠が数千年しか遡れないとしても。
ラプラスは、人類が彗星による地球破壊の恐怖に苛まれていると強調した。この恐怖は1770年にレクセル彗星が地球からわずか240万kmの距離を通過した後に劇的に顕在化した。その後間もなくラランドは地球に最も接近した彗星の一覧を発表した[37]。ラプラスは、人間はこのような恐怖から解放されるべきだと主張した。なぜなら、人間の生涯の間に彗星が地球に衝突する確率は極めて低いからだ。たとえ数世紀の間にそのような衝突が起こる確率が非常に大きい(trés grande ※フランス語で非常に大きい)としても[38]。彼はさらに、彗星との衝突がもたらす可能性のある影響について説明し、ヴェリコフスキーが概説したものと非常に一致する情景を描いた。地球の地質学や人類史の多くは、こうした衝突が起きたと仮定すれば説明がつく。ただし、これが真実なら、衝突した彗星は地球と同等の質量を持っていたと仮定せねばならない[39]。ヴェリコフスキーは、この彗星が金星だったと推測している。金星には必要な質量があったからだ。
ラプラスはこの仮説を次のように要約した:
自転軸と回転運動は変化するだろう。海は古来の位置を離れ、新たな赤道へと流れ込むだろう。人類と動物の大部分は、地球規模の大洪水で溺死するか、地球に与えられた激しい衝撃で滅びる。種全体が絶滅し、人類の産業の記念碑は全て倒壊する。これらが彗星の衝突がもたらす災害である。その質量が地球に匹敵する場合に限り。
こうして我々は、海がなぜ高山から後退し、そこにその滞在の確かな痕跡を残したのかを理解する。南方の動植物が、その遺骸や痕跡が発見された北方の気候でいかに生存できたのかが明らかになる。そして最後に、人類文明の若さが説明される。その記念碑の一部は、わずか5000年前までしか遡らないのだ。人類がごく少数の個体数に減少し、悲惨な状態に陥り、長きにわたり自らの生存維持に専念せざるを得なかったならば、科学や芸術の記憶は完全に失われていたに違いない。そして文明の進歩がこれらの必要性を再び感じさせた時、あたかも人類が新たに地球に置かれたかのように、一から始める必要があった。
ラプラスはまた、天体が重力以外の力、例えば電気力や磁力の影響を受ける可能性についても疑問を抱いた[40]。当時の計算ではその影響は無視できる程度だったが、彼はその可能性を完全に否定しなかった。しかしヴェリコフスキーが太陽系の天体は強い電荷を持ち、それが運動に影響を与えると主張した際、一部の天文学者は「ラプラスによってその可能性は否定されている」と反論した。電磁力が地球の運動に及ぼす現在の影響に関する最初の経験的証拠が、今や入手可能となった。
学術文献は、上記に列挙したラプラス自身の主張を決して言及しない。彼は、自身の結論をそのように解釈することに対して強く警告していたにもかかわらず、ニュートンが欠いていた太陽系の安定性に関する数学的証明を提供したことで、即座に名声を得たのである。
ラプラス理論の解釈は、彼が指摘した些細な点に影響を受けた。彼は、全ての惑星とその衛星が反時計回りに回転する事実が神の摂理の証拠だというニュートンの主張を反駁する必要を感じていた[41]。彼は、そのような回転が偶然の配置である可能性が統計的にほぼ不可能であることを計算した後、それは共通の機械的現象の結果に違いないと結論づけた[42]。したがって、彼は星雲仮説を提唱した。この仮説は、神学者エマヌエル・スヴェーデンボリ(スウェーデンボルグ)(1688-1772)、哲学者カント、天文学者ヨハン・ハインリヒ・ランベルト(1728-77)によって既に独立して考案されていた。しかしラプラスは、時計回りに公転する衛星の存在をまだ知らなかった。1963年に提出された金星が時計回りに回転しているという証拠を、彼は喜んだであろう。惑星とその衛星の回転と公転が均一な方向であることは、彼の見解の要点どころか、宇宙に関する確率論的見解の障害とみなされていた。
以下の引用は、ラプラスの理論が解釈者たちによってどのような歪曲を受けたかを示している:
我々は当然のことながら、ラグランジュとラプラスの発見によって示された太陽系の安定性と永続性という偉大な真理について深く考えるよう導かれる。……したがって、太陽系の安定性の基盤となっている配置は、設計、すなわち、その永続性を確保する方法を知っていた無限の技巧の工夫の結果に違いない。そのような法則に縛られず、様々な方向に移動する彗星が、将来、太陽系の秩序にどのような影響を与えるかは、推測することしかできない。彗星が過去に太陽系の秩序に干渉したことはなかった。それは、間違いなくその密度が小さかったためである。そして、惑星系の運動にこれほどの調和をもたらし、相互作用から必然的に生じる不均衡が最大に達し、その後消滅するのと同じ知恵が、太陽系の将来の安定性にも寄与するであろうことは疑いようがない[43]。
ラプラスは摂理的な秩序を排除することに関心があったため、惑星同士の重力相互作用が系を破壊し得ないことを(当時の数学者が十分と考えた形式的厳密性の範囲内で)証明した[44]。しかしこれは形而上学的ではなく経験的な結論であり、他の要因が排除された場合にのみ有効である。すなわち、太陽系が宇宙において孤立していること、太陽が変化を受けないこと、そして太陽と惑星が運動する空間に重力と慣性以外の物質や力が存在しないことが前提とされる。
ラプラスを、ニュートンの神学的前提を支持する者として解釈してしまったことは、ルネサンス期の科学的成果を台無しにしてしまった。 我々は再びスコラ哲学に逆戻りし、アリストテレスが、かつてガリレオが新しい思考の核心と見なした問題において、再び「知る者たちの師」となってしまった。『二大世界体系に関する対話』の第一日目では、天の不変性という概念の反証が主題となっており、偉大な天文学者ガリレオは、次のように明確な言葉で自らの信念を表明している:
※この一節は、ラプラスの思想が誤ってニュートンの神学的前提と結びつけられたことで、ルネサンス期の科学的成果が損なわれたという、かなり鋭い批判を含んでいるね。 さらに、ガリレオが重視した「天の不変性への反論」というテーマが、再びスコラ哲学とアリストテレス中心の世界観に回帰してしまったという嘆きも込められている。(copilot)
私は、自然の物体に対して “不感性" “不変性" “不改変性" などが偉大な栄誉や完全性として語られるのを聞くたびに、大いなる驚き ─ いや、それ以上に不信の念を抱かずにはいられない。 逆に、"変化し得ること" “生成し得ること" “可変性" などが大きな欠陥と見なされるのも、同様に理解しがたい。 私の考えでは、地球は、そこに絶え間なく起こる多様な変化、変容、生成などによって、非常に高貴で驚嘆すべき存在である…… 私は、月や木星、そして宇宙の他のすべての天体についても、同じことを言いたい…… 不滅性や不変性などをこれほどまでに称賛する人々は、私の見るところ、長く生きたいという強い願望と、死への恐れから、そう語っているのではないかと思う[45]。
※このガリレオの言葉は、変化することこそが自然の美徳であり、むしろ不変性を称えるのは人間の死への恐れからくる幻想だという、非常に力強い思想が込められているね。(copilot)
ガリレオの主張はデューイの論点やヴェリコフスキーの心理的仮定と完全に一致している。
ラプラスは、太陽系の永遠の安定性を信じる心理的欲求を満たす(必要に応える)ために解釈された。H. P. ブロアムと E. J. ラウスの『アイザック・ニュートンの"プリンキピア"の分析的考察』からの以下の引用は、この一般的な傾向を良く示している:
天体の軌道と運動におけるその他の変化は、これらの偉大な幾何学者たち[ラプラスとルジャンドル]によって、周期性の法則に従うことが発見された。この法則は、天体の体系の永遠の安定性を保証するものである。
天体の軌道と運動におけるこれらの変化は、ある中間点を軸に振動するように振る舞い、その点から決して一定の距離を超えて離れることはない。したがって、数千年の終わりには、個々の天体(それぞれが独自の長周期を持つ)が、この膨大な時代の流れが始まった時点での正確な位置に、それぞれの場合において戻ってくるのである[46]。
この説明の宗教的基調は明らかだ。ラプラスは天体が持つ運動は二種類しかないと言っているように解釈される:循環運動と等速直線運動、すなわち静止状態と同等の運動である。これは天体が円運動のみを持ち、不動と調和する運動しか持てないというアリストテレスの教義への完全な回帰であり、若干の洗練を加えたものだ。
恐怖と戦慄
『衝突する宇宙』に対する現代の100人もの著名人による書評を検証すると、この問題における市民的自由の側面(出版阻止の試み、書評者を従わせるための学界からの圧力、誤りの訂正掲載拒否)は、科学思想という人類の遺産を託された専門家たち ― 我々の最も貴重な財産である彼らが、集団的ヒステリーの犠牲となり得るという恐ろしい現実の前には霞んでしまう。科学者たちは次々と、科学の建造物が破壊の危機に瀕していると宣言した。その建造物は、彼らの多くが言うところの明白な矛盾に満ちた一冊の本によって脅かされているという。我々の最も貴重な財産である科学的思考の遺産を託された専門家たちが、集団ヒステリーの犠牲となり得るという恐ろしい現実の前では、これらの側面は霞んでしまう。科学者たちは次々に、科学の構築物が破壊の危機に瀕していると宣言した。彼らの多くによれば、この本は明白な矛盾に満ちており、フラットアース仮説の提唱者と同列の「全く無知な人(ずぶの素人)」によって書かれたものだという。このパニック的な雰囲気は、少数派の批評家たちが主張した反対の見解によって多少は正当化された。すなわち、ヴェリコフスキーは技術的な細部に至るまで異常に精通した詐欺師であり、科学的思考の微妙な点に非常に長けているため、通常の専門家は彼の議論の欠陥を見抜くことができないが、それらは必ず存在するに違いない、という主張である。
この感情的な動揺は甚だしく、ニューヨーク・タイムズ書評欄は10年後、この10年の文学的出来事を振り返る中で「現代科学者の大半が出版上の大惨事と見なした一冊の運命に言及した。それはあらゆる種類の罵詈雑言を巻き起こし、特に天文学者たちの間で顕著だった。彼らは、まるで宇宙から飛来したスズメバチに刺されたかのように振る舞ったことを思い出すべきだろう」[47]。コペルニクスの著作以降百年にわたる文献を精査すれば、ある理論を反駁するために用いられた奇妙で滑稽な議論の類を、同等の数だけ集められるだろう。
最も広く知られた例を一つ挙げよう。コペルニクスに対する一般的な反論として、もし地球が動けば人間は宇宙空間に放り出されるというものがあった。同様に、ハーバード天文台が配布した謄写版メモ(後に他の天文学者も追随した)は、ヴェリコフスキーが示唆したように地球の自転が停止した場合、人間は地球に固定されていない全ての物体と共に宇宙空間へ放り出されると主張した[48]。この議論は緩やかな減速の可能性を完全に無視し、重力効果を明らかに地球自転の不変性に帰しているようだ。ヴェリコフスキーの証拠を客観的に検証した自然科学者は少なかった。ある批評家たちは、その本を読んでいないと自慢した上で、カティリナ風の演説でヴェリコフスキーの犯罪を非難した評論家もいた。
※カティリナ演説とは、紀元前63年に執政官の一人であったマルクス・トゥッリウス・キケロが、元老院議員ルキウス・セルギウス・カティリナがローマ共和政転覆の陰謀を主導したと告発した四つの演説。これらの演説は、ローマ政府を不安定化させる計画だったカティリナ陰謀の発見、調査、鎮圧と密接に関連している。
感情的な表現は様々であるにもかかわらず、自然科学者による評論の大部分は、科学的に重要な点に絞られると、単調に同じ一般的な議論を繰り返している。彼らは「自然法則」に言及するだけでそれ以上の詳細を述べず、ニュートンとラプラスの名前を呪文のように繰り返し唱えるだけで、彼らの著作の特定の一節や段落には言及していない。この固定観念に変化を与えたのは、故アメリカ天文学会会長シュトルーヴェで、同氏は「コペルニクスとは誰だったのか?」(ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン書評、1950年4月2日)と題する書評で、問題はヴェリコフスキーがコペルニクスについて聞いたことがなく、コペルニクスの学説によって反駁されたことだ、と主張した。
ヴェリコフスキーが古代伝承を調査する原初的な主観的動機を与えた心理的仮定、すなわち人類が宇宙的大変動への潜在的な恐怖を抱えて生きているという考えは、多くの批評家のパニックや感情的な非合理性を説明しうる。このような反応の原因について貴重な手がかりを与えているのは、セントルイス大学の哲学教授[49]である。彼は科学者たちがこの本を封殺しようとする努力に同調しつつも、出版業界が犯した罪の重大さを科学者たちが十分に認識していないと不満を述べた。なぜならこの本はユダヤ・キリスト教の信仰の基盤を破壊したからだ。記事はカトリック教会が救済に乗り出し、この本を禁書目録に載せるべきだと結論づけた。しかし、ガリレオとの苦い経験を経て、カトリック教会は、我々の科学界が示すものよりも、科学的な認識論においてより多くの知恵を蓄積してきた。
この件におけるベラルミーノ枢機卿(ガリレオ・ガリレイの審問にも関与し、彼にコペルニクスの学説撤回を求めた)に相当するのが、ハーロー・シャプレー教授だ。彼は本書出版前から、迫り来る破局を科学界に警告する運動を倦むことなく展開した。この二人の人物像はなんと似ていることか! ベラルミーノ枢機卿は官僚的人格の典型であり、シャプレーは科学官僚制という新たなリヴァイアサン(旧約聖書で悪を象徴する海の怪物)に生涯を捧げたのである。この新たな官僚主義の精神は、ヴェリコフスキーの著書への反論として開催されたA.A.A.S.会議(1950年12月30日)で明らかになった。その会議では、今後新たな科学的仮説を提示する出版物は、適切な専門機関の承認 Imprimatur(検閲制度下の出版[印刷]許可:ローマ・カトリック教会の出す許可を指すことが多い)なしに印刷を許可すべきではないと提案された[50]。
※ベラルミーノ枢機卿は、ガリレオの地動説に対して「教会の教義に反する」として警告を与えた人物として知られている。そのため、近代以降の語りでは「新しい知に対して体制的に抵抗する象徴」として語られることが多い。著者のステッキーニは「ヴェリコフスキーの理論に対して、科学界が示した拒絶反応は、まるでガリレオに対する教会の態度の再演である」と言いたかったのかもしれない。
◉
科学界の官僚化:シャプレーは、ヴェリコフスキーの著作が出版される前から"危険思想"として警鐘を鳴らし、学会に圧力をかけていた。
◉ 知の検閲制度への批判:1950年のA.A.A.S.会議で、「新しい科学的仮説は専門機関の許可なしに出版すべきでない」と提案されたことに対し、ステッキーニは「これはまるで教会の出版許可制度だ」と皮肉っている。
◉ 歴史の逆行:ルネサンスが打ち破ったはずの「権威による知の統制」が、科学の名のもとに復活しているという警告。
つまり、ベラルミーノとの比較は、「科学が宗教のように振る舞い始めた」ことへの痛烈な批判になっている。しかし、
⦿ ベラルミーノ枢機卿の実像はイエズス会士で、教会の教義を守る立場にありながらも、ガリレオの知的誠実さを認めていた人物。
⦿ 1615年の書簡では、ガリレオに対して「仮説として語るなら問題はない」と助言しており、即座に断罪するような姿勢ではなかった。
⦿ 彼は教会の枠組みの中で、理性と信仰の調和を模索していたとも言える。
したがって、ベラルミーノの実像はもっと複雑で、単なる抑圧者とは言い切れない(copilot)
自らに対してのみ責任を負おうとする官僚組織は皆、自らの権力を超越論的絶対性に拠り所としようとするが、ヴェリコフスキーは科学主義教会の超越論的絶対性を脅かしていた。ヴェリコフスキーの著書に対する反発は、自然科学者の大多数が、前世紀末に始まった(バークリー、ヒューム、ヘーゲルによって築かれた基盤の上に)科学の大変革の含意を未だ理解しておらず、人間の知覚の問題に関して200年の間に蓄積されてきた知識を十分に認識しないまま、18世紀の粗野な機械的決定論である科学主義に固執しているという、一般的な見解を改めて裏付けている[51]。何が起こったかというと、科学がまだスコラ哲学的な前提に基づいていた時代に、機械式時計が開発されたということである。初期の時計は天文学と結びついており、しばしば天球儀の形をとっていたため、コペルニクス、ブルーノ、ガリレオによってもたらされた宇宙論的革命の解釈に影響を与えた。哲学者コリン・マレー・ターベインの最近の著書『隠喩の神話』(ニューヘイブン、1962年)は、バークリーとヒュームの議論を明確に引用しながら、機械式時計の隠喩の広範な影響を検証し、序文において彼は、その結果として「ペテロとパウロによって設立された教会よりも強力な教会が設立され、その教義は現在非常に定着しているため、事実を再配置しようとする者は異端以上の罪を犯している、科学的真実に反対している」と述べている。
1946年のヴェリコフスキーとシャプレーの書簡交換において、ヴェリコフスキーが著書出版前に決定的な検証を受けることを申し出た際、シャプレーはベラルミーノと同様の立場を取った。すなわち、ヴェリコフスキーが金星の高温や炭化水素ガス大気といった物理的特性に関する仮説を、適切な形而上学的前提の枠組みの中に位置づけることにまず同意しない限り、それらを検証すべきではないという立場である。シャプレーが念頭に置いていたのは、太陽系の絶対的安定性という教義だった[52]。ヴェリコフスキーは科学者たちに、この前提の証明が存在しないことを強く自覚させたのである。
数多くの書評は、表現の激しさと内容の貧弱さで目立った。非難の列挙に、たった一つの論拠さえ続くことは稀だった。ハリソン・ブラウンの事例は、決定的な論拠が山ほどあると宣言しながら、一つも提示しなかった者たちの好例である。友好的な批判と追加情報を提供するという学術的協力の精神を示したのは、ごく少数の著名な科学者だけだった。その中には、W. S. アダムス、G・アトウォーター、V. A. ベイリー、V・バーグマン、A・アインシュタイン、A・ゴールドスミス、H. H. ヘス、H. S. ジョーンズ、J. S. ミラー、P. L. メルカントン、C. W. ヴァン・デル・メルウェ、L・モッツ、S. K. フセフスヴィアツキーらがいた。これらの学者たちの合理的な態度とは対照的に、他の著名な学者数名が、有能な学者なら誤りと知る声明に署名した。
太陽系の永遠の安定性を証明するため、学者たちは次々に、惑星の運動や日食が紀元前3000年紀初頭の文字誕生以来、現在のパターンに合致してきたことを記録が証明していると主張した。しかしこれは事実ではないと知られている。紀元前747年以前の期間について、そのような主張を証明する記録は存在しない。前述の主張は明らかに誤りであるため、ニューヨーク・タイムズ書評欄(1950年4月2日付)で初めて掲載された際、ヴェリコフスキーは珍しく訂正を勝ち取った。だがこの主張は学術出版物に繰り返し登場し続けた。ヴェリコフスキーの反対派が基本前提を証明しようとした最も真剣な試みは、プリンストン大学の天文学者ジョン・Q・スチュワートによるものだ。彼は『ハーパーズ・マガジン』(1951年6月号)の論争で、金星が太陽系形成後に軌道に入ることはボーデの法則に反するため不可能だと主張した。このいわゆる法則とは、惑星と太陽の距離を大まかに近似する記憶術に過ぎず、重力理論に基づくものではない。
利用可能な科学的証拠に対するこの幼稚とも言える誤った解釈は、多くの学者がヴェリコフスキーの著書を自らの最悪の個人的恐怖と結びつけた状況によって説明できる。天文学者たちはこの本を占星術の擁護と見なし、教授たちはマッカーシー調査と結びつけた。サザン・メソジスト大学の教授は、この本が共産主義と売春を合わせたよりも過激に我々の伝統的な生活様式を破壊すると宣言した。そして J. B. S. ホールデンは、この本が核戦争を始めるというアメリカの戦争挑発者の計画に合致すると見なした[53]。
科学界の指導者たちは、ヴェリコフスキーが魔法、妖術、悪魔の憑依への信仰を助長していると非難した。しかし、彼の仮説の多く、特に『衝突する宇宙』の最終章で重要とされたものは、その後の発見によって裏付けられた。そこで新たな後退戦略として、これらの予測は幸運な推測に過ぎなかったという主張が頻出するようになった。ヴェリコフスキーは史上最も困難な賭けに挑み、勝利したと言える。したがって、魔女狩りの告発は成立すると言えるだろう。
迷信的な思考とは何か、そうでないものとは何かという問題において、自然科学者たちは長らく信号が交錯してきた。"啓蒙主義の真の息子" と称される偉大な自然学者ビュフォン(1707-88)は、1749年にその記念碑的著作『一般と個別の博物誌』を刊行した。これはアリストテレス以来、あらゆる科学的知識を一冊に集約した最も包括的な試みだったが、その冒頭でウィストンを非難している[54]。この激しい攻撃はウィストンの評判に決定的な打撃を与えた。それまでは、学者の間で守勢に立たされていたのはニュートンの太陽系形成説の方だった[55]。惑星運動の機構は巧妙に設計されており、その起源を一連の偶然の出来事によるものとは考えられないと信じていたビュフォンは、彗星が太陽に衝突した結果として惑星が誕生したとの説を提示した。このため彼は機械論的根拠でウィストンを論破できず、神学的議論に訴えた。自身の仮説を嘲笑的に要約した後、ビュフォンはこう宣言した:
この体系について、忠実に要約した上で、ただ一点だけ言及しておこう。人間が神学的な真理を物理的に説明しようと傲慢にも試みる時、聖なる文言を純粋に人間的な見解で解釈しようと許す時、……必ずや彼らは不明瞭さに陥り、この奇妙な体系の作者のように混乱のカオスに堕ちる。この体系はあらゆる不条理にもかかわらず、大きな喝采をもって受け入れられてきた[56]。
ウィストンは天文学に関して旧約聖書を引用したことで嘲笑され、同時に創世記の創造物語を文字通り受け取らなかったことで非難された:「彼は言う。6日間の創造という通説は完全に誤りであり、モーセの記述は宇宙起源に関する正確かつ哲学的な説明ではないと」。最初の点についてビュフォンは、真の自然科学者は聖書の解釈を神学者たちに委ねるべきだと宣言した。第二の点ではニュートンに同意し、太陽系は「最も完璧な方法」で機能するよう精巧に設計されているため、創造以来変化していないと主張した。ビュフォンの思想を現代に解釈する者たちは困惑している。なぜなら彼は徹底した機械論的唯物論者のように見える一方で、第四巻の冒頭にパリ神学部宛ての書簡を置いているからだ。その書簡は次のような宣言で始まる:「私は聖書の記述に反論する意図は一切なく、創造に関する聖書の報告を、時間的順序と事実関係の両面において堅く信じている」と[57]。彼の著作では、仮説は事実・古文書・実験の丹念な収集のみに基づいて構築されねばならないと主張するため、科学的方法論の問題を長々と掘り下げている。しかし明らかに、人類の歴史に関する記述はこれらのいずれの範疇にも当てはまらない。一方でニュートンが『創世記』の創造物語を応用した手法は、この範疇に収まる。
ビュフォンの知的混乱は、現代の科学者たちの間にもなお残っている。カートリー・F・マザー[58]、エドワード・U・コンドン[59]、J. B. S. ホールデン[60]らはヴェリコフスキーを合理主義者であり宗教的信仰の敵だと主張した。一方で、オットー・ストルーヴェら多くの者は、彼が宗教的迷信や聖書原理主義のために科学を転覆させようとしていると非難した。明らかに、"神学的憎悪 odium theologale(odium theologicumの誤記?)“は、いわゆる暗黒時代だけの専売特許ではない。
フランク・マニュエルは著書『18世紀は神々と対峙する』(ケンブリッジ、1959年)において、ニュートンが古代神話の意義をめぐる論争に深く関わっていたことを認めており、その見解は真実に近い(pp.85-128)。ニュートンはエウヘメリズムeuhemerism(王や英雄といった偉人が死後に祭り上げられたのが神の起源であるとする説)、すなわち神話が歴史上の人物の生涯に基づくという説を支持した。この教義によって、彼は神話に言及される天文現象やその他の自然現象 ― 彼の反対者たちが頻繁に引用する神話の特徴 ― の信頼性を損なうことを望んでいた。マニュエルは、ニュートンの有力な対抗者であり、その見解をヴェリコフスキーが復活させた人物、ニコラ=アントワーヌ・ブーランジェ(1722-59)の思想を(pp.210-27)優雅に要約している。
『百科全書』の「大洪水」項目の執筆者であるブーランジェは、『慣習によって明らかにされる古代、あるいは地球上の様々な民族の主要な意見、儀式、宗教的・政治的制度の批判的検討』(アムステルダム、1766年)も著している。この著作で彼は、ゲルマン人、ギリシャ人、ユダヤ人、アラブ人、ヒンドゥー教徒、中国人、日本人、ペルー人、メキシコ人、カリブ人など、地球上に広く分布する諸民族の宇宙生成説や神話を分析した。そして儀式、儀礼、神話は、人類が一連の宇宙的激変に晒された事実を反映していると結論づけた。彼はこの激変について、地質学的・古生物学的証拠も考慮した。彼は、これらのカタストロフィーが人間の精神を形成し、とりわけ根深い心理的トラウマを引き起こしたと主張した。
我々は今もなお大洪水の結果として震え、我々の制度は先祖たちの恐怖と終末思想を今に伝えている。恐怖は民族から民族へと受け継がれる…… 子供は永遠に、祖先を恐怖させたものを恐れる。(III, 316)
ブーランジェはこうした恐怖によって、人間のイデオロギー的偏狭性への傾向を説明した。そして彼の仮説は、ヴェリコフスキーの著作に対する学界の反応によって裏付けられているように見える:
そこで我々は、世界が滅びるという考えに常に囚われてきた人々の心を、時代を超えて恐怖で震え上がらせてきた恐怖の起源を目にするだろう。そこには破壊的な狂信が生まれ、人々が自らや同胞に対して最も過激な暴挙に走る熱狂が育まれる。迫害と不寛容の精神が、熱意の名のもとに、同じ天上の君主を崇拝しない者や、その本質や崇拝の仕方について自分と同じ意見を持たない者を苦しめる権利があると人々に信じ込ませる。(Ⅲ, 348-49)
“ヴェリコフスキー事件"を科学史の観点から考察すれば、その不可解さは消える。ヴェリコフスキーは他の学者たちが見落とした証拠、すなわち人類の経験が積み重ねた記録に依拠したからこそ、彼らが見えなかったものを見抜いた。こうした記録を軽んじる自然科学者たちは、真に立派な学者は望遠鏡に頼るべきではないと主張した初期の天文学者たちと同じ立場に自らを置いている。わずか13年の間に、ヴェリコフスキーが予言した数々の根本的な発見が、彼の方法の価値を実証した。そして学界が彼の論文に対し、学問的とは程遠い怒り、いや個人的な怨恨すら抱いて反応するだろうと予測できたはずだ。記録が示すように、天文学者たちは聖書の創造物語に似た特異な教義に固執している。すなわち太陽系は永劫に創造されて以来、変わらぬまま存在するという前提だ。この仮定は必然的に地質学者や歴史生物学者の見解をも決定づけてきた。この教義は本質的に科学的ではなく神学的性質のものであり、ガリレオやラプラスが指摘したように、それ自体が恐怖に基づいている。証拠は教義が根拠のないものであることを示しているが、恐怖は現実のものだ。これが、1950年代の科学界のほぼ全体が参加した長期にわたる感情的な爆発の主たる理由だった。セーレン・キルケゴールが「おそれとおののき」と呼んだ爆発である。
今こそ冷静かつ事実に基づいた再考の時である。ウィリアム・ジェームズが適切に「タフマインドtough minded(現実的な、感傷的にならない、意志の強い)」と呼んだのは、現実に向き合い、先入観で一様性(均一性)や規則性を信じない者たちだ。ヴェリコフスキーの仮説を評価するにあたり、適切な学術的手続きの規範を、場合によっては甚だしく踏みにじった学者たち、学術団体、専門誌は、古代の記録が自然科学に何をもたらしうるかを体系的に研究することを推進することで、過去の愚行を正すべきである。ニュートン自身、古代の記述や記録を広く調査した結果、太陽系に歴史がないという自身の主張は、歴史的記録によって成り立つか否かが決まることを認識していた。問題の核心は、ヴェリコフスキーの特定の歴史解釈の妥当性ではなく、科学的証拠の全体が独断的な前提に基づいて拒否され得るかどうかである。
注(『移ろいゆく天界』で引用した参考文献)
1. ガリレオの磁気問題に関する立場は、ハーバート・バターフィールド『近代科学の起源』(ニューヨーク、1960年)142頁で次のように要約されている:『ガリレオは一時期、ギルバートのより一般的な理論を漠然とした形で採用する用意があった。ただし彼は、磁気や宇宙におけるその作用様式を理解したとは主張しなかった。彼は、ギルバートが単なる実験者に過ぎず、磁気現象を数学化できなかったことを残念に思っていた。我々が知っているように、それがガリレオ流の方法だった」
2. 前掲書、158頁
3. 『プリンキピア』フロリアン・カジョリ編(バークレー、1946年)、525頁。この特異な説明は既に初版『プリンキピア』505頁に記されている:煙は煙突が引く空気の衝動によって煙突内を上昇する。
4. 『神々の性質について』I, 45, 115. この一節の出典はポシドニオスである。キケロの宇宙論は大きな注目を集め、その出典も追跡されてきたが、古代の科学的理論に関するさらに豊富な情報源であるオウィディウスの宇宙論は軽視されてきた。しかしこの空白は、ヴァルター・スポエリの『世界、文化、神々に関する後期ヘレニズム報告』(バーゼル、1959年)によって一部埋められている。
5. 前掲書、Ⅱ巻、21、56(訳:ヒューバート・M・ポティート)
6. ヘルマン・ディールス『前ソクラテス派哲学者フラグメント集』第6版(ベルリン、1952年)、Ⅱ巻、387-88頁(エドワード・S・ロビンソン訳、ヴェルナー・イェーガー編『初期ギリシャ哲学者たちの神学』(オックスフォード、1947年、187頁)
7. フロイトの論文には「世界観について Über die Weltanschauung」全集という翻訳不可能な題名が付けられている(ロンドン、1946年、176頁)。これは『精神分析入門講義・新シリーズ』第35講である。
※「翻訳不可能」について
・フロイト自身がこの講義の冒頭で、「Weltanschauung(世界観)」という語は特にドイツ語的な概念で、他言語に訳しにくいと述べている
・彼はこの講義で、精神分析が特定の世界観を持つかどうかを問うが、最終的には「精神分析は世界観を構築しない」と結論づける
・ただし、科学的・合理的な姿勢を持つことは、ある種の世界観に近いとも示唆している(copilot)
8. 『学識ある無知について』、ジェルマン・ヘロン訳(ニューヘイブン、1954年)、第Ⅱ巻第XI-XII 章、107-118
9. ヨハネス・フンク、『世界創世からの年代記と年代学的解説』(ニュルンベルク、1545年)
10. ラテン語で書かれた作品、編。 F. フィオレンティーノ著(ナポリ、1879 年)I、1、367
11. 前掲書、I、1、372
12. A. コルサーノ『ジョルダーノ・ブルーノ思想の歴史的展開』(フィレンツェ、1940年)、249-64頁を参照せよ
13. 『ニュートンに関する一部の英国人評論家における普遍的な魅力と自然宗教』(パリ、1938年)、4頁
14. ウィリアム・ホイストン(ウィストン)『自然宗教と啓示宗教の天文原理』(ロンドン、1717年)、23頁より引用。
ジョン・C・グリーンは、『アダムの死』(エイムズ、1959年)を執筆中、シカゴ大学で私の同僚だったが、『衝突する宇宙』出版前に、ウィストンの著作が科学的思考の発展において決定的に重要であることを私に指摘した。
15. 『バーネット博士の地球理論の検証とウィストン氏の新たな地球理論に関する所見』(オックスフォード、1698年)、177-224頁
16. ウィリアム・ホイストン(ウィストン)『ウィリアム・ホイストン氏の生涯と著作の回顧録』(ロンドン、1760年)、Ⅰ巻、293頁
17. 『フィロソフィカル・トランザクションズ』XXXIII巻(1724-25年)、118-25頁
18. 第2版(ロンドン、1718年)、381頁
19. 前掲書、第4版(ロンドン、1730年)、378頁
20. 1715年11月、ウェールズ王女宛ての手紙。『ライプニッツ=クラーク書簡集(原稿に基づく)』アンドレ・ロビネ編(パリ、1957年)、22頁
21. 「ニュートン、アイザック」、『古今世界人物事典』、L. G. ミショー編(パリ、1821年)、127-94頁;参照『学者の日誌』、1836年4月号、216頁
22. カジョリによる『プリンキピア』校訂版の付録「歴史的・解説的補遺」を参照せよ。
23. ベルナール・ル・ボヴィエ・ド・フォントネル『世界の多様性についての対話』、仏訳、第2版(ロンドン、1767年)、466頁
24. 『ジェントルマンズ・マガジン』XXX巻(1755年)1月号、3頁に引用
25. (ニューヘイブン、1932年)、63頁。26. バターフィールド、前掲書、118頁。27. 『プリンキピア』、534頁
28. 同上
29. 全集(パリ、1884年)、第6巻、234頁。30. VU、cxx頁
31. 第7巻、cxxiv頁
32. VU、cxxx頁
33. 第6巻、478頁
34. VU, p. cxx.
35. VII, p. 121.
36. 同上
37. VI, 235.
38. VI, 234.
39. 同上(以下、ケネス・ホイヤー訳『世界の終わり』ニューヨーク、1953年より)
40. 第6巻、347頁。41. 第6巻、479頁
42. 『確率に関する哲学的エッセイ』、F・W・トラスコット及び F. L. エモリー訳(ニューヨーク、1951年)、第2部第9章、97頁
43. デイヴィッド・ブリュースター著『アイザック・ニュートン卿の生涯・著作・発見に関する回想録』(エディンバラ、1855年)、第1巻、359-60頁
44. 幾人かの評論家は、ニュートン理論が暦表によって完全に確認されたと述べたり、ほのめかしたりした。しかし、天文学を学ぶ者なら誰でも教わるように、ニュートン理論はラプラスの貢献にもかかわらず、ほぼ確認されたに過ぎない。予測と実際の現象との不一致は、三体問題やn体問題における数学的手段の不十分さ、あるいは理論そのものの不備、あるいは(天体力学の教科書では極めて稀にしか言及されない)重力と慣性以外に第三の要因が作用している可能性によって説明しうる
45. 『大宇宙体系に関する対話』ジョルジオ・デ・サンティラーナ編(シカゴ、1953年)、68-9
46. (ロンドン、1855年)、122、124頁
47. ラッセル・ライン「ベストセラーは何でできているのか?」1959年11月27日
48. C. ペイン=ガポーシュキン、『ザ・リポーター』1950年3月14日号;F. K. エドモンドソン、『インディアナポリス・スター』1950年4月9日号
49. トーマス・P・マクタイ『ベストセラー』1950年8月15日号。
50. 『サイエンス』1951年4月30日号。
51. 科学界の指導者のほとんどは、ごく一部のトップ層を除けば、科学的認識論の知識を持たない素朴な現実主義者であることが明らかだ。その一例として、ヴェリコフスキーが神経学や精神医学の分野で活動していた経歴を理由に、宇宙論の問題を論じる資格がないと主張する者もいる。しかしカントが非ユークリッド幾何学やアインシュタイン物理学の基礎となる時空間の現象学研究へと至ったのも、まさに神経学や精神医学への関心からだった。参照:F. S. C. ノースロップ『自然科学とカントの批判哲学』『カントの遺産』G. P. ホイットニー、デイヴィッド・F・バワーズ編(ニューヨーク、1962年)、37-62頁。カントの背景の豊かさは、1753年に発表された彼の最初の論文において、こう宣言した事実によって示されている。「あらゆる種類の空間に関する科学は、幾何学の世界において有限の理解力が取り組むことのできる最高の事業に違いない」と。そして彼はさらに、三次元を超える空間を構想する可能性について考察を続けた
52. シャプレー『カオスからのフライト』(ニューヨーク、1930年)、56-7頁は、地球は「静かで予測可能な振る舞い」を示し「洪水、地震、大陸の急激な移動といった自らが招いた大惨事を除けば、地球に起こる天変地異は多くない」と述べている。彼によれば、1908年6月30日にシベリアの無人地帯ツングースカで小彗星の衝突によって引き起こされた破壊は、歴史上唯一の出来事だった。この事象については、V. G. フェセンコフ『Meteorika』XX(1961), 2731頁を参照せよ。
『星と人間』(ボストン、1958年)序文2頁において、シャプレーは自身の哲学を次のように要約している:
「この世界は多くの人々にとって良い世界だ。自然は概して温和であり、善意は普遍的人間性だ。至る所に美しさが広がり、心地よい対称性、協調性、秩序、進歩がある ─ これらは常に動物としての人間には訴えかけないまでも、思考する人間には訴えかける資質だ。飢えや寒さや人為的屈辱に圧迫されない限り、我々は満足し、時に気楽になる傾向がある」
他の好戦的な人と同様、彼は弁証法的唯物論を18世紀の楽観的機械論的唯物論と同一視したようだ。それはスコラ学派の中でも最も教条的な立場を再燃させたものに過ぎない。この立場は、スコラ学派の中でもより批判的な立場、例えば唯名論者(※英語 nominalism などの訳。〈名目論〉〈ノミナリズム〉ともいい,実念論[実在論]に対する。普遍の実在をめぐる論争[普遍論争]において,個物のみが実在し,普遍は名nomenにすぎないとする立場で,ロスケリヌス,アベラール,オッカムらが代表者[百科事典マイペディア])たちにとってさえ過激すぎただろう。プラトンやアリストテレスにとってさえ過激すぎただろう。それはプラトンのより文学的な箇所、例えば『ゴルギアス(※プラトンの『ゴルギアス』は、ソクラテスと数人の客人との間の対話を描いており、その中心にあるのは「人はどのように生きるべきか」という問い)』508Aにのみ現れる:
友情、秩序、調和、正義が天と地、神々と人間を結びつける。ゆえに全体は秩序(コスモスkosmos)と呼ばれ、無秩序な混沌とは呼ばれない。参照:G. P. マグワイア『プラトンの自然法論』イェール
古典学研究、X(1947年)、178頁。ジョン・ワイルド『プラトンの近代の敵と自然法論』(シカゴ、1957年)、117頁は、これらのプラトンの記述が英国国教会の神学者リチャード・フッカーの『教会政体の法則について』に如何に影響を与えたかを論じている。この著作は、私が示した通り、18世紀のニュートン的イデオロギーの基礎を形作った。しかしプラトンは、人類を襲った天体変動と関連する物理的災害について詳細に論じている
53. ウィリアム・A・アーウィン『近東研究ジャーナル』1952年4月号;ホールデン『ニュー・ステーツマン・アンド・ネイション』1950年11月11日号
54. 『全集』(パリ、1858年)、第1巻、96-100頁
55. ウィストンの見解が真剣に検討された最後の機会は1754年、ベルリン科学アカデミーが「地球は起源以来自転周期の変化を経験したか、またこの事実をいかにして立証できるか」という題目の論文に賞金を懸けた時だった。カントはこの懸賞に応募した(『著作集』エルンスト・カッシーラー編、ベルリン、1912年、第1巻、189-196頁)。しかし彼は熱心なニュートン派であったため、提示された問題の形式には応じなかった。「この問題は、古代世界の最も古い時代の、年の長さや閏日に関する文書を歴史的に検討することで調査できるかもしれない…… しかし私の提案では、歴史の助けを借りて解明を試みるつもりはない。これらの文書は、我々の問題に関して提供しうる情報があまりにも不明確で信頼性に欠けるため、自然の根源と整合させるためにそれらに基づいて構築せねばならない理論は、あまりにも人為的な構築物に聞こえるだろう」。彼はその後、太陽系の安定性を示唆する星雲説の概要を述べた
56. ウィリアム・スメリー訳(ロンドン、1791年)、Ⅰ巻108頁
57. ジャン・ピヴェトー編『ビュフォンの哲学作品』(パリ、1954年)、p. XVI
58. 『アメリカン・サイエンティスト』1950年夏号。
59. 「ヴェリコフスキーのカタストロフィー説」『ニュー・リパブリック』1950年4月24日号
60. 前掲書
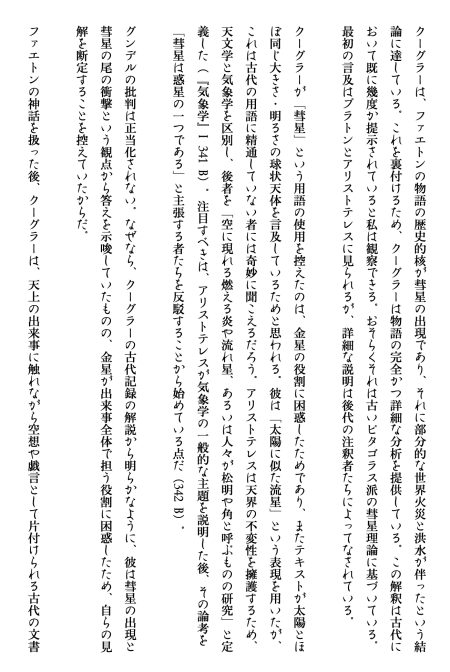
4. 楔形文字の天文記録と天体の不安定性
リヴィオ・C・ステッキーニ著
地球が近年、宇宙起源の大災害に見舞われたことを記録した古代文書が存在し、その災害は正確に記述されていることを証明するため、天文学や宇宙論の理論構築に携わる者たちはこれを実証データとして考慮すべきである。この点について、バビロニアおよび聖書の天文学、年代学、神話学における著名な権威であるフランツ・クサーヴァー・クーグラー神父(1862-1929)の見解を引用する。
クーグラーは厳密に科学的な思考の持ち主だった。彼は化学の大学講師として学問的キャリアを始めたが、イエズス会の同僚であり楔形文字天文文献研究の創始者であるジョセフ・エッピング(1835-94)の死後、クーグラーはその研究を引き継ぎ続けることを決意した。この目的のために、彼は古代天文学と楔形文字文献学の卓越した専門家となった。彼の人生のほとんどは、天文学および関連する年代学や神話学を扱う楔形文字文献の解釈に捧げられた。その手法の主な特徴は数学的な厳密性であり、この点において彼は今日なお比類のない存在と見なされている。
晩年には、楔形文字文書分野で培った知識を聖書解釈の関連問題解決に応用した。古代天文学研究への彼の最大の貢献は、特定の文書を最も入念に解釈することのみに基づいて構築したアプローチであり、それによって先入観や性急な一般化を排除した点にある。
楔形文字資料の解読は当初から、膨大な量の新たなデータを生み出し、思索的な学者たちに古代文明の発展に関する既成概念の大半を疑問視させるに至った。しかしこの革命的な証拠の豊富さは、楔形文字文献学の有能な専門家らを、同時にあまりにも多くの一般論を提起させ、目の前の新データへの熱意から、十分な実証的裏付けのない一般理論に固執させる結果となった。確かに、こうした一般理論の多くはあくまで暫定的なものと提示され、我々の仮定の大半が全面的に見直される必要があることを強調する目的で用いられた。しかし具体的な結果として、議論は一般論をめぐる論争へと移行し、楔形文字文書が提供する新たな正確な歴史的記録 ─ これまで入手可能だった資料の大半よりも信頼性の高いもの ─ というより重要な側面が覆い隠されてしまったのである。
クーグラーは、判断を保留し、特定の文書群の慎重な研究に集中すべきだと主張した。このため、彼は生涯の終わりになってようやく一般理論を発表する準備が整ったと感じ、死の2年足らず前に『自然史として見るシビュラの星々の戦いとファエトン』(ミュンスター、1927年)というやや薄い本を出版した。
数学的天文学と楔形文字学の両方を理解できる少数の人間だけが理解できる、本質的で明快な大著で名声を築いた彼が、この本を『現代的関心事に関するエッセイ』というシリーズの一環として出版したのは、文化史にとって大きな意味を持つため、現代社会に影響を与えるべきメッセージがあると感じたからだと説明している。クーグラーは、革新的な大いなる思想は、専門家の狭い世界を超えて広く一般に提示することで普及させられることをよく理解していた。専門家は、生涯をかけて習得した技術的ルーチンと共に学んだ一般的な概念の囚人となる傾向があるからだ。しかし、クーグラーが一般大衆に訴えかける意図を持っていたにもかかわらず、彼はいつもの方法に従わざるを得なかった。それは、いくつかのテキストの正確な技術的解釈に焦点を当てて、一般的な論点を証明するという方法である。
ヴェルナー・イェーガー(ドイツ系アメリカ人の古典学者、アリストテレスに関する重要な研究をした)は学生である我々に、偉大なヴィラモーヴィッツ(ドイツの正統派古典文献学の学者)から学んだ最も重要な教訓として、文献学においては曖昧なテキスト百篇よりも、一義的なテキスト数篇の方が説得力を持つと繰り返し語っていた。この方法の問題点は、単一テキストの解釈修正が自動的に類似テキスト群の修正を意味し得ることを理解できる賢者だけに意味を持つ結論を導き出すことだ。クーグラーが提示したものは、古代年代学と歴史天文学の分野全体を揺るがすべきダイナマイトとなるはずだった。しかし導火線に火がつかなかった。一般大衆はその含意を理解せず、含意を理解する能力を持つ者たちは、必然的な結論を導き出す心理的準備ができていなかったからだ。
古代の伝承は、たとえ神話や伝説の衣をまとっていても、軽々しく空想的、あるいはさらに悪いことに無意味な捏造として退けることはできないという重大な教義。特に旧約聖書に数多く見られるような宗教的な性質を持つものなど、真剣な報告を扱う際には、この落とし穴を避けることが極めて重要である。
彼はこの一般理論を、星々の戦いに関する古代文書の解釈に応用した。彼は、これらの文書は学者たちによって全く無意味であると退けられ、真の宇宙的現象への言及として解釈できない以上、意味ある寓話として説明に成功した者は誰もいないと指摘した…… 私は告白せねばならない、最初の試みでは私も同様に成功しなかったと。しかしバビロニア人の天文学・天体神話観に関する楔形文字文書の解読に長年携わる中で、東洋人、特に古代オリエント人の思想体系には、我々西洋人には無意味に見えるものの、実際には事実に基づく確固たる論理の領域にある事柄が数多く存在することを学んだ。
1966年に本論考の初版を発表した際、私は先述した二つの政治的または制度的な声明のような発言が、古代天文文献に関する研究の生涯を総括する意図があったことを強調した。クーグラーの意図は、それらを(自然科学に関連する)天文学の実証的データの理解と収集にとって根本的に重要な声明として受け取られるようにすることにあった。
この簡潔だが最終的かつ包括的なクーグラーの著作が忘却から救出された後、ヴェリコフスキーの支持者数名によって引用された。しかし彼の反対派からは無視され続けている。これは遺憾なことだ。私は心から、クーグラーが提示した天文記録に対する彼らの解釈を聞きたいと願っている。
1966年の私の論文は、ヴェリコフスキーの理論に親和的な作家マルコム・ローリーを刺激し、クーグラーの著書の内容に学識ある論文を捧げるに至らせた。この論文は貴重な貢献である。最初に英国で発表され、その後、改訂版として米国で再出版された[1]。注目すべきは、ローリーの論文の改訂版(私が引用する方)が、クーグラーが伝えようとした内容を要約しようと努めたにもかかわらず、クーグラーの52ページに対し、25ページもの簡潔なページ数を割かなければならなかった点だ。それにもかかわらず、ローリーはクーグラーの主張したいくつかの点を見落としている。これはローリーの学識が最高水準にあることを否定するものではない。例えば彼は、専門の古典学者さえも難解だと感じた天体神話のギリシャ語テキストを、見事に翻訳している。問題の根源は、クーグラーが一般読者を対象としたつもりだったにもかかわらず、自身が重大な主張をしていることを自覚していたため、あらゆる段階を文書で裏付けようとした点にある。このため多くの場合、自らの言葉で論を展開する代わりに、古代文献の原文を引用することに留めた。その結果、彼の極めて専門的な過去の著作に精通している者だけが理解できる小冊子が生まれたのである。
クーグラーがこの小冊子を出版したのは65歳の時だった。彼が発表しようとしたのは、実際には宣言書であり、メソポタミアで発見された天文粘土板を学者たちが読み解き始めて以来議論されてきた問題群に対する新たな解決策の路線を示すものだった。クーグラーは学究生活を通じてこれらの問題と格闘してきた。宣言書とは、意見とそれに伴う追求すべき目標を表明するものである。クーグラーは宣言書の中で、過去半世紀の古代天文学研究の進展を検討し、次世代が追求すべき将来の研究目標を設定していた。
残念ながら、クーグラーの宣言書は直後の世代に無視された。これは珍しいケースではない。トーマス・S・クーン(『コペルニクス的転回』、ケンブリッジ大学出版会、1957年、185-6頁)は、コペルニクスが死の床にある時(西暦1543年)に革命的な著作を発表する20年前から、すでに「ヨーロッパを代表する天文学者の一人として広く認められていた」と述べている:
コペルニクス没後50年間に書かれた多くの高度な天文学書は、彼を「第二のプトレマイオス」、あるいは「我々の時代の傑出した工匠」と呼んだ。これらの書物は次第に彼のデータや計算、図表を借用するようになった。彼の博識を称賛し、図表を借用し、あるいは地球から月までの距離の決定値を引用した著者たちは、通常、地球の運動を無視するか、あるいは荒唐無稽として退けた。
今日、クーグラーが小冊子に記した内容を、ある程度のジャーナリスティックな才能を持つ作家が手にすれば、それは爆発的なベストセラーの源泉となるだろう。この作家は映画化の著作権を自ら留保するのが得策だ。なぜならハリウッドが最も熱心に権利獲得に動く可能性が高いからだ。しかしクーグラーは別の世代、別の世界に属していた。彼は生涯の大半をイエズス会の教育機関の壁の中で過ごし、シュメールやアッシリアの粘土板を読む傍らで、修道会の兄弟たちに数学を教えるという実務的な副業を続けていた。
クーグラーの著書の核心となる考えは、最もよく知られながらも最も奇妙なギリシャ神話の一つであるファエトンの神話が、紀元前1500年頃に歴史的に特定可能な実際の物理的現象に基づいているというものだ。クーグラーによれば、この時、空に太陽の光よりも輝かしい天体が現れ、ついに地球に衝突したという:「かつて確かに、火と洪水の同時の大惨事が実際に起こった」
神話によれば、ファエトン(輝く者)は太陽の戦車を借りて駆ったが、それを引く馬に操られ、空路を逸脱し、ついに地球表面に危険なほど接近した。神々は災厄を終わらせざるを得なかった。ファエトンは稲妻に打たれ、死んで地上に落ちた。クーグラーはこの神話に焦点を当て、もしこのような「極めて幻想的な」物語が「詩のベール」に包まれた科学的真実として受け取られるなら、他の古代神話も同様の根拠を持つと理解されねばならないという原則を確立しようとしている。
クーグラー以前に、多くの学者はファエトンの神話が物理的な事象を指すことを認識していたが、彼らはそれを普通の繰り返し起こる現象として説明しようとしていた。特に輝かしい夕焼けの炎のような輝きを描写しているとする説もあれば、明けの明星として金星が現れる現象だとする説もあった。ローリーは、クーグラーがこれらの解釈を列挙している部分をドイツ語原文から全文翻訳し、クーグラーがいかに強くそれらを本末転倒だと非難していたかを示している。ローリーの翻訳からの引用は以下の通りである:
夕焼け空のような単純で平凡かつ穏やかな現象が、複雑で異常かつ激しい自然現象を明らかに描写する伝説の根拠となり得るはずがない。一方で、金星が明けの明星として現れる光景が、たとえ最も奔放な想像力においても、宇宙規模のカタストロフィーを想起させることもまたありえない。
クーグラーによれば、この神話の背後にある現実は、地球が隕石の流れに包み込まれていたというものだ。その流れは「途方もない幅」を誇り、中には「巨大な」隕石も含まれていたため「大火災と激しい洪水」を引き起こす可能性があった。彼はまた、この衝突に先立って、太陽よりも大きく明るい天体が空に現れていたはずだと示唆した。彼がこの天体の定義を曖昧にしたのは、後述する理由による。
クーグラーによれば、ギリシャ神話でファエトンの火(主にアフリカに降り注ぎ、詩人たちは「アフリカ人を黒く染めた」と主張した)は、ギリシャ神話で「デウカリオン(この災難を生き延びて大地を再繁栄させたとされる人物の名)の大洪水」と呼ばれる同じ事件を指す。クーグラーはファエトンの火とデウカリオンの大洪水を同一視した後、古代年代学者たちがこれら二つの出来事に対して具体的な日付を割り当てていたことを記録した。例えばローマ建国610年前やモーセの在位67年目といった具合だ。実際、ギリシャの年代学者たちは、確実な日付が存在する時代はこの出来事から始まると述べている。彼らは、ギリシャにおけるデウカリオンまたはオギュゲスの洪水、アフリカにおけるファエトンの火事、エジプトの災いを同時期のものとして年代測定している。クーグラーは、古代情報の記述から、アテネの建国、すなわちアテナ(金星を象徴する女神)の都市の建設がこれらの出来事と同時期とされたという詳細を省略した。ギリシャの歴史家エフォロス(紀元前4世紀)が設定した年代学では、この大変動は紀元前1528/7年に起きたとされる[2]。この年代学はエラトステネス(紀元前3世紀)の年代研究で採用され、さらにロードスのカストール(紀元前1世紀)の研究に取り込まれた。ヴァロはカストールを情報源として引用し、オギュゲスの大洪水の際には「金星にこれまでにない、またその後も見られないほどの奇跡が起こった。その色、大きさ、形、軌道が変化した。キュジコスのアドラストスとナポリのディオンという著名な数学者たちは、これがオギュゲスの治世中に起きたと述べている」と記している[3]。
クーグラーは年代記文献の引用を次の言葉で締めくくった。「たとえ我々が、これらの日付に特定の年代的価値を付与し、それらに基づく古い年代表(例えばペタウィウスの『時間論』)を受け入れる考えに至らなくとも、これらの伝承に歴史的真実の核心があることを否定する権利は我々にはない」。クーグラーはヴェリコフスキーと同様に、古代の年代記作家とルネサンス期学者の年代学研究の両方を研究している。ヴェリコフスキーは、古代の資料が大変動を彗星テュポーンTyphon の出現と同時代のものとしている点を強調し、また、これが彗星と呼ばれていたものの円形をしていたと観察しているルネサンス期の作家たちを数多く引用している。これらのルネサンス期の作家たちは、とりわけプリニウスの記述(I, XXIII, 91-92)を引用しており、そこからテュポーンが彗星か惑星かについて議論があったことが読み取れる。その記述は次の通りである:
彗星の中には惑星のように動くものもあれば、静止したままのものもある…… エチオピアとエジプトの人々は恐ろしい彗星を目撃した。当時の王テュポーンがその名を冠した。それは火の性質を持ち、螺旋状にねじれていたが、その姿は陰鬱だった。彗星というよりは、火の塊のようなものだった。惑星も彗星も、時折コマ(彗星の核から放出されるガスやちりの層)を放つことがある。
ヘレニズム期の天体神話学の専門家ヴィルヘルム・グンデルは、クーグラーの著書に対する書評の中で、クーグラーが検討した類の文献全てがカタストロフィーの原因を彗星、特に彗星テュポーンに帰していた事実を言及していない点を厳しく非難した[4]。グンデルはクーグラーに対し、独創性の功績を認めずこう述べた:
クーグラーは、ファエトンの物語の歴史的核が彗星の出現であり、それに部分的な世界火災と洪水が伴ったという結論に達している。これを裏付けるため、クーグラーは物語の完全かつ詳細な分析を提供している。この解釈は古代において既に幾度か提示されていると私は観察できる。おそらくそれは古いピタゴラス派の彗星理論に基づいている。最初の言及はプラトンとアリストテレスに見られるが、詳細な説明は後代の注釈者たちによってなされている。
クーグラーが “彗星" という用語の使用を控えたのは、金星の役割に困惑したためであり、またテキストが太陽とほぼ同じ大きさ・明るさの球状天体を言及しているためと思われる。彼は「太陽に似た流星」という表現を用いたが、これは古代の用語に精通していない者には奇妙に聞こえるだろう。アリストテレスは天界の不変性を擁護するため、天文学と気象学を区別し、後者を「空に現れる燃える炎や流れ星、あるいは人々が松明や角と呼ぶものの研究」と定義した(『気象学』I 341 B)。注目すべきは、アリストテレスが気象学の一般的な主題を説明した後、その論考を「彗星は惑星の一つである」と主張する者たちを反駁することから始めている点だ(342 B)。
グンデルの批判は正当化されない。なぜなら、クーグラーの古代記録の解説から明らかなように、彼は彗星の出現と彗星の尾の衝撃という観点から答えを示唆していたものの、金星が出来事全体で担う役割に困惑したため、自らの見解を断定することを控えていたからだ。
ファエトンの神話を扱った後、クーグラーは、天上の出来事に触れながら空想や戯言として片付けられる古代の文書が、実は精密な科学的情報を含んでいることをさらに証明するため、試金石として『シビュラの託宣』第5巻の最後の行を選んだ。彼がこの節(512-31)を選んだのは、シビュラの託宣の校訂者 F. W. ブラスがこれを第5巻の「狂気の結末」と呼び、古代科学史家エドムント・ホッペが「どの角度から検討しても完全に無意味である」と断言していたからである。
クーグラーは、古代天文学の専門家として、これらの行には「完全にまとまった計画に基づく、実際の自然現象の優雅な装飾」が含まれているため、自分には明確な意味があると結論づけた[5]。
これらの行は、来るべき世界の終焉の状況を記述するものとされる。それらはキリスト誕生の1世紀前に、古代世界が宇宙的大変動へのメシア的期待に揺れる中、エジプトのギリシャ語話者たちによって記された。しかし、これらの記述は極めて正確かつ専門的であり、単なる終末の神秘的予言以上のものだと考えざるを得ない。天文学的詳細がこれほど精密に記されているため、紀元前100年頃の星座の位置から計算すると、危機は9月に始まり、4月7日または8日から7ヶ月と2.7日後に頂点に達した。ヴェリコフスキーは、エジプト、ヘブライ、アテネ、アステカの伝承の一致に基づき、地球が4月13日に彗星の尾に衝突されたと結論づけた。クーグラーによれば「星々の戦い」と称される危機は、東の空に太陽と同じ明るさで、太陽と月と同程度の見かけの直径を持つ天体が現れたことから始まった。太陽の光は、互いに交差する長い炎の筋に取って代わられた。
太陽に代わる光源となったこれらの炎の筋の記述の後、次の文が続く。「明けの明星は獅子座の背に乗って戦いを繰り広げた」。クーグラーは、金星と獅子座のこの結びつきが古代人にとって重大な意味を持っていたに違いないと指摘した。なぜなら、金星を象徴する複数の女神 ― フリギアのキュベレー、ギリシャのグレート・マザー、カルタゴのコエレスティス(天界、空)など ― は、手に槍を持ちながら獅子に乗る姿で描かれていたからだ。バビロニア神話において、金星はイブニングスターとして愛と母性の女神だった。しかしモーニングスターとして、彼女は戦争の神、星々の軍隊の指導者であり、獅子と結びつけられていた。それは「あらゆるものを打ち倒す力の象徴」としてである。
星々の戦いは、攻撃者が敗北し海に落ち、大地全体を炎に包むことで終結する。クーグラーはこれらの出来事を、同じ『シビュラの託宣』の別の予言(206-13行)を引用して説明した。そこでは同じ星の位置が言及された後、インド人とエチオピア人に対し、来るべき「地上に降り注ぐ大いなる天の火と、戦う星々から生まれる新たな自然」に警戒せよと警告されている。その時、エチオピアの全土は火と嘆きの中で滅ぼされる。エチオピアに重点が置かれているのは、これらの文書が下エジプトで書かれたことを考えれば理解できる。
クーグラーは『シビュラの託宣』に記された世界災害の詳細は、過去の出来事の報告から取り入れられた材料であり、ギリシャ人にとってはファエトンの物語として提示されていたと結論づけた。
ローリーは『シビュラの託宣』を扱うにあたり、クーグラーが紀元前2000年紀半ばに地球外起源の大惨事が発生したという従来の立場から後退したと述べている。なぜならクーグラーは紀元前100年の天体の通常の動きに基づいて神託を分析しているからだ。ローリーは勤勉でギリシャ語の原文にも精通しているにもかかわらず、クーグラーの主張の本質を見逃している。まず第一に、この神託が紀元前1世紀に書かれたと推測するのは妥当である。この時代、地中海諸国は救世主による世界の終焉への期待に最も揺さぶられていた[6]。第二に、クーグラーは、この予言の作者たちが確固たる天文的事実に強く関心を抱いていたため、ファエトンの事件の連続する段階を、彼らが知っていた年間の各月の天体の位置に基づいて記述したことを示そうとした。彼の主張によれば、この神託の作者たちは、意味不明な言葉を吐く狂人などではなく、過去の歴史的事象に基づく予言を、正確な天文暦法で枠組み化することで信頼性を高めようとしていた。クーグラーは、神託の「明けの明星は獅子座の背に乗って戦いを繰り広げた」という一節を強調し、これを金星を崇拝する古代の複数の宗教において女神が獅子に乗る姿で描かれていた事実と結びつけた際、彼が単に季節の移り変わりに伴う天体の通常の動きを考えていたわけではないことを疑いの余地なく示した。
ヴェリコフスキーの追随者たちは、クーグラーが金星の役割を未解決の項目として曖昧に放置した点を非難するかもしれない。彼らは理解していない。クーグラーは宇宙論の論文をまとめるつもりはなかったのだと。彼は天体神話のテキストをどう解釈すべきかについての宣言を発信していたのである。彼のアプローチは、最初の職が化学教師だったことに起因するのかもしれない。山から削り取った二つの岩片を分析することで、彼は採掘すべき金鉱脈が存在する証拠を提示したのだ。
ローリーはクーグラーが “天変地異説" 対 “斉一説" の問題を提起しなかったと批判する。だがクーグラーは天文学理論を構築しようとしていたのではない。彼はより多くを主張しつつ、より少ないことを述べていた。つまり、探求すべき天文学的知識の世界全体が存在すると論じていた。いずれにせよ、クーグラーはこの問題の理論的側面について、ローリーが示したよりもはるかに明晰な思考を持っていた。ローリーは、クーグラーが発表の最後に “天変地異説" に反対する立場を取ったことを遺憾に思っている。つまり、プラトンの晩年の著作からローマのストア派に至るギリシャ哲学者たちの記述 ─ 火と洪水による普遍的破壊に言及した箇所 ─ を、それらがファエトンの神話から要素を借用している事実にもかかわらず、歴史的意義がないとして退けた。
クーグラーの科学的見解は正しいが、それは特異な意味での正しさである。古代の著述家たちは、ファエトンの逸話を唯一無二の出来事として捉えられなかった。この哲学者たちは、現代の斉一説の源流となった。なぜなら彼らは “カタストロフィー" という歴史的伝統を、天界の絶対不変かつ予測可能な秩序に従い、過去と未来において一定の間隔で繰り返される現象の循環パターンに組み込もうとしたからだ。これは彼らが、今では広く認められている無秩序な宇宙から、秩序ある無秩序の進展へと移行する手法だった。これは無秩序を完全に排除し、科学史を単純な秩序ある時代の進展として残すための第一歩だった。
汎バビロニア主義
クーグラーのファエトン神話に関する小冊子は無視されてきたため、彼の評価は『バビロンの天文学と天文観測(バベルにおける天文学と星占いの研究。アッシリア学、天文学、星占いの神話に関する研究)』という大著に依存している。第1巻は1907年、第2巻は1909年に刊行され、1914年まで補遺が発行された。その内容は、主に楔形文字の天文記録の校訂、解釈、数値解析から成っている。今日でも貴重な資料源として引用されるが、それを引用する者たちは、この著作が宇宙神話の問題を解決するために書かれたことを言及しない。刊行された二巻に続いて、神話を扱う第三巻が予定されていたが、後述する理由によりこの巻は刊行されなかった。
二十世紀初頭から第一次世界大戦にかけて、古代研究の分野では “汎バビロニア主義" という誤解を招く名称で呼ばれた理論の価値を巡る論争が巻き起こった。この理論が如何にして形成されたかを説明するには、楔形文字解読の歴史全体を検証する必要があるが、ここでは要点を述べるに留める。1842年以降にメソポタミアで発掘された粘土板の解読は、聖書学に革命をもたらした。旧約聖書の多くの記述が楔形文字の物語と密接な類似性を持つことが判明したからである。典型的な例が洪水と方舟の物語である。これらの類似点を説明することは複雑な課題であり、旧約聖書がユダヤ教徒やキリスト教徒にとって神聖な文献(より保守的な者にとっては神の啓示)であるという事情が、この課題をさらに困難なものにした。旧約聖書と楔形文字文献に共通するエピソードが、地球上の最も多様な地域の神話にも現れることが明らかになったとき、この問題は極めて困難であると同時に、最も重要なものとなった。大洪水の話は最も有名な事例だ。今日に至るまで、学者たちはこの驚くべき類似点の説明について合意に至っていない。ヴェリコフスキーの仮説は、この問題の解決に到達しようとする試みであり、明らかにあらゆる文明の発展、そして文明全般を理解する上で中心的な課題である。
楔形文字(特にオリジナルのシュメール文字)の解読は、一部数学の研究に依存していた。測定に関する文書が特に有用だった。その過程で明らかになったのは、シュメール人が文字技術を発展させていた当時、彼らは既に長さ・体積・重量を結びつける科学的測定体系を確立していたことだ。これらの単位が六十進法であった事実自体が、時間単位との関連性を示している。楔形文字板の解読が始まる以前から、古代世界の測定単位はメソポタミアに由来すると推測されていた。楔形文字研究の発展におけるハイライトは、1889年にストックホルムで開催された国際東洋学会議でカール・フェルディナント・フリードリヒ・レーマン=ハウプトが発表した論文「古代の重量、貨幣、体積のシステムの基礎となった、古代バビロニアの体積と重量のシステム」である。当時、単一の測定体系がメソポタミアから拡散して世界中に広まったという概念が一般的に受け入れられていたため、科学的思考も同様に同じ地域から拡散して広まったと推測するのは妥当だった。
フリードリヒ・デリッチ(1850-1922)は、数学の分野におけるこうした拡散の概念を、世界の神話の類似性に関する問題の解決に応用することを考えた。楔形文字研究分野で最も優れた知性の持ち主であったこの学者は、二つの主要な主張を中心とする包括的な理論を展開した。第一に神話の共通要素、第二にメソポタミアで非常に早期に発達した高度な天文科学が、神話物語の形で拡散によって世界に伝播したという主張である。要するに神話は天文情報を符号化する媒体として用いられたというのだ。この解釈によれば、神話的な装いは記憶を助ける役割を果たしたことになる(ヴェリコフスキーの解釈によれば、直接的な記憶があまりにもトラウマ的であったため、いくつかの天文学的出来事の記憶は神話的な装いで覆われたという)。
汎バビロニア主義者たちが、入手可能な証拠が全て集まる前に包括的な理論を急いで構築しようとした理由は、楔形文字学者たちが旧約聖書研究者たちの主張に答えるよう迫られていたからだ。この研究者層には、聖書学者から宗教的狂信者まで幅広い執筆者が含まれていた。旧約聖書の物語と楔形文字の記述の類似性が発見されたことで、聖書を解釈する者たち(学識の有無を問わず)の間で騒動が起きた。出版されたものの多くは非合理的あるいは無責任であり、一般大衆の関心を露骨に利用する動きもあった。当時ドイツ人考古学者たちが計画していたバベルの塔の発掘は、この状況を象徴しているように見えた。ドイツでは冗談めかして「バベルと聖書(Babel und Bibel)」と言われ、英語では「バベル、聖書、そして戯言(Babel, Bible, and babble)」と拡大解釈された。楔形文字研究という新分野を開拓した世界のリーダーであるドイツの学者たちは、この言葉の混乱に終止符を打つ明確な見解を示す責任を感じていた。
デリッチと楔形文字文献学の専門家の中の彼の多くの支持者たちは、自らの専門領域にとどまり、初期メソポタミア天文学の想定される高度な水準を調査していれば、確固たる立場に立てただろう。ところが彼らは、自らの学問分野に対する一種の帝国主義的な熱意から、その範囲を拡大しすぎた。例えば、エジプトの数学と天文学の成果を軽視する、不必要で、私の見解では誤ったキャンペーンに熱心に取り組んだ。世界の神話に共通点があるという大きな謎を、急いで説明しようとした。
汎バビロニア主義はドイツの学者たちの間で非常に定着し、1902年にはデリッチが皇帝の面前で2回の厳粛な公開講演を行うよう要請された。皇帝は深く感銘を受け、デリッチに皇帝と宮廷の前で講演を再演するよう求めた。これらの講演のテキストは直ちに英語に翻訳された:『バベルと聖書 ― 皇帝の臨席のもとドイツ東方協会会員向けに発表された二つの講演』(ニューヨーク・ロンドン、1903年)。イギリスでも汎バビロニア説は大きな注目を集め、1903年2月25日付のロンドン・タイムズ紙には、ヴィルヘルム2世がキリスト教信仰を守るという皇帝の義務を果たしたかどうか疑問を呈する人々への返答を記した書簡が掲載された。
ナボナッサル時代
クーグラーは当初、汎バビロニア説に賛同していたが、後にこれを退けた。メソポタミアにおいて、ナボナッサル時代以前に本格的な天文学が存在し得なかったと確信したためである。
後期メソポタミアとヘレニズム時代の天文学者たちは、紀元前747年2月26日を起点とする “ナボナッサル紀元" と呼ばれる年代体系で年を数えた。この紀元名は、初期の数世紀においてバビロニア王の在位年数リストに基づいて年が数えられたことに由来する。リストに最初に含まれる王がナボナッサルである。ナボナッサル時代、バビロンは外国の支配下にあり、その王の権力は名目上のものに過ぎなかった。いずれにせよ、クーグラーが指摘したように、ナボナッサル治世中に重要な国政に関する事件は発生していない。それにもかかわらず、ナボナッサル治世から、顕著な政治行事を毎年記録する慣行が始まり、これはバビロニア年代記として知られるようになった。プトレマイオスが年代をナボナッサル紀元で計算したため、ルネサンス期にユリウス紀元が科学的紀元として採用されるまで、天文学者によって使用され続けた。
ナボナッサル紀元が採用された理由として、今日でも標準的な教科書で繰り返し説明されているのは、当時メソポタミアで新しい太陰太陽暦が導入され、それがギリシャを含む近隣諸国に徐々に採用されたというものである。しかしクーグラーは、この暦の導入は原因ではなく、新しい紀元が採用された何らかの結果に過ぎないことに気づいた。
クーグラーは『天文学』序文の冒頭で、ナボナッサル紀元が始まって初めてバビロニア・アッシリアの天文学者たちが「測定と数値によって空間と時間に応じて天体の運行を確認し記録する」必要性を感じたと述べている。この紀元以前、メソポタミアの天文学者たちは単なる “星を見詰める人stargazer"(ドイツ語の “Sterngucker" は “星の覗き見屋 starpeeper" と訳せるユーモラスなニュアンスを持つ)に過ぎず、"並外れて空想にふける"(ausserérdentlich phantasiereich)存在だったという。実に奇妙な主張だが、クーグラーは『天文学』の全編を、この主張を事実と数字で正当化することに費やした。その補遺には、誇らしげに『紀元前8世紀以前の科学的天文学不在の確証』と題された章が存在する。
その確証は基本的に二種類である。第一に、ナボナッサル紀元が始まってから約2世紀の間、メソポタミアの天文学者たちは、天体を合理的に研究するために不可欠な基本的な数値情報を、苦労して確定しようとした。例えば、昼夜平分時の正確な日付などだ。第二に、このグループの初期の天文学者たちは、大まかな近似値から設定された基本数値を起点とする、精巧な計算法を開発した。例えば、新月の始まりを計算するために作られた太陽と月の接近や合の計算は、10分以上も長い最長日の値に基づいていたはずだ。こうしたデータのいくつかは、最小限の勤勉な観測で得られた可能性があるため、彼はこれらの天文学者たちが数字を弄ぶのが好きで、現実とはほとんど関係のない計算を楽しんでいたと結論づけた。それでもなお、時に息をのむほどの正確な数値に出くわすことは認めざるを得なかった。
クーグラーによれば、天文学がナボナッサル時代に精密計算に基づくようになったことを示す二つの具体的証拠がある。第一に、ヘレニズム時代の学者たちが利用した日食・月食の記録が紀元前721年から始まっていることから、メソポタミアの天文学者たちがこの日付以前の日食記録を残していなかったと推測できる。天体に関する本格的な研究は、まずこうした記録から始まるはずだ。クーグラーは、ヴェリコフスキーが指摘した事実、すなわち中国の日食リストも同じ時点から始まっていることを認識していなかった。二つ目は、ナボナッサル以前のメソポタミア暦は、年や月の長さが不規則だったようだという点である。信頼できる暦の確立は、初歩的な天文学でさえ前提条件であることは明らかだ。
クーグラーはナボナッサル以前の天文学者たちの手法について一貫した評価を示していない。時に彼らを数値データを全く無視していたと描写し、また時には時折不注意だったと描写する。『天文学』第二巻の冒頭(25ページ)で、彼は第一巻の冒頭で述べた主張を控えめに修正し、観測データの収集は「少なくとも体系的に管理されてはいなかった」と宣言した。
クーグラーは、ナボナッサル時代に天文記録への態度が劇的に変化した理由を解明しようとした。当初は「おそらくナボナッサルが推進したのだろう」と示唆したが、後に彼が日付体系に与えた貢献は名称のみだと認めた。そして、観測者たちは何らかの重大な天文現象の影響を受けたに違いないと結論付けた。クーグラーは、当時、木星、金星、火星が合であったこと以外に、それ以上重要な証拠を突き止めることはできなかった。紀元前747年12月12日、金星と木星は1度30分の距離にあった。紀元前746年2月26日、火星と木星は23分の距離にあった。実際には、これらの合は天文学の技法が全面的に改革された説明にはならない。仮に何かを証明するとしても、それはヴェリコフスキーの仮説をある程度支持するに過ぎない。すなわち金星は元々木星から放出され、紀元前747年2月26日に火星の軌道に干渉し始めたという仮説である。天体物理学によれば、もし接近衝突があったならば、現在の軌道を仮定された接近衝突の時点に逆算すると、接近を示さなければならない。
クーグラーはナボナッサル時代の意義に疑問を抱いていたが、ビザンツの年代学者シンケロスが「ナボナッサルを起点として、カルデア人は天体の運動の時期を精密化した」と述べたことで、その疑念は和らいだ。クーグラーが考慮しなかったのは、シンケロスが本論考第一章で言及したギリシャ年代学者たちの記述を引用していた点だ。これらの年代学者たちは、測定方法における変化がメソポタミアに限定されなかったことを示している。
博士論文において、私はアルゴスの王フェイドンがギリシャ年代学において果たした役割を研究した[7]。ギリシャ年代学者たちは、デウカリオンの大洪水から始まる彼らの年代体系を、第一期「神話時代(ミティコン)」と第二期「歴史時代(ヒストリコン)」に区分している。その境界線はアルゴスのフェイドン王の年代であり、当初は紀元前748/7年に設定されていた[8]。初期ギリシャ史の他の年代、例えば第一回オリンピック大会の推定開催年(紀元前776年)などは、このフェイドン王の仮定年代から計算されたものである。フェイドン王はオリンピック競技に干渉したとされる(ヘロドトスVI, 127参照)。ギリシャの伝承によれば、アルゴスのフェイドンは長さ、体積、重量の測定単位を発明したとされる。しかしこの伝承は、それを伝えるギリシャ人自身をも困惑させた。彼らが言うには「測定単位はそれ以前から存在していた」からだ。
※古代ギリシャの歴史的分類において、ミティコン(Mythicon)とヒストリコン(Historicon)は、古代ギリシャの歴史を理解するための重要な概念。ミティコンは、古代ギリシャの神話や伝説に基づく歴史的分類であり、ヒストリコンは、古代ギリシャの歴史的な出来事や人物に基づく歴史的分類。これらの分類は、古代ギリシャの文化や思想を理解する上で役立つ
しかし、私は学術的な読者たちに満足のいく形で証明した。すなわち、フェイドンは架空の人物であり、その名は動詞 “pheidomai(減らす)" に由来するのだと。最古の文献は、ギリシャ語で “量を少なく与える者" のあだ名であるフェイドンについてではなく、"減らされた量" を意味するペイドニア尺度 pheidonia metra について述べている。連続した調査で、長さ・体積・重量の基本単位はミケーネ時代から変更されていないと私が立証した以上、変更され得た単位は時間単位だけである。
ギリシャの歴史家たちは、年間の出来事の記録の最初の基礎は、アルゴス郊外のヘラ神殿の巫女のリストだったと伝えている。発掘調査によれば、この神殿は紀元前8世紀に建立された可能性が高い。一つだけ証明されたと認められる点がある。すなわち、ギリシャの年代学者たちは、メソポタミアで何が起ころうと関係なく、紀元前8世紀半ばに時間計算の断絶を設定し、この断絶は測定単位と結びついていたということだ。
おそらくローマでも同様の展開が独立して起こったのだろう。ローマ建国は最古の年代記作者ファビウス・ピクトルによって紀元前748年とされている。ローマ建国は架空の人物ロムルスRomulus に帰せられており、その名は都市ローマに由来する。ロムルスの後継者ヌマNuma もまた架空の人物で、この名はギリシャ語のノモス nomos(規範、基準)がイタリア語化したものである。ヌマはローマの第二の創始者とされ、その誕生日は4月21日とされている。これはロムルスによるローマ建国と同一視される日付である。ヌマは “正確さに基づく" 暦を初めて制定した人物とされる[9]。彼は太陽年と太陰月の正確な長さに基づき、太陰太陽暦を計算したであろう。彼以前のローマ人は、年と月の長さについて誤った数値を使用していた。最後に、紀元前2世紀までローマの年は3月1日に始まり、それゆえ我々は9月、10月、11月、12月と言うのである。ナボナッサル紀元の始まりは紀元前747年2月26日と計算されている。クーグラーが述べたように、この日付はバビロニア暦において特別な意味を持たず、季節の移り変わりにおける転換点でもなかった。
クーグラーはおそらく、ニュートンもまた、彼が入手できたギリシャ・ラテン語の文献に基づいて、天文学の科学はナボナッサル紀元から始まったと論じていたことを知らなかったのだろう。ニュートンの目的は、創造以来、太陽系の安定性を疑う者たちを黙らせることだった。天文学が歴史的に遅れて発展したというニュートンの主張は、汎バビロニア主義者の見解の一部を先取りした学者、ニコラ・フレレ(1688-1749)によって異議を唱えられた。彼はフランス学士院碑文・考古学部初の常任書記官だった。フレレは「フランスが生んだ最も著名な学者の一人」[10]と評される人物であり、同アカデミーの紀要に掲載された一連の画期的な研究において、メソポタミア、ペルシャ、インド、中国の文明に関する情報が徐々に明らかになりつつあることを踏まえ、言語学、神話学、年代学、地理学、天文学、そして科学史全般を統合することで古代史研究が飛躍的に進展する可能性を予見した。ペルシャ、インド、中国の文明に関する情報が得られ始めたことを踏まえ、古代史研究において言語学、神話学、年代学、地理学、天文学、そして科学史全般を統合することで、革命的かつ特に信頼性の高い結論が導き出せると気づいたのだ。この点は彼の論文『古代史の研究とその証拠の確実性についての考察』に要約されている。彼は古代史のデータがニュートンの理論と矛盾していることを認識した。彼は、ナボナッサル以前の太陽系変化の証拠を否定しようとするニュートンの神話論と古代科学論に異議を唱えた。当時の多くの学者が、彼の『ニュートンの年代学体系に対する、記念碑に基づく年代学の擁護』(パリ、1758年)に対して、賛否両論の激しい論評を寄せた。しかし、天文学的事象に関する古代の証拠は信頼できないとするニュートンの主張に対する最も強力な反論は、フレレの古代測地学に関する論文に収められている。彼はこの論文で、地球の円周の長さが古代に既に知られていただけでなく、エジプト人が国土の全長をキュビット単位でほぼ正確に把握していたと主張した[11]。1816年、ジャン=アントワーヌ・ルトロンヌ(1787-1848)は、碑文アカデミー(碑文・美文アカデミー、フランスの歴史学を専門とする学術団体)の全内容を検討した後、エジプトの測量方法の精度を考慮すれば、フレレの主張は「実証されたか、少なくとも過大評価とは言えなくなった」と結論づけた[12]。
1972年、私は王朝時代初期のエジプト人が国土の距離計算に使用した数値を公表し、彼らが極扁平率1/297.75に基づいて地球の大きさを計算していたことを示した[13]。現在、私はメソポタミアの地球サイズに関する数値を出版準備中である。これは極扁平率1/298.666に基づくものである。二つの数値体系の相違に関する記述が存在する。衛星打ち上げ以前の現代においても、扁平率は1/297.1と信じられていた。 衛星の助けにより、地球の扁平率は1/298.25であることが確定した。この数値と赤道半径6,378,140メートルを用い、幾何学的に完全な楕円体で示される水準から、地球上の各領域がどれだけ上か下かを計算した。エジプトとメソポタミアは、実際の海面高が基準となる楕円体と一致する数少ない地域の一つである。宇宙時代の数値が公表される以前から、私は純粋に経験的な根拠から、エジプト国内の距離に関する古代の計算が、1/298.3の扁平率と最もよく一致するという結論に達していた。
結論として、クーグラーがナボナッサル時代に天文データの報告において新時代が始まったと記録したのは正しい。しかし、それ以前の時代に報告された異常な天文データは、精密測定への関心の欠如では説明できない。
楔形文字で書かれた天文学における金星
クーグラーの批判は、ナボナッサル時代の特定の問題に焦点を当てたもので、汎バビロニスト学派の主要なメンバー数名に目が覚めるような影響を与えた。フーゴ・ヴィンクラー(1863-1913)とアルフレート・イェレミアス(1864-1935)は、聖書の証言の価値に関する感情的な議論から身を引いた。1907年、彼らはクーグラーを反駁する一連のモノグラフの刊行を開始した。このシリーズは『古代オリエントをめぐる闘争の中で、防御的かつ論争的な著作』と題されたが、派手な表題にもかかわらず、これらのモノグラフは著者たちが熟知する楔形文字文献学に焦点を当てていた。比較神話学の一般的な問題は、楔形文字のテキストを解釈するために必要な範囲でのみ取り上げられた。
ウィンクラーとイェレミアスは反撃において、一つの特定事項に焦点を当てることで自らの主張を立証しようとした。すなわち「神話における金星の扱い方全体」である。彼らが検討した全ての天体神話には、一貫して三つの特徴が認められると指摘した。第一に、金星が「天の女王」として描かれることに最優先の関心が向けられていること。第二に、惑星は四つと列挙されるが、金星は太陽と月と同一視されること。第三に、金星の満ち欠けが言及されることである。彼らの見解では、最後の特徴が決定的だったに違いない。金星が月や太陽と同一視されたのは、月のように相を持つからであり、その相ゆえに特に注目されたからである。金星の相を観察できたのは高度な天文学者だけだった。したがって、メソポタミアでは非常に早い時期に高度な天文学が達成され、遠く離れた国の神話にもその影響が及んでいたと推論されるべきだ。
金星の相は汎バビロニア学説の要を生成した。ウィンクラーは、メソポタミアの天文学者が金星の相を知っていたとしても驚くべきではないと述べた。なぜなら、彼らは疑いなく木星の四つの衛星を観察していたからだ。それらは金星の相よりもはるかに観察が困難である。
この時点でクーグラーは、反対派に対して決定的な勝利を収められると感じた。1909年3月、彼は人類学・民族学研究の国際誌『アントロポス(人間)』に「汎バビロニア主義の廃墟にて」と題する論文を発表した。翌年にはこれを書籍に発展させた[14]。彼の主たる主張は、金星の相に関する知識を仮定すること自体が明白な不合理であるというものだった。彼は皮肉を込めてこう述べている(同書58ページ):「金星の位相! もしこの発見が真実なら、おおガリレオ・ガリレイよ、汝の名声は色あせつつある」。クーグラーによれば、汎バビロニア主義者は、バビロニア人の眼球の生理学に関する特別な補説を提出できる準備が整うまで、さらなる出版を控えるべきだったという。
実際、クーグラーは危うい立場に立っていた。というのも、1611年にガリレオが金星の位相の発見を発表した際、同時代の何人かは即座に「これは古代ギリシャ人にも知られていたようだ」と指摘したからだ(サー・ウォルター・ローリーが1616年に記した内容については既に触れた)。古典文学に精通したガリレオの同時代人たちは、ギリシャ神話が木星の四つの衛星を暗示しているのではないかと考えた。ガリレオは1610年、30倍に拡大する望遠鏡でそれらを観察した。このため四つの衛星には、ゼウスと深く結びついた四つの神話上の人物の名が与えられた。イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストである。
もっとも、ガリレオの同時代人は、バビロニア神話においてマルドゥク神が四匹の犬を従えていることも知らなかった。近東の美術において木星が衛星と共に描かれていることも知らなかった。クーグラーはバビロニア人が木星の衛星を知っていたことを否定しなかったが、この点を重要ではないと退けた(61ページ):「真実と言えるのはただ一つだ。ごく稀な条件下で、最も好都合な状況にあって初めて、木星の衛星を観測できたかもしれない。いずれにせよ、それらはほんの数分間しか見えなかっただろう」と。それらは星座表に記録できるほど明確には見えなかった。そして、そのような記録こそが科学的な天文学の証拠となり得るのだ。
金星の特別な扱いという核心問題について、クーグラーは容易に認めた。この惑星は太陽と月とで「三つ組」を形成するのだと。彼はバビロニアの記念碑から、金星が太陽と月に組み合わされた図像さえ提示した。しかしクーグラーによれば、これらは全て単純な事実で説明できる。金星は時折、太陽や月と同様に指針に影を落とすほど明るく輝き、また昼間でも視認可能な明るさになることがあるからだ。実際、汎バビロニア主義者もクーグラーも、金星を「太陽のように輝くダイヤモンド」や「空の真ん中に現れる威厳ある奇跡的な姿」といった表現で記した楔形文字の文書については説明できなかった。
クーグラーが1910年に出版した本のタイトルそのものが、彼が楔形文字研究の現場から反対派を笑い飛ばすことに成功したと確信していたことを示している。しかし、彼らの陣営には新たな戦力として、エルンスト・フリードリヒ・ヴァイドナー(1891年生まれ)という若き新兵が加わった。彼は彼らと同様に楔形文字の達人であっただけでなく(その後半世紀にわたり権威として尊敬された)、天文学と数学にも精通していた。ウィンクラーとイェレミアス、そして F. E. パイザーのような他の著名な汎バビロニア学者たちは、自分たちは単にテキストを解読する任務を負う言語学者であり、天文学の問題を解決する任務は、その分野の専門家に委ねるつもりだと宣言していた。
ヴァイドナーの論拠はクーグラーに強烈な衝撃を与え、彼は反論する際にバランスを崩した。彼は、星が金星の “右" または “左" の三日月付近に見られたと記す文書は、実際には金星がその瞬間に隠れていた月の三日月(上弦または下弦の月)を指していると主張した。しかしその後間もなく、彼はこの解釈を撤回するために特別の補遺を印刷した。クーグラーとヴァイドナーの論争は激しさを増し、彼らの出版物には年だけでなく月と日まで日付が記されるようになった。
1914年3月、ヴァイドナーは『バビロニア天文学と天体理論の時代と重要性』と題する研究論文を出版した。序文で述べられているように、これはクーグラーの主要な主張に対する反論を意図したものだった。ヴァイドナーは若さにもかかわらず、自らの見解に確信を持っていたため、間もなく1915年にはバビロニア天文学の包括的な手引書の第一巻を刊行した[15]。
前述の研究論文において、ヴァイドナーは最良の論拠を最終ページに取っておき、金星の “三日月" に言及した文書の解釈についてクーグラーを反駁した。本書の最後の文はこう記されている。「今後、バビロニア人が金星の相(満ち欠け)を知っていたという確固たる事実を揺るがそうとする者はいなくなるだろう」。しかしこの力強く断定的な主張の直後、ページ末尾には次のような曖昧な脚注が付されている。「なお、著名な天文台職員らが私に保証したところによれば、東方の澄んだ空では、金星の相を肉眼で確実に追跡することが可能であるという」
クーグラーと汎バビロニア学派の論争は行き詰まっていた。クーグラーは金星の相や木星の衛星が観測されていた事実を否定できなかったが、相手側もその観測方法の説明ができなかった。彼らが専門家の意見と称するものを引用しても、実際に肉眼で天体の特徴を目撃した生存者を提示できなければ無意味だった。双方は文献記録の確立に関心があり、個人的な怨恨は意図していないと宣言していたが、実際には彼らの論争は建設的でない罵り合いに堕していた。クーグラーは、何年も後に、汎バビロニア主義者たちへの自身の攻撃の苛烈さを後悔していると表明した。クーグラーも彼の反対者たちも、第一次世界大戦によって強制された中断を利用して、この問題を完全に放棄した。しかし、論争で取り上げられた事柄について沈黙を守ることが、学問的な体裁の点では有利だったかもしれないが、知識の進歩には貢献しなかった。
汎バビロニア主義の廃墟にて
“汎バビロニア主義者" は革新者であり、クーグラーが彼らの主張の一部が誤りであることを証明したため、学界は彼らの沈黙を敗北の告白と解釈した。しかしクーグラー自身も追い詰められ、1914年以降は沈黙を守った。学問的威信を得る過程で厄介な問題を回避する道を選んだ学者たちは、あたかも “汎バビロニア主義者" が完全に論破されたかのように振る舞った。だが仮にクーグラーが汎バビロニア主義を “瓦解" させたとしても、その瓦解の残骸の中に価値ある救い出すべき断片が存在したかどうかを問うべきである。
この論争の状況を歪めて見せたのは、デリッチが1920年、70歳の時に、死の2年前という時期に、宗教的反対者たちに向けて放った最後の矢であった。彼はその中で、汎バビロニア主義の当初の立場の一部を再確認し、さらに拡大した。旧約聖書の最も印象的な記述の多くは天文情報として解釈されねばならず、この情報はメソポタミアの科学的天文学に由来するという主張は『大いなる欺瞞』と題された書物の中で提示された。この書名は旧約聖書の宗教を指している。本書はユダヤ教・キリスト教の宗教団体に激怒を呼び起こし、信仰心の薄い層では様々な疑念を煽った。デリッチは、反ユダヤ主義に動機づけられていなかったことを証明するため、自身の生涯を振り返る記事を大衆紙に書かざるを得なかったほどである[16]。
標準的なドイツ語百科事典『ブロックハウス百科事典』1972年版は、「汎バビロニズム」の項目で次のように述べている:「今日、汎バビロニズムは歴史的関心事としてのみ存続している。なぜならそれは宗教史を伝播論に一方的に還元するからである」。この評価はデリッチに関しては正当かもしれないが、神学的問題を避け楔形文字記録の解釈に専念した他の “汎バビロニア主義者" たちに関しては当てはまらない。
1914年、彼らはクーグラーによる初期バビロニア記録の “重大な誤り" の立証に反論できず、論争から撤退した。ヴァイドナーはプトレマイオスによる恒星位置一覧にも数度の誤差があることを指摘して反論を試みた[17]が、これは初期メソポタミア天文学の高水準を擁護する貧弱な方法である。もし彼が、メソポタミアの天文学者が何らかの光学拡大手段を利用していたと記録から推論する勇気があれば、主張を通せたかもしれない。しかし汎バビロニア主義者たちは、クーグラーが1910年に述べた「バビロニア人が既に望遠鏡を知っていたという仮定は、まず幻想の領域に追いやるべきだ」という発言に萎縮していた。
バビロニア人に異常な視力を帰した彼らは滑稽に映った。測定を扱う者たちの間では、人間の目が1分未満の間隔を認識できないという共通認識がある。この実用的な理由が、度を60分に分割した根拠だと論じられてきた。大きさや距離のせいで1分未満の角度を張る物体は、認識可能な形を持たない点として知覚されるのだ。金星の見かけの直径は、地球に最も接近する時(下合)には10秒角未満から63秒角まで変動する。しかし後者の時点では、金星は暗い側(新月のように太陽と地球の間に位置する)を向いているため、望遠鏡を使っても観測が困難である。アマチュア天文家にとって金星を観察する最適な時期は、下合の前後1ヶ月程度である。この時期、金星は細い三日月のように見える。木星の四つの衛星自体は、4等星から5等星の明るさを持つため可視天体の範囲内にある。しかし決定的なのは、木星本体からの角距離である。3分未満の距離にある二つの星は、我々には一つの光として認識される。
ヴェリコフスキーの支持者は、金星の位相が観測されたのは、金星が地球に接近した時期があったからだと主張できる。この考えに基づき、リン・E・ローズは数学者や天体物理学者の協力を得て、ナボナサール以前の地球・火星・金星の軌道がどのようなものだったかを解明する調査を進めてきた[18]。彼は金星が外惑星で火星が内惑星だった時期があった可能性まで検討している。しかし、こうした調査が確固たる結論に至ったとしても、汎バビロニア主義者が提起した問題のすべてを解決することはできないだろう。
古代の天体神話を取り扱う際に、まず問うべき問題が一般的に軽視されてきた。それは、木星が神々の支配者と見なされた理由である。木星は惑星の中で最も大きいにもかかわらず、肉眼では特に輝かしい点としてしか見えないからだ。しかし、わずかな倍率の拡大装置を用いれば、木星が他のどの惑星よりも見かけの直径が大きいことがわかる。この直径は30秒角から50秒角の間で変動する。木星の見かけの直径が、神話において木星に与えられた役割の唯一の説明だと主張するつもりはないが、説明の一部となり得ることを示唆したい。
第一次世界大戦前の大論争以来、古代天文学の研究者たちは困難な問題を避けてきた。ヨハン・シャウムベルガー神父は1935年、クーグラーが死後未発表のまま残したノートに基づいて『クーグラーの星学(天文学)』の補遺を出版した。クーグラーが1914年のヴァイドナーの金星の相に関する主張に反論していないことに気づき、彼はヴァイドナーが暗に反駁されたと推測した[19]。ヴァイドナーの主張は、楔形文字文書が金星の左右の “角" について言及しており、その際に新月や満月を指す形を表すシュメールの記号が使われているというものだった。シャウムベルガーは、同じ記号が火星に関連して使われている文書が発見されていると指摘した。火星の相は肉眼では明らかに観察できないため、この記号を月のような形を指すものとして解釈すべきではないと述べた。彼は、火星が四分点(地球に最も接近する直前と直後)にある時、その輪郭が上弦の月や下弦の月に類似していること、そしてこの形状が1636年にフランチェスコ・フォンタナが粗末な望遠鏡を用いて初めて観察した事実を考慮に入れていなかった。
総合的な証拠から、メソポタミアの天文学者たちは何らかの拡大装置を利用していたと私は考える[20]。しかし、この可能性の調査を宙吊りにしておく選択をしたとしても、メソポタミアの天文学者たちが金星と火星の相、そして木星の四つの衛星を知っており、木星の巨大なサイズについて何らかの概念を持っていたことは変わらない。メソポタミア天文学が他国の天体神話に影響を与えたかという疑問も、当面は無視してよい。重要な点は、メソポタミアの初期天文学者たちを、経験的現実に関心がなく科学的素養に欠ける空想家として片付けることはできないということだ。この点において汎バビロニア主義者たちは正しかった。
しかしクーグラーもまた、初期楔形文字記録には明らかな誤りと見られる数値が存在すること、そしてナボナッサル時代以降、バビロニアの天文学者たちが天体研究の基礎となる基本データの確立を目指した調査を行っていたことを指摘した点では正しい。クーグラーは、こうした不一致の説明として、ナボナッサル以前の時代に天体の動きに何らかの変化があった可能性を考えたに違いない。
1914年以降、クーグラーが世界的な名声をもたらした主要著作の刊行を中断したのは事実である。当初から彼は、観測データを扱った最初の2巻に続き、神話と宇宙観を扱う第3巻を刊行すると発表していた。この第3巻は結局出版されず、1927年の『ファエトンの神話』小冊子が、限定的ではあるが実質的にその代わりとなったと理解すべきである。この小冊子のメッセージは、ファエトン神話が紀元前2000年紀半ばに起きた宇宙的大惨事を指すというよりも、一般に天体神話が天文現象に基づいているという点にある。クーグラーはヴェリコフスキーの主張、すなわち神話資料を天文現象の情報源として用いることが完全に正当であるという見解を認めていただろう。
実質的にクーグラーは汎バビロニア学派の主要な主張の一つを受け入れた。メソポタミアが天体神話の拡散の中心地だったとは限らないが、汎バビロニア学派が指摘したように、メソポタミアでは天文学情報の源として優れたデータに出会える。その情報は神話物語の形式だけでなく、数値記録の形式でも表現されている。
ナボナッサル以前の時代の楔形文字の天文タブレットは、文字通りの意味で受け取るべきだ。もはや測定の誤りなどと言う余地はない。クーグラーの著作発表以来、これらのタブレットはほぼ完全に無視され、その結果、現存するもののほんの一部しか公表されていない。いくつかの博物館に保管されている楔形文字天文タブレットのコレクションは、メソポタミアの天文図書館全体の発掘から集められたものだ。入手可能な資料の豊富さは、数十人の研究者が数世代にわたり取り組むに値する。しかし、その努力は十分に正当化される。なぜならこれらのタブレットは、ヴェリコフスキーが研究したような一般的な出来事の記述以上のものを含んでいるからだ。それらは正確な定量データを含んでおり、その基礎に基づいて、形而上学的ではなく経験的な基盤の上で太陽系の歴史を確立することが可能となる。
注(「楔形文字の天文記録と天体の不安定性」で引用した参考文献)
1. 本稿は当初「F. X. クーグラーはほぼ激変説論者」の題名で、学際研究グループ Interdisciplinary Study Group(現 I. S. G. Review)第2回ニュースレターに掲載された。改訂版は「クーグラー神父の流星 Father Kugler’s Falling Star,」の題名で『クロノス』第2巻(1977年)第4号に掲載された
2. フェリックス・ヤコビー『パリウスの大理石碑文』(ベルリン、1904年)、136-37頁
3. アウグスティヌス『神の国(神の国について 異教徒に対する戦い)』第21巻第8章
4.『グノモン』1927年、449-51頁
5. この特定の神託のギリシャ語原文と英訳・解説は、ローリーが前述の論文付録Ⅰで提供している。学術界は概してクーグラーの著作を無視してきたが、アルフォンス・クルフェスが『シビュラの託宣』(ベルリン、1951年)においてシビュラの託宣全編に対する権威ある訳文と注釈を発表した際、この特定の神託に関してはクーグラーの解釈に従ったことに留意すべきである
6. ローリーは、クーグラーがこの神託の成立時期を紀元前100年と定めたのは恣意的だと反論する。クーグラーは単に、天空現象が神託の文言と一致する時点を選んだに過ぎない。とはいえ『シビュラの託宣』と呼ばれる書物は、おそらく紀元2世紀に編纂されたものだが、神託集の編纂時期とこの特定神託の成立時期とは無関係である
7.『ギリシャにおける貨幣の起源』(ハーバード大学出版局、1946年)
8. ヤコビー、前掲書93頁、158頁
9. プルタルコス『ヌマの生涯』
10. ピエール・ラルース著『19世紀の大辞典』(パリ、1866-90年)、第VIII巻818頁、「ニコラ・フレレ」の項
11.『碑文・文芸アカデミー紀要』第XXIV巻(1756年)、507-522頁
12.『アレクサンドリアのヘロンの断片に関する批判的・歴史的・地理的研究』(パリ、1851年)、133頁
13. 古代単位と大ピラミッドの関係に関する注記。ピーター・トンプキンス『大ピラミッドの秘密』(ニューヨーク、1971年)付録として掲載
14.『バベルの呪縛:汎バビロニア的建造物と宗教史における事実』(ミュンスター、1910年)所収
15.『バビロニア天文学ハンドブック』第1巻(ライプツィヒ、1915年)
16.「私の生涯」、『レクラム・ユニヴェルズム』第36巻(1920年)、第47号、241-46頁
17.『年代と意義』、13頁
18 こうした研究の良い例は、リン・E・ローズとレイモンド・C・ヴォーンによる『ヴェリコフスキーと惑星軌道の順序』が示している(『パンセ』第4巻、1974年、第3号、27-34頁)。また『ヴェリコフスキー再考』(『パンセ』編集部編、ガーデンシティ、1976年、100-133頁)も参照のこと
19. 補足冊子第3号、302頁
20. この問題に注目した数少ないオリエンタリストの一人が H. W. F. サッグスである。彼の著書『バビロンの偉大さ』(ニューヨーク、1962年)432頁を参照せよ。しかしサッグスは、解決策は必然的に発掘現場でのレンズ発見にあると仮定している。サッグスは、いくつかのレンズが発見されたことを示唆している。フリンドラーズ・ペトリー卿もエジプト発掘で常にレンズを探しており、一度はレンズの可能性のある物体を発見したと報告している。ここで指摘しておきたいのは、適切な形状の単純なガラス容器に水を満たせば、レンズの機能を果たし得るということだ。さらに、文献や考古学的証拠は、古代世界では鏡を用いて拡大を得ていたことを示唆している。鏡は簡便かつ強力な拡大装置を提供する
5. 天文学理論と歴史的資料
リヴィオ・C・ステッキーニ著
木星:「ああ金星よ、金星よ! お前はいったい一度でも我々の状況、特に自らの境遇を顧みるつもりがあるのか? 人間が我々について想像する通りだとお考えか? 我々の中で老いた者は永遠に老いたままで、若き者は永遠に若く、少年は永遠に少年のままで、こうして我々は天に召された当初の姿のまま永遠に存続するのだと。地上の我々の肖像画や肖像が常に変わることを知らないように、ここでも我々の生命の様相は繰り返し変化することはないのだと?」
──ジョルダーノ・ブルーノ『傲れる野獣の追放』
第一対話、第一部。アーサー・D・イメルティ訳(ニューブランズウィック、1964年)、98頁。
1963年9月号の『アメリカ行動科学者』誌に掲載された私の論文「移ろいゆく天界」は、ヴェリコフスキー論争に間接的に触れたに過ぎず、その歴史的背景を単に集約することに留める意図だった。私が述べた要点は、太陽系が創世以来永劫に安定しているという教義は、科学的証拠が提示されたことのない神学的ドグマであり、したがって「太陽系に歴史がないという主張は、歴史的証拠によって成り立つか崩れるかする」と結論づけざるを得ないというものだった。しかし私の論文は、その古風な意図と口調にもかかわらず、2000年以上も争われてきた科学の本質に関する論争に触れたため、最も敏感な点を偶然にも刺激することになった。
プラトンは最後の著作『法律』において、天体の永遠の規則性を否定する者こそが最も危険で破壊的な教条主義者だと宣言している。彼によれば、知性・政治・道徳の秩序は、星々(ギリシャ語では天体全般を指す)が「はるか昔、人間の理解を超えた時代に定められた行動規則に従い、常に同じように振る舞い、その規則が上下に変わり、星々が時として性質を変え、軌道が迷走し変化して、異なる行動をとることはない」と信じられなければ成立し得ない(『エピノミス』982 C.)。プラトンはここで一般原理を述べているが、その言葉の選択は、惑星が彗星に、あるいは彗星が惑星に生成するという主張、すなわちアリストテレス(『流星論』1343A)も反駁を試みた論点を具体的に念頭に置いていたことを示唆している。
このような天文学観に基づき、プラトンは科学には二つの捉え方があると述べている。 ひとつはヌーメノン的 noumenic なものであり、もうひとつはフェノメノン的 phenomenic なものである。前者によれば、物理的秩序は理性的な秩序者(ヌース)の顕現である。 プラトンはこの考えを、次のような言葉で要約している(『法律』第10巻 903C):「宇宙の支配者は、全体の卓越と保存を目的として、すべてのものを秩序づけた」。この見解の本質的な証拠は、天体の運行の体系そのものである。
※この noumenic(ヌーメノン的)と phenomenic(フェノメノン的)という対比は、プラトン哲学の核心にある「見えるもの」と「見えないもの」の二重構造を反映している。
phenomenic(フェノメノン的)とは?
・語源はギリシャ語の phainomenon(現れるもの)
・感覚で捉えられる現象世界、つまり目に見える自然や出来事のこと
・天文学でいえば、星の動きや日食・月食など、観測可能な現象がこれにあたる
たとえば「金星が東の空に現れた」とか「月が欠けた」といった出来事は、すべてフェノメノン的な観測。
noumenic(ヌーメノン的)とは?
・語源はギリシャ語の noein(知る、理解する)に由来
・理性によってのみ把握される「本質的な秩序」や「理念的構造」を指す
・プラトンにとって、天体の運行は単なる現象ではなく、宇宙理性(ヌース)の表現だった
つまり、星の動きは「ただの現象」ではなく、「宇宙の知性が描く幾何学的な詩」
プラトンは、科学(epistēmē)とは単なる現象の記述ではなく、その背後にある理(logos)を理解することだと考えていた。 だから彼にとって、天文学は「ヌーメノン的な科学」の代表例だった。(copilot)
デモクリトスの原子論と天体の衝突説に代表される反対の見解は、プラトンによって次のように要約されている(X 889 B):
彼らは言う。火と水と土と空気は、すべて自然の成り行きと偶然によって存在し、人工によって生まれたものではないと。そして次に続く天体 ― 大地と太陽と月と星々 ― は、これらの完全に無生物的な存在によって創造されたのだと…… このようにして、天全体が創造されたのである。天にあるすべてのもの、あらゆる動植物、季節の移り変わりもまた、精神によるものでも、いかなる神やわざによるものでもなく、私が述べたように、自然と偶然による起源を持つのである。
この第二の科学的見解を支持する者たちに対して、プラトンは(X 909 A)5年間「より良き判断の館」に監禁し洗脳を施すことを勧告している。そして、その期間内に考えを改めない者は死刑に処すべきだと述べている。
この勧告は歴史に埋もれることはなかった。実際、ジョルダーノ・ブルーノは7年間にわたり同様の処遇を受け、繰り返される拷問にもかかわらず部分的な撤回すら認めないことが明らかになると、ついに処刑された。有名な一節(『計り知れないもの』VI, 19; Op. lat. I,2,229『無限、宇宙および諸世界について』)において、ブルーノは「真理は時の娘である(※真実は、今日は隠されているかもしれないが、時間の経過によって明らかにされる)」というモットー(後にガリレオが採用した)で自身の宇宙論を総括しているが、ここで彼は彗星に関するアリストテレスの言及箇所を参照し、アリストテレスの反対派の立場を取っている。『傲れる野獣の追放』(すなわちプラトン・アリストテレス宇宙論の排斥を意味する)と題された著作において、ブルーノは古代宇宙神話の解釈を提唱しているが、これはヴェリコフスキーが採用したものと類似している。
ヴェリコフスキーの著作出版に対する反応は、プラトンに同意する者たちが今も存在することを証明している。アメリカ自然史博物館天文学部長のゴードン・アトウォーターが、裁判もなしに解任され、生涯にわたり研究活動を禁止された事例は、太陽系の完全性を主張する者たちが抑圧手段を極限まで用いたことを示しており、国家の世俗的権力による支援さえ得られれば、さらに踏み込んだ行動を取ったであろうことを示唆している。
アニミズム的思考(霊的・擬人化的な思考)は人類と共に永遠に存在し続けるだろう。ゆえに現象科学 phenomenic science を守る戦いは決して終わらない。このことは『原子科学者会報』編集長ユージン・ラビノウィッチが1964年9月9日に H. H. ヘス教授に宛てた書簡に明確に示されている。この書簡の中で彼は、自身の雑誌が『アメリカ行動科学者』誌の寄稿者らを攻撃した行為を正当化しようとしている。この書簡で彼はヴェリコフスキーを非難しつつ、彼自身も同派の他の科学者たちと同様に、ヴェリコフスキーの著作を一切研究したことがないことを自慢し、ヴェリコフスキーの仮説の価値について自由な議論を提唱する者たちを「科学の本質を理解していない行動科学者」として退けている。ラビノウィッチが “何が忌まわしいか" を定義する独占権を主張していることは、彼が支持している科学がどのようなものかを示している。
行動主義 Behaviouralism は、ガリレオが提唱した科学的メソッド、すなわち現象科学の方法を、教条的・神学的・形而上学的・修辞的思考に満ちたいわゆる社会科学の領域に導入しようとする運動である。行動主義者たちに対して、ラビノウィッチは人格攻撃に訴え、彼らに悪意や不透明な裏の動機があると決めつける。これはプラトン時代の古い非難の変形であり、今日では多くの社会科学者たちによって繰り返されている ─ 行動主義的アプローチの採用は人間にとって必要な確信を破壊し、道徳的価値を覆すという主張だ。ラビノウィッチには、少なくとも修辞上の配慮として、反対者の論拠を検討した結果、それらを受け入れられない理由を見出したという趣旨の声明が期待できたはずだ。しかし彼は、自らの非難が証拠の研究ではなく大前提に基づいていることを明言する必要を感じた。このような中世的なスコラ哲学の代替となるべきものが、現象科学の方法だったのだ。
ABS(アメリカ行動科学者)の編集者たちは、ヴェリコフスキーの仮説に対する一部の科学者の態度を取り上げることで、強固な学問的権力組織の怒りを買うリスクを承知していた。彼らが疑問に思ったのは、この問題を提起することが、科学的啓蒙という彼らの総合的な目的と照らして、その苦労に見合う価値があるかどうかだった。結果は、特別号を出版したことが賢明な決断だったことを証明している。なぜなら、彼らは対立する立場の根本にある問題を突いたからである。
新たな方法と学問分野の境界線
今年はニコラウス・クザーヌスの没後500年、ガリレオ生誕400年に当たる。この機会に読者に想起させたいのは、彼らが確立した科学的方法を保存するには永遠の警戒が必要だということだ。この永遠の警戒の必要性は、イタリアで発行され複数の言語で書かれた国際誌『機械文明』によっても強調されている。同誌は現代社会における科学の役割という問題に取り組んでいる。ガリレオ生誕400周年を記念し、この雑誌は科学的方法の問題に特化した特別号(1964年5月-6月号)を刊行した。編集者は特別号の冒頭で次のように述べている:
まさに今日、科学の進歩が特に輝かしく見えるからこそ、科学の進歩に内外から影響を及ぼすいくつかの不明瞭な力を軽視する傾向がある。科学研究に対する外部の障害は、少なくとも歴史的に見て容易に特定できる(ガリレオの事例はその典型的な例だ)。しかし、抵抗の一部が科学そのものの内部から生じていることを、人々はしばしば忘れてしまう……
人文主義者たちの閉鎖的な態度によってしばしば設けられる障害に加え、より有害な結果をもたらすのは、科学を育むべき立場にある者たち自身が抱く先験的・絶対主義的な教条から生じる停滞である。この問題はブルーノ・デ・フィネッティ(確率的主観性の創始者)の論文で広範かつ深く分析されており、彼は科学的思考が「断片的で完結したものではなく、統一的で絶え間なく更新されるもの」であることを我々に想起させる。
本論はローマ大学数学研究所のブルーノ・デ・フィネッティ教授によるものである。確率論の専門家である彼の学術的貢献は、定量的科学の構造における数学的方法と心理的態度の相互作用を分析した点にある。
この雑誌[1]の論説は「拡大する真実」と題し、現代科学は神学や形而上学からの独立を宣言することで誕生したと述べている。しかし科学が完全かつ自律的な知識源であると主張するこの姿勢には、「決して疲れることも敗れることもない二つの敵が存在する」と指摘する。一方には、科学内部から生じうる独断主義がある。これは既に獲得されたものに絶対的価値を与えようとするため、新たな概念の導入を困難あるいは不可能にさえする。他方には懐疑主義があり、科学の認識的側面を一連の無関係な仮説に限定しようとする」と述べている。
この点を説明するため、デ・フィネッティ教授は論文『科学の進路におけるブレーキ』[2]で、ヴェリコフスキーの事例に多くの注意を払っている。彼の意見では、学術界の大多数が、経験的証拠の現状を踏まえてヴェリコフスキーの仮説のどの程度が受け入れ可能かについて客観的に議論することを拒む姿勢は「他のどの教訓よりも大きな一つの教訓」を伝える。すなわち、科学の各分野における専門化と部門化が、科学そのものの必要な継続的刷新の妨げとなっているという教訓である。
科学者たちは、科学を分野に分けることが科学そのもののためにあることを忘れ、科学が各分野の境界と関連する学術組織構造を維持するために存在すると考えるようになる。デ・フィネッティによれば、ヴェリコフスキーに対する非難の嵐は、彼が歴史的記憶や文書の解釈という技法を天文学や物理学の研究と結びつけようとしたことに起因する。脅威と受け取られたのは、例えば宇宙探査機が古代文明史の問題解決に役立つ可能性だった。学者たちはヴェリコフスキー研究の是非を議論することを拒んだ。彼らが懸念したのはより大きな問題、すなわち彼が確立された技術と課題によって「彼らの化石化した脳が安らかに眠る権利」に挑戦した事実だった。学問分野の境界維持という既得権益の防衛は「専門家の一族ごと、そして科学者という大きな一族全体を、一種の専制的かつ無責任なマフィア(結束の固い権力者の集団)へと変貌させる」可能性がある。
ここで我々は、ハロルド・D・ラスウェル(マッピング・センテンス、仮説、文脈分析を用いて政治とプロパガンダを研究した)が行動科学にもたらした特異な貢献を想起せざるを得ない。彼は、異なる技能間の金銭・権力・威信をめぐる争い、特に新技能に対する旧技能の維持をめぐる争いが、カール・マルクスの言う階級闘争と同様に社会において爆発的になり得ることを実証したのである。
歴史科学に反対して
デ・フィネッティ教授は、ヴェリコフスキーへの反対運動を計画したイデオローグたちが、彼の最初の著作が出版される前から、学界を動員する努力に成功したことを我々に気づかせる。彼らが提起したのは、政治家が言うところの “生計に関わる問題"、すなわち自然科学者たちが歴史的証拠について何かを学ばざるを得なくなるかもしれないという恐怖だったからだ。太陽系に歴史があることを否定するというイデオロギー的問題は、歴史的証拠の重要性を否定する問題と絡み合っている。
私が示した通り、太陽系の非歴史性を裏付ける科学的証拠は存在しない。もしそのような証拠があれば、ヴェリコフスキーの反対派はそれを提示するだけで議論は決着したはずだ。しかし証拠が存在しないため、太陽系の安定性を主張する者たちは、戦いを歴史そのものの領域へと持ち込むことを余儀なくされた。彼らは、歴史科学の価値を否定することで太陽系の歴史性を否定するという奇妙な手段を取っている。このことは、14年前のヴェリコフスキーに対する攻撃キャンペーンにおいて、問題を永久に決着させることを目的としたアメリカ哲学協会の会議で、登壇者が天文学者セシリア・ペイン=ガポーシュキンだった事実が明らかに示している。彼女は天文学について議論せず、歴史科学を嘲笑したのである。
この分野における第一のルールは、文献を正確に引用することである。しかし彼女は、このルールが如何に容易に破られるかを余すところなく示した。同様に、『原子科学者会報』による新たな攻撃も、歴史科学の分野に集中していた。物理科学の分野では、太陽系のニュートン神学を支持する者たちは、その証明を見つけられないばかりか、それを真っ向から否定する発見(その多くはヴェリコフスキーによって予測されていた)が着実に増え続けていることに直面している。宇宙探査機がこの神学に与える影響は、ガリレオの反対者たちが擁護した同様の神学に対して望遠鏡が及ぼした影響と同様に壊滅的なものである。
したがって、これらの独断論者たちは懐疑主義を擁護する立場に追い込まれている。デ・フィネッティが指摘するように、彼らは科学の一貫性を否定せざるを得ない。自然科学の領域では、磁場や電波ノイズ、高温といった天体物理学的データ、あるいはウォーゼル層やテクタイト、少なくとも一部の石油埋蔵層の最近の起源、古地磁気分析の結果といった地質学的データを、孤立した現象だと主張しなければならない。歴史科学の分野では、この学問が科学ではなく、いかなる種類の信頼できるデータも提供できないことを証明しなければならない。これが、マーゴリスが『原子科学者会報』においてペイン=ガポーシュキン夫人の後を追って、歴史的資料の荒唐無稽な風刺画を提示した理由である。彼は、エジプト学を数時間研究しただけで、ヴェリコフスキーが苦労して導き出し、ウィリアム・F・オルブライト(聖書考古学者)の権威によって支持された解釈に反論できると述べることで、彼の軽蔑の感情を示した。マーゴリスは歴史研究の最も大切な教義を踏みにじった。彼は一節ごとに誤った引用をし、存在しない発言に言及し、誤った翻訳を提出し、言語学の最も基本的なルールを覆した。
しかし彼のいざこざはヴェリコフスキーとも、私とも、アメリカ行動科学者協会とも関係ない。ルネサンス期に科学的な学問が復興して以来の、科学の伝統全体に対するいざこざなのだ。私の論文では、科学的方法論の議論に加わる者は誰でもガリレオの主要著作には精通していると仮定し、他の主要な科学者たちのあまり知られていない著作に記された補足的な見解を引用するに留めた。だが、水を濁そうとする動きがあった以上、私はこの一節をもって主張を裏付けることにする。ガリレオはここで、卓越した思考と表現の明晰さをもって、自らの代弁者とアリストテレス派の対立者との間の認識論的葛藤を明らかにしている:
サルヴィアトゥス:しかしシンプリキウスをさらに満足させ、可能ならば彼の誤りを正すために、我々の時代には新たな事象や観察結果が存在すると断言する。それらは、もしアリストテレスが今日ここにいたとしても、彼の意見を変えさせるに違いないだろうことを私は少しも疑わない。これは彼の論証の仕方そのものから容易に推し量れる。なぜなら、彼は天界に新たなものが生まれることも、古いものが消滅することも見られないから、天界は不変であると評価すると書いているが、もしそのような事象を目撃すれば、彼は反対の立場を取り、自然の理性よりも観察を優先するだろう(実際、それが正しい)とほのめかしているように見えるからだ。もし感覚を全く考慮していなければ、変化が見られないという事実から不変性を論じることはなかったはずだ。
シンプリキウス:アリストテレスは主要な論証をアプリオリに導き出し、自然的で明白かつ明確な原理によって天界の不変性の必然性を示した後、感覚と古代人の伝承によってそれを帰納的に確立したのである[3]。
太陽系が不変であるかという天文学的問題は、アプリオリに決着をつけることはできず、"古代人の伝承" を検証することで帰納的に解決されねばならない。ガリレオは、太陽系の構造に関する天文学的理論は歴史的記録によって成立するか否かが決まると述べた。ニュートンでさえ、歴史的記録に記された内容に好ましく思わなかったものの、この点を認めていたことを私は示した。ニュートンの宇宙論を擁護するには、彼の歴史研究の結論も同時に擁護せねばならない。ゆえに、今日の天文学者が太陽系の力学について意見を述べるには、歴史的資料を無視できず、歴史学の研究成果に依拠せざるを得ないのだ。
『会報』の執筆者は、科学的方法の本質をめぐる論争を、個人攻撃の議論に矮小化しようとしている。彼はヴェリコフスキーを道徳的に疑わしい人物、でたらめを売り歩く者だと断じ、したがって同じ方向性の調査を提唱する者たちも同様に汚されていると主張する。同様に、ユージン・ラビノウィッチは一方ではヘス教授への書簡で『会報』の編集方針を説明しつつ『行動科学者』を隠された悪意ある意図で非難し、他方ではアメリカ行動科学者の編集者への書簡(1964年6月23日付)で歴史的証拠は「必然的に暫定的でしばしば論争の的となる事柄」だと主張している。
実際、現象学的な科学、つまり教条的に受け入れられたヌーメノン(直接的に知覚できない本質的な存在や事物)的な前提に基づかない科学は、必ず「必然的に暫定的で、しばしば論争の的となる問題」となる。ガリレオの裁判記録を読めば、これが彼に対する主な反論だったことがわかる。これが彼が撤回書に署名することを選んだ理由のようだ。絶対的な確実性を求める者たちにとって、彼の科学は無力であると認めたのである。
歴史学(ソ連でさえ今日では時代遅れとなった教条的でスコラ的なマルクス主義を信じるのでない限り[4])は経験科学であり、行動科学である。ラビノウィッチの主張を借りれば、まさにそう言える。したがって、歴史学は『会報』がプラトンに倣って科学の名を限定しようとする絶対的確証を生み出せない。しかし、天体現象の領域でさえ、歴史学が特異的かつ肯定的に意義ある情報体系を生み出せることが示せる。歴史科学は適切に用いられれば、他の科学と同等の成果を達成する。この学問に特有の唯一の限界は、偶然保存された過去の記録に依存する点であり、それらが破壊された場合には捏造できないことだ。したがって問題は、利用可能な文書の数と種類を評価するという事実に基づいた課題となる。以降、ヴェリコフスキー以外の学者の見解を参考にしながら、彼の論証の主要な要素を構成しない文書の重要性を強調しつつ、この問題に取り組むことにする。
注(『天文学理論と歴史的資料』で引用した参考文献)
1. 17ページ。この論説は所長のフランチェスコ・フローレス・ダルカイスが署名している
2. 19-24ページ
3. 『偉大な世界システムについての対話』、ジョルジオ・デ・サンティラーナ編(シカゴ:シカゴ大学出版局、1953年)、59ページ
4. 太陽系の構造が近年変化し、その結果、地球に大惨事が起きている可能性については、過去3年間にわたり一般科学雑誌『ナウカ・イ・ジズン(科学と生命。1890年から1900年にかけてロシア帝国で最初に発行され、その後1934年以降はソビエト連邦で、そして今日のロシア連邦で継続して発行された科学雑誌)』で議論されてきた。掲載記事は物理的証拠と歴史的証拠の両方を引用しており、その内容はヴェリコフスキーが提示した資料と類似し、時に同一のものである。
──つづく
最後までお読みいただき、ありがとうございました。